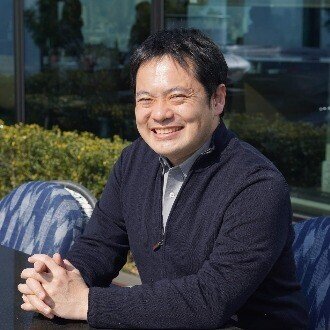社会起業家へ:嘆願書の事例
社会起業家としてデビューした際に、活動を実施する際に嘆願書を出して許可を頂きました。実際に使用したものですが、町の名前等は、全て「坪田」に変更しています。
実際に使用したものなので、参考にして頂ければ幸いです。
添付のワードファイルを少しいじくって、全文掲載します。ワードファイルは、編集履歴が残っているので、有料フィルタします。
嘆願書
眼科巡回診療実施要望書
坪田町における眼科巡回診療について(要望)
初秋の候、~~町長様におかれましては、益々ご検証のこととお慶び申し上げます。また、平素から坪田地区の発展に、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、坪田町の医療に関してですが、眼科などの特定疾患に関して医療機関が不足していることから、町の公共交通機関であるデマンドタクシーを使用して通院が困難であるということを伺いました。
坪田町の無医地区の住民の皆様への医療サービスを考え、開業させて頂いた私達、坪田クリニック坪田としましても、課題に関して考えて参りました。ご挨拶させて頂いた自治会長の方々やクリニックを利用される方々、坪田町で開業する先生方や芳賀郡市医師会からお話を伺ったところ、眼科の巡回診療に関する反対される方は居られませんでした。
特に眼科に関しましては、疫学研究において高齢者の視力と骨折率の因果関係やうつ病の因果関係が証明されており、坪田町の住民の皆様が、より高いクオリティオブライフをすごして頂くために、重要な診療科目だと考えております。
町内にて、眼科の巡回診療を実施するためには、坪田町にて巡回診療の必要性を認めて頂く必要性がございます。つきましては、是非とも坪田町内にて、眼科に関する巡回診療を実施させて頂く許可を頂きたくお願い申し上げます。
私達が調査致しました現状を添付致しますので、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
【はじめに】
我が国の医療提供体制は、国民皆保険制度とフリーアクセスの下で、国民が必要な医療を受けることができるよう整備が進められ、国民の健康を確保するための重要な基盤となっている。しかし、近年、へき地等における深刻な医師不足、都市部との医師偏在、疾患の多様化、住民ニーズの変化等により、地域における適正な医療供給を維持することが困難となってきている。今後、急速な高齢化、人口減少が進行する地方自治体において、持続可能な医療供給体制を構築することは喫緊の課題である。
私達は、平成25年より坪田町坪田地区で診療所を開設した。同地区は平成23年に地区唯一の医療機関である早田内科小児科医院が閉院して以降後継者がいないために生じた人口5000人規模の無医地区であった。同地区は、公共交通機関の発達が充分ではなく、診療所への移動は車が中心で車を運転出来ない高齢者及び高齢者を支える家族の困難を伴う他、私達の内科診療所以外に医療機関はないため、眼科等の特定診療科を受診するためには、近隣自治体まで移動しなくてはならない(坪田町全体にも、眼科や耳鼻科がない)。そのため、同地区は診療所を開設した今も、医療の確保が充分とは言い難い。
最低限度の医療供給という観点から、以前よりへき地の医療確保のために行われている巡回診療という診療スタイルがある。これは、診療機器を積んだ巡回診療車または巡回診療船等が週1回〜月1回程の頻度で地域の集会所等に赴き、集まった患者を診察するものである。これまでは実施主体が地方公共団体、公的医療機関、公益法人等に限り実施手続きが円滑化されていたが、昨年10月の厚生労働省医政局通知にて、巡回診療の実施主体に関わらず同様の円滑化が計られることとなった。同通知による手続きの円滑化を用いて、私達の診療所が実施主体となり坪田地区において眼科巡回診療を行うことにつき平成25年8月に厚生労働省に確認した結果、地方自治体の裁量に任せるとのことであり、栃木県県東保健センターへ相談したところ、坪田町役場の同意を得て巡回診療を行いたい旨の書類を御課へ提出し、許可がおりれば可能との返答であった。
以上のような経緯より、坪田町坪田地区における医療確保を目的として、坪田町に存在しない眼科の巡回診療を行うため、坪田町の同意を得て御課へ許可を求めるものである。
法的妥当性
【巡回診療を個人開業医の私が実施主体となり行う事の法的妥当性について】
巡回診療とは、巡回診療車等の移動式の診療施設又はそれ以外の施設を利用して公衆に対して医療を提供するものである。原則として、各拠点(診療会場)ごとに開設手続きを取るものであるが、巡回診療の目的が無医地区における医療の確保、地域住民に特に必要とされる結核、成人病等の健康診断の実施等である場合は特例的な取扱(手続きの簡素化)を受けることが出来る。これまで手続きの簡素化が認められるのは、実施主体が地方公共団体、公的医療機関の開設者又は公益法人等(医療法人も含む)に限定されていたが、平成24年10月の医政局通知にて、実施主体の制限は撤廃され(資料:医政発1001第7号)、個人開業医である我々が巡回診療を行う際に手続きを簡素化してもよいこととされた(厚生労働省へ照会済み)。
活動妥当性に関して
【坪田町坪田地区において通知を用いて巡回診療を行う妥当性について】
上記通知を用いて巡回診療が可能な場合は、「…巡回診療の目的が無医地区における医療の確保、地域住民に特に必要とされる結核、成人病等の健康診断の実施等である場合…」と記載されており、無医地区に限らず、準無医地区及びその他、医療の確保が必要とされる地区が含まれる(厚生労働省へ照会済み)。これは全国で準無医地区の巡回診療が広く行われている事からも明らかである。
以上より、坪田町坪田地区が無医地区に限らず準無医地区または医療の確保が必要とされる地区であれば通知を用いて手続きを簡素化した巡回診療が可能と考えられる。
必要地区か?
(坪田町坪田地区は準無医地区または医療の確保が必要とされる地区か?)
坪田町坪田地区は昭和29年に坪田村が坪田町に合併されて生まれた。坪田町の南部に位置し、西は真岡市、南は茨城県桜川市に接する5×8km程の地区である(資料:坪田地区地図参照)。平成25年時点で人口5776人であり坪田町の人口の約1/4を占める。
同地区では平成23年に唯一の医療機関(早田内科小児科医院)が閉鎖し、無医地区化した(平成21年の厚生労働省無医地区調査後の出来事であるため、無医地区の基準を満たしていても記載はされていない)。坪田町には他に医療機関が8箇所(資料:坪田町内クリニック参照)あるが、いずれも坪田町中心部及び北部の七井地区に集中しており、坪田地区住民は早田内科小児科医院が閉院してから、地区中心部から5km離れた中心部や近隣自治体の医院へ通院することを余儀なくされていた。
平成25年9月に私達が診療所(内科、リウマチ科)を開設した事で、一般内科に関してのアクセスは改善したが、診療所は週3日10:00-18:00の外来診療であり、依然として医療の確保は充分とは言えない。また、坪田町には眼科、耳鼻咽喉科等の特定診療科がなく、これらの科を受診するには、地区中心部より10km離れた真岡市の眼科診療所まで赴かねばならない。一方で坪田地区内に路線バスや鉄道は無く公共交通機関が脆弱である。移動手段としてデマンドタクシーサービスはあるが、自治体間をまたぐことは出来ない。従って自力で車を運転出来ないもの及び車を持たないものが近隣自治体の診療所へ行くには、デマンドタクシーで坪田駅まで出て鉄道に乗る必要があり、1日仕事となってしまう。
無医地区定義
さて、厚生労働省によると無医地区とは、「医療機関のない地域で当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径4kmの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区」と定義される。準無医地区は、「無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議出来る地区」である(資料:無医地区定義)。平成25年10月の時点で坪田地区は、私達が診療所を開院していることから無医地区ではない。しかし、準無医地区としての要件、
(イ)半径4kmの地区内に医療機関はあるが診療日数が少ないか(概ね3日以下)又は診療時間が短い(概ね4時間以下)のため、巡回診療等が必要である。
(ウ)半径4kmの地区内に医療機関はあるが、眼科、耳鼻いんこう科などの特定の診療科目がないため、特定診療科についての巡回診療が必要である。
を満たし、定義的には準無医地区として妥当と考えられた。
また、全国に坪田町坪田地区と類似した地区(内陸で特定診療科がない、または地区医療機関の診療日数が少ない事から準無医地区とされている地区)がないか検索したところ、いくつか前例を認めた。
事例
「和歌山県田辺市中辺路町」
和歌山県田辺市は人口77000人の都市で、中辺路町は約3000人が住む。町内に鉄道はないが、バスが発達しており、田辺市中心まで所用時間は40分である。町には2箇所診療所があり、いずれも週5日開院しているが、診療科は内科、小児科、循環器科であり、眼科、耳鼻いんこう科などの特定診療科がないため、町全域が準無医地区に認定されている。
「山梨県富士河口湖町富士ヶ嶺」
富士河口湖町は人口約26000人の町で富士ヶ嶺地区には約700人が住む。鉄道はないが、バスは2便運行しており河口湖町中心部まで1時間を要する。富士ヶ嶺地区に診療所は1箇所あるものの、内科、小児科であり、眼科、耳鼻いんこう科などの特定診療科がないため、富士ヶ嶺地区は準無医地区と認定されている。
「新潟県糸魚川市根知」
新潟県糸魚川市は人口46000人の都市で根知地区には約1200人が居住している。鉄道は糸魚川中心部まで9便運行され、所用時間10分、バスは8便運行されており、所要時間20分である。地区に診療所が1箇所あるが、内科のみであり、眼科、耳鼻いんこう科などの特定診療科がないため、根知地区は準無医地区と認定されている。
「岡山県津山市加茂」
岡山県津山市は人口104000人の都市で、加茂地区には約5000人が居住する。鉄道は津山市中心部まで9便運行され、所要時間は30分。バスも運行されている。加茂地区に診療所は2箇所あり、内科、外科、小児科、整形外科、リハビリ科、放射線科であり、眼科、耳鼻いんこう科などの特定診療科がないため、加茂地区は準無医地区と認定されている。
「山口県萩市明木」
山口県萩市は人口51000人の都市で、約1100人が住む地区である。鉄道はないが、バスは1日12本運行され、萩市中心部まで所用時間15分である。診療所は1箇所あるが、月・水・木の診療日であり、診療日数が少ない事から準無医地区と認定されている。
以上より、坪田町坪田地区は定義をみたし、同様に特定診療科が無いことや診療日数が少ない理由による前例もあることから、準無医地区として妥当と考えられた。通知を用いて巡回診療を行うことは差し支えないかを厚労省医政局指導課に確認したところ、準無医地区であるかどうかは、県による判断との事であった。また、無医地区、準無医地区に限らず、当該自治体が巡回診療による医療の確保を必要と考えれば通知を用いての巡回診療は認められるとの返答も得た。
坪田町を管轄する県東保険センターへ確認したところ、栃木県の判断としては、市町村からの巡回診療が必要であるとの同意を得た場合に限り、通知を用いての巡回診療を御課が許可されるとの事であった。
背景
【坪田町坪田地区で眼科巡回診療が必要と思われる背景】
(坪田町に眼科がないこと)
前述の通り、坪田町には眼科はなく、近隣自治体へ移動する必要がある。坪田地区はデマンドタクシー以外に鉄道、路線バスがないため、車を使用できない患者には1日がかりであり、家族が送迎する場合も負担は大きい。そのため、症状があってもなかなか医療機関にかからず治療機会を逸している患者がいると予想される。
(坪田町の視覚障害者数は全国平均より多い)
平成18年の厚生労働省身体障害者実態調査によると全国の視覚障害者は31万人であり、視覚障害の有病率は0.24%であった。一方、坪田町における平成25年の視覚障害者は96名で有病率0.4%(96/240000人)であり、全国統計と比較すると2倍近く高い(全国平均並みだと58人)。視覚障害者の有病率が高い理由として、一概には言えないものの上記のように眼科への医療アクセスが悪いことが関係している可能性がある。
重要疾患
(視覚障害によりリスクの上がる重要な疾患)
視覚障害により、様々な全身疾患のリスクが増加する。その中には、QOLを急速に損ない、医療費の増大、経済的損失を伴う疾病が多い。
例として、
・ 予期しない転倒の増加:オッズ比 1.43-2.3倍(Coleman,2004)
・ 転倒による股関節骨折:オッズ比 1.5-8.4倍(Fels on,1989)
・ うつ状態:オッズ比 3.5倍(Brumedi,2002)
・ 死亡リスク上昇:オッズ比 2.3倍(McCarty,2001)
などがある。
社会損失
(視覚障害がもたらす社会損失)
平成21年に日本眼科医会が視覚障害による社会損失を報告している。このレポートでは、視覚障害による直接経済コストとして、医療費、介護費、医療管理費などは1兆3400億円に上り、間接経済コストとして、生産性の低下(雇用率低下、欠勤、早死、課税収入減など)、社会によるケア(公的年金、視覚障害施設費用、補装具など)として、1兆5800億円、さらに、QOLが低下することによって個人が被る疾病負担は5兆8600億円と計算され、社会全体のコストとして、8兆8000億円が損失されているとした。このレポートでは、視力障害者を矯正視力<0.5と定義しており、定義を満たす164万人で除すると、1人当たり約500万円の損失となる。逆に言えば、積極的な早期発見へのアプローチや国民意識の向上等により、視力障害者を1人食い止めれば500万円のコストを減じることが出来る。
【全国で眼科巡回診療を実施している例】
(鹿児島県)
県内に離島を多くかかえる鹿児島県は、へき地拠点病院、大学病院、民間病院:県眼科医会と協働して眼科、耳鼻科、皮膚科など特定診療科の巡回診療を行っている。
(沖縄県)
沖縄県立宮古病院附属多良間診療所では、年数回の眼科巡回診療を行っている。
(岡山県)
岡山済生会総合病院が巡回診療船「済生丸」を用いて眼科巡回診療を行っている。
その他、平成11年度の厚労省無医地区調査では全国に眼科の巡回診療を行っている地区は90カ所あるとのことであった。
地域との関係性
【当クリニックと地域医師会との関係性】
当クリニックが坪田町坪田地区で眼科巡回診療を開始したい旨は、~~市医師会会長である~~~先生、副会長である~~~先生、坪田支部長の先生にお話しし了承頂いている。また坪田支部会員の~~~先生、~~~先生、~先生、ー先生、ー先生、ー先生、ー先生にもお話し御理解頂いており、良好な関係であると自覚している。
また、日本医師会会長~~~先生、~~医科大学学長の~~先生にもご助言頂いた次第である。
関係性
【当クリニックと坪田町との関係性】
開設前から坪田町行政の方々にはご指導頂いている。私達の診療所は町の所有物であった早田内科小児科医院を借り受けているほか、今後、トイレ等の改修も検討頂いており、関係は良好である。眼科巡回診療に関しても様々な観点からご助言頂いている。
【まとめ】
以上のように坪田町坪田地区は医療アクセスに乏しく、特に眼科においては坪田町自体に眼科診療所がなく容易に受診出来ない状況である。坪田町は全国平均に比べ視覚障害者が多く、社会的損失も大きい。私達は坪田町坪田地区での眼科巡回診療を行い、最低限の医療確保という観点で地域医療に役立ちたいと考えており、ここに御課へ巡回診療の許可を求めるものである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?