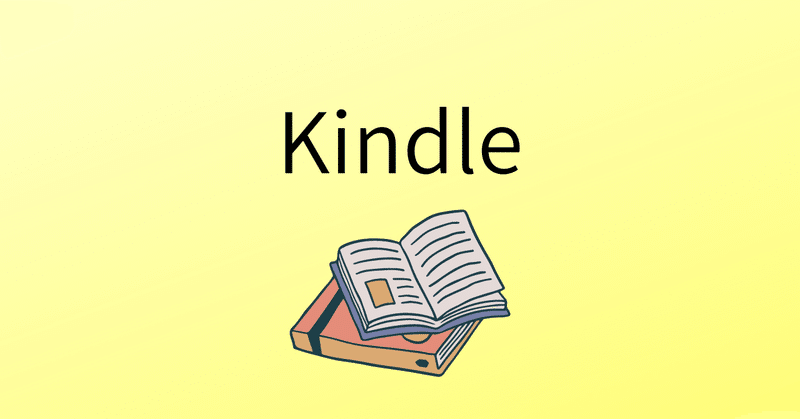
note記事をもとにKindle本を出版してみた
前回の投稿で触れたとおり、Kindle本を出版してみました。
実際にやってみて感じたことがあるので、まとめてみます。
感想
まず、やってよかったです!
転職の相談って、友人だからこそしにくい部分があるなと思います。いざ本気で転職活動するなら、年収とかも開示してもらうわけだし、どこの企業に受かったとか落ちたとか、入社を決めた企業の年収なども、転職エージェントは知ることになります。
友人からすると、ちょっと抵抗があるというのはとてもよくわかるんですよ。開示する情報量に差があるというか。例えば私だって泌尿器科医の友達がいても、診て欲しいとは思わないですし。
そんな友人に、これまでなかなか積極的には伝えられなかった転職関連の仕事で得た知見を伝えられたこと、さらにはそれを喜んでもらえたことが、今回何よりの財産です。
制作の流れ
2月頃に、note記事をまとめてKindle本を作ることを思い立ちました。
そこからほとんどの時間は、過去記事を読むことと添削することに費やしました。
そのほか、表紙を作ったり、全体の体裁を整えたりです。
平均1日30分〜1時間の作業時間で、ゆっくり取り組みましたが、2ヶ月ほどで出版に至りました。
苦労したこと
一つは構成です。
もともとnoteでは、キャリアに関することをあまりテーマを決めずに書いてきました。そのため、本にまとめる中でどんな章立てにしたらよいかはけっこう苦労しました。
あまり持論が強いものは本には掲載しないことに決めました。持論を語って読者を惹きつけるほどの実績とか肩書は持っていないので。誰が言うかの観点から、そのスタイルはそぐわない気がしました。
そこで、転職エージェントが見た、転職市場のレポートという立ち位置にして、多く接してきた事例について語ることにしました。
そのスタンスが決まってようやく過去記事のリライトの方向性も固まってきました。
過去記事は、読み返すとスタンスがバラバラで、ブログ形式だと問題ないのですが、本にするとなると一貫性が感じられなくて。そのリライトがしっくりこなくてボツにした原稿もそこそこ多いです。
もう一つは校正です。
大きな分岐点は縦書きにしたことです。どうもKindle本の多くが横書きらしいです。英語と同じ本の作りというか。でも私は縦書きの方がKindleは読みやすいし好きなので、縦書きで作ることにしました。
Wordで原稿を作ったのですが、縦書きだと半角の英数字の文字が90度右に傾く(横に寝る)ことになります。そこで、Wordの設定ですべて縦中横(たてちゅうよこ)にしたんですが、これが間違いでした。最後の最後に入稿してみたら、該当箇所が全て表示ずれしてました。一部のWordの設定が悪さをするみたいでした。
その後になって、全角表記をすれば文字が横に寝ることがないとわかって、全部直しました。ここ、無駄な労力がかかってしまって、とても苦労しました。
あとWordだと、段落の始まりに全角1文字分スペースを入れていたんですが、これもKindleの表示を見ると微妙で。私の環境だと、なんだか全角1.5文字分下がってしまうみたいなんです。
段落の始まりでわざわざ1文字分スペースを入れなくても、改行された文頭は半角分のスペースはKindle上では自動で入るみたいでした。
この辺も縦書きだから余計に気になるのかもしれません。次何か書くとしたら、わざわざスペース入れるのはやめにします。
Kindle出版にまつわる諸説
ブログ記事を出版してもいい?
これネットで調べると、けっこう意見が割れてます。意見とかの問題ではないですけど。
Amazon的には、有料で提供するコンテンツが、よそのサイトで無料で見れるというのは不都合があるわけです。ただどこまでなら同一のコンテンツだと認識されるのか、やってみるまでよくわかりませんでした。
私の場合、ブログ記事をリライトして再編集しているといっても、一つひとつの記事のタイトルは7割以上変わりありません。ほぼ同一のコンテンツと見なされる可能性もありました。
もしかしたらAmazonから確認の連絡が入るかもとは思ったものの、結果的には何も連絡なく承認されました。4月2日に原稿その他すべてアップロードして、3日には承認された、というスケジュール感です。
まったく同一のコンテンツが、Amazon以外のマーケットに提供されているのは不都合があるでしょうが、ブログを再編集したものは特に問題なさそうなのかな、という気がします。
表紙は必ず外注すべき?
これはどのKindle作家も言ってることです。とにかく外注しろと。それで売上が変わってくると。
私はデザインセンスがあるわけではないですが、ちまちまと自作してみました。
書店で目に入る本の表紙を20冊くらい選んで、ポイントを考察して、真似するデザインを決めました。
canvaというサービスだと、色味の組み合わせサンプルがたくさんあるので、それに頼りながらなんとか仕上げました。
売上にどんな影響があったかはわかりません。プロから見て違和感があるかも知れません。でも、まあ、いいかなと。この本で有名になりたいわけではないですし。
売れ筋ランキング1位を取る方法?
本を作ったらマーケティングを考えなければなりません。Kindle作家の方々はマーケティングのこともフォローしていて、売れ筋ランキング1位の取り方とかたくさん発信してるようでした。
とはいえ私はすごく売れたいわけでもなく、趣味的にまとめただけなのでそこまでこだわらずに進めました。こだわりすぎると、失敗しないように考えすぎて、楽しくないので。
(あと、そもそもAmazonで売れ筋ランキングを見て買ったことない)
結果、無料キャンペーンを設定して、知人友人に少し声かけしたくらいです。リアルの知人友人で買ってくれたのは多くみて15人くらいかなと。
それでも、いま80冊ほどダウンロードしてもらえていて、キャリア、職場文化、エッセー、学生の就活、ビジネス経済スキル、自己啓発、ビジネスライフ、事業開発で1位になったみたいです。(1時間ごとのランキングらしい)
どこまで意味があるのかはよくわからないです。
さいごに
noteやブログだと、Twitterほどではないにしろ、やはり古い情報はどんどん流されていってしまう気がします。古い記事は読まれないですし。
今回、書籍にまとめ直すことで、そんな少し古い記事にも新たに活躍の場が与えられたというか、古くなくなったというか。
本って、時間の流れを少し緩やかにしてくれる気がします。その分、本に書いてある情報も古く扱われにくいような。そんな感覚です。
これで稼ぐとかは全然別次元の話ですが、けっこうよかったです、Kindle出版。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
