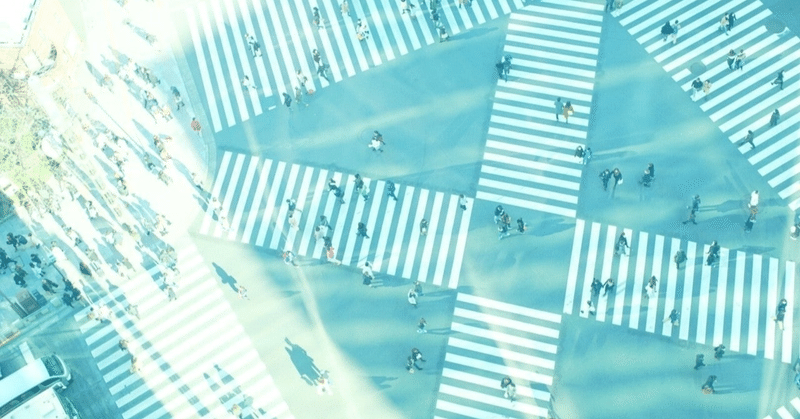
健康という"普遍的価値" #2
◆健康という道徳の差配人としての医療・福祉
うえむら 最近人間ドックに引っかかりまくったので身につまされましたけれど、P107「医療者のこうした助言には、無視しがたい響きが宿っている」については、「まあワイは無視するけどな」と思いましたね。「医者ごときがワイにパターナリスティックなことを言うのは許さない」という精神でいたいと思いました。
こにし 医者側にもコーチングの技術が必要そうですね。
うえむら コーチングされたい人にコーチングするのはいいけれど、私はコーチングをされたくないのよ。
こにし 押し付けコーチングは良くないですね。
しろくま おっしゃるとおりで、全然良い場にならないですからね。なにもこころを開かずに終わるという。
うえむら 私は医者にこころを開いていない。かかりつけの内科医はいい人なのですが、それだけに却って無視しているのが心苦しくて、足が遠のいてしまう。「ポテチ食うな」とか言われても「分かっとんねん、でも食いたいねん」で終わってしまう。
P108「医療者に対する信頼を欠いていなければならない」は、私は「信頼を欠いて」まではいないですが、最近はコロナワクチンにおけるトンデモ医療の医者たちや、ホメオパシーなどの代替医療を慫慂する医師は、部分的に信頼を落としてはいるよなと思いました。
こにし 医者を信頼しているというよりは、医術を信頼しているような気はしますよね。別に医者の人格を信頼しているわけではない。両方なのかもしれませんが。どちらかというとテクノロジーに対する信頼の方が大きい気がします。
しろくま 確かにね。テクノロジーへの信頼がまずあって、その上に人格への信頼が添えられるという感じ。
こにし その上で資格者がちゃんとやっているというのは添え物としては必要ですが、根本はテクノロジー。
うえむら 統計学的手法によってテクノロジーが信頼されているということであって、標準医療や薬剤は保険診療化・保険収載されることで、既に行政によるお墨付きが済んでいるし、社会が受け容れやすい体制になっている。
そうやって診療報酬体系の価値を信じているうちは良いのだけれど、あるときホメオパシーに行ってしまうのが何故かというと、難病のように、統計を武器として使えない分野において、「まだ保険化されておらず、許認可には至っていないけれど、しかし効果があるのではないかと、最先端の論文では論じられているのだ」みたいなところに行ってしまう。そうすると難病に苦しむ子どもを持つ親は、藁にも縋る思いで、非標準的医療にシフトしてしまう。そして保険外医療は10割負担なので多額のお金をドブに捨てている。
しかしそれも、寛解しないという意味ではドブに捨てているのだけれど、「これだけやったのだから」という精神の安寧には一定資しているとも言える。なかなか難しいですね。
こにし でもそこにおカネを払うのはやっぱりおかしいと思いますけどね。プラシーボ効果的なものにおカネを払っているのが相応かというと。
うえむら そういう人には「最新の知見」なんて教えてあげない方が良いよね。そうすれば「何もできなかった」という思いだけで、つらくはあるけれど、「方法があるのにおカネがなくてできなかった」とはまた違う結果なので。
こにし 難病は確かに難しいですね。
うえむら P110の「たとえ医療者自身が道徳の押し売りをしていなくても、おのずと医療が世の中の価値基準や通念や道徳に影響を与えるのは不可避では」は少し考えさせられました。具体的に現状において医療者のパターナリズムが私たちの行動をどのように規定しているかというと、「食」において健康志向に付加価値が付いたり、「運動習慣」でいうとジムが経済圏として成立したりするなど商品化されており、資本主義に資している。
そのようにマーケットに留まっている限りはいいのですが、やがてそれが法になっていくかもしれないと思いました。例えば「全ての人は健康のために毎日1時間の運動をしなければならない」といった可処分時間が縛られる規制ができる未来は、少しつらい。また直接的に「運動しなければならない」とまで言わないにしても、健康目的税みたいなものを徴収されて、健康プログラムを受益することが事実上必須になるインセンティブが働くこともあるかもしれない。
現状はマーケットという消費者の自由意志の中に留まっているけれど、やがてもう少し規範が強くなって、市民として強制される時代が訪れるのではないかと危惧するところではあります。それがまさに『ハーモニー』伊藤計劃によって描かれている健康ディストピアの極北なのだろうとは思います。
こにし 強制するかはともかく、国家がそういった規制をかける動機はたくさんありますよね。予防医療の促進や、医療費の抑制のツールとして、いくらでも推進する理由はある。
うえむら 「身体障害者はラジオ体操できないやん」とか、細かい調整が必要な部分はあるだろうけれど、すでに健康志向は政策にも取り入れられている。保健事業はかなりの政策リソースをつぎ込んで実施されていて、高齢者を地域の通いの場に引きずり出して「毎日、毎週体操しよう」とか、そのくらいの取り組みは行われている。それがもっと先鋭化して行くことは想像に難くない。
こにし 医療者自身の道徳観とは関係なく、そうなることはあり得ますよね。商売になると言い出す人もいるでしょうし、おカネではない別のステイクホルダーの利害によって推進される余地もある。
しろくま 今は自治体でやっている高齢者向けの運動教室なんかは、やりたい人だけがやっているけれど、ほぼ行かないといけないものに変わっていくのはあり得そうですよね。「65歳になったあなたはまず行きましょう!」とかステップ化されていきそう。
こにし 「保健所にマイナンバーを送っておくので、タッチしたら出席がとれます」みたいな。
うえむら 本当にラジオ体操のスタンプみたいだな。夏休み明けに先生にチェックされて、スタンプを押していない日は「何していたんだ」となる。
こにし 出席しない人にはマイナポータルに通知を出す。ありそう。
うえむら 診療報酬でもよくそういう方法がとられるのですが、最初はインセンティブにする。「来てくれたら商品券を渡します」と。しかしそれがやがてディスインセンティブになる。「来なかったら権利制限される」みたいな。最初は「やってくれたら加算」だけど、制度がある程度普及すると「やらないと減算」になる。
なんだか「日曜はミサに行きましょう」の相似形な気がするな。そういう宗教的抑圧をされていた時代から、「日曜は体操しましょう」という健康的抑圧をされる時代に変化してきている。
こにし 崇めているものが変わっている。健康が「崇める対象」になってきていることが、行動抑圧という共通側面に注目することで浮き彫りになりますね。
◆診断基準と資本主義的プラグマティズム
しろくま P114では「経済的損失」と「費用対効果」という話をしていますが、こういうときによく思うのが、経済的損失よりも医療費が大きい場合に、これからはどういう意思決定がされていくのでしょうか。ナイーブな話ですが、救って助け続けた方が、医療費がかかるケースとか。
うえむら 終末期医療、ホスピスの話ね。「経済的利益よりも医療費の方が大きい」つまり「延命することによって得られる利益よりも、延命にかかる医療費の方が大きい」場合に、医療を継続しないという選択がとられる場合があるのではないかということですね。高齢者の命の価値みたいな話になりますよね。
しろくま なります。高齢者だけではなく若い人でも病気になって治癒の見込みがなくなったときに、治療継続が選ばれなくなるのではないでしょうか。
うえむら 逸失利益という考え方を導入するなら、老衰しきって働けなくなった時点で資本主義からは退場している。経済的に利益を生み出す存在ではなくなった時点で、延命するインセンティブはなくなるよね。
しろくま そう思います。若者でも、本来は労働力としての可能性がありますけれど、働けなくなった瞬間に「延命する意義がない」と見捨てられてしまう。突き詰めるとそうなる。倫理的な問題で、そこまでの極論にならないかもしれないですが。
うえむら 終末期医療のあり方や尊厳死の問題は国の審議会でもずっと議論されていますね。そこまで詳しくないですが、その際の延命させる意味づけがどこまで説得力ある形で為されていくかは、文化によっても違うだろうけれど、少し注意して考えていく必要があるのでしょうね。
しろくま 今は「家族が個人で費用が払えるかどうか」が選択の基準になっているでしょうけれど、それが税金からも出ているのであれば、国全体の議論になりますよね。
うえむら P113~114あたりに書いてあることは、保険会社や、公的医療保険などのファイナンス側にとっては、医療費が増大すればするほど財政的に苦しくなるので、医療費を抑制するインセンティブが「資本主義的に」ある一方で、診療者側である医者、病院、あるいは製薬会社は、医療費がかかればかかるほど儲かるので、医療費を増大させるインセンティブが「資本主義的に」ある。そのように「支払側」と「診療側」というふたつの資本主義的要請が対立しているということです。
これは厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)における、診療報酬体系を決定する際の議論によって描写されている通りなのですよね。「支払側」と「診療側」が同じ数だけ委員を出し合って、診療報酬のスケールとメニューは「何を、どのくらい」が適切であるかを議論している。
そこにおいて「資本主義の論理」から抜け出した倫理的な側面を補強するモデレーターとしての役割を期待された公益委員も同数いますけれど、彼らの存在感は小さい。そうではなくてプラグマティックな怒号の飛び交う分捕り合いの場になってしまっている。「対GDP比○○%水準のスケール」とか指標はあり得るのですが、なかなか資本主義以外に、説得力のある形で医療費の適切なスケールを考えていくのは合意がとりにくい。
こにし 自分で健康を維持しなければならない。第一義には長生きするためにやっていると思いますが、ではなぜ長生きしないといけないのかという話もあって、それ以外にどういう理屈があるかというと、経済的損失の観点が出てくるとは思います。例えば将来的に病気にかかるのだとしても、医療を受ける側としてはかからなければ治療費はかからずに、経済的損失はないなと。確かにそう言われればそう考えているかもなとは思いました。
うえむら 要は病気になったとしても、受診しなければお金がかからないという話かな?
こにし それもありますし、そもそも病気にならなければ良い。もともともっと漠然と「長生きするために健康で」と言われていたけれど、言い方を変えれば「健康ならお金がかからない」というのも確かにそうだなと。そういう「トクだな」という視点で健康を志向していくのは分かりやすいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
