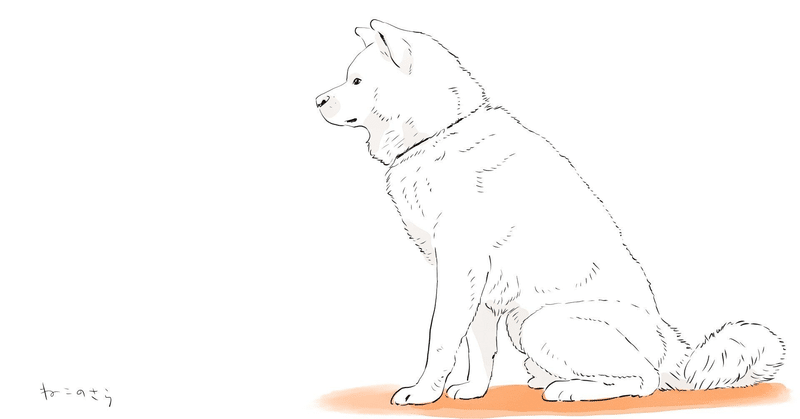
待つと待機と期待と靴下
夜中の駄文。
そして読書感想を。
スクーリングで都会に来ている。夕方のバスは予想通りの到着遅延と高速渋滞を見せながら、私を都会へと運んでいく。
「高速 渋滞とは云っても低速だろう」
林檎さんが着物を着て私の頭の中で歌い出した。やっつけ仕事の彼女が私は大好きだ。(髪型が好き)
私は駅に着くことを気長に待つことにした。
バスの中で、今日の仕事で書きそびれてしまったカルテをタブレットに記入した。書きながら本日はじめて関わった利用者さんについて思い出す。
腕組みした高齢男性。病気をしてから無意に過ごす。怒りやすくなる。妻は異様に彼を気づかう。目で指図をする。察した妻は靴下を「気づかなくてごめんね」と謝りながら、彼の足にはかせる。
妻の手によりするすると足の表面を滑る靴下。
かがむ妻。
何も言わない男性。
誰も聴いていないテレビ番組のコマーシャル。
綺麗に整えられた室内。
それを見つめる私。
男性は妻が靴下を履かせてくれるのを
ただ静かに待っている。
カルテを書いたあとは少し読書をした。
「待つ」ということ
鷲田清一著
この本は題名どおり「待つ」ということについて書かれている。
今の社会は前のめりの姿勢だと言う。
プロがついた言葉。
プロジェクト、プロフィット、プロスペクト、プログラムづくり、プロダクション、プログレス.....これらはみな、ギリシャ語やラテン語の動詞に「プロ」という(前にとか先にとかあらかじめという意味をもつらしい)接続辞をつけたことばのオンパレード。
公衆電話で確認していたお互いの所在は、今は携帯ですぐ確認できる。
書類は郵送ではなく、メールですぐ確認ができる。
テレビゲームやアプリのゲームは気に入らなければすぐリセットが押せる。
お腹が空いたらウーバーイーツで注文すれば、おいしいものを届けてくれる。
今日の天気もスマホを見れば、これからの一時間毎の変化が細かく表示されている。
待たなくてもボタンを「ピ」と押すだけで、勝手にあとはやってくれる。
それが悪いとは言っていない。
私の生活はかなりそういうものに頼っている。むしろ、そういうものがないと成り立たない場面さえある。
待たなくても自分でコントロールできるものが
増えて便利になってきている。見通しが立つこと。効率的に生産性をあげるために....無駄をなくすために.....今の世の中はそのような流れで動いているものが多いことに気づく。
「待てない社会」「待たない社会」
意のままにならないもの、どうしようもないもの、じっとしているしかないもの、そういうものへの感受性をわたしたちはいつか無くしたのだろうか。偶然を待つ、じぶんを超えたものにつきしたがうという心根をいつ喪ったのだろうか。時が満ちる、機が熟すのを待つ、それはもうわたしたちにはあたわぬことなのか......。
あえて、今の時代の中で「待つこと」とはいったいなんだろう。
この本はそこに関するヒントが書かれている。
靴下をはかせてもらう彼は妻がそのようにふるまうことを待っている。
〈待つ〉ことには「期待」や「希い」や「いのり」が内包されている。否、いなければならない。〈待つ〉とは、その意味で、抱くことなのだ。
〈待つ〉ことはしかし、待っても待っても〈応え〉はなかったという記憶をたえず放棄することなしに〈待つ〉ことはできない。
もし、彼は妻が一回でも靴下を履かせてくれなかったらどうだろう。
彼はあきらめて自分で履こうとするだろうか。
それとも、また足を差し出して待ち続けるのか。
履かせてくれなかった事実をどのように受け止めているのだろうか。
待つことの甲斐のなさ、それを忘れたところでひとははじめて待つことができる。〈待つ〉ことにはだから「忘却」が内包されていなければならない。〈待つ〉とは、その意味では消すことでもあるのだ。
抱きながら消す
もし、彼がまた足を差し出すのであれば、いったん履かせてくれなかった事実を消すことでまた待っているのかもしれない。
消すというのは、各々やり方が違うのだと思う。そこは非常に個性がでるところではないだろうか。
怒っている人は期待をしているからだと私はいつも思っている。
だから「怒っている」状態はまだそこの関係性に一縷の望みがあるようにも思う。
怒るより何も言わずに離れることが、関係性が閉ざされる方法の中で一番効果的なアクションだとも思う。
待たずに待つこと。待つ自分を鎮め、待つことじたいを抑えること。待っていると意識することなくじっと待つということ。これは、ある断念と引き換えにかろうじて手に入れる〈待つ〉である。とりあえずいまはあきらめる。もう期待しない、じりじり心待ちにすることはしない、心の隅っこでまだ待っているらしいこともすっかり忘れる。ここでなおじたばたしたりしたら、事態はきっと余計に拗れるから。
なぜ待つのか。
待っているのは彼だけなのか。
私は妻も待っているのだと思った。
靴下をはかせ続ける妻は、夫に対して何かを待ち続けているように.....私はその場面を見て感じていた。
ひょっとしたら「育児」というのはそういういとなみなのかもしれない。ひたすら待たずに待つこと、待っているのも忘れて待つこと。いつかわかってくれるということも願わずに待つこと、いつか待たれていたと気づかれることも期待せずに待つこと.....。
家族というものがときに身を無防備にさらしたまま寄りかかれる存在であるとしたら、この期待というもののかけらすらなくなってもそれでもじぶんが待たれているという感覚に根をはっているからかもしれない。その根があっけなく朽ちてしまうとも。その根がときにもっとも残酷なかたちで切り裂かれてしまうとしても。ただ、待たれるほうからすれば、それは何かが少しずつ堆積していく時間である。
むしろこの場面で静かに待っているのは妻の方なのかもしれない。
妻は病気をする前と後で彼の性格が変わってしまったことについて、さみしそうに話していた。
けれどもそこに戻ってほしいということも言わずにただ「主人が思っていることがもう少しわかってあげられたら....本人も苦しいのだと思う。」とだけ、私に話した。
その思いが堆積されている。
それはきっと彼にも伝わっているのだと思う。
わたしの行為の、あるいは発言の、どれひとつとしてだれにも待たれることがないという事態に、おそらくひとは耐ええない。
親を、友人を、恋人を、ひとが一生懸命求めつづけるのは「待たれる」ことがじぶんの最後の支えのひとつになりうることを知っているからである。
私を待ってくれている人がいる。
それだけで生きる力、支えになる。
私は自分を見失って、1人になることもある。
所詮、孤独な生き物だからと観念して、1人という状態をより鮮明に感じることもある。
崖の上でただ静かに立ちたい時もある。
でも、どこか遠くから聞こえて来る。
息づかいが感じられる。
あるいは風にのってやさしくやってくる。
こんな私でも待っていてくれている人がいることを
私は見過ごしてはいけないのだと思う。
※今回の記事は下書きを完成させたので、スクーリングには今は行っていないのですが、そのまま文章は残しました。ご了承ください。
サポートは読んでくれただけで充分です。あなたの資源はぜひ他のことにお使い下さい。それでもいただけるのであれば、私も他の方に渡していきたいです。
