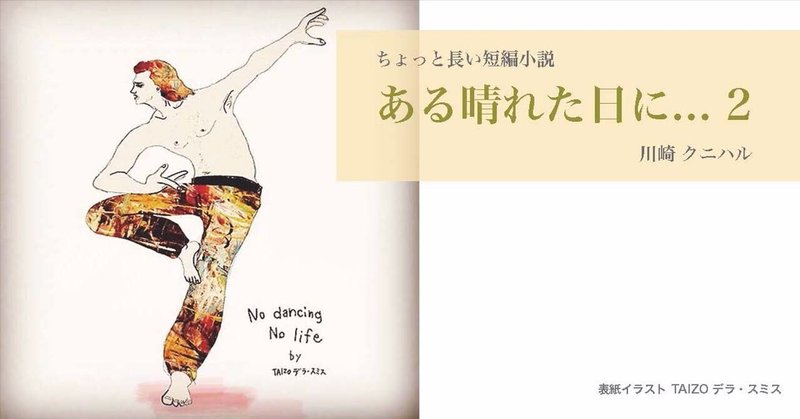
ある晴れた日に… 2
[ 前回の話はこちら… ]
到着した渋谷周辺はいつもならどこも人でごった返しているのだが、今日は人通りがやけに少ない。バスターミナルには沢山のバスが放置されており、運転手もいなければ乗車を待つ人もいない様だ。
時折すれ違う通行人は皆満面の笑顔で、挨拶を投げかけてくるが、それにいちいち応えるのもだんだん面倒になってくる。
繁華街を通り抜け、オフィスビルへ... さらに人影が少なくなった。
いつもいる警備員の姿も見えない。
エレベーターホールには誰もいなかったが、エレベーターはいつも通り動いている様だ。
広告代理店のあるフロアに上がったが、何故かガランと人気がなく、エレベーターホール脇の受付カウンターにも誰も居ない。
仕方なく、スマホを取り出し、今日の打ち合わせの担当者に直接電話を入れてみた。
『はいはーい、川村さん、おはよーございまーす』
「あ、波多野さん?今、受付まで来てるんだけど…誰もいないんだけど…」
『ああ、来て頂いたんですねっ。セキュリティー、全部解除されてますんで、そのまんま入って来て頂いて大丈夫です。俺、奥のいつもの部屋にいますんで…分かります?迎えに行きましょうか?』
「いや、大丈夫。分かるから…」
波多野とはこれまでグラフィックや動画コンテンツなどいくつもの仕事を一緒にこなしてきた長い付き合いだ。この代理店にも仕事の度に訪れているので、内部の配置もよく熟知している。
言われた様に、いつもなら社員のICカードが必要なオフィスの入り口は解錠されていた。広い社内に入るとあちらこちらで数人の社員が気が狂った様に電話やパソコンの対応に追われている様子だが、そこには何故かそれほど深刻さはない…
「ひゃあ、ははは…全然分かんない~。一体どうすればいいの~?こんなの知らないよ~。第一俺の仕事じゃねえし~ははは…参ったなあ。ねえ~誰かこれ分かる人誰かいないんですか~っ!」
「はいっ、はいはいっ、いや、そーなんすけどねっ、担当の人間がいないんですよー……いや、はは、だからあ、申し訳ないんですがあ、まだ出社していないんですよ~……いやあ、そう言われましてもね~あはは…」
「ないないないないっ!連絡先のメモなんてどこにもありませんよ~~!そんなの今時、パソコンの中なんじゃないですか~っ?大体あたし、総務なんだからあ、制作現場のことなんて知らないわよっ!もう…やめたやめたっ!もう知らないっ!あはは…もう帰ろっと…あたし、もうお家に帰りますっ!」
奥に進むと、いくつかの小さなテーブルが置かれた休憩スペースがある。
男女5、6人のスタッフが大笑いしながら肩や手を叩き合い、大盛り上がりで談笑している...隣のデスクスペースはあれほど恐慌状態なのにも関わらず、気にもしていない様子だ。中には顔見知りもいたが、なるべく関わらない様に、顔を伏せてそっと通り過ぎ、波多野が待つ奥のクリエイティブ局へと足を早めた。
「いや~、川村さん、なんだか、もう大変なんですよお」
クリエイティブ局の部屋にいたのは、波多野ただ1人だけだった。
ノートパソコンを前に、もうお手上げという表情で両手を挙げた。
「どうしたんですか?」
「出社しようと思って、家出たらうちの方はバスも電車も止まってるしタクシーも見つかんないし、しょうがないからまた家に戻って車で来たんですよお。で社に着いたら、この状況でしょ。それにしても川村さん、よく来られましたねえ」
「ああ、山手線は一応動いてたけど…」
「街もそうだけど、オフィスの様子見ました?」波多野は声を潜めて尋ねる。
「あ、ああ…みんなどうしちゃったの?何があったの?」
「いやあ、全く訳が分かんないんですよお…朝からテレビはどのチャンネルも放送してないし、殆ど社員も出社してこないんですよ。携帯で連絡しても繋がんないし…」
「じゃあ、打ち合わせは、どうすんの?」
「クライアントさんとも連絡取れないし…他のスタッフも来ねえし…なんか、それどこじゃない雰囲気ですよねえ…それより、川村さんは大丈夫なんですか?」
「大丈夫って、何が?」
波多野は疑わしそうな目つきで私の表情を暫く眺め、やがて気をとり直したように話を続けた。
「…ほら、オフィス見たでしょ?多少の社員は出社してるんだけど、なんかみんな様子が変で…なんていうのかなあ…気もそぞろっていうか、やけに陽気で、やってることもチグハグで、まともに相談もできなくて、おかしいんですよ。みんな、どうかなっちゃったみたいで…」
「そうか…うちでも今朝は家族の様子がちょっと変だったんだよねえ…」
私は、いつもと違う妻と娘の様子を話した。
「そうか…俺は独り身だから外出するまで分からなかったけど、ご家族もそんな感じなんですか…」
「で、どうするの?このまま少し様子見る?」
「いやあ、これは多分もう打ち合わせもへったくれもないでしょう。クライアントがいないんじゃ話になんないからなあ…川村さんは暫くここにいてもいいんですか?」
「いいも何も、こんなんじゃ、他の仕事も動かないだろうし…」
「じゃあ、ちょっと早いけど、その辺で軽く昼飯でも食いに出ませんか?ここにいても埒が明かないし、少し気分変えましょうよ。そのうちクライアントさんからも連絡が入るかも知れないですし…」
「そう…構わないよ」
どうやら波多野だけは私と同じくまともな精神状態に見えたので、2人で外に出ることにした。
ビルを出て、すぐ近所のイタリアンカフェに入った。
店の前では数人の学生らしき若者と中年のサラリーマンが入り混じり、手を取り合いながらダンスらしきものを踊っていたが、我々が入り口に近づくと、笑顔でさっと道を開けてくれた。
店内には、客は1人もいなかった…
「あれ?…この店、やってるのかな?…すいませ~ん!ここ、座ってもいいですかあ~っ!」
波多野が店内隅のテーブルを指差して誰もいない店の奥に声を掛ける…
ホールと厨房を仕切るカウンターの向こう側に座っていたらしい1人の男が立ち上がった。
「はいは~い!いらっしゃいませ~!どうぞどうぞ~っ」
黒いスラックスに白シャツ姿の男は笑顔を浮かべて踊るように素早くテーブルに近づいてきた。
「ええと…メニューは?」波多野が尋ねる。
「あっ、メニューですねっ。メニューは…ありません。あるんですけどおー、お出しできるものがねえ、あんまりねえ…へへ…」
「ここは、確か、ランチはピザかパスタだったよねえ?」
「ん~…えーとお…ハムとチーズとレタスのサンドイッチですか?」
「今日はパスタは何がおすすめなのかな?」
「え~…ハムとチーズとレタスのサンドイッチですかねえ」
聞こえているのか聞こえていないのか店員らしき男は笑顔のままだ。
「あの…ピザはありますか?」
「ん~…ハムとチーズとレタスのサンドイッチ…」
「サンドイッチ以外だと何ができます?」
「え~とお…ハムとチーズとレタスのサンドイッチですねえ」
私と波多野はお互い顔色を窺ったが、諦めて波多野が注文した。
「じゃあ、サンドイッチでいいや」
「はいっ!」男は笑顔のまま私に視線を移す。
「あ、ぼ、僕も同じサンドイッチで」
「はいっ!ハムとチーズとレタスのサンドイッチお2つですねっ」
「あと、コーヒーね」
「あ、僕もコーヒーで…」
「コーラお2つですねっ」
「いやいや、コーヒー。ホットコーヒー2つ」
「コーラですね、コーラ。コーラお2つ。ねっ」
「はは…じゃあ、コーラでいいや」波多野は苦笑している。
「あ、じゃ、僕もコーラで…」
「はーいっ!ハムとチーズとレタスのサンドイッチお2つ。コーラお2つ。少々お待ちくださ~い!」
男はそう言うと、華麗に身を翻し、再び踊るようにカウンターの向こう側に戻り、身を屈めた。
波多野は大きくため息をつくと、話し始めた。
「参ったなあ…急にどんどん酷くなるよなあ…はは…」
「これって、やっぱり酷くなってるの?」
「ええ。朝のうちはもう少しマシだったんすけど、どんどん踊ってる人が増えてきちゃって…話も通じない人とか…へへへ…まあ、なんて言うか、少し気持ちはわかるんですけどねえ…」
「えっ?気持ちが分かるって、どういうこと?」
「川村さんは、そういうのないですか?こう胸のあたり…いや鳩尾のあたりがなんかこう、ゾワゾワザワザワするっていうか…浮き浮きするっていうか…そういう感じ…へへ…ね?…」
「いやいやいや…そんなの全くないですよ。波多野さんは、そんな感じがするの?」
「ま、まあ…はは…いやね、ほんの、ほんの少しですよ。なんか…ちょ、ちょっとだけですよお。ま、どうでもいいかって感じで…あはは…嫌だなあ、そ、そんな顔で見ないでくださいよお…あはは…」
波多野という人物は恐ろしく現実主義者で、慎重を絵に描いたようなプロデューサーだ。現場のリスクは出来る限り排除し、クライアントを不安にさせたり、気分を害するようなことは絶対にしない。予算にも時間にも厳格で、仕事に対して手を抜いたりいい加減な態度を極端に嫌う人物である。そんな彼の心の中にも明らかに何か大きな変化が起きているようだ。
「はいは~いっ、お待たせいたしました~っ!ハムとチーズとレタスのサンドイッチとコーラですう」
店員がクルクルと軽快なステップを踏みながら、器用にトレイにサンドイッチとコーラを乗せて運んできた。
サンドイッチは耳もそのままの普通の食パンにハムとチーズとレタスを挟んだだけのおざなりなものだったが、波多野は殆ど気にしていない様だった。
「まあ、腹が減っては何とかだからね~。まずは頂きましょうよ。ねっ」波多野はそう言ってサンドイッチにガツガツとかぶりつき、コーラをゴクゴク飲んで、大きなゲップをする…
「…で…川村さんは、これから、どうします?」
「そうねえ…やっぱり、一度家に戻るかなあ…家内や娘の様子も心配だし…波多野さんは?」
「俺は社に戻りますよお。何だかヒマになっちゃいそうだし、ジタバタしたってしょうがない感じだし…ま、今日はデスクで溜まった仕事でも片付けとこうかなあ…あ、でも川村さん、帰るっていっても電車もう動いてないんじゃないのかなあ…タクシーもいないし…」
「そうか…まあ、電車止まってたら、歩いて帰りますよ。そんな大した距離でもないし」
「じゃあ、俺の車使ってくださいよ。ねっ。どうせ俺は独りもんだから帰ったってしょうがないし。いざとなりゃあ、会社の車もあるし。ねっ、ねっ。そうしてくださいよお。どうせこんなのいっときのことなんだろうから、落ち着いたら返しにきてくれりゃいいですから…」
波多野はそう言って、車の鍵を押し付けてきた。
波多野の自家用車はビルの玄関前に不躾に停められていた。
波多野は機嫌良さそうに踊る様な足取りで、ビルの中に戻っていった。
一体この異常な状況はいつまで続くのだろうか…私は一刻も早く収まってくれることを祈りながら、借りた車で帰宅の途についた。
帰路の街の様子はさらに酷いことになっている…
街に溢れ出した人々は…踊っている…
もはや、どこかに向かって歩いている人は少ない。
街にはベースとなる音楽やビートが流れているわけではない。
みんなそれぞれ自分勝手に踊っているだけなのだ。
なのにも関わらず、何故かそこには明らかに共通するリズムがある様に見える。
単に周囲と同調しているだけなのだろうか…
この時はまだ、いずれは収まる現象なのだろうと思っていたが、実はこれはほんの序章に過ぎなかった…
この短編小説ではイラストレーターのTAIZO デラ・スミス氏に表紙イラストを提供して頂きました。
TAIZO氏のProfile 作品紹介は…
https://i.fileweb.jp/taizodelasmith/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
