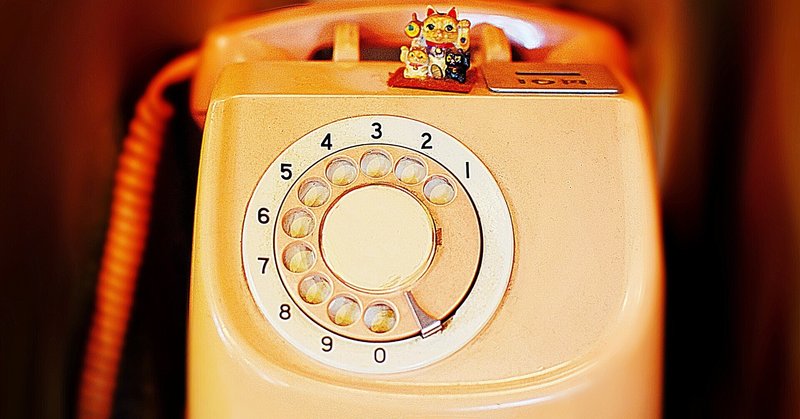
Photo by
subarasikiai
昭和はもうだいぶ前よ、はよ改正しよ
昭和に生まれ、昭和と平成で育ち、令和も経験中の私としても、昭和の残像が未だにあるのはちょっとどうかなぁと思うときが多々あります。
「制度変化が多くの人に納得がいくように表れるのには一世代かかる」。バブル崩壊後の「失われた20年」というフレーズに異を唱え、「移りゆく30年」と表現したのは制度分析で知られた経済学者の青木昌彦氏だった。
色々な制度が旧態依然のままであるというのが趣旨のこの記事ですが、まさに私もそう思います。
私たちにとって、コロナはかなりの災厄ではあるものの、多くの変化を受け入れる素地になっていると感じています。
「第3号被保険者」という制度や終身雇用を補強する法制や税制、デジタル化への対応が進まない霞が関などの事例を挙げているが、見渡せばもっともっとあります。
近現代の日本は2回、まったく新しい制度づくりに成功している。
1つは明治維新、2つ目は敗戦後の経済復興である。維新から敗戦までが77年、22年は敗戦から同じ77年にあたる。いずれもリーダー層の交代とセットだった。その意味でも昭和の残像と決別し、令和の国家像を示す頃合いといえる。
コロナからの復興がその77年目にあたるといいなと思っています。ちょうど、衆議院も解散しましたし、リーダー層の交代もあるかもしれません。現状に合わないものはどんどん改正して行ってほしいなと思うばかりです。
<改正>
まちがいや不十分な点を直して、よくすること。具合の悪い点などを変えること。
大河ドラマの渋沢栄一は、大蔵省改正掛に所属して、発案と実行をほぼ同時に進める物凄いスピード感で進めているのをみると、同じ日本人だし出来ないことはないと思うんですよね。
この記事を読んでいただいたみなさまへ 本当にありがとうございます! 感想とか教えて貰えると嬉しいです(^-^)
