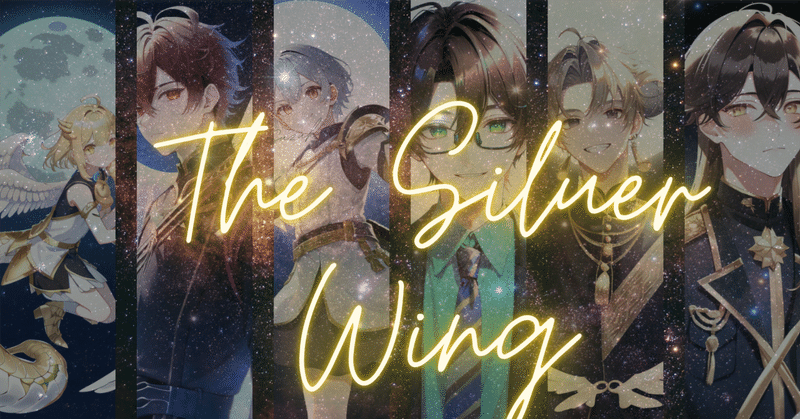
【小説】シルバー・ウィング《1》ジャンププラス原作大賞エントリー作品(9689文字)
《プロローグ》 如月直子①
あの日に美しく輝いていた月の光を、私は今でも覚えている。
両家顔合わせの食事会が終わり、車で帰路についたあの夜。ウインド越しに見えた月は、まるで自分のことを追っているかのように見えた。
「こんな可愛らしいお嬢さんが、我が家の娘になるなんて嬉しいですね」「入籍は直子が大学を卒業したらすぐに……」 「あと1年ですね」「なあに、あっという間ですよ」「式場はこのホテルの1フロアを貸しきって……」「そうそう子供の数は……」
「…………」
そんな月を見つめながら、私はさっきまで聞いていたお互いの両親たちの会話を思い出す。自分たちのことを話していたのにも関わらず、私の耳には何故か他人事のように響いていた。
もっとも、私のことを『お人形さん』にしたい両親にとっては、このぐらいの感覚が丁度いいのであろう。
「何だか実感が沸きませんね」
未来の『夫』となる男性と2人だけになった時、私は苦笑いをしながら口を開いた。
「そうですか?」
そんな返答をする彼は、私以上の『お人形さん』だ。一見お似合いのようだが、この2体の『お人形さん』は、お互いの事について一生分かり合えないような気がした。
私の気持ちを慮っているのは、月の光だけ……。
早く部屋に戻って一人になりたい。そしてベッドに入り、一刻も早く夢の中へと心を踏み入れたい。そこだけが自由になれる私の唯一の場所だった。
部屋へ戻った私は、左手薬指に輝いている指輪をおもむろに外す。
『……これは今日の記念に。直子さん、結納の時には改めてきちんとしたものを贈りますからね』
やがて義母になる人が私にそう伝えた。誕生石をあしらったゴールドの指輪は、家族旅行先のハワイで彼が買い求めたものだと言う。だだし率先して選んだのは間違いなく彼女だ。同調するようにうなずいた彼の中には『己』というものが全く見えなかったから……。
生れた頃から何不自由なく育った私は、何不自由ない生活を保障してくれる別の家庭へと送り出される。どう見積もってもかなり高価なこの指輪を『きちんとしていないもの』として仕分けることができる裕福な家庭へ……。
きっと私は幸せなのだろう。
それなのにモヤモヤした気持ちが日を追うごとに私の中で膨らみ続けている。
「…………」
私はその指輪を暗い部屋の隅に思い切り投げつけた。数時間前に満面の笑みで受け取った私がこんな非常識なことをしているなんて、あちらの家族は夢にも思うまい。
それが私の精一杯の抵抗。そう、精一杯の……。残念ながら、指輪を窓の外へ放り出すだけの勇気は持ち合わせていない。だって明日になれば、あの絨毯の上に転がっている指輪を自分の指に戻し、『結婚を指折り数えて待っている幸せな娘』を演じなくてはならないのだから。
幸せってなんなのだろう。
以前、信頼できる大学の友人に、この正体不明の『モヤモヤ』について相談したことがある。
「もしかして直子は他に好きな男性がいるの?」
その時の私は反射的に首を横に振った。小学生の頃から『親が決めた相手としか結婚できない』という現実を知っていた私は、恋愛に対して完全に諦めモードだったからだ。そんなこともあり、異性と関わることは極力避けていたつもりだった。
しかし、友人の前では完全否定したものの、『他の好きな男性』というワードを聞いた瞬間、私の脳裏にヒトの輪郭が現れ、今度は心の中がザワザワしてしまったのだ。
どうして!? 私は周りに誤解されないよう、慎重に行動していたはずなのに。
「…………」
まだ部屋の明かりはつけていない。
私は部屋の隅に転がり、月光に照らされた指輪を見つめながら、答えが出ないと分かっている疑問を自分に問いかけていた。
「……えっ?」
そんな私は、目の前で起こっている1つの事実に気がつく。今、空に浮かんでいるであろう月の位置では、この部屋に月光が降り注ぐハズがないことを……。指輪の光がそれを教えてくれた。
私は窓を開ける為に駆け寄り、鍵に手をかけた。そしてバルコニーへ一歩踏み出した瞬間!!
「……!?」
月光が眩しい!?
光で視界を遮られた私は、手のひらで顔を覆いながら、目が慣れるのを待った。そして、おそるおそる指の隙間から光の正体を確認しようと試みる。
「……羽?」
月光に反射していたのは大きな『翼』だった。それだけでも驚くべき事態なのに、その翼を広げていたのは、鳥ではなく人間の男性だったのだ!
いや、翼を持ち、ありえないバランスで手すりに立っている彼が人間であるわけがない。
天使!? ……そう私の目の前には天使がいた。
私はスローモーションで両手を下ろし、茫然とした目で『天使』を見つめる。この時に私が所有していた感情は、純粋な驚きのみで、恐怖は伴っていなかった。
何故なら私は彼に対して、以前も会っていたような感覚を覚えたからだ。
以前に!? 『天使』と会うこと自体があり得ない話なのに、それを覚えていないなんて、もっとあり得ない……。
それでも『私の中の私』からは懐かしさが込み上げてきて、勝手に涙が込み上げてくる。
「……直子」
『天使』が私の名前を口にした。
私はもう驚かない。そうだよね。あなたとは前にも会っていたんだよね。私はその声を何度も聞いていたんだよね。
夢の中で!!
現実ではずっとぼやけていた輪郭と、封じられていた眠りの中での記憶が一致する。
だから私も親しみを込めて彼の名を呼んだ。
「『テラ』……」
テラ①
俺は自分が思っている以上に直子に惹かれていたようだ。
彼女を初めて見たのは7年前。『悪夢狩り』を終えた俺は、何の気なしに夢の主である如月直子の寝顔を覗いた。
頬に涙の跡が残る彼女。夢に触れれば、その人間のバックグラウンドをある程度把握することができる俺は、直子が『家』に縛られ、心の底でもがいていることを知った。
自分と似ている。
直子の美しい容姿が忘れられなかったのも事実だが、彼女を特別視することとなった一番の原因は、この『共感』だった。
「いい加減にしろよテラ! 確かに俺たち『シルバーウィング』は人間たちの心の安定で栄えている突然変異の夢魔一族だ。だけど、お前があの女の子にしていることは、ただの私情だぞ!」
『悪夢狩り』のパートナーで、幼馴染みでもあるタスクは、とうとうキレてしまい、思いきり声を荒げた。無理もない。俺は時間が許す限り直子の元を訪れ、夢で彼女の心を癒しているのだから……。
「……すまない」
「それにお前は、下っ端夢魔の俺と違って、王族の一員なんだ! 未来の国王が人間の女にうつつを抜かしているなんて周りが知ったら、大変なことになるぞ!!」
「……すまない」
「だ・か・らっ!!……」
「タスク……すまない」
「…………」
タスクの拳から力が抜ける。そして彼はその手のひらを、優しく俺の肩に乗せた。「……ったく、テラのバカやろう」と呟きながら……。
「タスク」
「その……何かあったら、必ず俺に言え」
国民のほとんどが王位継承権第1位の俺に萎縮する中、身分を無視して、俺の為に言いにくいことを口にする彼は、大切な存在だった。
「ありがとうタスク」
「よかっただろ? 俺が友達で」
「自分で言うなよ」
俺たちはお互いを見て笑った。
ーー夢は便利だ。
現実であればあり得ない事態も、夢の中では、ほとんどの人間がそれを問題にすることはない。
だから目の前に現れた夢魔の俺を、直子はすんなりと受け入れてくれた。
俺たちは夢の中で語り、夢の中で笑い、そして夢の中で心の距離を近づけた。
ーー本当に夢は便利だ。
ほとんどの夢は忘れられてしまうから。
忘れてもいい。この儚い場所で与え続けた夢の一欠片が、彼女の心の奥底に温かく残るのであれば……。
そして時間は過ぎて行く。
世代交代の時期が近づくにつれて、俺は昔のように、自由な時間を確保しづらくなっていた。直子に会いに行くことは勿論、タスクとの『悪夢狩り』すらかなりのご無沙汰だ。
(……直子)
周りのお偉方は、『1日も早く、よい伴侶を……』と口うるさい。周りから祝福される結婚は、俺にとっての義務だ。それは直子も同じ……。
(もう、俺たちの『ままごと』は終了なのか……)
だからあの月夜の晩、彼女にそっと別れを告げる為に、俺は人間界へと舞い降りた。
そこで見たのは、自分の運命を無理矢理受け入れようとしている直子の姿……。
「…………」
立ち去ることが出来ない。
そんなウジウジした自分が側にいることを彼女に教えてくれたのは、冷たく光る2月の月だった。
「本当は……別れを告げに来た」
それでも俺の胸に飛び込んできた彼女を、どうしたら拒むことができよう!?俺は両腕を広げ、彼女の身体を包みこむ。
「……テラ」
夢の中でさえ、プラトニックな関係だったのに、俺たちはこの日、現実で一線を越えた。
月の光だけが、それを見ていた。
お互いの愛を確かめ合ったにも関わらず、あれから直子に会いに行けない日々が長いこと続いていた。
夢魔と人間が結婚できないことは百も承知だ。それでも俺は己の運命に限界まで抗うことに決めた。未熟な奴だと嗤うなら嗤えばいい。
そんなある日、俺はやっと人間界へ行けるチャンスを見つけた。タスクも協力してくれるという。唯一の理解者である彼に感謝しながら、俺は人間界へ向かった。
「おやっ?」
彼女の気配を感じられない家を見て、俺は首を傾げる。仕方がないので、自分の翼から1本の羽を抜き、彼女の姿を思い浮かべながら夜空に飛ばした。
羽が案内してくれたのは、直子の家とは似ても似つかない、小さな一軒家だ。
「直子?」
確かに直子はその家にいた。前に会った時よりも服装が地味になった感が否めないが、俺に気がついた時に見せた笑顔は相変わらず綺麗だ。
「テラ……」
その直後、彼女は俺に衝撃的な事実を口にした。
「テラ、私ね、お腹に赤ちゃんがいるの。あなたと私の赤ちゃんが……」
如月直子②
「出て行きなさい。あなたの顔なんか見たくもない」
私は両親から、あっさりと見放された。
テラと愛しあったあの夜以降、私はこの結婚に乗り気でないことを、露骨な態度で示すようになった。
初めはよくある『マリッジブルー』だと決めつけ、『大した問題ではない』と楽観していた両親だったが、私の生理が止まり、市販の検査薬で陽性と判断されたことで、ようやく気づいてくれたらしい。
もう私は彼らの『お人形さん』ではないと……。
家を飛び出した私は、歩道橋の上から、夜の道路に流れている車を眺めていた。
眼下に現れては去り、現れては去ってゆく車のヘッドライトが不規則に時を刻んでいるように見える。
「…………」
家を出たところで私に行く場所などない。人間と夢魔が一緒になることは出来ない。しかし私はテラ以外の男性を選ぶことはできない。ならば私が出来ることは1つしかない。
それはこの世から消えること……。
『死』が永遠の眠りにつくということならば、夢魔の彼に近づけるのではないか?
かなり強引ではあるが、今の私を突き動かすには充分な仮説だ。
ただし、私の身体に宿ったもう1つの命にだけは、心から謝りたいと思う気持ちが残っていたが……。
ごめんね、私の赤ちゃん。痛みは私が全身で受け止めるから。もしも神様が許してくれるなら、向こうの世界で一緒に生きようね!!
それ以外の悔いはない! さよなら…私が生きた世界。
そんなことを考えながら、私は歩道橋から飛び降りるタイミングを見計らっていた。そして唾を飲み込み、身を乗りだそうとした時……、
ーーダメ!!!!
若い女性だろうか? 私の耳に飛び込んできた声に一瞬固まる。
その僅かな瞬間で、私は誰かに腕を掴まれた。
「君、落ち着きなさい!!」
「!?」
その手の持ち主は、女性ではなく年輩の男性だった。私は混乱したものの、彼の静止にだけは素直に従う。
「……私……私は……」
私はその場にへなへなと座りこんでしまった。そして悔しさと安堵が入り交じった、なんとも言えない気持ちが涙を押し出す。
そんな私を見て、彼は言った。
「ウチへ来なさい。まずは温かいお茶でも飲もう」
男性は名を結城源三郎と告げた。ここから10分くらい歩いた所の一軒家で、奥さんと孫の3人暮らしだという。そして定年退職後は、こうやって夜の街の見廻りボランティアをしているらしい。
「ほぼ毎日見廻りをしてはいるが、あの歩道橋、普段の私なら近づかない場所だったよ……」
そう言って結城さんは、空を見上げる。そして「不思議なこともあるもんだな……」と独り言のように呟いた。
「不思議……ですか? 何が?」
「娘の声がしたんですよ。『お父さん、急いであの歩道橋へ行ってくれ』って……」
「えっ?」
そのニュアンスで、彼の娘はもうこの世にいないことがわかった。
「ウチの娘……飛び降りたんです。あの歩道橋から……」
「!?」
さっき私の耳に響いた女性の声が再び甦る。もしかして……? そう、あの時歩道橋にいたのは、私と結城さんだけだったのだから……。
「本当に……不思議なことがあるもんですな」
結城さんは、また同じ言葉を繰り返した。
結城家に着くと、彼の奥さんである志穂子さんが出迎えてくれた。
源三郎さんがことの成り行きを話すと、彼女は驚き、涙を流した。そして……、
「甘酒は好き? ちょうど今、作ってたの」
この夫婦は私の両親と違って、オーラの温度があたたかい。私は素直に首を縦に振った。
その時、奥の部屋から元気な赤ちゃんの泣き声が聞こえてきた。
「あらあら、なっちゃんは本当に寂しがり屋だわね。なっちゃーん! 待っててね! ばあば、今行くからねぇ……さぁさ、お嬢さんも上がって上がって」
「は、はい」
そういえば源三郎さんは、奥さんと孫の3人暮らしだと言っていたっけ……。さすがに赤ちゃんだとは思っていなかったので、私は心の中でかなり驚いていた。
赤ちゃんは女の子だった。
「……可愛い」
「『夏芽』っていうの。ウチの庭にある棗の木から名付けたのよ。この子のほっぺたが、棗の実のように真っ赤だったから……。それにね、花も目立たないけど、とっても可愛らしいの。でも『棗』の字は名前に使えなかったから、季節の『夏』と新芽の『芽』で『なつめ』」
「素敵な名前ですね」
夏芽ちゃんは志穂子さんに抱かれると、ピタッと泣き止んだ。
こんな可愛い子を残して、彼らの娘さんは命を断ってしまったのか……。もっとも私は私で、赤ちゃんを道連れにしようとしていたのだから、彼女について何も言う権利はない。
志穂子さんは、そんな私の心を読んだかのようにポツリポツリと語りだした。
「娘……美和子っていうんだけど……美和子の夫だった人が、妊娠中に愛人作って、2人で駆け落ちしてね……、それでも夏芽が生まれて、頑張っていたんだけど、やはり精神が不安定になっちゃったのよ。……でね、ある日突然、離婚届が一方的に送られてきて……夏芽を置いていなくなったと思ったら……」
志穂子さんは、そっと涙を拭いた。
「も、もういいです! ごめんなさい。辛いことを思い出させて。…………実は……その、……私、飛び降りる直前に若い女性の声を聞いたんです。『ダメ!』って……。源三郎さんは美和子さんの声を聞いて、あの歩道橋へ駆け付けてきたと言っていました。私を止めたのも娘さんだと思っています。……きっと、自分と同じことをしてはいけないって、必死に止めたんだと思います」
「…………」
志穂子さんは驚いて目を見開く。源三郎さんも「確かに俺にも聞こえた。あれは美和子だった」と呟いた。
夏芽ちゃんだけが、無邪気な笑顔を咲かせる中、私たち3人は、それぞれの思いと共に涙を流す。
「…………ねぇ直子さん、今度はあなたの話を聞かせてくれる?」
涙の跡を残したままの志穂子さんが、私の顔を優しく見つめた。
「はい」
話を聞いた源三郎さんは、せめ私たち親子の確執だけは何とかしたい……と思い、次の日に如月家を訪れたが、両親は聞く耳を持ってはくれなかった。
「源三郎さん、ありがとうございます。でも、こうなることは分かっていました。あの人たち、今は高3の妹に『家』の全てを賭けているはずですから、私は邪魔なんですよ」
「う~ん、俺らには理解できない世界だね」
彼は眉間にシワを寄せて首を傾げたが、急にニッコリと笑った。そして「じゃあ直子さんは、このままウチで暮らすといい。美和子が助けた娘さんだ。これも何かの縁だよ」と言ってくれた。
そして今に至る。
ずっと腕を組んで私の話を聞いていたテラは、私を抱き寄せ涙を流した。
「直子、すまない。君一人に辛い思いをさせて……」
「ううん、テラ……私は幸せだよ」
「直子……」
「だからテラ」
「何?」
「私たち……会うのはこれで最後にしましょう」
「直子!!??」
これは再び生きることを決めた私が、テラに再会したら伝えようと思っていた言葉だった。
「私にはこの子がいる。結城さんたちもいる。でもテラ、あなたの国にはあなたの代わりはいない」
「…………」
「あなたの国の幸せはあなたにかかっているんだよ」
「…………」
「私なら大丈夫。あなたの血を分けたこの子がいるから」
私たちの愛は無力だ。
出来ることと言えば、結論を先延ばしにすることだけ……。
そして責任を感じているテラの方からピリオドを打つことはできない。
ならばそれは私の役目だ。
「直子……本当にすまない」
「謝らないでテラ。私はあなたに感謝している。そして愛してる」
「俺もだ」
テラの両腕に力が入る。私も彼の背中に腕を回し、最後の抱擁をした。
そして、身体を離した私たちの間に雪が舞い込んでくる。
「雪だ」
「雪だね。4月の半ばだっていうのに」
夜空から落ちてくる雪は、まるで数千数万の白い羽のようだった。
さよなら……テラ。
あれから7ヶ月が経った。
私は分娩台で、彼の子をこの世に産み出そうとしていた。苦しみは覚悟していたハズなのに、想像を越えた痛みで何度も挫けそうになる。
「直子さん、頑張って!!」
志穂子さんがいなければ、痛みにも不安にも耐えられなかったに違いない。
そして担当医師の『いきんで下さい!』という言葉で、私は全身の力をふり絞る。
その途端、赤ちゃんの声が聞こえてきた!!
「おめでとうございます。元気な男の子ですよ」
テラと私の子供!! その顔を見た瞬間、私は涙が止まらなかった。
名前はもう決めてある。8ヶ月の段階で男の子だと判明していたので、テラを思いながらあれこれ考えていた。
そしてあちらの国で立派な君主になっているであろう姿を想像した時、1つの文字が頭に浮かんだ。
「はじめまして……卿」
テラ②
あれからかなりの年月が過ぎた。俺はこの国の王となり、政に忙殺される毎日を送っている。
もっともこの忙しさが、結婚を急かす小うるさい大臣連中を黙らせる格好の理由にはなっているのだが……。
直子と子供のことを1日でも忘れた日はない。
しかし今、この国に取り巻いている不穏な空気のことを考えると、直子と離れて正解だったかもしれない……と思っている。
(『ブラッド』か……)
『ブラッド・ウイング』とは、俺たち『シルバー・ウイング』同様、突然変異の夢魔一族だ。
普段は白いが、月光を浴びると銀色に輝く翼を持つ、俺たち『シルバー・ウイング』。
それに対し、夢を通して人間の命を吸い取る黒い翼の種族『ブラッド』には、『あの黒には人間の血が染み込んでいる』という言い伝えがあり、それがこの呼ばれ方の由縁とされている。
人間に安らぎを与える種族と殺戮種族が敵対しない訳がない。奴らと俺たちの歴史の中では何度も戦いがあった。
ただし『ブラッド』を敵とする種族は『シルバー』だけではない。どんな形であれ、人間と共存している夢魔にとって、奴らは共通の粛清対象だ。
そのため、『ブラッド』の勢力は、そこまで拡大することなく、今まで均衡を保ってきた。
(それなのに……)
最近、国のあちこちで『ブラッド』の仕業としか思えないような事件が相次いでいる。まるで、こちらの手の内を知っていると、嘲笑うかのように……。
「テラ様っ!!」
突然、俺の耳に聞き慣れた声が飛び込んできた。
「ティコか?」
ティコは俺が信頼している戦士の1人だ。小柄で童顔だが、これでも成人している女性である。そして剣の腕前はピカ一で、彼女の見かけだけで舐めてかかると大抵の男は痛い目に遭う。
そのティコが、腕から血を流した姿で俺の前に現れた。
「お見苦しい姿を……申し訳ありません」
ティコは今日、『対ブラッド・ウイング』のサブリーダーとして敵地に向かっていた。
「何があった!?」
「『対ブラッド・ウイング第1部隊』、自分以外の戦士は全員命を落としました」
「全員!? ではタスクもか!?」
今回のリーダーはタスクだ。ティコもそうだが、タスクが殺られる姿など、俺には想像ができない。
「テラ様……驚かないで下さい」
「どうした?」
ティコは俺から目をく逸らすと、無理矢理口を開いた。
「……この傷は、タスク様につけられたものです。おそらく我が国の情報は、彼によって筒抜けの状態であると……」
「!?」
「よぉ君主さま。あのティコはここに来たんだろ?」
ティコを逃がした後、タスクが俺の前に現れた。
この部屋にたどり着くまで、彼は何人の近衛兵たちの命を奪ったのだろうか。そう、ティコだって、タスクがその気になれば間違いなく殺されていた。彼女をあえて生かしたのは、傷だらけの姿で真実を伝えさせ、それによって俺に強いダメージを与えるためだったのだ。
「……あぁ」
「驚いた?」
「当たり前だろ! ……で、オマエはいつから俺を裏切っていた?」
「気持ちだけなら子供の頃からだよ。俺は恵まれているのに、悲劇の主人公ぶっているオマエが嫌いだった」
「!?」
「本当に自分の環境に不満があるなら、身体中の血を抜く勢いで全てに抗ってみろ! っていうんだよ! あっ? 聞いてるか? お坊っちゃん」
「…………」
「ほら、剣を構えろよ。俺は今まで陰でコソコソしていたけど、テラ! お前だけは正々堂々と殺る! 言っておくが、お前が知っている以上に俺は強いぞ。この日のために力はセーブしておいた。」
「そうか……。仕方ない」
「お前の血はここで絶やしてやるよ。……よかっただろ? 俺が友達で」
「……」
俺は自分の翼から抜いた1本の羽を剣に変えた。そして椅子から立ち上がり、タスクに刃を向ける。かつて笑い合い、励まし合った大切な友に!!
おそらく俺は負ける。タスクの本心を見抜けなかった俺にはふさわしい最期だ。しかしこの国のシルバー・ウイングたちは守らなくてはいけない。
だから、俺は1つの賭けをする。
タスクが剣の実力を隠していたように、俺もヤツには1つだけ隠し事をしていた。それによってこの賭けは可能になったのだ!
ティコを逃がす際、俺は人間界に血の繋がった子供がいると告げた。
「俺が死んだら、人間界でその子を見つけて新たな象徴とし、お前たちで国を取り戻せ」と……。
自分の血を嫌っていた俺が、その血にすがるなんて笑い話でしかない。そして直子! 本当にすまない! この国の崩壊はいずれ人間界にも悪影響を及ぼす。 そうならない為には俺たちの子が最後の希望だ。
直子……もう一度だけ会いたかった。
さようなら。
如月卿①
桜が舞う中、俺は高校の入学式会場へと向かっていた。
「ん!?」
「どうしたの卿?」
急に立ち止まった俺に、母は首を傾げる。
「声が……聞こえた」
「えっ?」
「『さようなら』って」
そう言って俺は空を見上げる。
青空から落ちてくる桜の花びらは、まるで数千数万の羽のようだった。
《2》↓に続く↓
