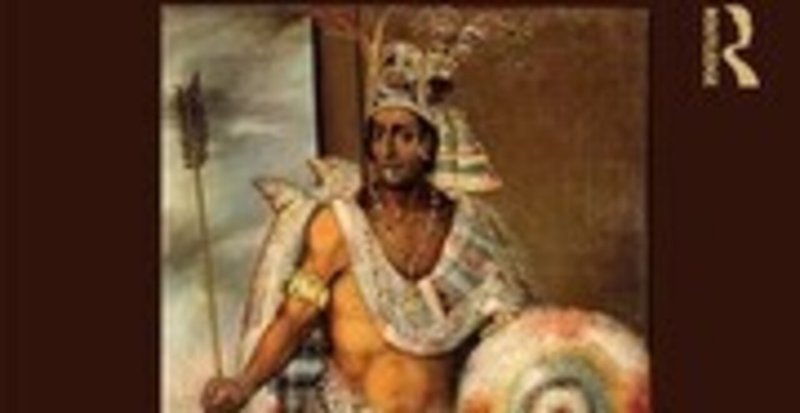
豊臣秀吉が天下統一していたころ、フランスのアンリ4世はなにをしていたのか?同時代人という切り口で歴史を見ること
Real Lives in the Sixteenth Century:
A Global Perspective
「16世紀を生きたそれぞれの人生」
By Rebecca Ard Boone
April 2018 (Routledge)
本の紹介の前に、欧米の出版社では当たり前のインプリントというものについて、少し。
たとえば、この本の出版社はテイラー・アンド・フランシス(Taylor & Francis)なのだが、インプリント(imprint)はラウトレッジ(Routledge)だ。
洋書業界に入ったら、まずこの出版社とインプリントを理解しなければいけない。和書にはないシステムだもんね。
ウィキペディアにちょうどいい説明があったので、そのまま引用する。
「出版業界におけるインプリント(英: imprint)とは、欧米の出版社が出版物を刊行する際に用いるブランド名。ひとつの出版社が複数のインプリントを持っていて、大きな組織であれば出版物の内容によってインプリントを使い分けている。」
どういうことかというと、たとえば先ほどのテイラー・アンド・フランシスでは、人文社会科学関係の書籍はラウトレッジというインプリントから刊行される。自然科学・工学関係であればCRCプレス(CRC Press)というインプリントから刊行される。
インプリントを見ただけで、どういう分野の本かというおおざっぱな把握ができるというわけだ。
なぜそのような仕組みになったのかというそもそものはじまりはよくわからないが、ラウトレッジもCRCプレスも元々は独立した出版社だった。それが、テイラー・アンド・フランシスに買収されて、インプリントとして社名が残った。そういうことはよくある。ウィキペディアにも書いてある。
「合併・買収された出版社の名前がインプリントとして残る場合もある。インプリントがさらにそのインプリントを持つこともある。」
そうそう。ラウトレッジのなかにも、じつはインプリントがあったのだ。カーゾン(Curzon)とか、キャベンディッシュ(Cavendish)とか。それはラウトレッジが買収した出版社だった。でも、そのラウトレッジがテイラー・アンド・フランシスに買収された。カーゾンもキャベンディッシュも最初のころはインプリントとして名前が残っていたが、次第に消えていった。
欧米の出版社では、私の印象では2000年ごろから合併・買収がさかんになり、小さい出版社は、ちょっと成功するとたちまち大手の出版社に買収されるようになった。
テイラー・アンド・フランシスは、どんどん小さい出版社を買収していった。なんでも飲みこむなぁ~。うわばみみたい。というか、あれだな、「千と千尋の神隠し」でごちそうだけでなく、なんでも飲みこんでいくようになる、カオナシ。私と同僚はテイラー・アンド・フランシスをひそかに「カオナシ」と呼ぶようになった。
アーススキャン(Earthscan)という環境問題についていい本を出していた出版社も、テイラー・アンド・フランシスに買収されてしまい、いつのまにかインプリントからも名前が消えた。大手に吸収されると、そのいい部分というのが埋もれてしまう。総合出版社のなかの、環境問題関係の書籍、という一部門になってしまうと、まったく目立たなくなってしまうのだ。
そしてシビアな話としては、買収された出版社の社員はほぼクビになっている。買収した出版社にそのまま移った人はごくわずか。いままでコンタクトを取っていた人が、買収されたとたん、いなくなってしまうのは、なんとも言えない嫌な気持ちだ。
欧米の出版社の合併・買収ってすごい。まさに弱肉強食。数年前にペンギンブックス(Penguin)とランダムハウス(Random House)という大手出版社が合併してペンギンランダムハウス(Penguin Random House)ができたときは、たいそう話題になった。そのペンギンランダムハウスが、今度は大手出版社のサイモン・アンド・シュースター(Simon & Schuster)を買収するらしい。買収額は200億ドル以上。
買収金額もすごいけど、名前、どうするんだろう?ペンギンランダムハウスってだけですでに長すぎるけど。でも、サイモン・アンド・シュースターだって歴史と伝統ある出版社だからねー。
というわけで、やっと本題。
今回紹介する本は、16世紀に活躍した人物を、1対1で対比させて、その人生というか生き様を比較考察してみようというユニークな企画。
まずはじめに取りあげられるのが、豊臣秀吉とフランスのアンリ4世。
豊臣秀吉は、戦国時代の人だから、だいだい16世紀後半かなぁとわかるが、アンリ4世ってだれだっけ?
調べてみると、アンリ4世はブルボン王朝初代の王で、フランス絶対王政の基礎を築いた人らしい。アンリ4世のあと、ルイ13世、ルイ14世とつづき、ルイ14世のとき全盛期を迎える。ヴェルサイユ宮殿をたてたのは、ルイ14世だ。
豊臣秀吉は1537年生まれ、アンリ4世は1553年生まれ。秀吉より16歳年下だ。
1582年、明智光秀が本能寺で織田信長を倒したとき、秀吉は備中から京都にとってかえし、すぐさま光秀を討った。そのとき、アンリ4世はまだフランス国王にはなっていなかった。イベリア半島北東部のナバラ王国というところの王であり、アンリ4世が王になるのは、1589年のことだ。
秀吉は、1583年に大阪城を築き、1585年には関白になっている。秀吉が天下統一したのは、1591年。アンリ4世がフランス国王となってから2年後のことだ。秀吉は戦国時代という戦乱の世を生きてきたが、アンリ4世もユグノー派とカトリックが争う30年戦争という乱世に生きていた。
たしかにこの2人を対比して見ていくのはおもしろいかもしれない。日本史と世界史って別々に勉強したから、秀吉と同時代に誰が生きていたのかってぜんぜん意識してなかった。
秀吉とアンリ4世のほかには、オスマン帝国のスレイマン1世の皇后、ロクセラーナと魏の文帝曹丕の妻、文昭皇后。コンゴ王国のアフォンソ1世とイギリスのエリザベス1世。ローマ教皇のクレメンス7世とアステカの第9代君主、モクテスマ2世。
エリザベス1世ぐらいしか知らないけど、みな16世紀を生きたひとかどの人物なんだろう。こういう比較っておもしろいなー。
こういう角度から、歴史に興味を持っていくのもありだと思う。
これ、16世紀だけじゃなく、17世紀、18世紀ってずっとやっていけるじゃん!と思ったら、そもそもがそういう企画のシリーズだった。Real Lives in Global Perspectiveというシリーズで、16世紀から現在まで、同時代で似たような境遇だけど、地理的には離れたところにいる2人の人物の生き様を比較して見ていくらしい。
さて、17世紀以降は、どういう人物をとりあげていくんだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
