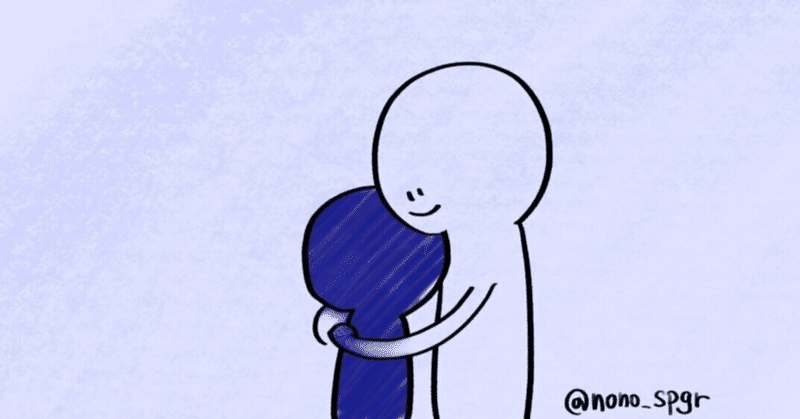
悲しみが人と人を結びつける
この言葉は、以前休みの日に映画のパンフレットに書いていた言葉だ。
とある音楽教師が、寄宿制の学校に赴任する。しかし、その学校はいわゆる「問題児」が集まった場所と言われている。そのような場でも、少年達を「音楽」の力で教育させ、最後は人々を感動させる素晴らしい楽団に創り上げるのだ。
ざっくりではあるが、話の大筋はこのような感じ。もちろんその他にも、様々な人との出会いや葛藤の日々も描かれているが、それはこの作品を観て直接感じてほしい。言葉だけで言い表すことはできない。
私はこの映画を観て、色んな感情が込み上げてきたが、やはり今の仕事と結びつけて考えることが多かった。それを感じたのがこの言葉だった。
人と人を結びつけるのは、もしかしたら悲しみではないだろうか
実際この映画での少年達は、「問題児」と言われているが、本当に全員がそうなのかといえばそうではない。時は第二次世界大戦後の1949年。戦争で両親を亡くした人もいる。親が「また土曜に迎えに行く」と言ったが一向に迎えに来ない子どももいる。つまり、周りの環境や当時の時代背景が原因で「悲しみ」を抱えているのだ。
そして、赴任してきた音楽教師もそうだ。元々は音楽家になりたかったがなれなかった。そのため、舎監の仕事を「仕方なく」しているというのだ。
ここに共通点がある。少年達の心の「悲しみ」と音楽教師の夢を打ち砕かれた「悲しみ」が重なっているのだ。この悲しみの共有こそが、少年達の心をぐっとつかみ、成長へと導くことができたのではないかというのだ。
これを思い返してみると、確かにそうだと感じる場面がある。それは、面談などで「悩みを聞いてくれて嬉しかった」「話を聞いてくれて嬉しかった」と生徒から話しかけてくれたときである。そしてそれを話してくれたときは、教師がいろいろアドバイスしたときではなく、ほとんどが、話を聴き、共感した時だ。
逆に、子どもたちが悲しみを感じていないときはどうか。「何か悩みはある?」「気になることはある?」と聞いても「ありませ~ん」とすぐに言う人だ。確かにそのような子どもたちに対しては、深い話はなかなかできないように思える。なぜなら子どもたちは心も体も充実しているから。話を聞いてもらう必要はないと感じているからだと思える。(言葉では大丈夫と言っているが、実際はそうではなかったりする。それに気づけるかどうかは本当に難しいのだが)
「悲しみの共有」はそんなに簡単にできることではない。私自身の「悲しみ」は何かと言ってもすぐに答えが出てくるものではない。しかし、子ども含め色々な人と接してみると、それぞれの人には、その人しか分からない「喜び」「悲しみ」があるように思える。それを100%分かることは無理だが、私は少しでも「悲しみ」に寄り添える人になりたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
