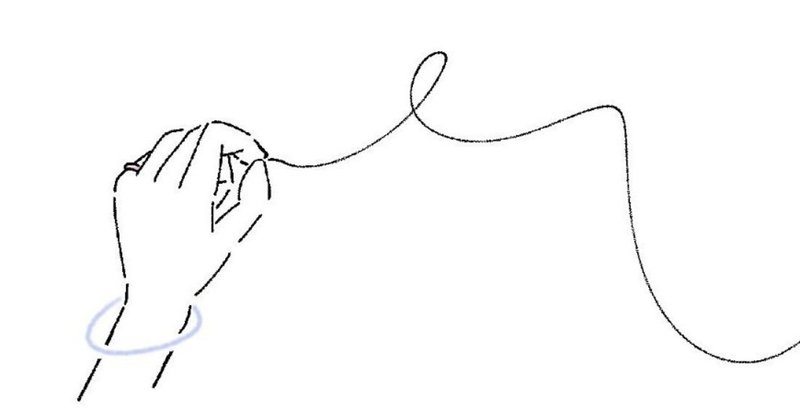
青いミサンガと、16の夏。
「じゃあ、行ってくるね」
「うん、健闘を祈る」
閉祭宣言。熱気と興奮に包まれた校庭。
まだ火が完全に消えていないキャンプファイヤー。
それに名残惜しそうに群がる生徒たち。
祭りのあとの恒例行事が行われているのを横目に、
わたしは一緒にいた友人にそう告げてひとりで班室棟へと向かった。
心の中で、イチかバチかの小さな賭けをして。
◆ ◆ ◆
はじまりは、雨の日だった。
自宅からは少し離れた隣の市の公立高校に入学したわたしは、中学に引き続き演劇班に入ることになった。
ちなみにわたしの地元・長野で進学校とよばれる高校では、部活のことを班活とよぶ。たとえば、吹奏楽の略称は「すいぶ」ではなく「すいはん」なのである。
わたしはこの演劇班で、ひとりの先輩と出会った。
野球部でもないのに坊主。独特な話し方。顔は整っているけれど、おしゃれや恋愛には無頓着そうで、とにかく変な人という印象だった。
その先輩は演劇班の班長で、3年生。
なぜかわたしは、会ったそのときからその人を好きになるような予感がしていた。
そして案の定、あっさりと好きになってしまった。
雨の中、傘を持っていなくて困っていたところに、ほい、と傘を差しかけて駅まで入れてくれたことがきっかけで。
人生初の相合傘にわたしの心臓は破裂寸前、ときめきはピーク。話しているうちに先輩の独特な感性と演劇に対する思いに惹かれ、気づいたらもう好きだった。
5月を過ぎるとさっそく文化祭の本番に向けて日々稽古が始まった。先輩は演出。わたしは、主役に選ばれた。
演じるのは狐が化けた男性家庭教師。嫌みたらしく、かついやらしい。ほとんどの台詞が10行にも及ぶ長台詞で、とにかく難しい役だった。
稽古中、わたしは先輩に何度も怒られた。恥ずかしがっていて全く解放できていないと。
好きな人の前でさらけ出すことが恥ずかしかった。でも、可愛こぶっていたら余計に怒られるし嫌われる。乙女心と役者としての葛藤。
わたしは腹をくくり、「3歳児のように」という先輩の演出を受け入れ、全力で動いて、叫んだ。椅子と椅子の間を飛び回りながら、台詞を吐いた。
「いいじゃん」
そう先輩に言われたときは、涙が出るくらい本当にうれしかった。
もう、先輩の前で可愛くいるなんてどうでもよくなっていた。
大道具を作ったり、搬入したりしていたら嫌でも汗まみれになるし、日々の練習で食らいついていくことに必死だったから。最後のほうはもう、先輩に戦いを挑むような気持ちだったと思う。
おかげで、文化祭本番の舞台は無事成功。
いろいろと吹っ切れたわたしは、ちゃんと嫌みたらしくていやらしい家庭教師として、舞台上に存在することができていたようだ。
ほっと一息をついたのも束の間、わたしにはもうひとつ大きなミッションがあったことを思い出した。
後夜祭恒例、ミサンガ交換。
男女それぞれに違う色のミサンガが配られ、気になる相手と交換するという学校をあげてのビッグイベント。
そう、わたしのもうひとつのミッションは、後夜祭のあとに先輩とミサンガを交換することだ。
◆ ◆ ◆
ドクドク。
自分の心臓が大きく波打っているのを感じる。
演劇班と書かれた扉の前でそわそわとしながら立っていると、あらわれたのは見覚えのある坊主頭。
「おー、おつかれ」
「おつかれさまです」
声が震えた。
先輩の手首にミサンガは、ない。
やばい。さらに波打つ鼓動。
待ち伏せをしていた理由を聞くこともなく、部室の段ボールをがさごそとあさっている先輩の背後から、思い切ってもう一声。
「あの、先輩、もうミサンガって交換しましたか?」
わあ、言っちゃった。
どうしよう、どうしよう。
「あーこれ?あげるよ」
そういって、先輩はポケットから青いミサンガを取り出して、ほい、とわたしに渡した。
「え、いいんですか…?
ありがとうございます。」
意外にもあっさりと、それは手に入ってしまった。
そのときの先輩は、やけにやさしい顔をしていた。本番当日までずっとピリピリと厳しい顔をしていたから、その顔が何だか懐かしくて、やっぱり好きだなあとちょっと泣きそうになってしまった。
じゃあおつかれ、また来週なと言って先輩は班室を出て行った。
はああ。
うれしさと恥ずかしさと安堵の気持ちが一気にこみ上げて、へなへなと座り込んでしまった。
キャンプファイヤーで踊っている最中に見つけられなかったぶん、後夜祭のあとに先輩が班室に来るかどうか、イチかバチかの賭けだった。そして、先輩がすでに他の誰かとミサンガを交換していないということも。
そのふたつの賭けに、わたしは勝ったようだ。
気になる相手とミサンガを交換する。たったそれだけのことに、ドキドキしたり、そわそわしていた16の夏。
手首につけることはなんとなく躊躇われて、リュックのポケットにしまいこんだ。交換することは叶わなかった、自分のピンクのミサンガと一緒に。
◆ ◆ ◆
それから7年以上の年月が過ぎた。今わたしはもう、24の年だ。演劇は結局大学まで続けた。
文化祭のあと先輩に告白したものの、受験を理由に見事に玉砕。卒業とともに関西の大学へと行ってしまった。
人生で初めての告白は実らなかったけれど、けして忘れられない出来事として今も胸の中にある。先輩とは、むしろ卒業してから仲良くなり、わたしが上京してからは頻繁に連絡が来るようになった。ちょっと惜しいことしたな、って思っていたりして。
今でも帰省したタイミングや、舞台を観に東京に来たときに連絡をくれて、たまーに一緒にお酒を飲む。
あの頃は、先輩が自販で買ってきてくれた少しぬるいペットボトルのお茶で乾杯だったのに、今はキンキンに冷えたビールで乾杯してる。「お疲れさま」という掛け声は同じなのに、なんだか不思議だ。
話す内容といえば、あのときの舞台はこうだったとか、あの先生の演出はどうだったとか、今注目している劇団はどこだとか、結局演劇の話ばっかり。
でもそんな先輩の相変わらずな部分はやっぱり魅力的だから、そのまま変わらずにいてほしいなと思ったりする。
どんなに時がたっても、夏が来ると先輩のあのやけにやさしい笑顔を思い出す。そして会うたび、少し年をとった先輩の顔に、あのときの笑顔を重ねてしまう。
やっぱり、何かちがうな。
でも、それでいい。
すてきな夏の思い出をくれた先輩に、いつか恩返しができますように。あわよくば、先輩をびっくりさせられるようなビッグな人になって、また「いいじゃん」って言わせられますように。
そんなことを思いながら、8月最後の夜を眠る。
#エッセイ #コラム #日記 #夏 #恋愛 #note #つぶやき #青春
いつも読んでくださってありがとうございます。大好きです。 サポートいただけたら、とてもうれしいです^^ どうか、穏やかで優しい日々が続きますように。
