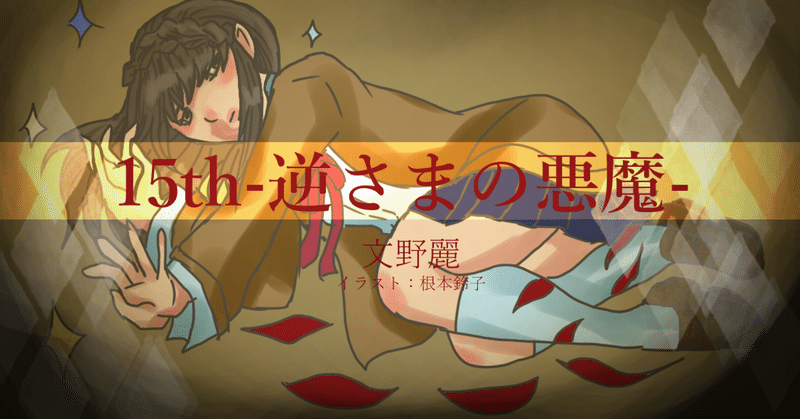
第五話「もう一つの始まり」長編小説「15th-逆さまの悪魔」
朝、琴音が不安を抱えながらバスターミナルへ着くと、数分後に歌羽がバスから降りて、姿を見せた。
歌羽は辺りを見回して琴音の姿を探し、見つけたようだったが、いつものように手を振ってこなかった。しばらく躊躇しているようだったが、やがて無言でゆっくり近づいてきた。
琴音は挨拶をしてみることにした。
「おはよう」
すると歌羽も気まずそうな声で返してきた。
「おはよう」
その様子を見て、歌羽は絶交するつもりなのではなく仲直りする気なのだと察し、とりあえず琴音は安心した。
歌羽は学校へ向かって歩き出した。琴音も連れだって歩く。
しばらく沈黙が流れた。あるとき歌羽が言い出した。
「数学は三時間目だよね?」
「そうだよ」
「だよね。宿題の残り休み時間にやらなきゃ」
登校中、二人の間に交わされた会話はそれだけだった。琴音は一人でいるときよりも孤独だった。歌羽が何か話しかけてくればよいのにとやきもきした。
午前中の授業の合間の休み時間は、歌羽は言っていた通り宿題をやっているらしく、机に向かって問題を解いていて琴音の席に来なかった。琴音は不安なままずっと一人で過ごしていた。
昼休み、どうしたらよいか分からなかったが、琴音は弁当箱をもって歌羽の席に行った。
歌羽は琴音を拒絶せず、いつも通り机を動かして二人向かい合う形にした。
歌羽が弁当箱を開けるので、琴音も開けた。
だが歌羽は食べ始めなかった。しばらく逡巡した様子を見せた。そして
「昨日は感情的になって悪かったよ。ごめんね」
と謝ってきた。
私に謝る人なんているんだ、と琴音は驚いた。今までは常に自分が赦しを乞う側で、相手が赦すかどうか決める側だった。なんて謝ろうか考えていたので、大いに戸惑った。
そして自分も謝ることにした。
「私も、ごめんね。怒りをそのままぶつけてしまって、よくなかった。仲直りできたら嬉しいな」
「私も仲直りしたい。これで、仲直りできたよね」
歌羽は申し訳なさそうに微笑んできた。琴音は安堵し、頷いた。
仲直りしたものの、二人のやりとりはまだ何もかもぎこちなかった。互いに相手の反応を全力で気にしていて、まるで友だち同士のやりとりというものを知らないままに真似事でやっているようだった。
歌羽を逃したら孤立することが分かっているので、琴音は好悪とは関係なく彼女から離れられないのだった。おそらくそれは歌羽の方も同じだろうと琴音は感じていた。
歌羽のことを全て嫌いになったわけではないから、と琴音は何度も自分に言い聞かせた。彼女は琴音に優しくしてくれるし、先に謝ってくれたし、よいところを褒めてくれる心をもっている。そういったところは好きだ。確かに趣味はよくない。だが人間、欠点もあって当然だろう。
琴音と歌羽は極力気を遣い合いながら帰り道会話をして、バスターミナルまでやってきて、別れた。
バスの座席に座ると、琴音は安堵して力が抜けた。歌羽と仲直りできた。向こうはもう怒っていないようだ。危機は去った。今は会話に違和感があるが、数日経てばきっと元通りになる。仲直りの難関を突破できたんだから、違和感くらい容易く乗り越えられるだろう。
窓から外を見ると、景色の中に自分の顔が半透明に映っていた。
それにしても、これでよいのだろうか。
私は麻理恵に失礼な歌羽と離れられないし、噂を止めることもできない。
麻理恵のことを何一つ守れていない。相変わらず自分のエゴで一杯だ。
どうして私はこんな人間なんだろう。最低じゃないか。
そもそもあのときだって、自分でも驚くくらい、直視に堪えない悪意をもって、麻理恵の背中を押した。白田先生とセックスすることになると分かっていながら彼の部屋に行くことを勧めた。完全なる悪意からだ。確かにほんの出来心だった。麻理恵より上の位置にいたいから、と考えて、麻理恵を転落させようとしたんだ。
でもあんなことにまでなるなんて思わなかった。まさか妊娠までしてしまうなんて。しかも白田先生はあっさり麻理恵を捨て、彼とは音信不通になり、麻理恵は相当絶望しただろう。
大人たちの間で一応決着はついたらしかった。だが麻理恵の心の傷が消えることはない。なぜなら麻理恵のお腹に宿っていた命はもう戻ってこないからだ。
もしあのときの子どもが、私がそそのかしたときにできたのだとしたら。
琴音は涙をこらえた。私が泣いてどうするの。泣きたいのは麻理恵であって、悪人の私には泣く権利なんてない。
あれで私は反省したはずなのに。二度と麻理恵を傷つけないと何度も誓ったのに。
たとえそれを実行するのだとしても麻理恵の傷は消えないというのに。
私は結局最低な人間のまま、悪人のまま。
あの誓いは言葉だけだったの? どうなの、私?
夕食時、琴音はご飯が盛られた茶碗と色々なおかずがのった皿、味噌汁が注がれたお椀を力なく見つめていた。
胃がコンクリートでも詰められたかのように重くて、全然食欲が湧かなかった。どちらかというと、食べる気力もしくは元気が湧かないといった方が正しかった。腕と口と消化器官を動かす力が出ない。
「どうしたの? 早く食べなよ」
と母が言う。
「食欲がないの」
「風邪でも引いた?」
「食べられそうなものはあるか?」
父も心配そうに琴音の様子を見てくる。
「何も食べたくない」
「でもねえ、食べないと力が出ないよ。少しでいいから、食べない?」
「うん」
そう言いながらも琴音は食べ物をじっと見つめたまま、何もせず座っていた。両親が食べ終わっても、琴音は一切箸をつけなかった。
「そんなに食欲がないの?」
「顔色が悪い気がするな」
「食べたくない」
「しょうがないね。食べたくなったら言うんだよ」
母はそう言って、琴音の食器を片付けた。全部捨てることはせず、一部は後で食べられるよう保存しておくようだった。
それを見て琴音は申し訳ない気がした。
たぶん明日も明後日も、その先もずっと、ご飯は食べられないだろう。
悪人の私なんかがまともに食事をするのは申し訳ない。私は食べてはいけないんだ。食べ物の味を楽しみ、お腹いっぱい食べて満足する権利なんてない。そもそも食べる気がしない。食べる気力が失われてしまった。
豊子ちゃんにも、後輩たちにも太っていると言って散々馬鹿にされた。だから痩せるべきだし、ちょうどいい。
食事をするのはやめよう。琴音はベッドの中で掛け布団にくるまって丸まったまま、そう決意した。
身体は精神と同様にまとまりがなく、言いようのない不快感が全身を覆っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
