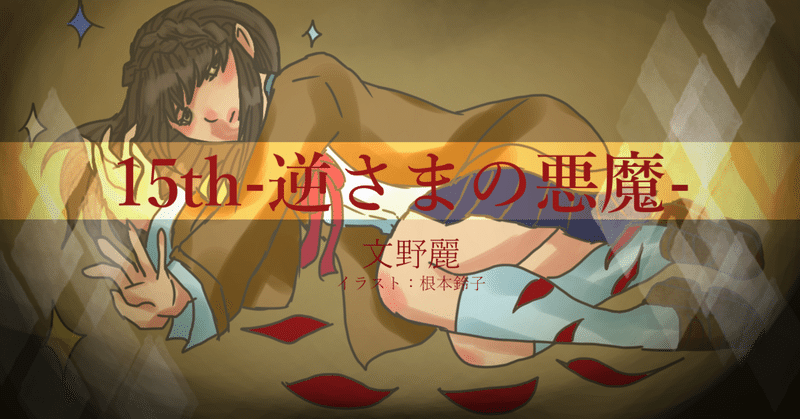
第一話「一つの始まり」長編小説「15th-逆さまの悪魔-」
見えない。分からない。これから先、積極的に生きたいと思える日はいつか訪れるのだろうか。心にはいつだって暗い影。
黒板を背にして自己紹介する教科担当の教師を眺めながら、視界の端に映る見知らぬ同級生たちを意識してみたが、結局何も見えてこないことに変わりはなかった。だがかつての未来は既に現実となり、最初のページがめくられたのだった。
新生活はあまりに茫漠としていて、捉えどころなくだだっ広い白紙の未来の中に、自己が飲み込まれ消えてしまいそうな感覚を、琴音は覚えた。加えて、感受性と感覚はまたもやうまく機能しなくなっていた。だがこれまでに経験した幾度かの氾濫と喪失によって、後者の空虚にはもう慣れてしまっていた。
通い慣れた中学校を卒業してから、瞬く間に何もかも過ぎ去ってしまい、自分の周りで何が起こっているのかほとんど理解する暇がなかった。他のことは何も分からなかったが、とにかく琴音は新入生として、高校の教室にいた。
入学式を前日に終え、一時間目の朝礼と二三年生との顔合わせも済んで、いよいよ高校生活最初の授業が始まったのであった。授業はどれもまだオリエンテーションの段階で、授業形式やノートの取り方、望ましい学習方法や心構えが説明された。教師たちは初日とあってか愛想がよく、これからの日々の授業と、やる気に満ちた生徒たちとの交流に希望を持っているというような態度を見せていた。
ここまで嫌なことは特になかったが、琴音の胸の中は淀んでいた。気分が晴れるという感覚を琴音はもう数年間は味わったことがないのだ。
午前中の授業が終わりかけると、琴音の陰鬱をよそに、昼食を誰と食べるか、という問題が教室全体で発生していた。
教師が教室を離れ、昼休みが始まるや否や探り合いが起こった。近くの席の生徒同士で固まるグループや、同じ中学校から来たと思しき、元々仲がよさそうな集団などが見られた。琴音はクラスを見回しながら、私なんかが話しかけたら嫌がられるだろうなと考え、困っていた。
そんな琴音のところへ、ある女子生徒が恥ずかしそうに近づいてきた。
「ねえ、植田琴音さん、だよね?」
その生徒に琴音は見覚えがあった。自分より少し背が低くて、よく切りそろえられた短髪が赤みががった丸顔に被さっており、窓枠みたいにしっかりした銀色のフレームの眼鏡を掛けている。笹野歌羽という子だった。琴音と同じT中学校の出身であった。
「そうだよ。あなたは、笹野さんだっけ?」
「うん。一緒にお弁当食べない?」
「いいよ」
琴音は歌羽に連れられて彼女の席へ行った。歌羽が周りの様子を見計らって二人分の席を確保した。歌羽が机を動かして背を向けている間、琴音は顔を背けて、荒い呼吸に自分の緊張を感じ取った。よかった、一緒にお昼食べる子見つかった、と心の中でつぶやいた。ろくに機能しない感受性も、さすがにこの状況では緊張を覚えるらしかった。
歌羽が席に就き、琴音は一応勧められてから向かいの席に座った。
「お弁当、お母さんの手作り?」
と歌羽が聞いてきた。
「そうだよ」
「お母さん作ってくれるのありがたいよね。私も作ってもらった。朝苦手だから、自分では作れないだろうな」
二人は弁当箱の蓋を開けた。
「いただきます」
とそれぞれ小声で言ってから、明るい色をしたプラスチックの箸を突っ込んで食べ始めた。
「午後の授業もオリエンテーションだよねきっと」
「だと思うよ」
「授業、分かりそう?」
琴音はなんと答えればよいか分からなかった。授業が分かるかどうか、ここまで全然考えなかったのだ。
「えっとね」
「うん」
「まだオリエだから分かんない」
歌羽はぎこちなく表情を動かして、同意した。
「そうだよね。まだ内容入ってないもんね。
でも、難しいんだろうな」
「笹野さんは」
「歌羽でいいよ」
「分かった」
「そっちも、琴音ちゃんでいい?」
「琴音でいいよ」
琴音ちゃん呼びされるのは過去を思い出すし不吉でしかなかったので、呼び捨てが気楽だった。
「それで?」
「歌羽は確かF組だったよね」
「中学ではね」
「何部だったっけ?」
「私はね、美術部だった」
「いいなあ」
「琴音……は吹奏楽部だよね」
「よく知ってるね」
「だいたい誰が何部か、覚えてない?」
「覚えてた」
ここで歌羽のことは忘れたと言うのは憚られたので、付け足した。
「でも卒業したら記憶が薄れちゃって」
「あー、分かる。春休みでみんな忘れるよね」
歌羽はここで初めて取り繕った様子のない笑顔を見せた。そして照れた顔で、付け加えた。
「私は、勉強も忘れちゃったかも」
歌羽とは帰り道もバスターミナルまで一緒だということが判明した。琴音は数日間昼休みと帰り道、意識して歌羽と一緒にいた。他に相手はいなかったし、歌羽から離れる理由もなかったからだ。自然と休み時間は歌羽の席に足が向くようになり、歌羽も琴音の席に来て、やっほー、と手を振って話しかけてくるようになった。
歌羽とは、中学時代はほとんど交流がなかった。クラスも部活も違っていて、話をする機会がなかった。それなのに急にどうしてそんなに仲良くなったのかと聞かれたら、二人とも困っただろう。
だが、その辺りの違和感は互いに気にしないようにしていた。琴音はそれをはっきり自覚していた。とりあえず同じクラスで誰かと仲良くなりたかった。同じ中学出身で一応互いに認識している相手は、全く知らない者より話しやすい。本当のところはそれが一緒にいる理由だった。互いに打算から始まった関係だったわけである。
それでも琴音は歌羽が話しかけてきてくれたことが嬉しかったし、実際助かってもいたのだった。
週末に差し掛かる金曜日の夕方、帰り道で
「ねえ、ライン交換しよ」
と歌羽の方から打診してきた。
「うん、いいよ」
アカウントが繋がると、歌羽はさっそくメッセージを送ってきた。
――友だちになれてうれしい!――
直後にアニメキャラと思われる男の子のイラストのスタンプが送られてきた。「嬉しいわあ」と関西弁の文字が書かれている。
――これから一緒に過ごしていこうね――
――私も歌羽と友達になれてよかったよ。一緒に高校生活楽しもうね――
琴音もそう書き込んでから、スタンプを送り返した。これで最初の難関は突破できた、と琴音は一応安堵した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
