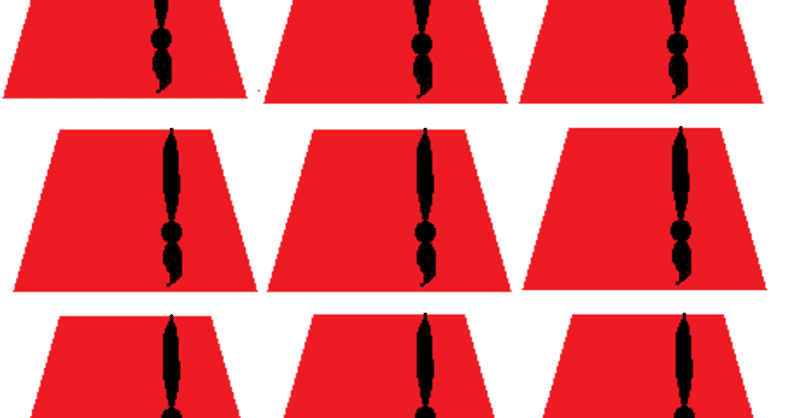
極東のトルコ帽始末(2)文士と詩人
(この文章は、調べていることを記した備忘録です。新たにわかったことがありましたら、追記していきます)
前回の記事では、日本近代洋画家のうち、「黒田清輝をはじめ最低でも5人が、(もちろん常時ではないのだろうが)トルコ帽を着用していた」ということを述べたが、実はその後、和歌山県出身の画家・彫刻家、保田龍門(1891~1965)の、「トルコ帽の自画像 」(1913~1914(大正2~3)年頃)という絵があることを知った。これで6人目である。保田もまた東京美術学校出身で、フランス留学経験があった。
ところで、トルコ帽に魅せられたのは画家だけではない。
小説家、ジャーナリストといった「文士」や詩人の中にもトルコ帽をかぶった者たちがいた。
今回見つけたところでは、最も早い事例が中江兆民(1847~1901)である。幸徳秋水(1871~1911)の書いた兆民の伝記『兆民先生』によれば、1888(明治21)年、大阪の日刊紙『東雲新聞』の主筆として活動していた兆民は、「長髪+東雲新聞の印半纏+トルコ帽」という姿であったという。何とも名状しがたいいでたちである。ただ、兆民は奇癖で有名な人物でもあったから、トルコ帽は周囲の人から見れば、「さもありなん」という感じだったかもしれない。
明治末から大正時代に入ると、文士のトルコ帽熱はいっそう高まったようである。1912(明治45)年3月24日付『東京朝日新聞』の「春の人 流行の帽子と洋服」という記事に、こんなくだりがある。
近頃銀座の商店で新案の土耳其帽を売り出したが、プランタンの文士画家連中に大分歓迎されて居ると云ふ事だ。
この「プランタン」というのは、日本初の会員制のカフェ、銀座の「カフェー・プランタン」のことだろう。1911年、東京美術学校出身の松山省三(1884~1970)が、友人の洋画家、平岡権八郎(1883~1943)とともに始めた。会員には、両者の師でもある黒田清輝をはじめ、名だたる画家たちが名を連ねていたが、文士でこの店の常連となる者も多かった。
そのうちの一人で、トルコ帽をかぶっていた可能性があるのが、何と谷崎潤一郎(1886~1965)である。作家の正岡容(1904~1958)が随筆『旧東京と蝙蝠』(1946年)の中でこんなことを書いているのだ。正岡は幼き日の東京の思い出の一つは、夜空を蝙蝠が舞っていたことだ、と述べ、
さては名作「少年」をいま書けた許りの仄紅く双頬を興奮させながら遮二無二永代橋附近辺りのし歩いて行くわかき日の谷崎潤一郎のむらさきのトルコ帽の真上にも、一様に愛す可きこの小妖精は身をひるがへして飛び交つてゐたにちがひない。
と想像する。谷崎が短編小説『少年』を書いたのは1911(明治44)年6月、彼が東京帝国大学を中退する直前のことだ。あくまで正岡の想像なので、本当かどうかはわからないが、24歳の谷崎が何やら「若気の至り」でトルコ帽をかぶっていたとしたら、と考えると、それはそれで非常に興味深い。
☆☆☆
プランタンの常連ではさらにもう一人、北原白秋(1885~1942)もトルコ帽をかぶっていた。谷崎の小説『詩人のわかれ』(1916(大正5)年)には、白秋をモデルにした田園詩人Fが登場するが、紺ビロードの二重織にピンク色のトルコ帽をかぶりながら、まるでオランダ人のような風采となって現れた、と描写されている。(まさにその姿とおぼしき写真は、新潮日本文学アルバム『北原白秋』で見ることができる(p.77))『詩人のわかれ』には、白秋(詩人F)は異国趣味で、司馬江漢の絵と、長崎のオランダ人風俗の絵を自宅に飾っていた、と書かれている。白秋はそうした心のうちにあるエキゾチズムをトルコ帽で表現していたのかもしれない。
さらに調べていくと、この白秋の周囲にいた詩人たち、例えば若山牧水(1885~1928)や、萩原朔太郎(1886~1942)もまた、トルコ帽をかぶっていたことがわかった。牧水は1916(大正5)年に盛岡を訪れた時にトルコ帽をかぶっていたことが、雑誌『創作』の若山牧水追悼集(第16巻第11号、168頁、1928年12月)で判明した。萩原朔太郎に関しては盟友の室生犀星(1889~1962)が、
前橋市にはじめて萩原朔太郎を訪ねたのは、私の二十五歳くらいの時であり今から四十何年か前の、早春の日であった。前橋の停車場に迎えに出た萩原はトルコ帽をかむり、半コートを着用に及び愛煙のタバコを口に咥えていた。第一印象は何て気障な虫唾の走る男だろうと私は身ブルイを感じたが、(『我が愛する詩人の伝記』(講談社文芸文庫、2016年、p.54)
と述べている。犀星が25歳ということは、1914(大正3)年頃であったと思われる。(朔太郎のトルコ帽姿の写真も、新潮日本文学アルバム『萩原朔太郎』で見ることができる(p.38))田舎育ちの犀星にとって、トルコ帽がキザの象徴だった、というのが面白い。当時文学をやっていた青年たちは、みな強烈な個性の持ち主であったろうが、その中でも、ある種の自意識を表現するための必須アイテムがトルコ帽だったのかもしれない。それが何なのかは今はまだ正確にはわからないが、同じ文士仲間でも、吉井勇(1886~1960)はなぜトルコ帽をかぶらなかったのか、長田秀雄(1885~1949)はなぜトルコ帽をかぶらなかったのか、室生犀星はなぜトルコ帽をかぶらなかったのか、ということを考えていけば、おのずと答えが出てくるような気もする。
☆☆☆
1916(大正5)年の8月、文壇にはある論争が起きていた。評論家の赤木桁平(1891~1949)が、「『遊蕩文学』の撲滅」という記事を『読売新聞』に掲載し、花柳界を舞台にした小説を激しく攻撃したのである。
その槍玉にあげられたのが、いわゆる「情痴文学」として有名な小説家の近松秋江(1876~1944)であった。撲滅キャンペーンの数週間後、1916(大正5)年8月25日付『読売新聞』には、「遊蕩文学の人々」という記事が掲載され、攻撃された作家たちがどんな風に過ごしているかが皮肉まじりに伝えられている。
独身者の近松秋江君は、例の『別れた妻に送る手紙』以来の因縁地たる日光の某僧房から、我が党形成非なりと見てかそこは知らぬが、先日帰っては来たものの近日下宿を後に再び荘厳崇美な霊山にトルコ帽の姿を見せるといふ。
何と近松はトルコ帽をかぶっていたのだった。芹沢光治良の『人間の運命』に出てきた主人公の同級生、トルコ帽姿の清木も、戯作者志望の青年であったことを考えると、単なるエキゾチズムを越えて、もしかしたらどこか露悪的で、悪目立ちしたいような欲求や、何かしらこじらせた思いがあって、隠しても隠しきれぬその欲求や思いが彼らをしてトルコ帽に手を伸ばさせたのかもしれない。
(芥川龍之介(1892~1927)の未完の小説『路上』に出てくる仏文科の大学生、藤沢や、坂口安吾(1906~1955)の「我が人生観(8)安吾風流譚」に出てくる先輩弁護士など、文学作品にも、こうした心の中に何かを抱えているトルコ帽キャラクターが登場する。ちなみにこのあたり、Twitterでご教示いただいた。ありがとうございます)
もちろん、トルコ帽をこうした文学者の「若さ」「エキゾチズム」「自意識」「目立ちたがり」だけで語ることはできない。文学作品の中にはトルコ帽姿の老人も出てくるし(二葉亭四迷(1864~1909)『平凡』や幸田露伴(1867~1947)『野道』)、何といっても、大杉栄(1885~1923)をはじめとした、当時のアナーキストたちの人気アイテムでもあったからだ。さらに、大正時代にトルコ帽は子どもの帽子としても流行していた節がある。次回では日本におけるトルコ帽の広がりと末路を追いかけていきたい。(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
