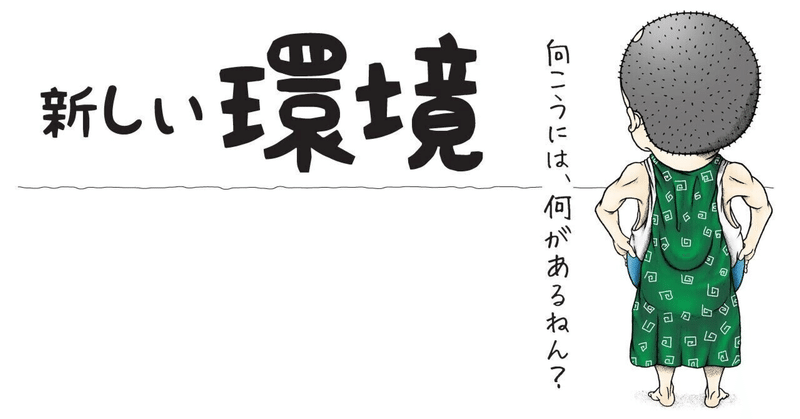
リディラバ転職記-松平健が繋いだバトン-
リディラバに入社したことや、入社後に担当した事業のことはFacebookにちょくちょく載せてましたが、つい先日YouTubeで松平健さんが歌う『マツケンサンバ』※の動画を観ていたところ入社前のことや過去のキャリアについて諸々思い返すという稀有な体験をしたので、備忘録として書こうと思います。
リディラバ(正式には株式会社Ridilover)に入社したのは2022年の8月15日のことで、なんだかんだで一年以上が経ちます。
大学を出て新卒で入って約7年半務めたのは漁業団体で、その後、株式会社Libry(EdTech企業)を経て3社目になります。
いずれの団体・会社も入った動機は変わらず「社会に貢献したい」ということでしたが、その考え方のルーツに自分の中でようやく整理が付きました。
※YouTubeにアップされている曲のタイトルは『マツケンサンバⅡ』となっていますが、『Ⅰ』が何なのかよくわからないので、以降単に『マツケンサンバ』で統一します。
ヒーロー像の変質:変身ヒーローから生身の人間へ
少し遡りますが、物心ついた頃から仮面ライダーやウルトラマンに戦隊と、テレビやビデオで観る変身ヒーロー作品が大好きでした。
特に好きだったのは戦闘シーンで、「正義の味方が悪い奴をぶっ飛ばす」というカタルシスが子供ながらにクセになっており、将来の夢は当然のようにこれらの変身ヒーローになることでした。
一方、年齢が上がるに連れて(少なくとも当時の)現実社会には巨大な怪獣も存在しなければ人間が変身して怪獣や怪人と戦う技術もないということがわかってくるため、変身ヒーローに憧れ続けるのは難しくなってきます。
必然的に変身ヒーロー作品を観るのが気恥ずかしくなる時期というものが訪れました。
仮面ライダーを例に取ると、『仮面ライダークウガ』を皮切りに「平成ライダーシリーズ」が始まったのが2000年(私が9歳の時)で、覚えている限りではリアルタイムで最後に観たのは2003年に放映開始された『仮面ライダー555』です。
それでも「正義の味方が悪い奴をぶっ飛ばす」というカタルシス自体は求め続けていたのでしょう。
テレビで放映していたカンフー映画や再放送の『暴れん坊将軍』は変身ヒーロー作品を観ていた時から好きで、変身ヒーロー作品を卒業してからも観続けていました。
カンフー映画は主にジャッキー・チェン主演の『酔拳2』等、主人公が悪の組織を相手に大立ち回りをするもの、『暴れん坊将軍』は松平健さん(タイトルでは語呂優先で呼び捨てにしてます。健さん、すみません)が徳川8代目将軍・吉宗を演じた時代劇シリーズで、こちらも悪い奴らを吉宗が成敗するのがお決まりの展開でした。
これらの作品はアクションやカタルシスへのニーズを満たしてくれたコンテンツであったのと同時に、活躍しているのは光の巨人でもなければ改造人間でもなく、超人的な武術や剣技を身に付けてはいるもののあくまで等身大、生身の人間であり、「ヒーロー像」そのものを変質させるきっかけでもありました。
ちなみに最近では、色々な作品の影響でヒーローが「変身」するということについて再評価しているのですが、話が長くなるので機会を改めます。
アクションを真似した中学時代
時が経ち、中学に入るのと同時に剣道部に入りました(卒業前に幽霊部員になったが一応の有段者)。
入部動機の一つには『暴れん坊将軍』をはじめとする時代劇のチャンバラ、日本の時代劇もモチーフになっている『スター・ウォーズ』シリーズのライトセーバー・アクションへの憧れがありました。
他の部活と違って朝練、日曜日の稽古がなくてラッキーという邪な気持ちもありましたが。
入部以降は、『暴れん坊将軍』で松平健さん演じる吉宗が悪者を成敗する時の峰打ちのようにきれいな胴打ちを理想にしていました(峰打ちの描写については今振り返ると色々と思うところはあれど、それも書き始めるとあまりに長くなるので機会を改めます)。
『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』の冒頭でオビ=ワン・ケノービが通商連合の船内でドロイドと戦った際に見せた、すれ違いざまに斬り上げる→ライトセーバーを逆手に持ち替えてドロイドの背中側から貫通させる→順手に持ち直して残心、のシーンも非常に印象的だったため、小学校の修学旅行先で買った短い木刀を手に家の中で真似しようとして父に怒られたのを覚えています。
ただ当時の技術や体格では竹刀を扱う上でこれらのシーンの再現はできなかったため、実際によく使っていたのは「出小手」という、時代劇のチャンバラや『スター・ウォーズ』シリーズではおよそ登場しない細かな技でしたが。
また、稽古前後の遊びとして竹刀を使ってカンフー映画の棒術を真似たりもしていました。
ジャッキー・チェン主演の作品で棒術を使うのは敵役が多かったけれど。
どう考えても真面目な部員でなかったことがバレるような話ばかりですが、ヒーローの動きを真似たい中学生男子にとって当時の剣道場は理想の実験場、そしておもちゃ箱でした。
今では、剣道はやっていませんが趣味で古流の剣術を習ったり、棒術・杖術も多少教えて頂いて見よう見真似ではない動きを学んだりと、良くも悪くも幼少期や中学時代からやりたいこと自体は変わっていないと感じています。
ここまでは『暴れん坊将軍』という作品やカンフー映画のアクションを真似ているというだけの話です。
それだけでも自分の人生に与えた影響は少なくないのですが、ここからは価値観に与えた影響について書きます。
アクション以上に真似したかったこと
"A single man can make a difference."
日本では2007年に劇場公開されたサム・ライミ版の『スパイダーマン3』において、数々のマーベル作品の原作者であるスタン・リーがお馴染みのカメオ出演をしており、スパイダーマンのスーツを着ていない素顔のピーター・パーカーにそんなようなことを言って諭すというシーンがあります("single"が入ったかどうかは記憶が定かでない)。
幼い頃からヒーローは好きだったし、テレビやビデオで映画を観るのも好きだったので、覚えている限りではサム・ライミ版の『スパイダーマン』の一作目が親の付き添いなしで初めて映画館で観た映画です(日本公開が2002年なので、11歳くらいの時)。
それ以降も、現在のMCUに至るまで広義のマーベル作品を含めてヒーローやアクションといった要素のある映画は結構な確率で劇場で鑑賞しており、『スパイダーマン3』も当然のように劇場で観ていました。
先のセリフの字幕は「ひとりの人間でも世界は変えられる」という訳になっていた記憶で、それを普通のおじいちゃん(に見えるが実は重鎮のスタン・リー)がスパイダーマンというヒーロー(には見えない冴えない青年ピーター)に言うという可笑しさがあるシーンにも関わらず、当時16歳だった私は妙に感じ入ったのを覚えています。
"make a difference"という表現については、「世界を変える」という大層な意味ではなく「世の中に違いをもたらす」というように直訳に近いニュアンスで捉えるのが好きで、生身の人間でも、小さいながらも違いをもたらすことができるのだと背中を押された気がしました。
事程左様に、ヒーロー達が作品の中で見せるアクション=戦闘技術以上に真似したかったのは生き方でした。
「皆がやっていることはやりたくない」「誰もやりたがらないことが好き」という生来ひねくれた性格があることも否定しがたい事実ですが、一方で「誰かがやらなきゃいけないことなら自分がやる」という生真面目さはヒーロー作品から受けた影響なのではないかと思います。
というか、そうであってほしい。
中学時代とて無邪気にヒーローごっこに勤しんでいただけではなく、学級委員とかクラスの文化祭実行委員とかを進んで引き受けていて、それこそ剣道部の顧問から嫌味を言われるくらい部活そっちのけで文化祭の準備に精を出していました(剣道部の顧問はクラスの担任でもあったので、少しは理解してくれてもよかったのに、と今でも思う)。
社会人になってからも職場の衛生管理委員とか労働者代表とか、募集がかかると平均2秒で立候補しています。
リディフェスも大人の文化祭として張り切った。笑
マーベル作品において印象に残っているシーンを再び例に出しますが、『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018年公開)において、ワカンダに襲来したサノスの軍勢を迎え打つ際、ワカンダの国王でもあるブラック・パンサーとキャプテン・アメリカが前線から真っ先に飛び出すシーンがあります。
この二人は、それぞれ不思議な植物の力やら米軍のスーパー・ソルジャー計画やらで超人的な身体能力を手に入れており、常人とは桁違いなスピードで前線から飛び出すことで各キャラクターの背景を印象付ける効果があるシーンです。
しかし、身体能力以上に「国や地球の危機にあって真っ先に飛び込んで行く意志」こそがシビれるポイントであり、MCU作品を通しても二番目に好きなシーンです(ちなみに一番はブラック・パンサーの宿敵キルモンガーが登場する全シーンです)。
このシーンにも自分を肯定されると共に、「常に真っ先に飛び込んで行く意志と、それを可能にする能力を身に付けなさい」と叱咤激励された気がしました。
いざ、職業選択へ
中学時代に自分の中で育てたヒーロー像は、生身でも世のため人のために戦う等身大の人間です。
自らの行動によってたとえ小さくとも世の中に違いをもたらす存在。
それが実現できる職業は何か、高校・大学生活において進路を考える際は決まってそんなことを考えていました。
一方で、「正義の味方が悪い奴をぶっ飛ばす」という解決が単純過ぎるということも映画が教えてくれていました。
正義とは、悪とは何か。暴力による問題解決は許容されるのか。
自分の価値観を揺さぶるような作品を多く観たし、それを学び考えることが自分にとっての「勉強」でした。
高校時代には自分が受験勉強をする中で予備校の教師から受けた影響が少なくなかったことから、教育関係の職業に就きたいと考えました。
自分が培ってきたヒーロー像とか正義感とか、未来の社会を担う学生に伝えたいと思っていました。
その後、大学で勉強する中で教育以上に「経済」「自然環境」「コミュニティ」「文化」といった領域に関心を抱くようになりました。
それと同時に、自分のヒーロー像や正義感もまだまだ人に伝えるレベルにないと思うようになり、最初のキャリアでは教育業界ではなく民間企業で経験を積むことにしました。
「社会貢献」という志望動機を引っ提げ、就職活動の始まりです。
今でこそ当たり前になっているSDGsという概念や、リディラバでも取り組んでいる社会インパクトを評価する取組といったものは、少なくとも当時の私が知る限りでは一般的ではなく、企業の社会貢献といえば本業と関係ないCSR活動が関の山といった感じでした。
それでも民間企業へのこだわりがあったので、自分の関心領域やそれを通じた社会貢献という考え方と折り合いの付きそうな事業を行っている会社を受けました。
案の定といってしまうと悲しいものがありますが、志望動機が「社会貢献」というのは、企業相手にはなかなか伝わらないことが多かったです。
特に大企業の選考を受けていると、「この会社(グループ)にどのような形で貢献できますか」と聞かれるのですが、そもそも会社に貢献しようなどとは思っていないので答えようがありません。
今も昔も心にもないことは口にはできず、何よりそんな質問をされる時点で気持ちが冷めてしまいました。
志望する会社のいいところや、その会社に自分がどう貢献できるかを笑顔で上手に伝えられる器用な同級生達は一足先に大企業の内定をもらっていました。
でも、実際にやりたいことは企業のためではなく社会のために働くことなので、そこをわかってくれないのであればしょうがない、むしろそんな企業は所詮その程度であると、若く血気盛んな時は思っていました。
最終的に新卒では漁業団体に入ることになりました。
よく聞かれるのですが、特別魚が好きであるとか、親が漁師であるとかいう背景はありません。
魚は幼少期から食べていましたが、より積極的に好きになったのは業界で働く中で一流の水産物を沢山頂いてからです。
ではなぜ漁業の道を選んだかといえば、大学時代に関心を抱いていた「経済」「自然環境」「コミュニティ」「文化」という領域に同時にアプローチできる産業であるという魅力があったからです。
これまたよく聞かれることですが、公的な役割を担っているものの国や自治体の機関ではなく、あくまで事業収益によって運営されている組織であることも魅力に感じました。
就職活動をしている時も、漁業団体に入ってからも伝わらないことが多かったですが、ともかく本気で「社会貢献」を目指して入り、約7年半務める中でそれなりの充足感を得ていました。
その後、EdTech企業である株式会社Libryとの出会いがあり、転職することになりました。
漁業への思い入れはあったのものの、組織としては色々と限界を感じていただけに、業界も組織形態も思いっきり違う世界に入りたかったのです。
業界としてはかつて一度は憧れた「教育」に関わる仕事です。
自分がプレイヤーとして課題解決を目指すのではなく、教育を通じて未来を作るという、社会の根幹により近い領域で働くという方向にシフトし、実際、同じ志を持つ仲間達と楽しい日々を送りました。
その後、残念ながら色々とあって転職活動をすることになるのですが、新卒の時と同様、選考を受ける中で志望動機を理解してもらうのに大いに苦労しました。
志望動機は自分の中では既に当たり前になってしまっていて言語化が難しく、加えて過去のキャリア、特に漁業団体の時に携わっていた業務内容がなかなか理解してもらえないことも相まってそれなりに苦戦しました。
そんな中で出会ったのがリディラバでした。
転職エージェントからの紹介文で、「社会課題の解決」×「スタートアップ」という掛け合わせに大いに魅力を感じ、迷わずエントリーしました。
リディラバの面接では、カルチャーフィットが大きかったためか楽しく進むことができました。
トントン拍子で迎える最終面談。
相手は代表の安部さんです。
これがまたかつてないほどにスムーズに進みました。
安部さんは、東大に入っておきながら学生時代にはマグロを素手で捕まえる仕事に携わっていたという不思議な方なので、私の漁業団体における業務内容は「遠洋マグロ船の海外入港手続きとかをやってました」というだけで伝わりました。
通常の面接では「そもそも遠洋マグロ漁業とは何か」という話に始まり、「なぜ海外入港が必要か」「海外入港手続きでは何をするか」という説明のために貴重な時間を使わなければなりません。
時間をかけて理解してもらったとしても「何が大変なのか」とか「その業務を経験するとどのようなスキル、強みが身に付くのか」といったことは、なかなか面接官の実感として湧きにくいためアピールが難しいものです。
一方、安部さんは先の一言を伝えただけで、業務内容はおろか「それは物凄く調整能力が身に付くね」とスキルまで理解してくれました。
ありがたい限りです。
また、過去のキャリアにおいて社会貢献を目指す上でなぜ漁業を選んだか、ということもそれほど言葉を要さずに伝えることができました。
一方で、「なぜそこまで社会貢献にこだわるのか」という問いに対して、伝えることができたのはこの記事で書いたことの断片のみでした。
安部さんが汲み取ってくれて内定に至ったからよかったものの、特に幼少期に好きだった変身ヒーロー作品から現在の趣味、価値観への変遷はうまく説明できなかったと思います。
先日『マツケンサンバ』の動画を観たことをきっかけに、幼少期から現在への結節点として『暴れん坊将軍』が意外なほど重要な役割を果たしていたことに気付き、この記事を書くに至っています。
タイトルにある「松平健が繋いだバトン」とはこのことです。
ヒーロー像の変質、再び
リディラバ入社後は、事業開発チームで官公庁の委託事業を主に担当しています。
文部科学省の事業では前職の株式会社Libryに引き続き、広くいえば教育に関わる仕事をしています。
ところで、リディラバのカルチャーでは社会課題の解決を目指す上で最前線で取り組んでいる方々とのリレーションや、我々自身も現場に足を運んで一次情報を取得することを重視しています。
この点も『暴れん坊将軍』を通じて非常に馴染みがあるやり方です。
というのも、主人公・吉宗は徳川8代目将軍であるにも関わらず貧乏旗本のふりをして市井に紛れ込み、自分で見聞きした問題を自分の手で、時に市井で得た仲間と共に片付けます。
時代劇なので悪代官を成敗するだけで問題が解決されてしまうのは現実とは異なりますが、リディラバにおける課題解決のプロセスはかつて憧れたヒーロー像と変わらないと感じています。
また、リディラバに入ってからも自分の中のヒーロー像を変質させる作品に出会いました。
2022年3月から1年間テレビ放映していた戦隊シリーズ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』です(漢字の部分は「あばたろうせんたい」と読みます)。
かつて気恥ずかしくて観るのをやめた変身ヒーロー作品も、ある程度大人になればそんな恥をかなぐり捨てて観ることができ、大学時代あたりから結構観てます。
『ドンブラザーズ』は東映特撮ヒーローシリーズにおける重鎮、井上敏樹さんが脚本を務め、その作家性が爆発していて他の作品とは一線を画するヒーローのあり方を打ち出しています。
ヒーローに必要なものといえば敵であり、ヒーローは敵を倒すことによって自らのヒーロー性を担保するというのが他の(過去の)ヒーロー作品に多い展開ですが、『ドンブラザーズ』(や、他の井上敏樹作品)は違います。
『ドンブラザーズ』には、「ヒトツ鬼」(ひとつき)と呼ばれる怪人が登場するのですが、ヒトツ鬼の正体は欲望を肥大化させた人間の成れの果てです。
通常のヒーロー作品ではヒーローは怪物を退治し、退治されることは怪物にとっての消失(死)を意味します。
ところが、ドンブラザーズがヒトツ鬼を退治すると、ヒトツ鬼は怪人になる前の普通の人間の状態に戻ります。
ここが井上作品ならではの点で、『ドンブラザーズ』には「敵」が存在しません。
唯一、ヒトツ鬼を人間に戻すのではなく完全に消滅させようとする「脳人」(のうと)というグループがあって、ドンブラザーズとは考え方の違いにより対立するものの、次第に人間関係が改善したり考え方がすり合ってきたりして、最後には味方になります。
社会が敷いたレールを踏み外した人がいたとしても、そっと優しく押し戻す。
むしろ、社会が勝手に敷いたレールなんか踏み外してもいいと伝えてあげる。
踏み外した結果として関係ない人を傷付けそうになった時には責任を持って止める。
「病人」を治療する「医療」ではなく、「犯罪者」を逮捕する「警察」でもない、「他者」を包摂する「福祉」のようなヒーロー。
そんなヒーロー像が、今たまらなくかっこよく見えます。
医療も警察も間違いなく社会に必要なものではあるけれど。
福祉がかっこいいというイメージは、リディラバに入ってから担当している文部科学省や厚生労働省の委託事業において福祉の現場で働くリアルヒーロー達の言葉を直に聞いているからでもあり、今後自分としてもそんなヒーロー像を目指して取り組んでいきます。
また、ドンブラザーズと脳人の関係性は、考え方が違う者同士が地道な対話を積み重ねたことによる産物です。
対話を通じて完璧ではないにしてもなんとなくの調和が生まれるというのは、今のリディラバのロゴマークに込められた思いでもあります(多分)。
そんな『ドンブラザーズ』の理念を体現しているのが、皆大好き森崎ウィンさんが歌うオープニングテーマとエンディングテーマです。
どちらも歌詞に注目して聴いてほしいのですが、特にエンディングテーマは秀逸です。
いずれの曲も重要な題材を扱っていながら押しつけがましくなければ説教臭くなくもない、バカバカしいほどの祝祭感にあふれています。
『マツケンサンバ』にしてもそうですが、きっと私は祝祭感が好きなのでしょう。
リディフェスなんて最たる例で、祝祭感どころか祝祭そのものなので、部活そっちのけで準備した学生時代の文化祭と同様、担当業務そっちのけで準備や集客に張り切っちゃった訳ですね。
こうして振り返ると、「現場」「連帯」「包摂」「対話」「祝祭感」あたりが今の自分のヒーロー像を考える上でのキーワードである気がします。
お待たせしました。
それでは聴いて下さい。
松平健さんで『マツケンサンバ』。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
