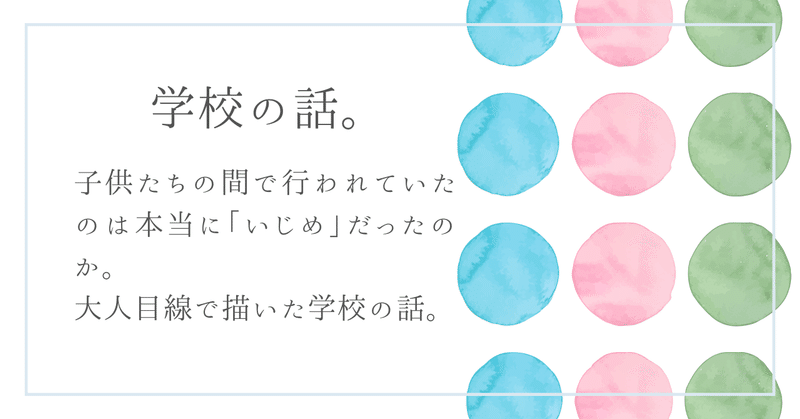
【小説】学校の話。<承>
▼前話
1)
問題が起きたのは、二月に入って間もなくのことだった。
「こんな手紙が落ちていました」
3年1組担任、学年主任の及川が声を張り上げた。
朝の会の時間帯に急遽、学年集会が開かれている。児童たちは、狭い廊下でぎゅうぎゅう詰めになって並んでいた。
手紙は二通。
1組付近の廊下に落ちていたものを及川が拾い、問題視した。
手紙はいずれも自由帳を破って折り畳んだもので、次のようなことが書かれている。
【○○のことがキライ】
【わたしもだよ。キモいよね】
この場では差出人や受け取った児童の名は伏せているが、後から個別に呼び出されるはずだ。
こういった手紙が出回るのは初めてのことではない。今回の手紙の主は、1組の児童だった。
「手紙は、感謝の気持ちや愛情を伝えるものです。
悪口を書くものじゃないよね」
子供たちは、多くが無関心な様子である。
この中の誰が内心ヒヤヒヤしているか、今の段階で窺い知ることはできなかった。
「今から大切な話をします。注目」
及川がピシッと刺すように言うと、余所事をしていた子も一応は前を向く。
「今日から、校内での手紙のやりとりを禁止にします」
同じことを繰り返させないための措置だった。 不満の声が上がるかと危惧されたが、予想に反して子供たちはポカンとしている。
2組担任の瀬尾 実咲は、暗い気分で脇に控えていた。
禁止することが解決策といえるだろうか。
「禁止にするより手紙の書き方を学ぶ機会を作っては?
国語や道徳の授業で……」
出勤後の慌ただしい打ち合わせで瀬尾も意見を出したが、及川も小渕沢もそれぞれに
「今は時間がないわ」
「そんな暇ないでしょう。カリキュラムが追いつかない。
もう年度末なんですよ?」
と言って取り合ってもらえなかった。
まだ二年目の新米の意見など、一瞬で捻り潰されてしまう。
「みんな。及川先生が言ったこと、きちんと守りましょうね」
2組の教室に戻ってから、学年集会の振り返りが行われる。
学年としての決定事項なので、自分の意に反することでも伝えなければならない。
ぐるりと教室を見渡せば、子供たちは澄んだ目でこちらに注目している。
瀬尾の言葉を信じ、吸収しているのだ。
この可愛い子供たちと目を合わせる資格が自分にあるのか。
瀬尾は、罪悪感を飲み込んだ。
朝の学年集会を終え、問題はひとまず落ち着いたかに見えた。
しかし、その日の昼休みのこと。
午前中から雨が降り始め、瀬尾は他の児童たちとともに2組の教室に留まっている。
「ああ、及川先生。ちょうど良かった、来てください!」
小渕沢の声が廊下に響いたのは、そんな時であった。
子供たちが気にして廊下を覗き始める。
「誰か怒られてるよ」
「千乃ちゃんたちだ」
「実咲先生も来て」
子供たちに手を引かれ、瀬尾も教室を出た。
及川に手招きされる。
この時、既に学年中の児童が遠巻きにこの様子を眺めていた。
「この子たち、手紙を書いてたっていうのよ。
朝、学年集会で話があったばかりなのに」
及川から、溜め息混じりにそう伝えられた。
小渕沢の前にいるのは、向かって右から笹木 凛音、伊藤 葵、中嶋 千乃の三人。それぞれに硬い表情をしている。
瀬尾の第一印象は、「どうしてこの子たちが?」というものであった。
「何があったの?」
瀬尾は三人の前に腰を落とす。
凛音が訴えるような目でこちらを見たが、すぐに俯いてしまった。
「今、何してた? どうして答えられないんだ」
小渕沢が紙切れを突き出す。
折り紙が二枚。裏に何か書いてあるようだが、瀬尾の位置からは見えなかった。
「首を傾げてるだけじゃ分からないよ。
どうしてこんな物を写させたりしたの?」
「ちゃんと先生の目を見なさい」
及川からも厳しい声が飛ぶ。
「朝の学年集会で言ったばかりだろう!」
立たされているのは三人だが、叱責は主に千乃に向かっているようだ。
予鈴が鳴った。間もなく五限目が始まる。
それを潮に、葵と凛音は解放された。
及川は野次馬の児童たちを促しつつ教室へ戻っていき、瀬尾もそれに倣う。
廊下には頬を強張らせた千乃と、小渕沢が残った。
「ほら、みんな。前を見てね」
子供たちは五限目が始まっても廊下の方が気になるらしく、よそ見ばかりしている。
瀬尾は子供たちを宥め、授業に集中させるのに苦労した。
千乃への叱責は、五限目を半分過ぎるまで続いた。
2)
その日、下校前にも3年生の児童が集められ、及川の口から改めて禁止事項が伝えられた。
校内での手紙のやり取りは禁止。
昼休みの出来事を受けての話だった。
午前からの雨は止む気配がない。
傘の花が雨に打たれながら、ぞろぞろと校門を通り過ぎていく。
瀬尾は千乃たちのことが気にかかったが、大勢の児童に紛れて見つけることができなかった。
「これですよ」
職員室で、小渕沢が二枚の折り紙を示した。
及川と瀬尾が覗き込む。
【ひどい人がいるから 気をつける】
茶色の折り紙の裏側に、鉛筆で書かれていた。
そして、何故か同じものがもう一枚。
「中嶋 千乃が伊藤 葵に、この手紙を強制的に書かせていたんです」
今日の昼休みのこと。
小渕沢が教室内で連絡帳に目を通していると、例の三人がまた固まってコソコソやっていた。
千乃が何かを書いており、葵がそれを覗きながら写し取っているようだ。
凛音は笑いながら眺めている。
嫌な予感が働いた小渕沢が様子を見に行くと、三人は一斉に紙を隠した──。
詳細を知らされた及川が腕を組む。
「朝、禁止したことを同じ日に堂々とやるというのはちょっとね。
千乃ちゃんがやったっていうのが信じられないけど」
「それだけじゃない。文面も良い内容とは言えんでしょう」
”ひどい人”という言葉が出てくるところを見ると、小渕沢が言う通りかもしれない。
(でも引っかかる。何だろう、この感じ……)
違和感を持ちながらも、瀬尾は先輩二人の会話を聞いていることしかできなかった。
「手紙を写させて葵さんに罪をなすりつけるつもりだったんだ。
彼女の筆跡で、誰の元へ行くのか分からないんですよ?」
小渕沢がヒートアップしていく。
「今回は未然に防ぎましたがね。これは大きな問題だ。
十七時に、お母さんを呼んでます」
「そうね……お家の人に知っておいてもらう必要はあるわね。
丈二先生、よろしくお願いします」
及川が深刻な表情で応じた。
瀬尾はまだ違和感が拭えないものの、その正体が分からず発言できない。
ただ。
彼女は、このあと小渕沢が漏らした呟きを聞き逃さなかった。
「よし。よぉし──」
3)
「何か問題があったんですって?
大変ですねぇ、小渕沢先生」
中嶋 千乃の母親を迎えるべく職員室を出ようとすると、ちょうどコピー機を使用していた殿山に声をかけられた。
(何なのか、この男は。
みっともない。僻むのもいい加減にしろよ)
小渕沢は、無視してコピー機の前を通り過ぎる。
「声が大きくて丸聞こえでしたよ。
問題が起きたというのに、えらく嬉しそうなことで」
職員室の引き戸をやや強めに閉め、殿山の粘着質な声をシャットアウトした。
3年3組の教室へ向かう途中、力任せに壁を蹴る。
図画の時間に児童たちが描いた絵が傾いた。
「ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
葵ちゃんにもご家族にも、どうお詫びしたらいいか」
小渕沢が今日の経緯を説明すると、中嶋 千乃の母親は真っ青な顔で頭を下げた。
「いえいえ。
ただ、やはり現物を見て頂いたほうが良いと思いましてね」
教室内の机を向かい合わせた状態で面談の形が取られている。
小渕沢と千乃の母親の間には、例の折り紙が置かれていた。
【ひどい人がいるから 気をつける】
折り紙の裏に子供の筆跡。
そして、まったく同じものがもう一枚──。
「念のため確認なんですが。
お母さんから見て、この手紙を写させたのはどちらだと思われますか?」
「……性格上、娘の可能性が高いと思いますが」
小渕沢は大きく頷いた。
「そうですね。子供の間には力関係がありますから」
「はあ……」
二人の力関係は千乃が上だ。
「どうです? 良い内容じゃないでしょう」
「そう……です、ね」
自分に向けられた折り紙を前に、千乃の母親は力なく首を傾げた。
「力が上の者が弱い者に、こうして手紙を書かせる。
葵さんの筆跡で誰かの手に渡ったら大変なことになります」
禁止されている手紙、しかも内容が良くない手紙を葵が出したことになってしまうからだ。
「そうですよね……あの」
千乃の母親がおずおずと切り出す。
「娘は先生の指摘を認めた、ということでしょうか?」
「いえ。何も答えないです」
「……」
小渕沢は眼鏡のブリッジを押し上げた。
母親からの返答がないと判断すると、早口で告げる。
「友達だからと従ってばかりいては危険です。
伊藤さんの方へも気をつけるよう連絡させてもらいますので」
「はい、それはもう。お手数をおかけしまして……」
「禁止だと言われたことを堂々とやっておいて、学年主任も含めた教員に囲まれても頑として認めない。
低学年なら泣くくらい厳しい対応をしたにも関わらずです」
「え?」
「五限目の途中までかかりました。あれは相当ですよ」
「それは、ご迷惑を……」
千乃の母親は、夢でも見ているのかといったような面持ちである。
「親御さんの前じゃどうか分かりませんが、教員の前では大人しい。
そのくせ、休み時間になった途端に友達を『葵!』なんて乱暴に呼び捨てたりしてね」
「はあ」
「娘さんは、そういう子です」
「……」
「大切なのはこれからです。
対話には時間を要するでしょう」
中嶋 千乃の母親は、放心したような様子で帰っていった。
「よし」
親にも伝わった。
親は、手紙を写させたのは千乃だろうと言った。
諦めの悪いことに、「娘は認めているのか」などという質問をぶつけられたが。
この期に及んで。
とんでもない親がいたものだ。だから子供がああなる。
ともかく、伊藤家へコンタクトを取ることについては了解を得られた。
最悪の事態を未然に防いだのだ。自分が。
小渕沢は、意気揚々と受話器を取り上げた。
「ああ、葵さんのお母さんですか」
小渕沢は、今日の出来事のあらましを説明する。
『千乃ちゃんがですか? あーちゃんに……』
葵の母親はそう言ったきり、受話器の向こうで絶句した。
「現場を押さえましたから。
良くない手紙を写させている現場、いじめに繋がる現場を」
『いじめ……?』
「しかし、ご安心ください。
こちらは現場を見てるんで、いつでも介入できますからね。
中嶋さんの親御さんにもお伝えしていますので」
『……』
重要な話だというのに、葵の母親は何をぼんやりしているのか。
小渕沢は呆れた。
「言われるままになっていてはいかん。
あの手紙が誰かに渡ったら大変なことになっていましたよ。
断る勇気を持つことを、親御さんからも伝えてください」
4)
及川が受話器を戻した。
「またですか?」
瀬尾が声をかけると、及川は「まあね」と手短に答えて首の付け根付近を指で揉み込む。
手紙を禁止にしたことが、思わぬ波紋を広げていた。
父兄からの電話は、これで六件。
いずれもPTA活動などに積極的な家庭からで、内容は
いつまで禁止なのか。
3年生だけに限った話か。学年をまたいだ手紙のやり取りは?
校外の友達にも手紙を出せないのか。
といったものだ。
子供の伝え方だと限界があるのか、「校内では」という部分が抜け落ちてしまっている。
だからといって、及川は特段疲れている様子はなさそうである。
ベテランともなると、父兄への対応にも余裕がある。
小渕沢は、顔を真っ赤にして「こんなのは嫌がらせだ」と吐き捨てた。
しかし、瀬尾は小渕沢に完全には同調できない。
重箱の隅を突くような問い合わせが大半ではあるが、中にはまともな意見もあった。
禁止すれば解決できる問題なのか。
瀬尾も感じた疑問だ。
違和感を持ちながらも学年の方針に従い、結果このような指摘を受けたことに、瀬尾は心苦しい思いであった。
「長い一日だったなぁ」
瀬尾は疲れ切っていた。
職員用の玄関でパンプスに履き替える。
「実咲? キミも帰るところ?」
声をかけてきたのは、カナダ出身の英語講師、オリバーだ。
「どうしたの? 珍しく元気がないじゃないか」
「そんなことがあったのか」
騒がしい居酒屋のカウンター席に、オリバーは長い足を折り畳むようにして納まっていた。
日本をこよなく愛する彼は、瀬尾が案内した大衆居酒屋をいたく気に入ったようだ。
お猪口を持つ姿もサマになっている。
「ボクも禁止というのはおかしいと思うよ。
やりながら学ぶべきだ」
「そうよね……」
瀬尾は、りんごサワーのジョッキを傾けた。
自身の感覚が間違ってはいなかったことに安堵する。
「キミは自分の考えを伝えたのかい?」
「もちろんよ! 学ぶ機会を作ろうって。
でも、カリキュラムがどうのこうのと言われて終わり」
「カリキュラムか。
日本人ってのは、何でもキッチリするのが好きだね」
オリバーは呆れたように言って、お猪口を口に運んだ。
瀬尾は残りのりんごサワーをあおる。あまり酒が強くない彼女は、すぐにジョッキから口を離して咽せた。
情けない言葉が口をつく。
「いつもそうやって止められる。カリキュラムが大事なのはわかるけど!
自分が思うことができないの。私、そんなに頼りないのかしら」
夢をもってこの世界に飛び込んだ頃は、こんな壁があるなんて想像もしなかった。
屈託のない子供たちの笑顔を思い出すと泣きそうになる。
少し、酔いが回っているのかもしれない。
「実咲。キミの唯一の欠点は、自信を持てないところだ」
オリバーが静かに言った。
「実咲は丈二なんかよりずっと素晴らしい教師だよ。
あの人は経験年数が多いだけだ」
「丈二先生がどうかしたの?」
「だって、丈二は子供の方を向いてないじゃないか」
瀬尾が隣を見遣ると、オリバーは眉をひそめていた。
彼はクラスを順に回って英語の授業を行い、授業を終えると休み時間を子供たちと過ごす。
3年3組の様子を見て感じるところがあったのだろう。
「実咲はそのまま、今できることをやればいいんだ。
自信を持って」
「ありがとう、オリバー」
「まだ何か悩んでる?」
「別で引っかかってることはあるけどね。でも、元気出た!」
瀬尾は笑顔を見せ、自分なりにできることを探してみようと気持ちを切り替えた。
「おでん、お待たせしましたー」
快活そうな店員がオーダーした品を運んでくる。
「お箸、お上手ですね。俺なんかより全然キレイな使い方だ」
「そうかな。どうもありがとう」
「彼氏さん、日本は長いんですか?」
オリバーは「まあね」などと普通に応じているが、瀬尾は酒を吹きそうになった。
少し雑談してから店員が下がると、顔を見合わせて苦笑いする。
ちょっとお調子者だが憎めない店員だ。勘違いの相手がオリバーなら、瀬尾も悪い気はしない。
でも、今は仕事以外のことは考えられなかった。
オリバーだって同じはずだ。
「それで、引っかかることって?」
おでんをつつきながら、瀬尾は昼休みの出来事を話した。
「手紙を写させた、か。ヘンな話だね」
オリバーは、器用に箸を使って切った大根を口に運ぶ。
「葵ちゃんにそれを書かせて罪を被せようとしたって、丈二先生は言うんだけど」
「罪?」
「葵ちゃんの字で書かれた、良くない内容の手紙。
それが誰かに渡ったら……」
瀬尾はコンニャクを口いっぱいに頬張り、熱さに目を白黒させて言葉を切った。オリバーが「そういうことか」と頷いて箸を置く。
「でも、千乃がそんな複雑なことを考えるかな?」
「私も同じ思いよ」
「あの子は、もっと子供らしい子供だと思うんだけど」
瀬尾が持つ中嶋 千乃のイメージも同じだ。
だからこそ、あの手紙にはずっと違和感を持ち続けている。
少々酔いが回った頭を働かせるように、瀬尾は木で組まれた天井を見上げた。
「千乃ちゃんのイメージとギャップがあるからなのかなぁ。
手紙自体も、なんか変な感じがするのよ」
「その手紙って、具体的にはどんなものだったの?」
瀬尾は記憶を辿る。
職員室で小渕沢が示した二通の手紙。
茶色の折り紙の裏側に書かれていた文面。
【ひどい人がいるから 気をつける】
まったく同じものが、もう一枚。
千乃が葵に書き写させたのだと、小渕沢は言っていた。
「ちょっと待って。
折り紙に書いてあったの?」
オリバーの声が鋭くなった。
瀬尾が「そうよ」と応じると、彼は口の中であの文章を繰り返す。
ひどい人がいるから、気をつける──。
「ねえ、実咲。それは一体、誰が誰に宛てたものなんだ?」
「あッ……」
大鉢の中のおでんは、半分ほどを残して既に冷めきっていた。
「千乃たちが書いていたのは、本当は何だったんだ──?」
▼次話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
