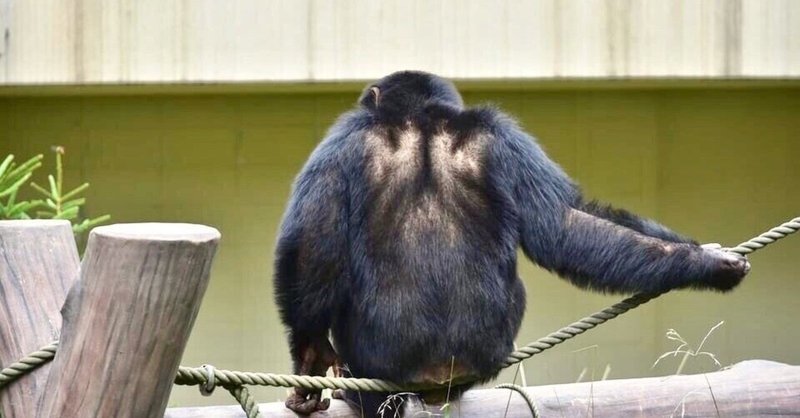
無関心につける薬
教育活動の目標に、興味関心を持たせるというのがある。目を向けさせるとか、視野を広げるとか、言い方はいろいろある。要するに、無関心を何とかしようということだ。
関心があるかどうかの基準は?
フードロスに関心はありますか?
DXに関心はありますか?
パラリンピックに関心はありますか?
財政赤字に関心はありますか?
関心がある人は、最新の情報があれば、目に止まる状態にあり、変化する状況を注視して追っている。関心がない人は、何か起こっていても気づかない。教育活動を通じて関心を持たせるにはどうすればいいのか。教師が授業で生徒に興味を持ってもらうにはどうすればいいか。
関心を持ってほしいという教員の願いは、もう一種類ある。他人に関心を持ってほしい。他の人があなたの言動をどう受け取るかを考えてほしい。なりふり構わない行動の原因は、他者への無関心である場合がある。
考えたこともなかった。
知らなかった。
クスリ1
眼中に入れる。
知らないものに関心は持てない。まずは知ってもらう。紹介するという活動から始まる。紹介するという段階で、覚えてもらおうと欲張ってはいけない。まずは知らせるだけでいい。しかし、工夫は必要だ。最初の出会いをつくるつもりで、紹介するのがいい。こんなのがあるんだよ、とリストを見せるだけでは、ふーん、で終わる。
関心がある人をお手本にする
関心がある人はどうして関心があるのか、どこに着目して興味を持っているのかを下調べして、授業づくりの視点に取り入れたい。愛好家やファン、マニアや事情通、専門家は何にワクワクしているのか、関心を持ち続けるモチベーションは何かが手がかりになる。深海魚に興味がない人は、深海魚なんてどれも同じだと考えていたり、知っても何の意味もないと思ってしまう。知る能力がないと、目に映っても気にせず見過ごしてしまう。着眼点、見方を提供することが大事だ。
勢いよく戸を閉める生徒は、戸の近くに席に一日中座っていると、乱暴に戸を閉める生徒がいかに気になるかを考えたことがない。だから、戸の近くの生徒の感じていることを知らない。この場合も、知ることが大事だ。静かに閉めろと注意するだけでわからないなら、手荒い方法だが、戸の近くの席に座らせて、乱暴に戸を閉めてやり、どう感じるかを知ってもらう必要がある。極端な例をあげたが、相手がどう感じるか、何を思ったかは意図的に機会を作らないと、知ることはできない。授業づくりも同じ側面がある。
クスリ2
関係をつくる。
無関係なものに関心は持てない。関係があるという状態は、自分の一部であるととらえること、自分の一部と考えることである。班やグループをつくれば、いきなり関係ができる。共同してすることを与えれば、共同体だ。一緒に何かをするためには、相手の協力が必要であり、何でもうまくやるためには、相手からついて、班員について知ることから始まる。当然、班員相互の開示が求められる。
クスリ3
間接的に役立つように示す。
直接的に自分に関係がないと思ってしまうと、情報は遮断されて入りにくくなる。直接的な実益に終始せず、応用可能性を見せなければ、自分への関連付けができない。メダリストやヒーローインタビューのコメントが、スポーツ界以外の人の心をつかんだり、昔の歌謡曲が時代を超えて人々に良さが伝わるのは、そのことだけじゃないという応用可能性を含んでいるからだ。
議院内閣制に関心が持てなくても、企業経営なら興味を持つかもしれない。組織運営や意思決定、ガバナンスなど、統治機構につながる制度設計の視点として議院内閣制を扱えば、企業統治や学校内の意思決定など、何かを気づかせるヒントになる。
他にも同様の構造があること、扱う内容の中身だけでなく、枠組みや柱に着目し、同じ枠組みが他にもないかということを考えて、応用可能性を教員は探して、授業で紹介してほしい。いろいろな世界を知ることの意義を伝えることで興味関心を引き出したい。
国民的アイドルからグループアイドル、ユニットへアイドルの形態は変化した。
ブッダ亡き後、仏教は阿弥陀など諸仏や菩薩など信仰の対象は広がった。
同じ枠組み、構造を見つけられませんか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
