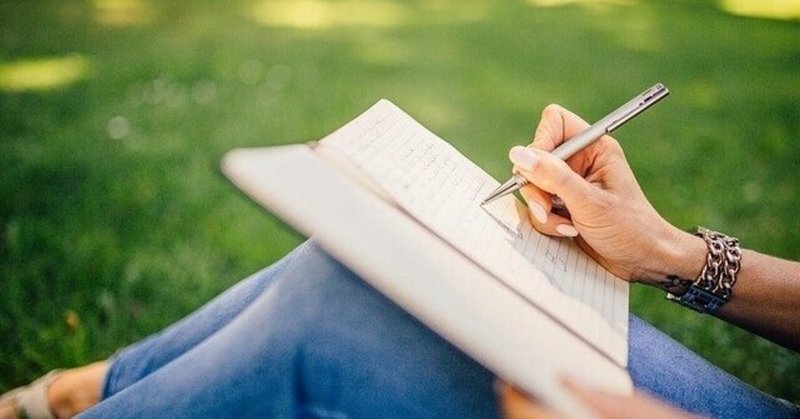
職業、ライター。「取材・執筆・推敲 書く人の教科書」を読んで
「取材・執筆・推敲 書く人の教科書」。こんな本に出会いました。
ライターとして稼ぐ方法や刺さる文章の書き方ではなく、取材して文章を書くことの本質を綴った本を、ずっと探していました。
一字一句を、また丁寧に読み返したいと思えるような本は他にありません。
全480ページ。その分厚さに、著者の「書くこと」への思いがぎゅっと詰まっているような気がします。
読みながらたくさん線を引き、付箋をつけました。私がこの本の要約をすることなんてとてもできないけれど、心に残った文章を私の感想とともに、ここに残します。
書く力より前に必要な、「世界」を読む力
取材相手への敬意が深いほど、返事はていねいになるだろう。取材相手を軽んじているほど、返事は雑になるだろう。返事(原稿)には、取材者としての姿勢がかならず反映される。p.33
著者の古賀史健さんは、原稿のことを「返事」と表現します。取材に協力してくれたあなたへの返事。
誰かに手紙を書くとき、その人の表情や仕草を思い浮かべます。自分が伝えたいこととともに、どんなことを書いたら喜んでもらえるかを考えたりもします。
原稿を返事を捉えると、「いい文章を書こう」というより「こころを込めて丁寧に書こう」と思えます。
すぐれた書き手たちはひとりの例外もなく、すぐれた取材者である。p.46
鍛えるべきは「書く力」ではない。まずは「読む力」を鍛えてこそ、すぐれたライターたりえるのだと。p.48
以前、すぐれた画家は「描く力」ではなく、対象を「見る力」があるのだと耳にしたことがあります。ライターが鍛えるのは、「読む力」。
質問する力ももちろん大切だと思うけれど、それ以外にも、何か違う力が必要なのかもしれない。相手の世界に浸り、相手を感じること。
人間としてどんな生き方をしているかが、取材者として現れるような気がしています。
自分を変える勇気を持つ
いい取材者であるために、自分を変える勇気を持とう。自分を守らずに、対象に染まり、何度でも自分を更新していく勇気を持とう。他人ごととして書かれた原稿など、「返事」にはなりえないのだ。p.73
自分が心から相手の世界に入れたとき、その原稿はたくさんの人に届く。けれどどこか入り込めていないとき、なぜだか届かない。
私はときどき、自分を変えずに守り抜きたいと思ってしまいます。それが、読み手への届き方に現れてしまうのです。
自分を変えるのは勇気がいることだけど、何度でも自分を更新していくことで、取材者としての自分のレベルは一歩ずつ上がっていくのかもしれません。
取材者としての、「聴く」態度
そもそも取材相手に「おもしろい話」を求めること自体が間違いなのだ。「相手がおもしろい話をしてくれなかったから、いい原稿にできなかった」なんて、まったくプロ失格である。p.83
「原稿を書くときに苦労したくない」「原稿に必要な材料を、確実に集めておきたい」「決められた時間のなかで、首尾よく取材を終わらせたい」ただそれだけの理由で取材の流れを決め、脱線を許さず、つまりは相手の自由を奪いながら場をコントロールしているに過ぎない。職業ライターとして考えれば、それが近道なのかもしれない。しかし、インタビュアーとしてその態度は、正しいと言えるだろうか?p.86
取材中、原稿の「獲れ高」ばかりを考えているあなたは、取材者としていちばん大切な敬意を失っている。p.90
相手のことばを遮って ーー事前に用意したーー 次の質問に移るような取材からは、なにも生まれない。p.102
インタビュアーとしての自分に言い聞かせたい言葉。
インタビューをしながらもライターとしての自分がどこかにいて、「いい記事になるだろうか?」「どこが使えるだろうか?」なんて考えてしまうことがあります。きっとそれは、取材相手に伝わっている。
私自身、取材のときに心がけていることがあります。取材の時間が、相手にとって新しい自分の気づきに繋がったり、世界が広がるような体験になるといいなと、そう思いながらやっています。
もう一度それを、心得る。
自分のこころを動かすのは、自分自身
なにを聴いても「へぇー」で終わり、なにに触れても感動できない人は、「与えられること」に慣れすぎている。与えられるのを待っていてはいけない。自分のこころを動かすのは、あなた自身なのだ。p.104
相手の話を聴いて、さらに聴いてみたい何かがあるかどうかは、私自身の受け止め方による。一部のことにしか関心が持てないようであれば、無理矢理質問を絞り出すような状態になってしまいます。
それでは、相手にとってはもちろん、自分にとっても苦しい時間になってしまう。
心から「面白い」「もっと知りたい」という気持ちを持てるように、日々の生活の中で、色んなモノに触れることへのアンテナを立てていたい。
取材相手の「人」を読み取る
声が聞こえない文章からは、「情報」を読み取ることはできても、「人」を読み取ることができない。「人」が読みとれない原稿には、どうしても入り込むことができない。p.118
しっかり音源を聴き込んで、その声をあたまに焼きつけよう。目を閉じればいつでもその人の声が耳元に聞こえてくるくらい。音源に触れよう。もちろんこれは、口調や口ぐせまで含んだ話だ。p.122
「人」を感じられる文章からは、書き手の想いも感じられる。そんな文章は、一気に引き込まれるようにして読んでしまいます。
日本語として正しい文章が書けているかどうかよりも大切なこと。
取材のなかで「わたし」はなにを感じ、なにを思い、そこからなにを考えたのか。なにをおもしろいと思い、なにをノイズだと判断したのか。本を読むとき、人によって付箋を貼る場所が違うように、主体としての「わたし」が違えば、つくられる原稿の姿も変わってくるのである。p.126
書き手自身がおもしろいと思っていないことに筆を費やしても、原稿はおもしろくならない。p.220
この文章は、「わたしが書く意味」を考えるきっかけになりました。
綺麗な文章を書ける人は「わたし」以外にもたくさんいる。けれど「わたし」を通して書けるのは、「わたし」しかいない。
「なにを書かないか」を考える
なにかを書こうとするときのライターは、絵描きというより彫刻家に近い。鑿と木槌を手に不要な箇所を削りとっていった結果、ぼんやりと像(書くこと)が浮かび上がってくる。実際に「書く」のはそれからである。p.191
つい、せっかく聴いたのだからとあれこれ詰め込んで書いてしまう。
書く前に、この文章を通して何を伝えたいのかを考えたとき、きっと「なにを書かないか」が決まってくるのだと思います。
余計なものをたくさんくっつけた文章より、シンプルに本当に大切なものを残した文章の方が、きっと読み手には届きやすい。
「人」を描き、ファンになってもらう
ぼくの考えるインタビュー原稿のゴールは、「その人のファンになってもらうこと」である。p.265
「言っていることの正しさ」に同意するというよりも、「人としての在り方」に親しみや好感を持ってもらうこと。それがインタビューする側の責務だ。p.265
「ファンになってもらう」。
この考え方、とても好きです。あぁ、私が大切にしたいのはこれなんだと、そう思えました。
「こんな素敵な人がいるんですよ」という気持ちを込めて、私が思う素敵ポイントを凝縮して、記事を書いていきたい。
推敲とは、「自分への取材」
推敲とは「書き手としての自分」と「読者としての自分」を切り離しておこなうものである。このときあなたは、なにを考えていたのか。なぜこう書いたのか。このエピソードはほんとうに必要なのか。もっと別の話、別のたとえ、別のことばはないのか。赤ペンをたずさえて書き手 ーーすなわち過去の自分ーー に取材していく。p.372
ライターは、「相手を読む人」であり、「原稿を書く人」であり、「原稿の読者」でもある。
すべて自分なのだけど、その時々で立場が変化する。どの立場であっても一貫して、「問う力」は必要なのかもしれません。
「迷ったら捨てる」の原則
推敲に「もったいない」は禁句である。読者はあなたの「苦労」を読むのではない。そしてあなたに支払われる原稿料は、「苦労」の対価ではまったくない。そこに投じたれた時間や労力に関係なく、読者はただ「おもしろいコンテンツ」を読みたいのだ。p.384
時には「こんなに時間をかけたのに…」と思ってしまう部分をカットすることもあるかもしれない。けれど、そこまでかけた時間や労力は、きっとその原稿全体の質を高めてくれると思います。
捨てたからといって、かけた時間や労力が無駄になるわけではない。
編集者は、「プロの読者」
編集者の意図を汲み取ったうえで、できれば編集者からの提案とは違ったやり方で ーーつまりはその提案を超えるやり方でーー「自分だったらこう書く」の翻訳をほどこしていく。それが、編集者との理想的な共同作業だ。p.404
編集者とライターの役割がわからず、ずっとモヤモヤしていました。
ライターとしての自分も読者だけど、編集者は自分とは違う視点を持った「プロの読者」。3人目の読者に届ける前に、まずは2人の読者で、原稿の質を高める作業をしていく。そんなやりとりができたら理想的だなと思いました。
最後に
ここで紹介した文章以外にも、この本を読みながらたくさん線を引きました。
もしもあなたが、書くことに誇りを持ち、書くことで自分の世界を広げたいのなら、この本を読む価値はあると思います。
肝に銘じてほしい。ライターは、作家に満たない書き手の総称などでは、まったくない。「わたし」を主語とせず、「わたしたち」を主語に生きようとする書き手の総称が、すなわちライターなのだ。ぼくはその価値を、これからも強く訴え、証明していきたい。p.425
最後までお読みいただきありがとうございます(*´-`) また覗きに来てください。
