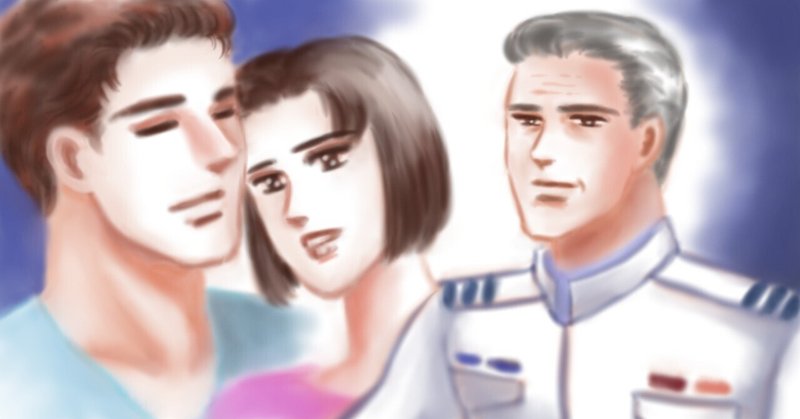
古典リメイク『レッド・レンズマン』13章
13章 リック
Q砲を装備した新型艦で狩りまくったおかげで、海賊船はほとんど出なくなった。下級基地と中級基地もかなり発見して、構成員を逮捕し、パトロール隊の監視下に置いた。まだ海賊組織を壊滅させたわけではないが、活動はおおむね凍結させたといえるだろう。
おかげで、連動していた麻薬組織も弱体化したのはいいが、今度は船の失踪事件が増えてきた。
パトロール艦であっても、民間船であっても経過は同じだ。平穏だった航路の途中で、突然、消滅する。恒星の異変や小惑星との衝突のような、自然現象に由来する事故でもない。
最初は海賊の残党か、デルゴン貴族の仕業だろうと思っていたが、どうやらパターンが違う。襲われた船の、残骸すら発見できないのだ。最後に通信があったあたりを捜索しても、何の痕跡も発見できない。破壊された船の破片もなければ、そこから逃れた救命艇も見当たらないし、手掛かりになるような通信も受信されていない。
そういえば、デッサの消え方も普通ではなかった。今でもレンズマンたちがあらゆる方法であらゆる星区を捜索しているのに、デッサについてもアイヒ族についても、何の手掛かりもない。
やはりボスコーンには、何かまだ、我々の知らない秘密があるらしい。
奴らはライレーンからは手を引いたが、今度はまた、違う方面から銀河文明に攻撃を仕掛けてくるだろう。今の静けさは、これから起こるだろう反攻の時間稼ぎであるに違いない。
《当面は、失踪事件を追うつもりです。そこに何か、上級種族への手掛かりがあるかもしれません》
ヘインズ司令にそう報告して、ドーントレス号で宇宙を飛び回った。各星区に散っているパトロール艦隊からの報告を受けつつ、レンズで広範囲の索敵をする。
数週間、そして数か月。
襲撃の現場に立ち会えないまま、日々が過ぎる。向こうの襲撃パターンを読み、逆利用できないか。囮船を仕立てて、それが襲われるのを待つのはどうか。
あれこれ試しているうち、ついに、貴重な手掛かりが得られた。民間の商船が襲われて消え去る寸前、かなり離れた位置を航行中のレンズマンが、彼らの心の叫びを、かすかに聞いたのだ。
宇宙の地獄穴、吸い込まれる、と。
突然に遭遇した、小さなブラックホールだろうか。しかし、ブラックホールなら観測できるはずだ。運悪く近づきすぎてしまっても、助けを求める通信くらい、送る暇はあるのではないか。
それに、後からそのあたり一帯を捜索しても、移動するブラックホールは発見できなかった。既に蒸発してしまったとしても、その航跡くらいは残っているはずだ。
大勢のレンズマンが精神融合で参加した会議で、情報が共有され、対策が検討された。
《宇宙の地獄穴、ですか》
《ボスコーンの新しい兵器かもしれません》
《確かに、自然現象ではなさそうだ》
《物理的な遠隔攻撃でしょうか。精神を破壊するような幻覚ならば、乗員に船を自爆させるにしても、残骸が残るはずです》
結局は、銀河系全体に大量の観測機器を撒くことにした。物量に頼るのは情けないが、とにかく、攻撃の手法がわからないことには、手の打ちようがない。
(きりがないな……)
末端の麻薬組織や海賊組織を潰しても、本体が無事である限り、ボスコーンはまた別の芽を伸ばしてくるのだ。
銀河系内で発見できた知的種族は、ほとんど銀河評議会に誘い入れ、パトロール隊に協力してもらっているのに。ボスコーンの上級者は、どこに潜んでいるというのだ。
(やはり……)
ボスコーンが、この銀河の外に本拠地を持っているとしたら。その仮定を、本気で考える頃合いだ。
それとも、既に他の銀河を征服し終えて、この銀河の攻略に取りかかっている?
宇宙に散らばる多くの銀河が、既にボスコーンの支配下にあるのだとしたら。海賊たちは、他の銀河に真の拠点を持ち、そこから遠征してきているのだとしたら。
以前なら、考えすぎだと思っただろう。しかし今では、その可能性が高まってきたと感じている。もしそれが真実だとしたら、我々は、根底から対応を考え直す必要がある。
我々は当初、ボスコーンを単なる犯罪組織と思っていたが、実際には、帝国とも呼ぶべき一大文化圏だったことが判明した。表の銀河文明に対する、裏面の暗黒帝国だと。
だが、真実は、それより更に巨大な……この宇宙の大半を支配している、闇の文明なのかもしれない。
我々の銀河は、闇の中にぽつんと取り残された、ただの小島なのかもしれないだろう。
改めてヘインズ司令に呼びかけ、他の独立レンズマンたちと精神感応で疑惑を共有することにした。ヴェランシアのウォーゼル、パレイン系のナドレック、リゲルのトレゴンシー。グレー・レンズマンの中でもトップクラスの面々だ。
《アイヒ族など、ボスコーンの上級種族が、本来、他の銀河の住人だとしたら……既に近隣の銀河は、ボスコーンに征服されているのかもしれません。我々の銀河だけが、アリシア人の庇護のおかげで、助かっているのかもしれない。ならば、その庇護があるうち、こちらから打って出るべきではありませんか!!》
彼らの理解と決断は、早かった。こんなに早くていいのか、と思うくらいだ。
《十分にありえる話だ》
《近隣の銀河に、探査隊を送るべきかもしれない》
《いや、探査隊というより、戦闘艦隊とすべきだろう。ボスコーンとぶつかったら、撃破しながら先へ進むのだ》
《では、その計画を立てるとしよう》
つまりは彼らも、ボスコーンが根絶できないことはおかしいと考え、次の段階に進むことを企図していたのだ。ぼくが呼びかけずとも、彼らのうちの誰かが訴えていたことか。
《いや、そうではない、リック》
ウォーゼルが思考を投射してきた。
《我々は、この銀河を防衛しなければ、とは考えていた。だが、全宇宙の未来のために、他の銀河へ出向こうとまでは、決心していなかった。きみの意志に触れて、初めて、それが不可避の未来だと確信したのだ》
ナドレック、トレゴンシーも同意見だった。
《このままでは手詰まりだ》
《視点を変える時が来たのだろう》
ほっとした。方針は共有されたのだ。それならば、後は実務を進めるだけだ。
《手始めは、アンドロメダ銀河だろう。もしも、そこがボスコーンの巣になっているとすれば、探査隊がそのまま戦闘の前衛になる。大規模艦隊が必要だ》
《これから建造にかかるとして、どう急いでも、一年から二年は準備期間が必要だ》
《まず、銀河評議会で決議しなければ。銀河市民全体の承認がなければ、それだけの予算と人員を投入することはできない》
そこから他の全てのレンズマンに呼びかけ、積極的な賛同を得た。もはや、この銀河だけの戦いでは済まないことを、彼らも感じていたのだ。
かくて話は銀河評議会に持ち込まれ、報道されて、全ての銀河市民の知るところとなった。マスコミが熱狂的に報道し、銀河パトロール隊への支援を呼びかける。
「ボスコーンの本拠は、他銀河かもしれない!!」
「ボスコーンとは、複数の銀河にまたがる闇の文明なのか!?」
「アンドロメダ遠征のため、史上最強の艦隊が建造されることになる!!」
「若者よ、パトロール隊に来たれ!!」
「あらゆる種族、企業の協力を求む!!」
大艦隊の建造には、多くの資源とエネルギーを結集しなければならない。具体策は、多くのレンズマンたちに割り振られた。資源惑星の確保、新たな工場建設、各種族からの技術陣の招集……司令部は休みなしでフル活動し、クリス姉さんも忙しく調整に駆け回る。
そういう日々の中、改めてヘインズ司令から、レンズ越しの接触を受けた。
《遠征艦隊には、総司令官が必要だ。リック、そのつもりでいてくれたまえ》
さすがに、ぼくも震え上がった。やっと三十を過ぎたくらいの若造に、アンドロメダ遠征軍の指揮官とは……途方もなさすぎて、眩暈がする。
《もっとベテランのレンズマンがいるはずです。その副官くらいなら、何とか務めるつもりですが》
《ベテランはいるとも。白髪で、老眼で、満身創痍のな》
初老の司令官司は、自嘲の笑みを浮かべてみせた。
《だが、これから長い戦いになるとわかっているのだ。まだ疲弊していない、若い指揮官の方がいい。それにきみは、その重荷を、他の誰に背負わせるつもりかね?》
《人類以外のレンズマンは、もっと寿命が長いですよ》
《それは、彼らが穏健な種族だからだ。ヴェランシア人でさえ、多くは、デルゴン貴族と戦うことしか望んでいない。それに、パトロール隊の主力が人類であることは間違いない。我々が先頭に立って、初めて、他の種族がついてくる。心配するな。ウォーゼルとナドレック、トレゴンシーがきみを補佐してくれる》
ぼくは抵抗をあきらめた。仕方あるまい。ヘインズ司令自身は、天の川銀河の防衛に必要だ。最強クラスであるウォーゼルやナドレック、トレゴンシーが一緒に来てくれるのなら……若造であっても、ぼくがやるしかない。
それにしても、これから先、何千年、何万年の戦いになるのだろうか。もし、ボスコーンが、宇宙に散らばる銀河のうちの、多くを支配しているのだとしたら。
弱気になるつもりはないが、途方もない話ではないか。
我々はこれまで、この天の川銀河を……自分たちの銀河を守れば、それでいいと思っていた。しかし、もしも、他の銀河全てのことまで考えなければ、宇宙全体の安寧が守れないとしたら……
ぼく一代で済む話ではない。子供、孫、更にその孫……はるかな未来まで続く戦いになる。
初めて、クリス姉さんの言うことが腹に落ちた気がする。自分の子供を残すこと、それもまた、戦いの一部なのだ。いや、それこそが、真に重要な責務なのかもしれない。
いま戦うのは、子供の、子供の、そのまた子供たちのためだ。何としてでも、前へ進むしかないだろう。さもなければ、暗黒の帝国の支配下に置かれてしまうのだ。
アリシア人は、そのことを知っていたのだろうか。そして、我々が自らその結論にたどり着くまで、黙って待っていたのだろうか。
できれば、もう一度、アリシアのメンターに会いたい。だが、彼は、ぼくに宣言した。二度と戻ってくるなと。ならば、それに従う他はない。我々にレンズをくれた老種族は、きっと、はるかな未来まで見通しているのに違いないのだ。
***
大艦隊の建造を見守りながら、哨戒任務を続けた。ただし、今では毎日のように、レンズでベルと交信している。
《具合はどうだい? 無理はしてないか? ちゃんと食事は摂っているだろうね?》
《まあ、リック……》
ベルは目の前にいるようにくっきりと見え、はにかんで微笑んでいる。
《見ての通り、無事よ。毎日、もりもり食べているし。とってもお腹が空くの》
ベルのお腹にいるのは、女の子だ。まだほんの小さな胎児だが、ぼくには見える。賢い子だ。母親を通して、外界の物音を聞き分け、外の世界を推し量ろうとしている。
きっと将来は、ベルのような科学者になるのではないか。いや、何になってくれてもいい。幸せな一生を送ってくれるなら。そのために、ぼくはこうして宇宙を飛び回っている。
自分が父親になる……それは、奇跡的な幸福だった。少し前までは、夢想することすら避けていたのだ。
ぼくが死んでも、命が続いていく。
先祖から受け継いだ命を、次代につなぐことができたのなら、それだけで、ぼくの人生は成功だったと言えるのではないか。
おかげでずいぶん、気持ちが楽になった。愛する気持ちを無理に抑えるよりも、それを自分に許した方が、結局は、仕事にも集中しやすい。背中を押してれたクリス姉さんには、感謝するしかない。
《産み月には、きっと戻るから》
大艦隊の発進には、まだ時間がかかる。
《大丈夫よ。あなたがこうして、毎日、話しかけてくれるもの。それに、この子が一緒だし》
女は強い。ベルは最高基地の研究所で働き、何種類もの新造艦や武器の基本設計をしながら、子育てをするという。
他にも大勢、パトロール隊員の妻たちが、そうして子育てをしているから、育児の協力体制はできている。何も困ることはないと、笑って言う。
《あなたはわたしを心配しないで、仕事に集中してね》
《ああ、集中してる……地獄穴とやらを、一度、自分で確かめてみたいのでね》
ベルは身震いした。
《お願いよ、それは無人の観測機に任せて。有人船が近づかない方がいいわ。とても厭な感じがするもの》
ベルの印象では、通常の無慣性推進ではない、別の原理で作動する移動手段があるのではないか、ということだ。それがどんなものか、色々と理論を考えてはいるが、まだ雲をつかむようだと。
《アイヒ族も、まだ一人も発見できていないのでしょ。ボスコーンにはまだまだ、隠し玉がある感じだわ》
《わかっている。無用な危険は冒さない。生きて、きみの元に帰りたいからね》
互いにキスを送り合い、精神接触を終えた。ボスコーンとの戦いは、これまで何百年も続いてきたのだ。これからも、どれだけ続くかわからない。だから、焦る必要はない。
それでも、出来ることなら、娘が大きくなる頃には、平和な世界になっていて欲しいのだが。
『レッド・レンズマン』14章に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
