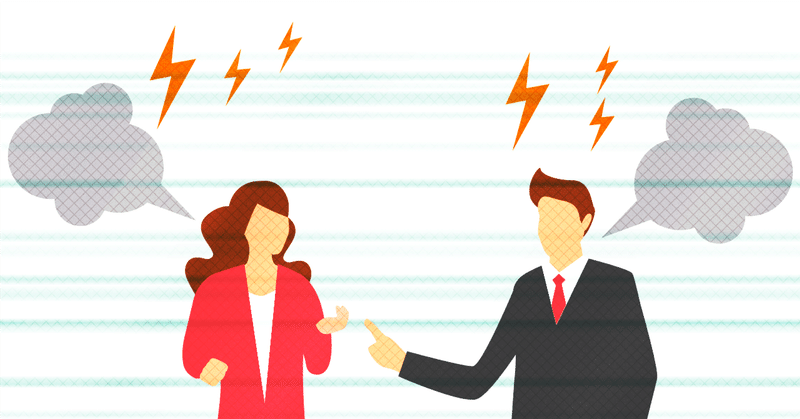
ほっといてくれ! 第9話
それからしばらくは、何事もなかった。ごく普通に仕事も入り、順調にこなしていった。小林さんからの案件もそんなに難しいものはなかったので、対応は簡単だった。
(最近は割と順調ね。)
(うん、特に問題ないし、作業も簡単だしね。)
(ずっと、こんなんだったら、いいのにね。)
(今日は早めに店じまいして、飲みにいこうか?)
(そうね、たまにはいいかもね。)
最近ボクらは、ふたりで食事をしに行くときは、個室を頼むようにしている。無言で黙々と食事をする様子は、他の人には違和感を与えるらしいからだ。ボクらにとっても、この方が気楽でいい。
(ところでさ、一度、ゆうちゃんのお母さんに挨拶に行きたいんだけど。)
(ん~、どうしよう?)
(どういうこと?)
(うちの母はめんどくさいから、会わせたくないの。)
(でも、そういうわけにもいかんやろ。)
(聡子とも相談するわ。それからでいい?)
(わかった。じゃ、改めてボクんちにくる?)
(そうね、なぶクンのお母さんに会いたいわ。)
(了解、じゃ日にちを決めて連絡するよ。)
ボクらがそんな話をしながら、食事をしていると、女性の店員さんが入ってきた。
「お飲み物は?」
「いや、まだ大丈夫です。」
「あれ、呼びませんでしたか?」
「呼んでませんよ。」
(この人・・・)
(わかった?)
(えっ、ボクらと同じ?)
(そうよ。)
こういう能力を持っている人が、ボクらだけのはずがないとは思っていた。だが、こんな局面で現れるとは。
(私たち、仲間でしょ。)
(いや、同じ能力を持っているに過ぎないでしょ。)
(そんな、冷たいなぁ。私も仲間に入れてよ。)
(じゃ、一度、君の話を聞かせてくれよ。)
(いいわよ、じゃ、あなたたちの事務所に、明日いくわね。)
(わかった、待ってるよ。)
これじゃ、今までの話はじゃじゃ漏れだったということか。まいったな。でも、今の話の感じからすると、敵意はないから仲間になれるかも知れないな。
(これからはボクらの話が、他に流れないように、ピアツーピア化しないとだめだね。)
(それはどういうこと?)
(つまり、二人の間だけでシールドしてしまって、他に漏れないようにするんだよ。)
(インターネットでいうトンネリングという技術だね。)
(難しいわね。)
(どうしても無理なら、言葉にだして話さないとね。)
(できるかどうかわからないけど、試してみないとね。)
(今はじゃじゃ漏れよ。)
(あっ。)
(だって、聞こえてくるんだもん。)
こまったもんだ。早いうちにピアツーピア的な話し方を習得せねば。
翌日、彼女がやってきた。
(こっちの話し方がいい?)
(そうだね、ボクらはもっぱら、この話し方でやってるよ。)
(じゃ、改めまして、私、本多恵子と言います。)
(ボクは竹内学。)
(私は栗原裕子よ。)
(ここで調査会社をしてるのよね。)
(そうだよ。で、君はどんな能力があるの?)
(これ以外にってこと?)
(そうだね。)
(ボクは多少なら、ものを動かせる。)
(私はこれだけよ。)
(私もこれだけ。)
(この能力もいろいろあって、ボクは普段は人の声は聞こえてこない。)
(私も同じ。聞こうとしないと無理ね。栗原さんは?)
(私は聞きたくなくても勝手に聞こえてくる。)
(それって、大変ね。)
(大変。でも、最近は食い止めれるの。)
(実は私、あなた方の話をだいぶ前から聞いていたの。)
(やはり、そうなんだね。)
(ふたりは恋人同士でしょ。それにこの事務所も能力を使ってやっていることも。)
(まあ、知られても仕方ないね。)
(私もいろいろと仕事をしたけど、どうもしっくりいかなくって。)
(この事務所にってことか。)
(私だって、同じ能力があるんだし、役に立つと思うの。ねえ、お願い。私も雇ってくれない?)
なんとなく、そんなことを言ってくるような気がした。
(その件は一旦預かって、明日には返事させてもらうよ。)
(今、決めてほしいんだけど、ん~、まあいいっか。)
もしかして、今後、この人のように能力をもった人たちが集まってくるんだろうか。
彼女が帰ったあと、ボクらはどうするか話し合った。
「今回はこの話し方で。」
「そうね、まる聞こえだもんね。」
「さて、どうしよう。」
「入れるつもりなの?」
「いや、まだ決めてないよ。」
「即答でNOだと思ったわ。」
「なぜ?」
「なぜって、決まってるでしょ。絶対無理よ。」
「これはビジネスの関係だけだよ。」
「わかってるわ。でも、この仕事ってプライベートと区別することが難しいのよ。」
「そう思う?」
「私たちの間だから、プライベートとか気にしないでできるけど、彼女が入ってきたら、それは絶対無理よ。」
「そうか、わかった。君の言う通りだね。」
「なぶクン、即答だと思っていたのに、こんなことで悩むなんてあり得ないわ。」
「そんなにせめんなよ。」
「絶対に人は入れない。ここはそういう仕事場よ。」
「わかったよ。」
ゆうちゃんがこんなに激高するなんて、ボクはかなり驚いた。もっと、物静かな人だと思っていたのに。
(ねえ、どう?)
(えっ、本多さん?)
いきなり声をかけられてびっくりした。
(これは栗原さんには聞こえないわよ。)
(どうして?)
(あなたの言うピアツーピアになってるわ。)
(どうしてそんなことができるん?)
(栗原さんが入るとどうしても、ジャジャ漏れよ。でも、私たちみたいな能力だと、こうなるみたい。)
(そうなのか。)
(で、どうなの?入れてくれるの?)
(悪いけど、だめという結論だよ。)
(やっぱりね。栗原さんが反対すると思ってたわ。でも、あなたはそうじゃなかったでしょ?)
(なんでそう思う?)
(だって、同じ能力をもった仲間でしょ。)
(なるほど。)
(まあ、仕方ないわ。でも、たまに話はできるでしょ?)
(それは問題ないよ。)
(よかった。じゃ、またね。)
本多さんは多分、今までこういった能力を持った人と出会ってなかったんだろうから、ボクと話をしたいんだろう。でも、女同士の方が話しやすいこともあるだろうに。
ボクは一つ勉強になった。ボクのように自分からいかないと人の心の声を聞けない能力者同士は、ピアツーピアで話しができるということだ。ゆうちゃんと話しをするときは、声に出して話をしてくようにしないといけないな。
その日、ボクらは極力声にだして話をするようにした。だけど、今までそんなことしてこなかったので、ついやってしまうこともある。これからはだんだん慣れていかないとな。
「だけど、心で話すのが、ジャジャ漏れだったとはね。」
「私もまさかそんなことになっていたなんて、知らなかったわ。」
「普段、こうして面と向かっているときは話しができるけど、離れているときはスマホを活用しないといけないね。」
「慣れているから、面倒臭いよね。」
「まあ、仕方ないよ。」
「そうね。」
そうこうしてベッドに入ってからのことだった。
(ねえ、まだ起きてる?)
(本多さん?どうしたん?こんな時間に?)
(隣に栗原さん、いるの?)
(いや、最近は別の部屋で寝てるよ。)
(そうなんだ。)
(で、なんだい?)
(相談に乗ってほしいの。)
(栗原さんじゃなくていいの?)
(なんで?)
(だって、女同士の方がいいのかな?って思うからさ。)
(あなたがいいの。同じ能力を持ってるから。)
(そっか。じゃ、今からでも話く聞くよ。)
(面と向かって話がしたいから、明日でもいい?)
(ああ、構わないけど。)
(じゃ・・・)
明日、本多さんと待ち合わせをして、話を聞いてあげることにした。
「今日は、本多さんが話を聞いてほしいということなんで、いってくるよ。」
「えっ、何それ?」
「んっ?どういうこと?」
「だって、私がいるのよ。」
「話を聞くだけだけど?」
「私たち、付き合っているんじゃないの?」
「当然、そうだよ。」
「だったら、やめて。」
「相談に乗ってほしいって言われただけだよ。この前の件は断ったし、問題ないだろ?」
「私以外の女性と2人ってことでしょ?絶対だめよ。」
「意味がわからないよ。特に問題ないとボクは思うよ。」
「もう、勝手にしたら。」
なんでそんなに怒るんだ?よくわからない。本多さんの相談に乗ることが、そんなに問題なのか?ボクもなんかムカついた。
夕方、ボクは待ち合わせ場所に行った。先に本多さんが来ていた。
「ご飯、いいわよね?」
「ああ、構わないよ。」
「じゃ、私に任せて。」
「了解。」
本多さんはイタリアンの店に連れていってくれた。
「ふふふ、ケンカしたでしょ?」
「なんでわかるん?」
「そんな顔してるもん。」
「ボクが本多さんと話をすることが気に食わないらしい。」
「さて、どうしてでしょうね?」
「ボクにもわからないよ。」
なんか、本多さんは意味ありげな笑みを浮かべていたが、ボクはあまり気にならなかった。それから、他愛もない話が続いたが、本多さんは一向に本論に入っていかない。いったい、何を相談したかったのだろう。
「で、何を相談したかったん?」
「それはもっとあとでね。」
ボクらは結構、ワインを飲んでいた。
「竹内クンは、なんで栗原さんと付き合っているの?」
ボクは栗原さんと付き合うことになったいきさつを話した。
「ふ~ん、そうなんだ。じゃ、仕方なしにってことだよね。」
「まあ、そうかもしれないね。」
「じゃ、私のこと、どう思う?」
「まだ、会って間もないし、どうと言われても・・・」
「第一印象は?」
「そうだな、チャーミングだし、綺麗な人って感じかな?」
「ありがとう。竹内クンも素敵よ。」
素敵なんて言われたことないから、ちょっとうれしかった。
「そうかな。」
「ねえ、このあと、ちょっと私んちに来ない?」
「いいの?」
だいぶ酔ったから、コーヒー飲みたいなぁ。
「おいしいコーヒー、入れてあげる。」
「ありがとう。」
ボクはうれしくなって、本多さんちへお邪魔することになった。なんか、栗原さんなんかどうでもよくなっていた。それから先は、本多さんの心地いい言葉、心地いい部屋、心地いいからだに酔いしれた。ボクは完全に本多さんに惚れ込んでしまっていた。
翌日も、その翌日もずっと本多さんとふたりで過ごした。ほんとに心地いい。最高の気分だ。なんで、栗原さんと一緒にいたんだろう。やっぱり、あり得ない。
「もう、ずっとここにいていいのよ。」
「そうか、ありがとう。」
「あの事務所もたたんでいいのよ。」
「でも、働かないと経済的に破綻しちゃうよ。」
「大丈夫、私にまかせておいて。」
「いいのか?」
「いいの、気にしないで。」
よくわからないけど、本多さんは多少の蓄えを持っているのかもしれない。ふと気がつくと、ボクのスマホに多量のメールや受信履歴が入っていた。全部、栗原さんだ。なんて、うっとうしいんだ。
「あ、それ、大丈夫、私が話つけておくから。」
「そう、ありがとう。」
なんて、本多さんは優しいんだろう。この子、最高だ。
ボクはこの時、何もわかっていなかった。ボクは、完全に本多さんに操られていたのだ。彼女の能力は、テレパシーだけではなかった。心を自在に操れる。生かすも殺すも自由自在だったのだ。ボクは彼女に完全に操られてしまっていた。
しばらくして、松ノ木事務所は廃業した。栗原さんが事務所をたたんだのだった。そして、彼女は田舎へ帰っていった。完全にボクのことを忘れてしまってね。これもすべて、本多さんの能力によるものだった。本多さんはこの能力をつかって、いろんな男を自分に貢がせて、多額の資産を手に入れていた。
だが、ボクにはそんなことを知る由もなかった。本多さんとの幸せな時間を過ごしている感覚でしかなかった。だが、ボクが我に返ったのは、それからまもなくのことだった。ボクは本多さんにとって用済みになったのだ。ボクには、すでに本多さんの記憶もなくなっていた。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
