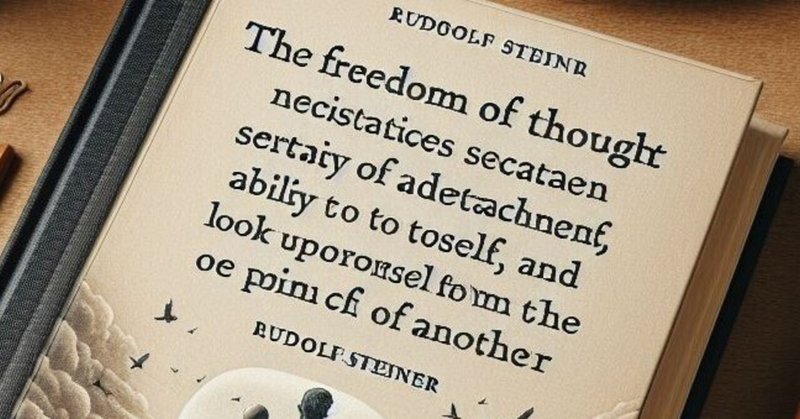
寝ながらシュタイナー『自由の哲学』(7/9)
Ⅴ 各章の二項対置による簡潔な要約
『自由の哲学』第2章の冒頭で、ゲーテの『ファウスト』の詩の一部が掲げられ、人間は二つの欲望・誘惑の間にいる存在であることが紹介されます。
シュタイナーの「一元論(自由の哲学)」も、19世紀末までの様々な思想・哲学との対置関係を通して、一歩前に踏み出す哲学となっています。
「一元論」は、それらの思想・哲学と対立しつつも、それらを「必要な前段階」だとして、最終的には「一元論」へ収斂していきます。
未熟な(未自由な)人間が自由な人間へと進化するように、古い(未熟な)哲学すべてが「一元論(自由の哲学)」へと進化する、その進化の一過程として位置づけられるのです。
本章では、『自由の哲学』の各章を二項対置によって簡潔に要約していきます。
第1章 〈動機を意識せずに行う行動〉と〈動機を意識して行う行為〉
(第1章は、『自由の哲学』の前奏『真理と学問』の最終章の問い、「人間に「動機を意識して行う行為」の領域があるか」ということが主題です。この領域は、直観的思考(理念的直観)を受けとめる領域であり、自由な意志を展開しうる魂の領域です。)
シュタイナーは、19世紀末までの様々な思想・哲学が「動機を(完全に)意識して行う行為の領域」が人間にあることを認めない(認めなかった)ことを例証していきます。
シュタイナーは、この領域を認め、この領域に人間の自由を見ます。この領域は、人間の本性(構成要素)の中に(萌芽のようなものとしてですが)確かにあり、だからこそ私たちはこの領域を育成し、目覚めさせるのです。
この領域の存在は、人間の認識について洞察することで理解されます。そのためには、思考を直に体験的に理解する必要があり、私たちは思考の根源に向かうよう促されます。
第2章 〈世界(自然)〉と〈私(自我)〉
19世紀末までの思想・哲学(二元論や旧い一元論(唯物論、唯心論(観念論))は、世界と私の間を架橋することができませんでした。
シュタイナーは、自らの内面へ下りていき、そこに、いわば内なる自然として(本来の)思考を見出すことで、この架橋をなし得るとします。
世界(宇宙・自然)は、実は(本来の)思考=精神・霊と一体であり、それが私たちの内なる自然((本来の)思考)とつながることで、世界と私との架橋がなされるのです。
第3章 〈観察〉と〈思考〉
あらゆる精神的活動の出発点は、「観察」と「思考」です。
シュタイナーは、「思考の観察」(「思考」を「観察」すること、または「思考」による「観察」)で、思考の本性の一つである認識における始原性を確認できるとします。通常、観察は思考に先行しますが、思考を観察対象にしようとすると、思考が観察に先行していなくてはならないからです。
また、思考は、それ自体に根拠をもち(絶対性)、人間にとって最も身近で根源的な要素です。それゆえ、(本来の)思考は認識の出発点に置かれるべきなのです。
第4章 〈知覚(観察内容)〉と〈概念・理念(思考内容)〉
思考は、絶対的、始原的、根源的、(普遍的@第5章)なものであり、主観や客観、また意識をも超えます。
私たちは、このような思考によって命を得て、事物とともにありながら、事物と対峙し、認識する存在なのです。
思考は、ばらばらな知覚を思考の糸によって結びつけることで、認識を成立させます。知覚と思考の結びつき表象の出現の場は(私の意識という)主観ですが、その内容は(理念界との結びついており)客観性をもつのです。
批判的観念論者は、知覚内容を主観的だと主張しますが、その際、知覚者自身の知覚器官は無批判に実在(客観)としており、そのことを彼は見落としているのです。
第5章 〈自己を制約された存在だと知覚する〉と〈自己を普遍的存在として(思考)規定する〉、〈宇宙の中心〉と〈宇宙の辺縁〉
植物が花をつけるのと同様に、世界は人間の頭の中に思考を出現させます。それは、思考が世界に普遍的に広がっているという意味でもあります。
人間は、自己を時間的空間的に制約された存在であると知覚します。しかし、思考によっては自己を(自己を超える)普遍的存在として理念界におけるつながりのもとで規定します。
また、人間は、宇宙の中心から流れ出る思考を宇宙の辺縁で捉える存在でもあります。
思考の意識への出現形式「直観」は、知覚の出現形式「観察」に対応するものです。
第6章 〈感情:個人生へひきこもる〉と〈思考:世界へ拡がり共生する〉
人間は、感情によっては個人の生へひきこもり、思考によっては世界へ拡がり、普遍的に共生します。そしてまた、この両者を共に内包する存在です。
感情は、概念に命を与える(概念を生き生きとさせる)際に媒介となるものです。
それゆえ、自らの感情を伴いつつ、理念(思考)領域に最も高く上った者こそが、真の実態をもつ個人(人間的個)と言えるのです。
第7章 〈素朴実在論、批判的観念論、形而上的実在論〉と〈「一元論」〉— 認識 —
シュタイナーの「一元論」は、人間にとって知覚と概念とに分かれて(二元的に)出現するものを一つに統合(一元化)することで、認識に至るとするものです。(二元的一元論)
素朴実在論は、批判的観念論、さらには形而上的(超越論的)実在論へと進まざるを得ませんが、形而上的実在論の捉えた理念界を知覚の側からではなく、思考の側から捉え直すことによって「一元論」に至るはずです。
「一元論」においては、知覚と思考を結びつける際の不備(認識者の立脚点や生理的条件)は克服可能であり、事物は真に(客観的に)捉えることができます。(「一元論」においては「認識の限界」はなく、行為の動機を完全に意識することが可能であり、そこに「自由」が成立するのです。)
第8章 〈感情や意志を認識の根底に置く〉と〈本来の思考を認識の根底に置く〉
第一部では、知覚や通常の思考を認識の根底におくことはできないと理解されました。
第8章では、感情や意欲(内的な意志)もまた認識の根底におくことはできないことが理解されます。個的なものを世界に敷衍することになり、それでは真の認識に至ることはできないからです。
人間個人は、感情や(内的な)意志との結びつきを強く感じる存在ですが、〈本来の思考〉においては自己や世界と最も強く広く結びつきます。
通常の思考は、〈本来の思考〉の影であり、冷たく、生き生きとしていませんが、〈本来の思考〉は、その光の織り成す世界現象の中に温かく浸った現実であり、認識の根底におくことができるのです。
第9章 〔〈起動力〉と〈動因」〉〕による〈動機〉と〈意志行為〉
人間の生体機構・意識上の要因である起動力が、概念・表象的要因である動因を受け止め(結びつい)て動機となり、その動機が意志行為へと移されます。
起動力の最高段階(概念的思考/実践理性)と動因の最高段階(直観把握された個々の倫理目標)は重なっており、その重なりである理念的直観(直観的思考)を動機とする意志行為において、人間は、対象への愛、行為への愛を見出します。この行為を自らの行為であると感じ、そこに自由を認めるのです。
自由な人間の基本命題は、「行為への愛において生きること、他者の意志を理解しつつ生かすこと」です。それゆえ、自由な人間同士においては、真の共同体が成立するのです。
後半から、自由な人間と不自由(未自由)な人間とが対比されていきます。
第10章 〈素朴実在論、批判的観念論、形而上的実在論〉と〈「一元論」〉—意志行為—
素朴実在論は、動機を(認識のときと同様に)目に見える存在に求め、批判的観念論や形而上的実在論は、それを物質的経過や絶対者の意志に求めます。ともに自由はありません。
「一元論(自由の哲学)」では、動機は、個人がその都度つくりだします。(それゆえ、「一元論」は、意志行為の領域では「倫理的個体主義(自由の哲学)」と呼ばれます。)
「一元論」は、自由を獲得する(した)人間の哲学です。(「自由」が人間進化の究極であるのと同様に「一元論」は思想・哲学の究極と言えます。)
第11章 〈世界における合法則性〉と〈人間(の行為)における合目的性〉
「一元論」は、世界(自然)には、神の目的ではなく、自然法則(ただし、ゲーテの言う根源現象)を見ます。世界(自然)は合法則的なのです。
しかし、人間の行為には、神の目的でもなく、単なる自然法則でもなく、合目的性を見ます。ただし、この目的は、神が与えたものではなく、人間が自らに与えた目的です。
確かに動物も目的にかなった行動をするように見えますが、実際には動物は固有の内的必然性に従って行動しているだけです。あらかじめ決定されている必然性に従うという意味では、不自由(未自由)な人間も動物と同列の存在であると言えるかもしれません。
第12章 〈進化論〉と〈倫理的個体主義=精神化された進化論〉
自由な人間は、道徳的ファンタジーをもち、それによって理念的直観(直観的思考)を実現します。彼は、道徳的理念獲得力によって捉えた道徳的理念を道徳的ファンタジーで表象にかえ(それを動機とし)、その表象を道徳実現技術によって現象界で具体的に実現します。彼は、その都度、動機を創り出し、現実的に行為するのです。
一方、未自由な人間は、道徳的ファンタジー等をもたず、理念的直観を行為に移すことができません。彼は、動機をこれまでに見聞してきた内容(過去の経験)や社会的規範に基づいた表象など、あらかじめ外的に決定された表象から選びとり、それに従うだけの存在です。
倫理的個体主義は、倫理的営みに移し替えられた精神化された進化論です。
第13章〈ライプニッツ・ショーペンハウアー・ハルトマンの哲学〉と〈「一元論」〉
ライプニッツの楽観論、ショ―ペンハウアーの厭世主義、ハルトマンの悲観主義哲学は、いずれも自由な人間の哲学としては不十分です。
ライプニッツの楽観論は、神なき時代を生きる哲学としては不十分です。
ショウ―ペンハウアーは、「やれるだけやった」という喜びを見落としています。
ハルトマンは、人間を高次の目的(神の救済)へと向かわせようとしますが、それを「強制」することで、結局、ニヒリズムは克服されません。
自由な人間は、快(喜び)や不快(苦)を自らの欲求と結びつけ、自ら高次の目的に向かいます。彼の倫理性は、自らの欲求の内にあるのです。
自由な人間が自らの欲求の充足を求める行為はすでに倫理的行為なのです。
第14章 〈類的なもの〉と〈個的なもの〉
人間は、完全に個的な存在になる素質を持っていますが、現実的には、類的なものと個的なものが統合された存在です。
自由は、類的なものを媒介(手段)としながら、それから解放されて、個的なものが表出するときに成立します。
私たちは、類的なものを洗練し、個的なものを出現するよう努める必要があるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
