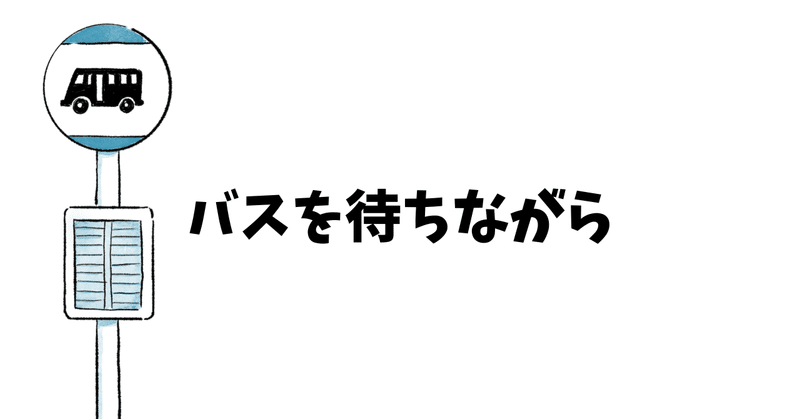
【短編小説】バスを待ちながら
真っ白い霧があたりを覆っていてまるでミルクの中のようだった。
私は家に帰るために、バスを待っていたのに、眼の前にあったはずのバス停の標識が無くなっている。下を見ても地面が見えない。まるでミルク色の靄の中に自分の体が浮かんでいるみたいだ。
「ばにぱにまーしゅんしゅん」
丸眼鏡の中年男性が向こうから体を左右に揺らしながら、歩いてくるのが見えた。
叔父だった。
大阪にいるはずの叔父がなんで東京にいるんだろう。なんかもぞもぞするような変な感じを覚えた。大切な事を忘れてしまったような…
「叔父さん、どうして東京なんかに来ているんです」
「うぱぱ、ごろん、ちんちろーりん」
真面目が服を着て歩いていると言われた叔父がこんな意味不明な事を言うとは思えなかった。また、酒に強い叔父が酒に飲まれるとは思えない。
そんな事を考えていると、何者かが近づいてくる気配を感じた。顔を上げると
面長で背の高い人物が向こうから歩いてくるのが見えた。
「ほうれんそうやっぽぽ。ちーちぃ」
呪文のようなセリフを吐きながら、歩いてくる男が祖父に似ているような気がしたが、祖父もまじめな人だったから、そんな変な事を言うとは思えなかった。
くらくらしきた。私は思わず、目頭を押さえた。周りの音が一気に遠ざかっていった。
目を開けると、一番はじめに見えたのは妻の顔だった。妻は泣き腫らしたかのような赤い目をしていた。
上半身を起こして周りを見るといくつものベッドが並べられている。ここは病院らしかった。
「あんた、バス停でいきなり倒れたって」
「叔父さん…叔父さんはどこにいったんだ?お祖父ちゃんは」
妻は顔をしかめた。
「何言ってんの。もうふたりともなくなったじゃない」
そうだ、叔父も祖父ももうすでに亡くなったのだった。
「いや、さっき叔父さんにあって…いや、あれはあったというのか…もうなんでもない」
「変なの。分かった。なんでもないなら聞かないわ」
妻は私の手を握った。暖かった。
よろしければサポートお願いします。
