
できる!デザイン経営塾(第二回)メモ
エイトブランディングデザイン代表 西澤明洋さんが自身の仕事での知見を踏まえながら、デザインを経営に生かす方法を全6回にわたって無料ライブ配信している企画の第二回の受講メモです。
第二回の今回は、実際にブランディングを行ったかっぱ橋道具街にある「釜浅商店」の事例を代表熊澤さんとともに振り返りながらブランディングについて考える回でした。
ここでは西澤さんの提唱するブランディングプロセス「フォーカスRPCD」の考え方を軸に実際の仕事を振り返りました。
R(リサーチ):かっぱ橋の変化と釜浅商店の独自性
リサーチを行いながらブランディングの取っ掛かりになる情報や自社の強みの発掘を行います。
○周辺環境
バブル期以降閑散としたかっぱ橋道具街
しかし近隣のスカイツリー建設による観光客の増加が見込める
○自社の強み
釜浅商店の目利きによる独自の道具のセレクト
全国各地の職人とのつながり
P(プランニング):BtoB+Cへのシフト
次の段階ではRの内容を受けて、実際にどのようにブランドを組み立てていくかを戦略立てていきます。
代表の熊澤さんには「かっぱ橋道具街に人を呼び戻したい」という強い思いがありました。
ある店では実店舗での販売からネット販売にシフトしてある程度の利益を得た店もあったとのことですが、「道具は実際に店に足を運んで手にとって選んでほしい」という思いがありました。
そこで釜浅商店の戦略としては、これまで顧客として積極的にアプローチしてこなかった一般層へも訴求すべくこれまでのBtoBからBtoB"+C"というブランドの方向性を打ち出しました。
ビジネスを全く違う方向へ転換するのではなく、”+C”としてパイを拡大させていく、という部分がミソなのかな、と思いました。
C(コンセプト):「良い理の道具」の訴求
Pで打ち出された戦略からブランドコンセプトとブランドステートメントを立ち上げました。
良理道具 りょうりどうぐ
良い道具には、良い理ことわりがあります。
それは長い時間で培われた普遍的なかたち。
例えば庖丁の刃は繊維を断ち切るため
曲線を描きながら先へと鋭く尖ります。
良理道具には料理を美味しくするかたちがあります。
釜浅商店が培ってきた独自の目利き力と全国の職人との繋がりをもって、お客様に「良い理の道具」をご提供するという温かみと親しみも感じられるメッセージに感じます。
「プロ」と考えると商品の機能性や素材感みたいな部分に注目されがちなイメージがありますが、このコピーやステートメントからは、商品の背景にある物語がにじみ出ているような優しい印象があります。
D(デザイン):より一般消費者へ向けたデザインに
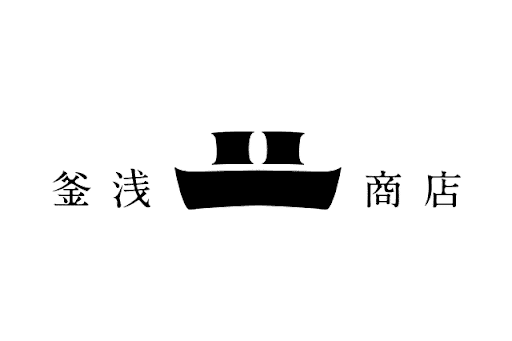
ロゴは日本の伝統や文化を感じさせるイメージを大切にし、鍋のフタと漢字の部首をモチーフにしてデザインしたもの。
また、これまではプロ向けの商品販売なため店独自のショッピングバッグなどはないことが一般的でしたが、BtoB+Cの戦略のもと、贈呈用などにも映えるバッグのデザインも合わせて行いました。

また、店舗デザインも刷新しました。
これまでプロの料理人が多くの道具を手にできるようにと雑然と道具が置かれていた店内でしたが、外から見ると店内が見えず、一般のお客様が入りづらい印象のある店舗デザインとなっていました。
そこで店内の商品を整理し、特注の什器などを活用して低コストながら一般顧客にも魅力的な店舗へリデザインしました。

また、時代に合わせて様々なシーンでブランドを訴求できるようにする試作として、ブランドをステートメントの文字だけでなく、動画でも伝わるように表現されています。
作っている職人の姿や苦労が見えたりすると思わず欲しくなります。ちょっとスーパーの野菜コーナーによくある「私が作りました」にも近いのかもしれませんが(でもあれに関してはもっと言い見せ方できないのかなぁとも思いますが、)
ブランドのその後
・パリへの出店
・国立新美術館への出店(移動式店舗)
・若い人材(20代〜30代)の獲得
ざっとまとめていますがすごいです。
質疑応答メモ
Q:コンセプトを立てた後に企業理念やビジョンも立てた?
A:立てていない。ブランドの伝言ゲームにおいては、伝える言葉は少ないほうがブレないため、コンセプトの作成に注力した。
Q:B to Bからto Cに寄せると、店舗とビジネスともデザインが中途半端になりがちだと思いますが、その懸念を払拭する方法は?
A:見た目は変わっても、やっていることや志は変わらないため、時間をかけて理解してもらった。
リブランディングをする際に既存顧客とのすれ違いが起こることは多いが、信念を曲げずに伝えていけば納得してもらえるはず。
Q:客観的(制作側)に見ていいと思うところと、社長(当事者)の立場から見ていいところの違いなどで、すり合わせが難しい部分は?
A:特になかった。デザイナーとしては一般目線から見て良い、と思えるものを採用するように心がけていた。また、デザインに入るまでの半年間、クライアントと密なコミュニケーションを取れていたことが良かった。
感想:ストーリーを売るデザイン
釜浅商店の事例を見て、商品ではなくその背後にあるストーリーをどのようにお客様に届けるのか、の部分の戦略がとてもクリアな印象でした。
ホリエモンの本の受け売りも入ってますが、現代において商品自体の価値での差別化は不可能で、背後にあるストーリーでしか他との違いを表現できなくなっています。
特に釜浅商店商店の場合は商品を作るメーカーでなく小売業のため、さらに他との差別化が困難な中、釜浅商店が長年培ってきた目利き力と職人との関係性でもって背後のストーリーの見える化に成功し、それをデザインというツールでお客様までメッセージを届けるルートを明快に設計した例だと感じました。
実はこの釜浅商店の事例のお話を聞くのは2度目だったのですが、ステートメントを改めて見ると、やはり言葉のディティールというか、雰囲気がひとつひとつ洗練されている秀逸なテキストだなぁと改めて関心しました。
ビジュアルやロジックだけでなく、言葉の持つ力を操れる能力も身につけたいなぁと思う今日このごろでした。
あ、ちなみに自分が読んだホリエモンの本はコチラです↓
サポートいただいたお金は今後の発信活動に関わるものに活用させていただきます。
