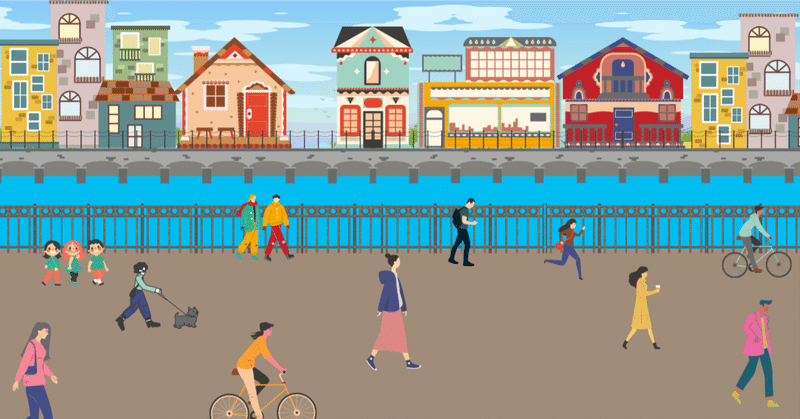
年間テーマ評論〈幻想とリアリズム〉④今井恵子「覚醒の手法」
覚醒の手法 今井恵子
最近見た映画『アバター』は、地球からはるか遠い星を舞台にして、先住民族と地球人との間で繰り広げられる戦争と愛を描いた物語である。興味深かったのは、星の先住民族の容姿も思考も、わたしたちの見知った生物の姿形や歴史文化のアレンジだったことである。そこにはおのずから想像のおよぶ枠があり、わたしたちが地球上で共有している知見や経験や習慣が色濃く反映されており、まったく理解不能なものところはない。そうでなければわたしたち自身の物語として訴えかける映画とならないだろう。創造は、幻想的な場合でも共有する経験の上に成り立っていることを改めて思った。
今年「まひる野」の前半期に論じられてきた「幻想とリアリズム」は読み応えがあった。幻想とリアリズムは対立するのでなく表現としての必然を獲得する相互補完的な概念である、という点で共通していた。ここでは、すこし角度を変えて、いわゆる短歌的幻想に覚醒をもたらす手法について考えてみたい。
*
ルネ・マルグリットに「これはパイプではない」「これは林檎ではない」という表題をもつ絵がある。それぞれのカンバスにはパイプと林檎が描かれている。かつてこれを初めて見た娘は、「パイプや林檎でなければこれはいったい何なの」と言った。「これはパイプの絵であり、林檎の絵であって、パイプそのものでも林檎そのものではないでしょう」とわたしは答えた。絵は「あなたはカンバスの図像を見てパイプや林檎を見たつもりになっていませんか」と問いかけている。
三十年後のある日、成長した娘に、六本木の小さな画廊で開かれていたゲルハルト・リヒターの「森の小径」という展覧会に誘われた。入口から奥へ、森の小径を描いた絵が並んでいた。が、歩けば心地よさそうに描かれた明るい森の絵のいずれにも、鋭利な金属で引搔いた線が無惨に引かれていた。なるほど、である。カンバスの傷はマルグリットと同じく問いかける。「あなたは絵を見ているのであって、森を見ているのではありません」である。この手法は、絵の風景や物語に感情移入してうっとりしている人々の意識を、たちまちにして覚醒させる。マルグリットもリヒターも、絵に触発される気分や感情や物語は、見る人の内部に生じている幻想であることを、するどく提示している。絵の中に現実があるのではないということだ。
絵と幻想のこの関係は言葉についてもいえる。〈パイプ〉〈林檎〉という言葉は、音声であり文字であり約束であって、パイプや林檎そのものではない。言葉の習得によって、わたしたちは事物の存在に、音声や文字を結び付けられるように訓練される。これを前提にして、わたしたちは先達の遺業に新たな物語や情趣や意味を積み上げる。すなわち創作である。が、それは言葉の幻想の上に成り立っていることを忘れてはならないだろう。この言葉の幻想≒意味は、作者の恣意的なものではなく、歴史的に継承されてきたことも。
フランスの社会学者ピエール・ブルデューが唱えたハビトゥス (habitus)という概念があるそうだ。「人々の日常経験において蓄積されていくが、個人にそれと自覚されない知覚・思考・行為を生み出す性向」をいう。属している或る集団(ここでは短歌界)に関わり続けることで知らず知らずのうちに身についてゆく知覚や思考や行為である。問題にしたいのは、短歌界の師匠と弟子というような社会的慣習の在り方ではない。そうではなく、短歌定型に受け継がれて来た、言語化できない「短歌」のことである。
わたしたちは「短歌」は三十一拍の五音と七音できた定型詩だと定義しているが、では改めて「短歌」とは何かと問われて、十全に言い表すことは難しい。定型をまもっていれば「短歌」だというわけでもないからだ。次のような歌がある。
・自然がずんずん体(からだ)の中を通過する―山、山、山
・一途に雲の上を飛びながら、青空の寂しさを初めて知る
前田夕暮
昭和四年に朝日新聞社の旅客機で土岐善麿、斎藤茂吉、吉植庄亮、前田夕暮が東京上空を周回し作歌したことは夙に有名である。これはその折りに詠まれ『水源地帯』に収められた夕暮の歌である。短歌というよりは一行詩と呼ぶのが相応しい形をしているが、通常自由律短歌と呼んでいる。「短歌」として認められているからである。
三枝昂之は「結果的には四歌人全員が飛行体験の表現は定型では間に合わないと判断した。それを自由律という言葉で一括すれば、この時の飛行体験は、自由律の迫力を人々に認識させる役割を果たした」(『昭和短歌の精神史』巻頭「花ひらく自由律」)といっている。続いて、昭和初期の自由律短歌を散文化の問題に結び、「自由律は定型律の拡大という形で意識すると有効だが、定型から切れた時にはきわめて困難」、つまり衰退すると指摘している。これは「短歌」にとって重要な指摘だ。四人の歌人は、上空を飛行するという、これまでにない事態の体験を忠実に詠もうとすればするほど、既成の定型枠を破壊せざるをえなかった。遭遇した体験を既成の定型枠にむりやり収めると、臨場する迫力や新味が失われてしまう。「四歌人全員が飛行体験の表現は定型では間に合わないと判断した」のは、飛行体験という新事態のまえで、定型の限界に遭遇したことを意味している。短歌作者としての根幹が大きく揺らいだにちがいない。
「短歌」の散文化は、つきつめれば短歌は「短歌」である必要がなくなり、短詩として生き延びればよいということになる。それも一つの道であったかもしれないが、短歌史は自由律短歌に加担しなかった。これは、「短歌」とは何か、なぜ「短歌」なのか、という問いをわたしたちに投げかける。三枝は自由律衰退の最大の原因を「定型律以上に類型化の危険にさらされる」(前掲書)ことに見た。卓見と思う。
いま自由律短歌を例にあげたが、ふたたび定型へ回帰した(夕暮や牧水など)としても、このような作品が短歌史に投げかける意味は大きい。近代短歌は短歌滅亡論との戦いであったといわれるように、「短歌」が問い直されるたびに、「短歌」とは何かという問いは深く掘り起こされ、領域を広げてきた。おのずから受け継がれ言語化できないハビトゥスという概念を念頭におくと、「短歌」はそれ自体に形骸化し衰退する要素を含んでいるのだと思われる。「短歌」は常に、外側からの検証が必要である。
・民こぞり健気に貧に耐へし日を「悪の枢軸」たりしニッポン
・道の上に人生あればののしりあひ道の下より老夫婦出で来
島田修三
右は『東洋の秋』に収められている。小高賢はこうした歌を「学生にいかり、政治を馬鹿にし、戦後的繁栄を、まるで千切っては投げるように批判する露悪的作品群の過激さ」(『現代の歌人140』島田修三の項)と述べた。日本人の勤勉や従順と帝国主義的侵略。人生のしみじみした老境と「ののしりあひ」。ここに時代相や物語、作者の立場や向き合い方を読みとることは容易いが、しかしもう一つ、小高があえていう「露悪的」手法の表現に注目したい。
「短歌」にしみじみとした優美や雅や寂寥、または善意や温かさをもとめる人は多い。大多数の読者はそれを望んでいるだろう。「短歌」には今でも花鳥諷詠的美意識が流れているし、わたしもそれを「短歌」が磨き上げてきた大切なものと考える一人で、手放そうとは思わない。しかし、そこに何の疑念も持たず無条件に「短歌」として肯定し続ければ、いずれ「短歌」は形骸化する。もともと音声と文字の言葉は、作者と読者双方の幻想の上に成り立っている。幻想だけが気離反されると、たちまちに膨らんで扇情的になる危険があることを、わたしたちは短歌史の上でよく知っている。すべてが美しく善良で平和な言葉と情趣に吞み込まれ一色になってしまうとき、それは幻想ですらなくなるのではないか。
島田の、一見「露悪的」と見える手法は、健気な日本人という概念や深々とした老境という幻想を、たちどころに現実へ引き戻し、そんな安直な気分にひたっていてよいのですか、と問いかけて来る。問いかけられて、読者は我に帰る。前田夕暮の自由律が定型の破壊だとすれば、島田修三の「露悪」は短歌的既成概念の破壊であるといえよう。
・きれいな言葉を使ってきれいにしたような町できれいにぼくは育った
岡野大嗣
・三越のライオン見つけられなくて悲しいだった、悲しいだった
平岡直子
穂村弘以降の短歌アンソロジー『桜前線開花宣言』(山田航編著)から二首。近年定着した口語短歌の一面をよく伝える歌と思う。
岡野の歌は、島田の投げかけた問題とも関わり、言葉のもたらす幻想を言い当てている。島田の歌に並べてみると歯車が一つ回り、「きれいな言葉」が、すでに現実を覆ってしまっているかのようだ。この歌が収録される『サイレンと犀』について、山田航が「システムへの批判的視点」を指摘している(前掲書『岡野大嗣の項)。
平岡の歌は「悲しいだった」の繰り返しが印象的。文法的正しさを至上のものとして「悲しかった」と書けば、ここに見る「悲しいだった」の現場感は失われるだろう。悲しいと感じた状況そのものを脳裏に想起し、それが過去「だった」と辿る丁寧さが、記憶に現場感をもたらしている。この表現は、過去の感情を「いま、ここ」の作者主体の位置人称に集約すると消えてしまう、リアルな感覚を呼び起こす。文法を破ることで、わたしたちが捉われている言葉の幻想性に気づかせる。マルグリットやリヒターの手法に似てると思う。
「短歌」が「短歌」であるために、言葉が幻想の上に成り立っていることを念頭に置きながら表現の可能性を考えたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
