
「見えない相手」と対峙する:想像の人類史
(※この記事は2020/01/24に公開されたものを再編集しています。)
見えるものと見えないもの
私たちは、目に見えるもので囲まれている。モニター、メガネ、スマホ、テーブル、床、天井、建築、指先、ほかの人間、私たちの身体……。タンジブルなもの、つまり、触ることのできる具体的なものがどれほど多くあるかは、枚挙できないほどあると言えば足るだろう。
しかし同時に「目に見えないもの」、それほど確からしくないものも、私たちの身の回りにはある。例えば、以前このまなびとき の書評でも扱った「信頼」は、机などのようには目に見えない。テクノロジーを使って、どれぐらい「いい人」なのかをレーティングさせることはできる。けれども、数値によって可視化されたものが、私たちが「信頼」と呼ぶすべてを過不足なく表しているわけではない。
というより、私たち自身が、「信頼とは何か」をある程度は知りながら、それを十分知っているわけではない。信頼は大切だという主張に多くの人は同意するだろう――それゆえ信頼とは何かを少しは知っている――が、しかし同時に、私たちにとって信頼は「未知のもの」ですらある。「信頼」と同じように、「愛情」のような感覚も、「社会」や「集団」のような社会的な区切りも、ヴァーチャルに存在してはいるが、路傍の石のように取り出して見せ、触ることができるほど具体的ではない。昨今流行りの、「ウェルビーイング(幸福)」も。
ゲームと「見えない相手」
かねてよりゲーム論を書いていたことで知られる、人類学者の中沢新一は、共著作『ゲームする人類:新しいゲーム学の射程』で、ゲームの背後にも「見えないもの」があると指摘する。(なお、〔〕は私の追加した補足)
あれ〔=デジタルゲームの起源の一つとされる『PONG』(1972)〕を見たときはけっこう感動しました。見えない相手がパドルを動かしてくるんです。アナログゲームだったら自分と同じ人間が向こうにいて思考しながら対処していくけれど、これは見えない相手が動かしている。
『スペースインベーダー』〔(1978)〕になると、それがもっとはっきりしてくる。「インベーダー」と名づけたところがすごいですよね。未知のもの、見えないものが操作していて、それに対峙していくというところにとても惹かれました。それは人間を相手にしているんじゃないからこその面白さだと思います。(pp.147-8)
デジタルゲームは、私たちの相手をして「遊んでくれる」存在だが、それは同じ人間ではなくて、何が何だかわからない「未知のもの」「見えない相手」であり、それに対峙するのだという点をおさえておきたい。
例えば、「スペースインベーダー」を最初プレイすると、(特に説明書もない場合なら)何をどうするべきか、どうすればステージをクリアできるのか、どのような方略が望ましいか、インベーダーの行動パターンは何かといった事実を何も知らない。わからないなりに何らかの操作し、プレイを繰り返すことで、何をすればどんな帰結が生じ、どのように振舞えば順調にゲームを進行させられるかに気づいていける(自分の癖や相手の行動パターンを把握し、戦略を立てられる)。
「見えない相手に対峙する」という表現には、この事例のように、不可解な何かに対峙し、実験的にやりとりを進めながら、どうすればうまくいくのかを探り当てていくプロセスが念頭にある。つまり、ある種の探求であり、学習である。
スマホというノンヒューマンに触れる
この構図は、(あなたがスマホを見ているとすれば)スマホ上のアプリケーション(例えばSafariやソシャゲ)にも当てはまる。私たちは、何かの文字やアイコンを基準にしながら、指先を動かし、人間とは異なる原理で動くものと付き合っている。そこにあるのは、見えないもの、未知のものとの相互作用だ。
別のウェブサイトにつながるリンクを指先で叩いたとき、その背後に人間のような存在がいて、人間のような思考や判断を発揮しながら、別のウェブサイトを表示してくれるなどと私たちは思っていない。情報処理の背後には、「よーし、この人はウェブサイトが見たいんだな、表示するぞー」という思考があるとは考えない。そうした思考の習慣は、少なくとも私たちのものではない。
だが、この少数の事例からもわかることもある。簡素化され、人間にとって直感的に理解できるような視覚的記号に基づいて、私たちはマシンというノンヒューマンに対峙している。それゆえ、インターフェイス・デザインとは、実のところ、ユーザーと「見えない相手」とのコミュニケーションの土台を整える試みだと言える。
(特に言及はしなかったが、もちろんプログラマーやエンジニアのような人たちは、ユーザーとは違う水準で機械とコミュニケーションしている。)
機械とのコミュニケーション
中沢は、上に示した引用のすぐ後で、武道や華道というときの「道」に言及する。そこで、道は「常に自分との闘いだ」と言われるけれども、実際には、道とは、どこにどう向かい何と闘うかもはっきりしないままに、「見えない世界に向かって自分を対峙させ」ることだと話を拡げている(p.148)。彼はここで何を言おうとしているのだろうか。同書に特に手がかりはないのだが、私なりに思考を進めてみたい。
プログラミング、スマートフォン、アプリケーションは、それぞれ異なる水準で、私たちを、「機械」という非人間(ノンヒューマン)と対峙させるための道具だ。そして、ゲームもまた、私たちが「見えない相手」とコミュニケーションするための装置である。
しかし、冒頭では、「信頼」「愛情」「社会」のような概念的な存在者をも例に挙げていたことを思い出されたい。こうした概念も、実はマシンの場合と同じことが当てはまる。概念は、私たちが何か重大だと思う「未知のもの」、それがあれば助かると感じる「見えない相手」と対峙するためのツールなのだ。
「神」という未知で不可視のもの
こうした思考を進めると、私たちにとって窺い知れない最たるものとして「神」が思い浮かぶだろう(単数形でも複数形でも汎神論でも構わない)。人間には窺い知りがたい超越的なものを念頭に置いてもらえれば、「神」以外の言葉で呼んでも構わない。
人類は、時代や文化を問わず、不可解な事柄、未知のもの、生の不安のような不確かな事柄と対峙せざるをえなかった。未知や不可知であるにもかかわらず、そこに何らかの秩序や説明を見出そうとして私たちが発達させてきたのが、「神的なもの」や「神」に類する概念群だ。ここでは、読者が神秘的な存在者を信じているかどうかは関係ない(私自身は、不可知論者)。重要なのは、人類は、その歴史と同じくらい長く、ノンヒューマンと付き合ってきたということだ。
実際には、どこにどう向かい何と闘うかもはっきりしないままに、見えない世界に向かって自分を対峙させているという点で、みなが神を素朴に信じた時代も、機械と対峙して24時間の大半を使う現代も、人類は変わっていない。
宗教/芸術的な含みを持つ「道」という概念に言及した中沢の延長で、こうした「未知で、見えない、不可解なもの」と付き合い続けてきた人類史を思い描くことができる。

『サピエンス全史』と、私たちの想像力
ひと頃、とかく話題をさらったユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』のキーワードが「虚構」だった、というのは故なきことではない。私たちは、タンジブルなものと同じくらい、見えない相手、未知のものと付き合い続けてきた。
ひどい腹痛で何かに祈るときも、オノ・ナツメの漫画を読むときも、数学の問題を解くときも、私たちは何か見えないものと対峙している。スマートフォンに指先を躍らせるときも、友人や家族を見て微笑みがこぼれたときも、同じである。私たちは、見えないものを想像している。
私たちの周囲は、未知で不可解なもので溢れている。未知に対峙し、それとうまく付き合うことを望む中で、私たちは、あれこれ試行錯誤し、想像を働かせたことで、私たちが「文化」と呼ぶものが生まれた。いわば、文化は想像の産物なのだ。想像のない瞬間をほとんど生きていないと言えるくらい、私たちは想像の生き物である。
中沢新一・遠藤雅伸・中川大地『ゲームする人類―新しいゲーム学の射程』https://www.amazon.co.jp/dp/4906811256/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_FIPgEbC8QVT6V
中沢新一https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%B2%A2%E6%96%B0%E4%B8%80
PONG(ゲーム)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%B3_(%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0)
スペースインベーダー公式サイト
https://spaceinvaders.jp/
ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史:文明の構造と人類の幸福』上下合本版https://www.amazon.co.jp/dp/B01KLAFEZ4/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_JGPgEbE4RSJC7
オノ・ナツメhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%8E%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%83%84%E3%83%A1
以前書いた書評
「評価経済、あるいは、信用を求め合うユートピア ――小川さやか『チョンキンマンションのボスは知っている』レビュー①」https://manabitoki.castalia.co.jp/home/bookreview-underground-economy-and-anthropology-ver1
2020/01/24
著者紹介
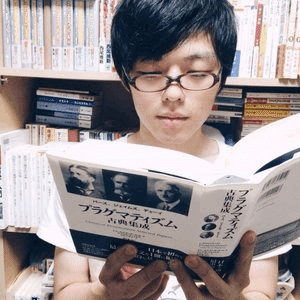
博士(人間・環境学)。1990年生まれ、京都市在住の哲学者。
京都大学大学院人文学連携研究員、京都市立芸術大学特任講師などを経て、現在、京都市立芸術大学デザイン科講師、近畿大学非常勤講師など。 著作に、『スマホ時代の哲学:失われた孤独をめぐる冒険』(Discover 21)、『鶴見俊輔の言葉と倫理:想像力、大衆文化、プラグマティズム』(人文書院)、『信仰と想像力の哲学:ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜』(勁草書房)、『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎)など多数。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
