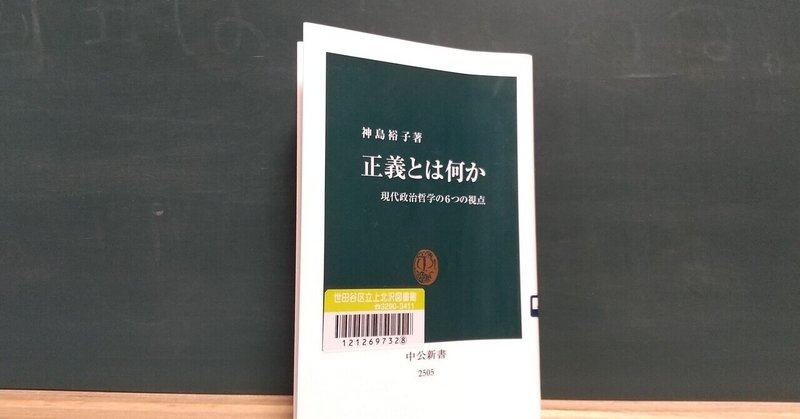
自由はどこまで保障されるのか。
有島武郎の童話の一つは次のようにはじまるのである。
昔トゥロンというフランスのある町に、二人のかたわ者がいました。一人はめくらで一人はちんばでした。この町はなかなか大きな町で、ずいぶんたくさんのかたわ者がいましたけれども、この二人だけは特別に人の目をひきました。なぜだというと、ほかのかたわ者は自分の不運をなげいてなんとかしてなおりたいなおりたいと思い、人に見られるのをはずかしがって、あまり人目に立つような所にはすがたを現わしませんでしたが、その二人のかたわ者だけは、ことさら人の集まるような所にはきっとでしゃばるので、かたわ者といえば、この二人だけがかたわ者であるように人々は思うのでした。 有島武郎「かたわ者」(角川文庫『一房の葡萄』p.54)
さて、われわれは涼しいビルの会議室で社会制度を論じるときは、「多様性」を口にし、「人権の尊重」をスローガンに掲げます。しかし、そこで念頭に置かれている〈人間〉とは、端から自由を謳歌できる活力を平等に分け与えられた抽象的な人格ではないでしょうか。たしかに、神の視点に立てばすべては平等でしょう。しかし、現実の社会に生きるわれわれはでこぼこしており、持って生まれたどうにも抗えない欠落や、努力して得られた能力だけでは切り開けない運の悪さを抱えた存在ではないでしょうか。そして、それらの欠落や不運すらも「個性」や「多様性」の美名のもとに、会議室での哲学談義は隠そうとしてきたのではないでしょうか。
今回は〈自由はどこまで保障されるのか〉という問いを問うてみたい。
まず、ここでの自由は社会的自由のことである。哲学には、「自由と決定」「自由と必然」の系で問われるべき自由意志の問題がある(黒田亘『行為と規範』p.78)が、今回はひとまずそれではない。先の童話での二人の登場人物は、「自分の不運」を顧みず、行きたいところで出歩いている。ここで語り手はいくぶん町の「良識派」の立って、「あまり人目に立つような所」には来ないのが「普通」であると仄めかしている。しかし、現代の観点からすれば、たとえ良識派の「嫌悪」を招いたとしても、二人には出歩く「自由」が保障されていると考えるのが「普通」なのかもしれない。現にわが国の日本国憲法の第18条には、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。」とある。どこへいこうと、まして公道を歩くことはその人の自由なのである。
では、問われている社会的自由をわれわれはどのように考えればいいだろうか。その取り扱いの参考を哲学史に探ろう。J・S・ミルの『自由論』は、1856年に刊行された。自立した個人の時代としての十九世紀にふさわしく、『自由論』の1章と2章では、思想を表現する自由が肯定的に詳述された。そして、つづく第3章は、「幸福の要素としての個性」と題されている。その中で、幸福の要素としての自由が説明される。その自由とは、各人でそれぞれの理性や信念だけではなく、欲求や衝動の異なりも叙述される。
各人の欲求と衝動もやはり各人のものでなければならず、自分自身の衝動をもっているとき、その衝動がいかに強くても、危険や落とし穴ではまったくない……欲求と衝動も信念や自制心と同様に、完全な人間に欠くことができないものである。……衝動が強いとは、活力があるということを言い換えたものにすぎない。 (光文社古典新訳文庫『自由論』pp.134‐135)
つまり、ミルによる社会のあり様もまた、われわれがでこぼこでそれぞれに異なるという点に焦点が当てて描かれている。そして、その異なりとは「活力」の違いなのである。つまり、社会的自由には、その大きな要素として、個人の活力があるということである。
今後、社会的自由とは、個人の活力の異なりであるという観点から、自由はどこまで保障されているのかという問いを考察していく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
