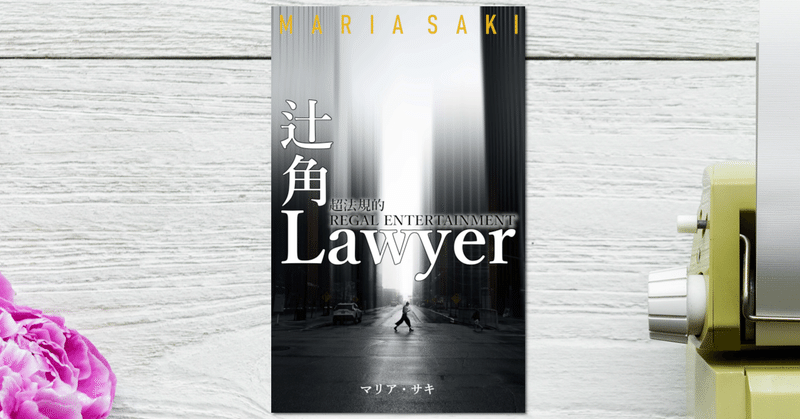
『辻角Lawyer』Kindle版/Teaser3/3
3
瑠璃の帯締に斜子の帯、黒地の留袖は白一色で竹林を描いた総模様。閉店まぎわ店の前に立った女性は、ひと目でクラブのママさんだと判ったが、夜半にコートもショールもなしにクラッチバッグだけを持った装いは、とても無防備にみえた。
「失礼ですが、三浦さんですか」
女性が道案内でも乞うように会釈して訊ねた。早紀はためらわずうなずいた。この女性が誰なのか、すでに察しはついていた。
「はじめまして。朋美の母でございます」
早紀はイスを立って名刺をうけとった。クラブ『千花』の千葉理恵は腰を折って深々とお辞儀をした。あまやかな香りが鼻先をくすぐった。
「さきほど娘がおじゃましたそうで」
イスにすわるやいなや理恵はきりだした。のんびり話している時間はなさそうだった。早紀は相槌だけうって話の先をうながした。
「じつは、うかがいましたのはその娘のことです。娘はいまある方とおつきあいをしています。店のお客様で、お仕事は弁護士をなさっているということなのですが、それを確かめていただきたいのです」
やや早口に言いおえると、理恵は逸る気持を抑えるようにちいさく息をついた。
「朋美さんが交際している男性がほんとうに弁護士かどうか、それを調べてほしいということですね」
「そうです。三浦さんは元弁護士だったと娘から聞きました。それにこまっていることがあれば、どんなことでも相談にのってくださるとも。お引きうけ願えますか」
理恵はまっすぐに早紀を見つめた。
早紀は、よっしゃと叫びたいところをグッとおさえて、
「お引き受けいたします」
理恵の肩から、すうっと力が抜けるのがわかった。
早紀は咳払いをひとついれてシステム手帳をひらいた。
「その人の名刺はありますか」
「いただいてないんです」
「では名前をおしえてください」
早紀は理恵が口伝えする字と読みを手帳に書きつけた。
"太刀川秀樹"
その名前に心当たりはなかった。
「写真か写メはありますか」
理恵はくびをふった。
「店内での撮影はご遠慮いただいておりますので」
とうぜん店側も客の写真を撮ることはない。
早紀は質問をかえ理恵から見た太刀川の年齢、身長、体重、顔つきその他の身体的特徴、さらには服装の趣味、喫煙の習慣、方言の有無などを聴きとり、さしつかえなければと前置きして店での支払い方法について訊ねた。
支払いはいつもキャッシュということだった。カードでもなく、請求書を送らせるでもなく、その場で現金で払う。
早紀は唇をなめた。銀座のクラブで現金払いする客とは、いったいどんな人種なのか。
「所属している弁護士会はわかりますか」
早紀の質問に理恵はうつむきかげんにくびをかしげた。きれいに結いあげた襟足が抜襟からのぞいた。
早紀はボールペンを指先に持ちなおして、バトンのように一回転させた。するとなにかを思いだしたように理恵は顔をあげた。
「そういえば事務所は永田町だと言っていました。それと住まいは世田谷のほうだと」
これは手掛りになる。早紀は二つの地名をメモしてつづけた。
「その人はどのくらいのペースでお店にきますか」
「月に一度で、いつも金曜日です」
「最後にきたのは」
「先月の下旬です」
「今日は?」
念のため訊いてみたが案の定、理恵はくびをふった。
「今日はいらっしゃらないようです」
「朋美さんがそう言ったんですね」
「メールで連絡があったようです」
「ふたりはお店の外でも会っているのでしょうか」
「それはまだないとは思いますが……」
最後のほうは熄え入るような声だった。
早紀は息を深く吸って声に力をこめた。
「わかりました。まず名簿をあたってみます。それで結論がでなければ面割りをします」
理恵はそら恐ろしい予言でも聞かされたようにびくりとした。早紀は具体的な段取りを説明し理恵に協力を求めた。
実務的な段になると理恵は積極的に意見を述べた。もはや不安や戸惑いは感じられなかった。早紀はその気丈さに客あしらいに長けた女将の顔と、娘を思いやる母の顔を重ね見る気がした。
最後に互いのケイタイで通話とメールの送受信をおこない、番号とアドレスを登録して作戦会議は終わった。
早紀が手帳をとじると、理恵はふうっと息をつき、右手の中指をこめかみにあてた。
「だいじょうぶですか」
早紀が気づかうと、理恵は口の端を持ちあげて頬笑んでみせた。最後の質問をするのは、いまだと思った。
「なぜ疑問をもたれたのですか」
理恵は伏目がちに目をそらすと、しばし間をおいて言った。
「うちの店では、ほとんどのお客様が名刺をくださいます。でもなかには、そうでないお客様もいらっしゃいます。そういう場合、どんなお仕事だろうと想像するんですが、これが意外とむずかしいんです。もちろん、あたることもありますけど、はずれることも多いんです。ですから仕事を聞かされて、びっくりしたことがなんどもあります。でもそんなときでも、それがほんとうなら納得できるんです。でも太刀川さんの場合、それがなかった。弁護士だと聞かされても納得することができなかったんです」
「自分から弁護士だと言ったんですね。それはいつのことですか」
「初めて店にいらした日、五月ごろのことです」
横断歩道のまん中でツーショットの記念撮影をしている若いカップルにタクシーがクラクションを鳴らした。理恵はハッとしたようにあたりをうかがうと、心持ち身をのりだして声をひそめた。
「それとこのことは……」
わかっている。このことは朋美にはもちろん、太刀川本人にも気づかれてはならない。それが本件の難しさだと思いながら、早紀はうなずいた。
理恵はひとつ肩の荷がおりたというように息をつくと左の手首を裏返した。早紀も腕時計を見た。時刻は十一時をまわっているが『千花』の営業はまだ終わっていないのだろう。クラッチバッグをかかえた理恵は、にわかにそわそわしだした。
「では、こちらの準備が整いましたらお知らせします」
早紀はイスを立った。が、理恵はすわったまま。しかたなく腰をおろすと、理恵はこまったような顔できりだした。
「見料は」
ケンリョウ?
この言葉の意味を理解するのに三秒かかった。しかし足元においた木箱を取りあげ、机のまん中においてすわりなおすのには五秒とかからなかった。
『聴導犬育成支援』と書かれた錠付きの募金箱を見て、こんどは理恵が目をしばたいた。早紀は手をひざのうえにおいて言った。
「見料は無料なんです。そのかわり募金をお願いします」
早紀はぺこんと頭をさげて、観光ポスターのモデルのように頬笑んでみせた。しかしその笑顔が引きつっているであろうことは、含み笑いをこらえている理恵の反応からも明らかだった。
理恵はクラッチバッグから一万円札を取りだすと四つに畳んで募金箱にいれた。早紀は物慣れた一連の所作に彼我の通貨単位のちがいを実感した。
──ニナ・リッチ!
早紀が香水の名前を思いだしたのは、理恵の残り香をビル風がはこんだときだった。
(to be continued…)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
