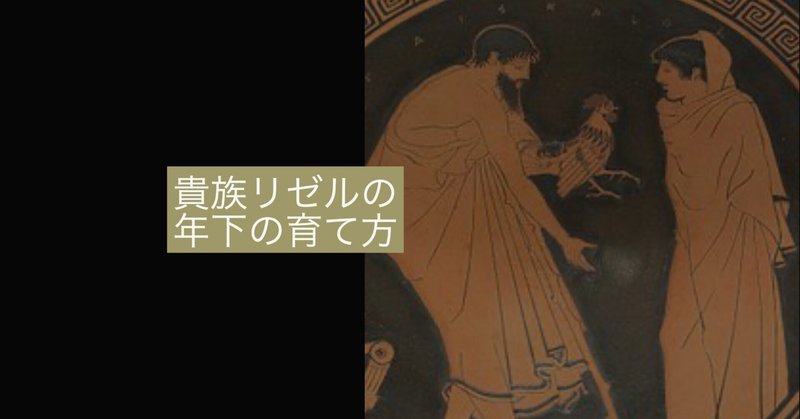
リゼルとパイデラスティア論 ー 穏やか貴族の休暇のすすめ。[スタッド&ジャッジの育成]
本稿は考察というより妄言なので解釈の是非は不問にしてください!…と、『結婚商売』雑学④「騎士道と愛とキリスト教と」と同じ謝罪をします。あのときはカトリックの教義についてでしたが今回は哲学です。
リゼルはなぜスタッドとジャッジをああも甘やかすのか?という点に関して、無理やりにでも自分が納得したくて編み出した持論の供養です。
パイデラスティアを念頭にリゼル本人が行動しているわけではなく、またリゼルがパイデラスティア肯定者だと思っているわけでもありません。そして筆者個人はNLの既婚者ですが同性愛について何らの主義主張はないことを最初に明言しておきます。単に、リゼルの年下たちへのふるまいについて「かつて我々の世界でこういう風習があった以上、彼の行いはあり得ないものではない」という話です。
今では考えられない文化・風俗の古代地中海世界
古代ギリシアは極端な男性社会
如何せん2000年以上も前なので、古代の文化や風習は、現代からすると奇異に映るものばかりです。以前、『結婚商売』雑学⑤「貴婦人はスーパーウーマン!?」で挙げたウェディングの起源も「おいおい女性の尊厳とは?」というものばかりでしたし、古代ローマ貴族が美味をひたすら楽しめるように吐き戻しをして満腹を防いだという有名な話は、現代からすれば奇行でしかありません。全然SDGsじゃないし。
そんな中でも個人的に「理解はできるけど納得できない」ぶっちぎりNO.1がパイデラスティア(希: Παιδεραστία, 英: paiderastia)、日本語訳「少年愛」です。
同性愛はユダヤ教およびキリスト教の教義では禁忌とされるものの、古今東西で連綿と存在し続けるものです。特に歴史的側面で興味深いのは、極端な男性優位社会(戦争が多発する時代)においては公然の目的さえ持つ関係性だということです。日本人に馴染み深いのは「武将と小姓」かもしれません。実際、イギリスの詩人で社会主義思想家のエドワード・カーペンターは、同性愛に関する著述の中でパイデラスティアと日本の武士階級の男色慣行を事例として取り上げています。
本来のパイデラスティアとはなんだったのか
「パイデラスティア」は「少年愛」と和訳されますがそれは広義の意味合いです。狭義あるいは本質は、古代ギリシアのドーリア人が支配した都市国家アテナイやスパルタ、テーバイ等で行われた、成人男性市民が成長過程にある青少年を戦士または政治家として一人前にする"育成の義務"のことを指します。政治的・軍事的な同胞愛を育み、自らの人生を顧みず社会のために命さえ投げ出す戦士を育成することを目的としていました。
パイデラスティアが公然のものだった前提がふたつあります。ひとつは古代ギリシアの住民の多くは奴隷であり、"市民"とは支配層の成人男性を指したことです。絶対数が少なかったんですね。そしてもうひとつが市民活動、ひいては思想や人間関係において女性は存在しないも同然だったということです。アテナイにおいては女性は家の中でのみ育ち、やがて親が決めた嫁ぎ先へ運び出され、夫以外の男性の子を産むことがないように守られたため(現代では権利を取り上げ抑圧されていると解釈されますが)、結果として社会的存在感は無に等しかった事実があります。
いわば男しかいない世界だと割り切って考えないといけません。でないと脳がバグってる気がして仕方ないです。つい「いやカミさんはどうしてたんだよ!」って言いたくなりますから。
以上を踏まえて、パイデラスティアについてのwikiをざくっと整理・引用します。
少年愛は男性市民(国民皆兵制のスパルタでは、それは戦士であることを意味した)にとって法文化された義務であった。
知性や知識において、また戦士としての肉体の素晴らしさや勇気、戦闘技能の卓越性、更に弁論の巧みさや、指導力を持ち、道徳的にも優れた家柄の良い男子市民は「徳(アレテー)を持つ人」とされ、彼らはエラステースと呼ばれた。エラステースが持てるアレテーを若い男性、すなわち、青年・少年(エローメノスあるいはパイディカと呼ばれる)に授けるための文化制度がギリシアの「少年愛」であった。またこれが社会の「制度的範型としての少年愛」である。
愛される少年に求められる資質は、戦士としての倫理性であり、精神的な卓越性、則ち「善き少年」であった。
女性不在の社会で男性同士の恋愛が公然かつ上位であった時代のことですから鶏が先か卵が先かわかりませんが、ともかくパイデラスティアとは単に同性愛を指す言葉ではなく、高位の年長者が次世代の戦士や政治家候補者の青少年を(往々にして恋愛関係を結びながら)指導する制度だったわけです。青少年の育成に基づく関係ですから、エローメノスあるいはパイディカが一人前になった時点で解消されます。
パイデラスティア的な同性愛の軍事的成功例は、テーバイの最強歩兵部隊「ヒエロス・ロコス」(神聖隊)でしょう。この部隊は300人150組の男性カップルで編成されたのですが、その狙いは「愛人の前で無様な姿は晒せない」ため果敢に戦うという点にありました。紀元前378年に編成され度々武勲を挙げ、40年後の戦争で全滅するまで無敗を誇ったとされています。
哲学的にはさらにここから、肉体関係を伴わないことで美の本質、すなわち精神性たるイデアを年長者自らが探求する「プラトニック・ラヴ」へと話が至ります。この関係性をわかりやすく体現した有名人が、紀元前5世紀ごろの哲学者ソクラテスです。
ソクラテスは多くの青年に心酔される哲学者でした。その信奉者の一人に、才気溢れるが傲慢極まりない良家の美少年アルキビアデスがいます。アルキビアデスはソクラテスとのディベートの結果、老哲学者を師匠として崇めたばかりか、師匠が他者に少しでも目を向けようものなら激しく嫉妬したと言います。しかしソクラテスはアルキビアデスの精神性を愛していると公言し、本質的パイデラスティアのみを貫いたのだそうです。
ただし、話はこれで終わりません。やがて政治家となったアルキビアデスがペロポネソス戦争でアテナイが負けるきっかけを作った(あるいは一時スパルタに寝返った)ことや、暴政を敷いた三十人政権の関係者が軒並みソクラテスの弟子と認識されていたことから「ソクラテス裁判」が開かれ、ソクラテスは若者を堕落させた罪で死刑。実際には減刑も脱出も可能だったにもかかわらず、ソクラテスは一貫して無罪を主張しながら毒を賜って死んでいったそうです。
そして、自らの哲学を記録しなかったソクラテスの代わりに彼の言葉を書き残し、パイデラスティアを含む愛(エロス)や徳(アレテー)について対話篇『饗宴』にまとめたのが「プラトニック・ラヴ」の語源となったプラトンです。
古代から精神愛を示す名詞がプラトンの名を冠していたわけではありません。プラトニック・ラヴの直接の語源は、ルネサンス期の人文主義者フィチーノが『饗宴』をラテン語に翻訳した際、注釈書の中でパイデラスティアをアモル・プラトニクス(amor platonicus)と記したことによるそうです。
優秀な人材を逃さない宰相様のエゴイズム
話がソクラテス裁判にまで及んで前段が長くなりました。リゼルの話ですよ。
リゼルが優秀な人材好きなのは「上に立つ者として当然の感覚」と序盤で書かれています。正論ですが、その"人たらし"ぶり、とりわけ年下の相手をする時の様子にどうしてもギョッとしてしまいます。
ここで言う"年下"にイレヴンは含みません。スタッドとジャッジのことです。
ふたりとも、仕事ぶりは周囲が認めるほど優秀な青年ながら精神的に非常に未熟というのが共通点です。
彼らに対してリゼルは、いい子にしていれば頭を撫でて、ニコッと笑ってあげて、「君はそのままでいいんですよ」と肯定してあげる。スキンシップが多いのは幼かった"ヘーカ"の教育係をしていた名残なのでしょうが、高位の年長者に認められることで若輩が歓喜と成長を得るのは、性的な意味はともかく、パイデラスティアと同じ構図です。
スタッドに与えるのは人間教育そのもの
スタッドは特異な幼少期を過ごした影響が濃過ぎます。初期は感情がないように見え、自分自身にも興味がない。命を繋ぐために幼くして暗殺者になるほど生命への執着はあれど、あらゆる感情が出現していない状態でした。周囲もそんなスタッドにあれこれ言わない。親族でも友人でもないのに、言ったところでどうにかなると思えないでしょうから。
ところがリゼルはそうではなかったわけです。冒険者登録をする際、スタッドは受付窓口で的確な対応をした上、本屋を教えてくれた。一見なんてことのない業務対応に、リゼルは感謝を素直に表現したのです。その瞬間、スタッドの人間としての発育が始まったと考えられます。
それに気付いたリゼルは、幼な子を養育するようにスタッドに接していきます。「君は大切な存在ですよ」と伝え、ジルへの無自覚な嫉妬にも付き合い、イレヴンの加入時には「苦手で構わないし受け入れなくてもいいけど、才覚は認め合ってほしい」とする。スタッドは肯定されることにまず安心感を覚えて、我儘を言い、駄駄を捏ね、やがて自分の考えや思いを人に伝えるようになり、ジルにもあからさまには噛み付かなくなっていきます。そして最近(ノベル17巻)になって、我儘や甘えだけを続けるのは許されないと暗にリゼルに示されています。まるで、生まれて数年経った頃に弟妹ができて幼児退行した子が、徐々に分別を身につけていく過程のようです。
それを受けるスタッドは、ギルド職員としての自分を最大限使ってもらうことで愛に応えるわけです。決して、リゼルのようになりたいなどという憧れは持ちません。そのあたりスタッドは自分の価値だけは理解しているのです。
ジャッジに与えるのは自己肯定から来る自信
ジャッジはごく普通の青年ですが、生来から弱気で臆病なくせにどこか傲慢です。本人にも自覚があります。これ、インサイさんの悪影響だと思いますね個人的には。
リゼルはスタッドと同様にジャッジを甘やかしますが、方向性は少し異なります。けしかける、とでも言うのでしょうか。鑑定にしろ、商売にしろ、料理やもてなしにしろ、対価として何かを要求させること、大商人インサイの影でなく自分に価値があると自覚させることを念頭に甘やかしている印象です。
「君は一流の提供ができるのだから、それを供する相手に相応のものを求めてもいいのだ」と。
感情は出ないが自分の利用価値を自覚しているスタッドとは真逆なんですよね。
実際、王都を離れるときにジャッジが「行かないでほしい」「寂しいと思ってくれるなら自分を身内に入れてくれた理由を教えてほしい」という傲慢な感情を口にしたことに対して、リゼルは怒ることなく「自信が出てきた」と見ています。
以前のジャッジならば図々しくおこがましいと考え、口にはせず赤面するばかりだったであろうと。
ただ、それでもなおジャッジの自己評価基準は社会ではなくリゼルです。貴人然としたリゼルに憧れ、リゼルを美術品の如く扱い、リゼルに認められるものだけが至高。そこにリゼル本人の意思は介在させない。自分こそリゼルの価値を知り、リゼルに相応しいことだけをリゼルに認めさせるのだという傲慢さ。リゼルが街で覚えてくるスラングに泣き、リゼルがしたいことでもジャッジが気に入らなければ「やらないでくれ」と泣くメンヘラぶり。
でもそれではダメなのです。祖父インサイからの「いつまでも可愛い孫」扱いを打破し、方向性は違っても自分もまた商売人として実力があるという評価をリゼル以外から感じられなければ一人前とは言えないのでしょう。ノベル17巻で、隻腕の元Sランク(彼もまたインサイの知己)が真正面から言った「冒険者相手にすんにはちょいと弱腰みてぇだ」に対して、リゼルは「押さなくてもいいだけの実力と誠実さがある」とフォローしましたが、実はとても的を得ているのではないでしょうか。本質は押しの強さの話ではない。若さや、インサイの孫という良くも悪くも強いラベルは、言わばモラトリアム。いずれは無くなるのです。インサイの商売相手であるサルスの老紳士(裏の情報屋・蜘蛛)に対して「苦手で気が引ける」と言っているうちは道半ばかもしれません。
(メンヘラだけが加速するのはホントどうかと思うんですがね…)
不完全な才能を育てるのは誰のため?
リゼルがやたらと年下に甘くするのは何故なのか?を、パイデラスティアの制度に実例を見つつ書いてきました。
実のところ、リゼルはジルが言うようにジジィ感覚なのかもしれません。ふたりとの精神年齢差を考えればあながち間違いでもない。リゼルは徹底した貴族教育を受け、若くして公爵位を継ぎ、宰相として国の中枢を担ってきた。20代後半で「まだまだ若輩」といいつつ、精神的にどれほど老獪さを要求されてきたことでしょう。それに比べて、ふたりの何と幼いことか。50歳くらい離されているんじゃないでしょうか。
いずれスタッドの精神年齢が実年齢に追いつき、ジャッジが堂々と大人の世界を渡り歩けるようになったら、リゼルは彼らを一人前の男として扱うのでしょう。
リゼルにとって休暇世界は仮初であり、古代ギリシアの市民のように社会全体を考える必要はありません。そしてスタッドもジャッジも精神的に未熟なままでも、リゼルにとっては優秀な人材であり、冒険者として休暇世界を生きる自分の助けになっていたはずです。
それにもかかわらずここまで目をかけるのは、やはり職業病なのか、それとも"ヘーカ"が最近おっしゃる「冒険者制度をこっちでもやるならオペレーションできるやつ連れて帰ってこい」が念頭にあるのか。
教育係歴を持つゆえに、優秀だが幼い子を一人前にする手助けをしたいタイプなのかもしれませんが、最終的に、自分に還元されるものがあるのは言うまでもないことです。
参考文献:
江戸川乱歩と精神分析一論文「J ・A・シモンズのひそかなる情熱(ニ)」を読むー
(広島国際大学 心理科学部臨床心理学科 鸛田一郎)
エドワード・カーペンターの同性愛思想─ジョン・アディントン・シモンズとの関わりから
(宮崎 かすみ)
古代ギリシアの社会をジェンダーの 視点から読み解いてみる
(桜井万里子)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
