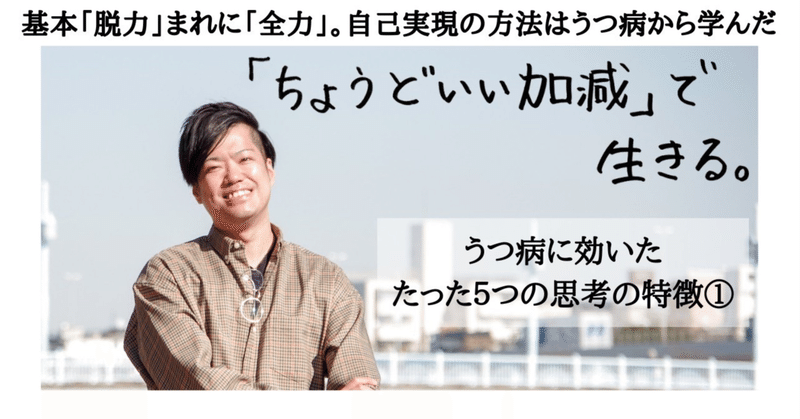
うつ病に効いた、たった5つの思考の特徴①|連載『「ちょうどいい加減」で生きる。』うつ病体験記
気がつけば桜が咲いていてね――。
ある年のこと。季節が移り変わり、桜が満開になっていました。うつ病になって以来、花の開花に鈍感になるほど私の感覚は鈍っていました。どの季節に自分が生きているかに思いを馳せられない。というか、季節に関心が持てない。そんな私が桜の香りにハッとして心を奪われたのは、うつ病を発症して8年が経過したころでした。すこしずつですが、五感が反応し始めるのを感じて私は喜びを抱きしめ、涙しました。
「世界はなんて美しいんだろう……」
季節の香りがうつ病回復の道しるべだった
本章までで私は、自身のうつ病体験にかんするさまざまな経過をつづってきました。病の発症、引き込もり、自殺未遂、いろいろな奇行、友だちによる献身的な支え、復職・休職の繰り返し、支えになった言葉、そして精神病棟への入院。これらを経て、しかし体調はすこしずつ回復していきました。
じつは、私には「あのときがあったから、うつ病が快癒に向かった」といった転換点のようなものはありません。復調は、アップダウンを経ながらカタツムリの速度で進んでいきました。苦悩のなかから、しなやかな生き方の芽を育てていったという感じです。真っ暗闇のなか、もがきつつも、出口が見えない地獄のトンネルを歩きつづけました。ところが、あるとき突然、わずかな光がさしたのです。春の芽吹き、夏の入道雲、秋の落葉、冬の木枯らし――。自然の変化を味わうことのできる感覚が、私にとって体調回復の道しるべでした。季節感に、前進の確かさと喜びの光を見ることができたのです。また、涙でした。
13年以上の闘病生活のなかで、私の考え方は少しずつ変化していきました。とくに、ある5つの思考の変化は、うつ病回復に良い効果をもたらしたと感じています。それは私の個人的な経験に基づく効果であって、医療的な保証のあるものではないですが、内容を紹介していきます(万が一それで体調に違和感を持たれる方がいらっしゃいましたら、専門医の判断を仰ぐことをおすすめします)。
うつ病に効いた「5つの手放し」
最初にまず前提だけ確認させてください。これから述べる思考転換の実践について――それを私は「5つの手放し」と表現しています――ですが、精神疾患を抱えている方は、けっして、実践しようと「頑張り過ぎないで」ください。気負いは心身によくありません。ほどほどにして、できないときは「まあ仕方ないか」とゆるく考えていただきたいのです。できないことで自分を責める必要はありません。
そもそも、これから述べることは実践を強制されるべきものではないですし、「しなければならない」治療でもありません。実践するもしないも、自由です。その上で実践するとしたら、焦らず、じっくり、少しずつ、歩みを進めてください。ゆっくりとした歩みは、散策的です。歩く速さは、遅いかもしれません。でも、散策的だからこそ、道ばたのタンポポに胸をときめかせるようにして、季節の移ろいをより楽しむことができます。そんな風に思考の変化も「楽しむ」くらいの感覚でいてもらえれば嬉しいです。
個人的には、考え方の良き変化はうつ病に効くと実感しています。考え方を変えるというと「ものすごくハードルが高い」と思われるかもしれませんが、一日一日のわずかな思考をとらえて、「あ、この思考は変えていこう」という「気づき」が得られたら、それは立派なステップになります。他人から見れば小さな一歩かもしれませんけれど、その積み重ねが思考転換の偉大な一歩につながります。ここは、信頼してください。
「5つの手放し」を具体的に見ていきましょう。
・「自分イジメ」を手放す
最初に取りあげたいのは、自分を責める「癖」を手放すことです。ともすると私は、ことあるごとに自分を責めて「俺なんて消えた方がいい」と自己卑下していました。もしくは「俺は頑張りが足りない」「これができないなんてダメだ」「甘えるな」と自らを叱咤して何とか頑張ろうとしていました。しかし、責めれば責めるほどつらくなり、病気も回復しません。
そもそも、なぜこんなに自分を責める必要があるのでしょうか。頑張る自分でいるべきだから? 人の「役に立つ」自分であらねばならないから? ほんとうにそうあるべきでしょうか。私は、その「~ねばならない」「~すべき」という自己規定から自分を解放した方がいいなと思いました。この「ねば・べき」が、自らを強迫観念に駆り立てていたのです。でも、自分をそう強迫したところで、うつ病ですから「ねば・べき」には対応し切れません。結局、凹むことばかりです。それなら、「ねば・べき」は手放した方がいい。いまから振り返ると明確にいえますが、「~ねばならない」「~すべき」のほとんどは、案外「しなくても何とかなるもの」です。直面している際にはそう感じられないこともあるでしょうけれど、これらは人生を豊かにする必要条件でも何でもありません。大胆に手放してみてください。
「自分のことを大切にできない人は、他人も大切にできない」
これは、ある種の真理をついた言葉です。「俺は頑張りが足りない」「これができないなんてダメだ」「甘えるな」「俺なんて消えた方がいい」と責めつづける自分自身について、あるとき私は思いました。これらの言葉を、はたして他人に向かっても言えるかな? と。私は、言えないと思いました。だから、他人に言えないことは自分にも言わないようにしようと私の心は決まりました。まず自らを大切にする。で、自分がご機嫌になることをする。実践は、ここからスタートです。
私は自分を解放していきました。
「もっと楽しんで生きていいんだ」
「自分のことをもっと優先していいんだ」
「体が警告サインを出していたら、大胆に休んでいいんだ」
自らを大切にするのが下手だった私は、下手だからこそ、逆に自身を甘やかしまくりました(「しまくる」くらいがちょうどよかったです)。そして、「誰かにしてほしかったように、自分にしてあげる」を実践しました。そうしていくと徐々に「そもそも俺、生きているだけで十分頑張っているじゃないか」と思えるようになりました。「うん、きょうも生きているぞ。お釈迦さまが『一切皆苦』といったようなこの世界を、俺はきょうも生きている。それだけですごいじゃないか」と。
そして「自分ができないこと」を指折り数えて落ち込むのではなく、「それでも今できること」をささやかながら行って、自分をほめるようにしました。これは以前、読書の例を引き合いに出しながら触れた話ですね。たった1行でも読めたら、それで「すごいじゃないか」と自らをたたえる。他人からすれば「たかが1行」かもしれませんが、私は努力とも呼べないかもしれないその一歩を抱きしめるようにして価値を見いだして、読めたことに感動しました。この感性が、長い闘病で磨かれていったのをよく覚えています。
・「努力信仰」を手放す
以前の私は、どこかに「過剰な努力信仰」を持っていました。努力さえすれば何でもできると思っていました。この考えは「ものごとを成し遂げられない人は努力が足りないからだ」という発想に結びつきます。かつてはこの考えに基づいて「できない他人」を責めていました。で、いざ自身がうつ病で努力ができなくなると、責めの矛先を自分に向けてしまったのです。
ですが、人生には「流れ」のようなものがあります。調子がいいときもあれば、どうあがいてもうまくいかないときもある。不思議なことですけれど、努力が結果に結びつきやすいときもあれば、どう努力してもうまくいかないときもあります。努力信仰が通用しない時節は、確実に存在します。うつ病は、後者に近い側面があるかもしれません。そんなときは、変にあがくことはせずに、時の流れに身を任せたっていい。努力を手放したっていい。そんな鷹揚(おうよう)な発想ができるようになったとき、私の気持ちがラクになりました。うまくいかないときは「ジタバタせずに、だらんとしていよう」「今はそういうときなんだから」といった感じで、いい意味で肩の力が抜けるようになったのです。
かの名言を思い出します。
「何も咲かない寒い日は下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く」
また、かつての私は、どこかに「努力できない自分が恥ずかしい」という観念も持っていました。当然ながら、他人に弱みを見せることはしません。いつも、きちんとした自分、完璧主義的な自分を他人に見せていた気がします。要は「適当にするのが苦手」で「欠点・弱点は敵だ」と思い、「些細なことが気になって仕方が」なかったのです。でも、それでは疲れてしまう。そもそも、人間は弱い生き物だし、弱くたって何も悪いことはない。弱さは、善悪とは関係がない。なのに、弱さを悪だと思い込んで、人に見せなかったのです。ちなみに、先ほどの「ねば・べき」の発想も、それを達成することが善だと私は思っていました。ですが、「ねば・べき」も本来、善悪とは関係がありません。「できない自分」は、けっして悪ではないのです。私はこうやって、ものごとをいちいち善悪でジャッジするのもやめました。そして――。
私は「弱くったっていいじゃないか」と開き直るようにしました。
そして、やがて私は、他人に弱音を吐くようになっていきました。「はあ、きっついわあ」とかんたんに言うみたいな感覚ですね。これは以前の私には考えられなかったことです。加えて私は、万人から好かれようという謎の願望にしがみつくのもやめました。そんなことは、どだい無理な話です。「100%の人に好かれるより、わずかでもいいから自分を知って深く愛してくれる人がいればいいじゃないか」と、発想の転換を行いました。
誰かから嫌われても仕方ないという自分を受け入れる。また、頑張らない自分を受け入れる。これは難しいことでしたけれど、やはり、長い闘病生活がそれを可能にしてくれました。それに、人が私を必要としてくれていることの本質は、努力や頑張りとは関係のないところにあるとあるとき気づいたのです。
あなたを必要としてくれる人は、あなたが頑張っているから、あなたを好きなのではありません。努力の人だから好きなのではありません。役に立つから好きなのでもありません。そういったこと無しに、ただ「好き」で、だから必要としてくれています。だから「何かをしないと見捨てられるんじゃないか」なんて思わなくていいのです。あなたはあなたのままで必要とされています。その事実に、私自身は盲目的でした。でも、うつ病によって開眼しました。
(「5つの手放し」残りは、次回記事にて)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
