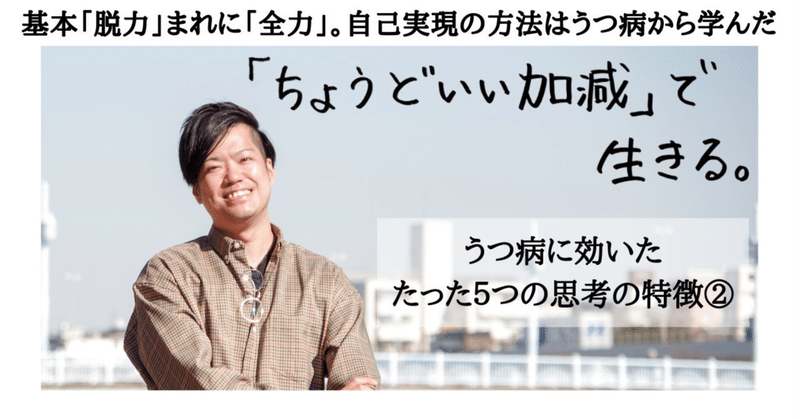
うつ病に効いた、たった5つの思考の特徴②|連載『「ちょうどいい加減」で生きる。』うつ病体験記
自身の弱さを認めて、受け入れて、さらには「弱くたっていいじゃないか」と肯定すらしていく。この態度は、弱者の遠吠えにすぎないのでしょうか。「否」「違う」と私は考えています。むしろ、みなさんに知ってほしい。弱さを含みこむことは、しなやかな強さをもった生き方に通じます。私はこのことを、しなやかな知性を持つ詩人・茨木のり子から教わりました。彼女は謡(うた)いました。
「大人になってもどぎまぎしたっていいんだな/ぎこちない挨拶 醜く赤くなる/失語症 なめらかでないしぐさ/子供の悪態にさえ傷ついてしまう/頼りない生牡蠣(なまがき)のような感受性/それらを鍛える必要は少しもなかったのだな」
ふれたら壊れてしまうような"やわい"感受性は、語弊を恐れずに言えば、茨木のり子最大の武器です。それは、強烈な競争社会となってしまった現代にあっては「弱さ」と受け取られがちなものですが――すぐに傷つき、凹み、恥じらいにつながってしまうのですから――しかし、ひとたび詩作のかたちをとると、彼女の言葉は人びとの心を射抜きます。弱さが強さに反転し、もはや強弱では測れない価値にまで変わるのです。
強者になることに憧れを抱かされ、強者になるべく仕向けられる現代社会の構造を、私はあえて「異常」と表現しますが、そんな異常に適応することが「普通」とされる世のなかで、「ちょっと、これって異常じゃないかな」と言える感覚が素晴らしい――彼女の力強い言葉の響きは、今も人の心をとらえて離しません。この"弱さを含みこんだ強さ"については、本連載の後半で描いていきます。
さて、「5つの手放し」の残り3つについて述べていきましょう。
・過去と未来を手放す
うつが酷かったとき、私は過去に縛られ、未来にとらわれていました。過去に後悔し、未来に不安を抱いていました。ですが、いくら後悔を重ねても、どんなに不安がっても、前進することはありません。事実的な過去は変わらないし、未来はわからないままです。何千何万回と過去や未来を嘆いても、「うつで、いま苦しんでいる私」の現実は1㍉も変化しなかったのです。そんな恨み節の果てに、私は悟りました。「過去はもう過ぎ去った。未来はまだ来ていない。私が生きられるのは、どこまでいっても『いま・ここ』、この瞬間だけだ」と。ならば「いまこの瞬間を、丁寧に生きよう」と。
それでも「あのとき、ああすればよかった」と後悔する場面はあります。そんなとき、私は「でも、当時はそれがベストだと思って選択したんだよな」等と考えて、昔の自分とのあいだに折り合いをつけていきました。未来については、「将来の心配ごとのほとんどは頭のなかでしか起こらないんだよな」と思って、「(いい意味で)未来はわからないぞ」と発想の転換を行いました。未来は、悪くもなりますが良くもなり得ます。私は、良い可能性にも目配せしました。
もちろん、思考の変化を一朝一夕で起こせるわけではありません。私には、何千何万回と過去・未来を"呪詛"する過程が必要でした。最終的に私は、過去や未来について考えるのに疲れて、「いま・ここ」の現実以外を手放すようになったのです。
・「闘病」を手放す
また、私は、うつ病と「闘う」という態度も手放しました。なぜなら、「治そう」「治そう」と思うと、かえってうつ病が悪化したからです。精神科医の泉谷閑示氏はこう語っています。
「『病と闘う』という考え方そのものが、実は『うつ』の回復を妨げてしまう側面を持っています。『一日も早く治りたい』と思えば思うほど、『病を克服せねば』『病気に負けるな』と考えてしまうのは当然の心理なのですが、それが皮肉なことにかえって『うつ』を長引かせる結果を生んでしまうのです」
本連載では便宜上、「闘病」という表現をつかっていますが、正確には、闘病というのは私がしたことではありません。むしろ私は、うつ病と良好な関係を築くようにしました。うつは闘う相手ではなく、己れを知るための鏡で、自分について教えてくれる「活かすべき友」だと思ったのです。
うつは、いま自身がしていることを見直す絶好のチャンスです。でてくる症状は、「あなたの苦しい考え方、生き方を見直してほしい」という心身からのメッセージです。うつになって「何もしたくない」という気持ちを抱いたり、朝起きられなくなったりするのは、自分ではうまく休めないその人に対して、体が、心が、「休んでね」と訴えかけているのです。ですから、うつになったことを「いけないことだ」として否定する必要はありません。自分を責めてしまえば、悪循環に陥ります。繰り返しになりますが、うつは「考え方」や「生き方」を見直す大切な機会になります。私はそう思って、うつと和解する道を選びました。それはそのまま自分自身との和解にもつながります。
もちろん、うつからのメッセージには、先のような「休んでね」といったシンプルな訴えもあれば、重層的で、それこそ、その人の存在基盤を問い直すようなものもあります。つらい症状が伝えてくる内容は、うつを患った人それぞれで、千差万別です。大切なのは、その「うつからのメッセージ」に耳を澄まして、本来の自分に立ち戻り、自分らしさを取り戻し、自分自身でハンドリングしながら人生をふたたび歩みだすことです。

ちなみに「病気を治す」というと「病気になる前の状態に戻ること」を想像する人も多いかもしれません。ですが、こと「うつ病」に限って言えば、治癒のイメージは違います。さまざまなうつ病体験談を読んでいて私も感じるところですが、見事なうつの治り方をしている人たちは、みな、発症前までの自身の考え方や生き方について根本的な見直しを行っています。いわば「生まれ変わって」います。うつ病からの脱出は、「モデルチェンジしたような、より自然体の自分に新しく生まれ変わるような形で実現され」(泉谷閑示、前掲書)るのです。
・「他人との比較」を手放す
最後に私が手放したのは「他人との比較」です。
うつ病が酷かったときの私は、とにかく人の目を気にしました。成果を出している同僚と比べては嫉妬し、自己卑下をしましたし、あるいは、テレビに出ているキラキラ輝いた(ように見える)タレントを見かけては世界から取り残されたように感じました。他人は、うらやみ、憧れ、期待し、勝手に「裏切られた感」を抱き、絶望し、妬み、「俺なんてクズだ」と落ち込んでいくための比較対象でしかなかったのです。この"比較グセ"を手放したときに、気分が大幅にラクになったのを覚えています。
注意したいのは、「他人との比較」が上記だけにとどまらない点です。前回の記事で、「ねば・べき」の話をしましたね。「~ねばならない」「~すべき」という考えですが、ほとんどは特定の誰かに言われたり、世間から要請されてきた価値観だったりします。私はそれら「ねば・べき」を、自身に照らして「自分もそうあらねばならない」と思いこんでいました。しかしこれは、他人の考えを自分に当てはめようとする「他人軸の生き方」です。他人の意見や価値観に軸足を置いて生きて、振り回されてしまうと、私はどんどん生きづらくなっていきました。「ねば・べき」が意識化されるのは、大抵、「それができなかったとき」です。そのたびに「できない自分」に凹んでしまえば、自分へのダメ出しばかりが加速します。地獄です。しかも「あるべき自分」を理想像として掲げて比較しだすと、「怠惰な自分は律しなければならない」という「ねば・べき」の無限ループに陥ります。どこかでストッパーをかけなければなりません。
そこで私は、他人軸の生き方をやめ、自分軸で生きていこうと考えました。
具体的には、他人や世間の「ねば・べき」から離れて、ありのままの自分、あるがままの自分の声に耳を澄まして、自分に軸足を置いて生きることを選ぶようにしていきました。哲学者ルソーは主著『エミール』のなかで、自然に生まれたあるがままの人間に比べて、人の手が入って"加工"されてしまった人間を「調教された乗馬」「ねじまげられた庭木」にたとえましたが――「ねば・べき」などの慣習が人を加工してしまうのです!――私は「調教される前、ねじまげられる前の自分ってどんな感じだったのかな」と想像しながら「自分らしい生き方とはどんなものか」について思いを馳せました(がんばりすぎない程度に)。
私は、自身の本音と向き合いました。本音は、意外にも自分ではわからないものです。ですので、私はまず思いつくままに出来事や感情をノートに書きなぐりました。文字どおり、書き「殴って」いたと思います。ほとんどはネガティブなことがらや感情でしたが、そのまま書いて、書いて、今度は「なぜそう思うのか」を自身に問いかけました。そうして「書く」と「なぜ」を追求していくと、だんだんと「一貫して自分がネガティブに感じている『もの』『こと』」が見えてきます。それを反転させれば「一貫して自分が大切にしたいと思っている『もの』『こと』」がわかります。私が本音だと思うことは大抵、「自分にとって心地いいもの」でした。「自分らしさ」を探る指標になるのは、きっと「自分にとって何が心地いいか」なのでしょう。そんな感じで気持ちをアウトプットしながら、私は本音を見いだし、自分らしく本音に正直に生きる選択をしていきました。
長くかかりましたけれど……。
さて、ここまで紹介してきた「5つの手放し」の考え方についてですが、みなさんはどう感じられたでしょうか。改めて5つを確認します。
・「自分イジメ」を手放す
・「努力信仰」を手放す
・過去と未来を手放す
・「闘病」を手放す
・「他人との比較」を手放す
うつ病の渦中にいる人のなかには、「そんなことを言ったって、実践は無理だよ」と思う人もいるかもしれません。「手放すなんてことができるなら、いまごろとっくにやっているよ」と言うかもしれません。私も、そう思っていました。でも、まずはその「無理だよ」という意識を手放してみませんか。もちろんその逆、「可能だよ」という意識もあえて持たなくていいです。ただ、時の流れに身を任せるようにして、自身が変わるのを待ってみませんか。
夢は、ないかもしれない。
希望も、ないかもしれない。
でも、目の前のはるかな道をただただ歩んでみて。
やがて光が、どこかのタイミングで射しだすかもしれない。
あなたがどんなにそれを信じられなくても、
光が射す可能性は、つねに存在してしまっている――。
私が紹介した「5つの手放し」が、うつ病の苦しみのみならず、悩みにうずくみなさんの心を軽くするヒントになれば幸いです。ただし、一方でこの記述が誰かを傷つけているかもしれないことにも私は敏感です。不純な何かを、感じています。このジレンマについては、次の記事にて。
前回記事> <次回記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
