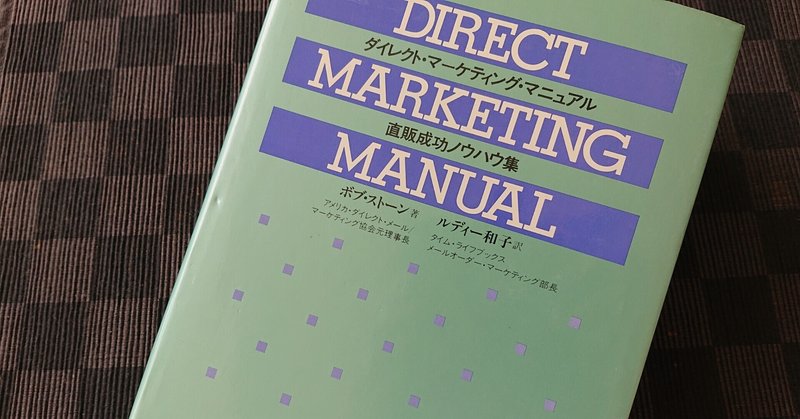
こころざし(3の2)「天職篇」【エッセイ】二〇〇〇字(本文)
20代までの挫折から一変し、幸いにも全てが好転して行きます。
しかし、決して華々しい成功談ではありません。あくまでも貫いたのは、「“小山”の大将」。少しでも若人の参考になればと、綴りました。
20代で挑戦した外食チェーン事業に全て失敗し、三十路前の年に入った職業訓練学校が、ターニング・ポイントだったように思います。訓練校での充電が終わり求職活動を始めるのだが、一貫して変えなかったのが、「競合がないこと」と「既成ではなく新興の事業に関わること」。
訓練校時代の話
(その2)で記すのは、やっと“天職”と思える仕事と出会った、17年間の会社員時代の話。ほどほどに成功できたとすれば、その要因は次の3つでなかったかと。
・楽しく仕事できること(“やらされ感”ではなく、“やっている感”があること)
・頑固なこだわりと、“真綿”のような素直さ
・そして、“運” 小さじ一杯ほど
※
新聞の人材募集広告で、「翻訳」の字が目に入った。大学入試のとき、最大の苦手が英語だったので、「翻訳」に興味があったわけではない。が、新しさを感じた。しかも、翻訳者を養成する教育会社。当時、翻訳を教育する学校は始まったばかり、かつ、学校以外に通信教育をやっている。通信教育というと、信頼性が低かった。いまでは主流の通信販売でさえも、 “眉唾もの”と見られていた。「いつでも、どこでも、だれもが」勉強できるのが、通信教育。この先、その利便性が受け入れられないはずがない。まだマイナーなところもいい、と応募する。外国語の試験では合格できないだろう(絶対に)。しかし、経理募集ともある。訓練校で取得した簿記2級の資格でなんとか入れないかと、希望職種を経理とする。
結果、合格。後に知るのだが、採用理由は、硬式野球の経験が買われたらしい。当時社内にあったチームのピッチャー候補として(補欠だったようだ。実は、後に共に常務となるH氏も補欠だった。しかも、硬式野球の経験者だったことも共通していた)。
社長は女性で、なかなかのやり手。売り上げが5億。社員50名。創業して5年の会社だった。月刊翻訳学習誌「翻訳の世界」を発行していた。

いざ、初体験の経理実務。しかし、終業時、台帳に1円の狂いでもあれば残業となる。上司の女性係長は、そろばん。私は、すでに電卓を使っていたのだが、速さで敵わない。いつも、その間違いは彼女が見つける。達成感なくトボトボと自宅に戻っていた。1年が経過しようとした、ある日。「ご迷惑をおかけしているので」と、社長に辞表を出した。しかし、慰留され、配置転換となる(ピッチャーを失いたくなかったのかもしれない・・・)。
配属先は、広報企画部。通学と通信教育の受講生を募集する。広告や、ダイレクトメールの企画・運営が仕事。これが面白かった。毎日、終電までの残業も苦ではなかった。
米国で一定のステータスを得ていた“ダイレクトマーケティング(無店舗販売)”理論がベース。日本でも、ルディ和子氏の翻訳で、『ダイレクト・マーケティング・マニュアル』(1982.5 ダイヤモンド社)が発刊され、その直後に購入し、バイブルとした。
ダイレクトメールはもちろん、新聞や雑誌の広告でも、効果測定をする。経理で扱う受け身の数字ではなく(決して受け身ではないのだが、そう感じていた)、“攻め”の数字と思った。
広告に、「あなたの翻訳力を無料で診断します」というキャッチの下に英文を置き、葉書で応募してもらう。住所の枝番にその媒体のコードを入れ、その反応を集計する。添削・診断し、講座のリーフレットと申込書とを一緒に送る。申込書には、どの広告とDMから反応したかを判別できるコードが入っている。その数値をデータ化し、企画・媒体ごとにどれほどに効果があったのかを測定。次の企画に反映する。という仕組みである。
ある企画が大ヒットする。DMに同封する受講案内文を、手書きのレター風に特殊印刷。よく見れば印刷であることは分かるのだが、一見、手書きの手紙が入ってきたと思っていただいたようだ(注目していただけるのがポイントなのだ)。
学校は、大阪、名古屋に拡大し、会社全体の売り上げが順調に推移。創業20年目には40億円にまでになっていた。
その間、取締役、最終的に常務取締役になるのだが、実績だけではない。運もあった。というのは、ある事件が幸いしたのだ。その会社は、某会社(いま化粧品・健康食品で超有名な企業に成長)の子会社だったのだが、親会社の社長をバックに我が社の常務による「クーデター」が発生。しかし争いに勝ち、その貢献が評価されたこともある(政治の世界にある“論功行賞”ということだったのだろうか?)。
その内容は、以下で触れている。
入社8年目には経営陣の一人となり、5年後。社長が上場宣言をし、経営コンサルタントを入れる。その2人目の人物が、「広告費を圧縮し、純益率を確保しよう」と言い始めたのだ。その方針に、入社後初めて社長とぶつかった。「縮小再生産に陥ります」と主張したのだった。
結果、部下ふたりのインターネット研究事業部の閑職に。ひとりは見張り役だった。が、もうひとりは、元タイム・ジャパンの出身。アメリカでもまだ「インターネット」の「イン」くらいだったが、そのタイム本社でインターネットに関わっていたのだった。
このことが、独立を決断させ、その後の起業の骨格になっていったのだった。
一方40憶まで伸びた会社は、その後、売り上げが激減。最近では3億円までになっている。自分の主張が正しかったとは言わない。もし認められていたとしても、同様の結果になっていたかもしれない。だが、明らかなのは、閑職に追いやられることなく独立する考えも消えていただろう。何が正解かは、誰にも判らない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
