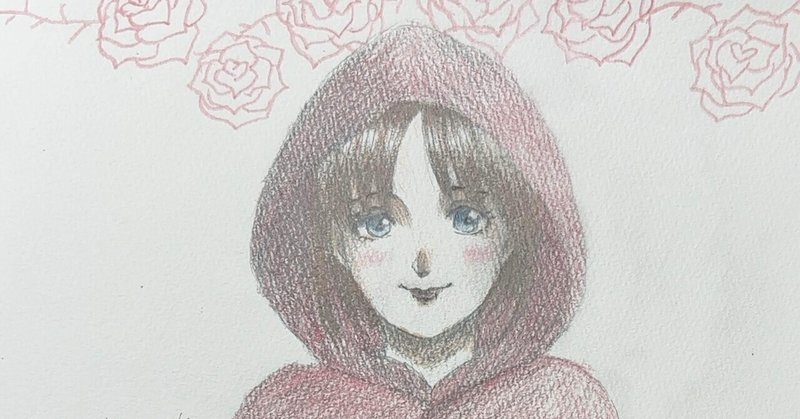
【小説】赤ずきんの銃弾 第1話「おつかい」
「わぁ、でっかいお家!」
ロザリー・ペルティエは背の高い木に囲まれた屋敷を見上げ、感嘆の声を漏らした。背後から視線を感じて振り返ると、先程入ってきた門のそばで、二人の警備員が小声で話し合っている。本当にあんな子どもが、ありえない、などという会話が耳に入ってきたが、気にせず玄関の呼び鈴を鳴らす。
「こんにちは! フックス社長はこちらにいらっしゃいますか?」
扉が開き、分厚い辞書が辛うじて入るくらいの隙間が作られる。そこから厳つい男が怪訝な顔を覗かせた。男は鋭い目でロザリーを見下ろし、「社長、ガキが来ましたよ」と室内の人物に呼びかけた。
「ガキ?」
低く、威圧感のある声が響く。
「ええ。なんか赤いずきん被ったガキです。絵本の中から遊びに来たんですかねぇ」
小馬鹿にしたような口調で言うと、「中に通せ」と社長らしき人物の声が命じた。
「え? でも……」
「いいから通せ。私が招いた客人だ」
「は、はぁ……承知しました。おい、入れ」
「お邪魔します」
少し戸惑った様子の男の後ろを、ロザリーはちょこちょこと付いていった。
部屋に案内されると、ロザリーは持ってきた大きなトランクをそっと床に下ろした。
暗い赤を基調とした壁に、鹿の剥製や美しい絵画が飾られている。部屋の入り口付近には応接用の黒い革のソファとローテーブルがある。奥にはデスクと背の高い椅子が置かれ、それにどっしりと身を預けて座っているのが、依頼主であるフックス社長だった。
「君が『赤ずきん』か? あの……殺し屋の」
ロザリーは赤いワンピースの裾をつまんでお辞儀した。
「はい。今回はご依頼いただきありがとうございます」
「ほう……随分と若いな。武器は何を?」
「これです」
床のトランクを開けて中身を見せる。カメラの三脚のようなスタンドと、大まかに分解された銃口やグリップが鈍く光った。愛用のガトリングガンである。
社長と先程の男が口をあんぐりさせているのを見て、ロザリーはちょっぴり得意げに微笑んだ。
「それで、社長。今回のご依頼ですけど、誰をターゲットにすれば良いですか?」
「え? あ、あぁ、そうだな……まぁ、そこのソファにでも座りなさい。茶でも飲みながらゆっくり話そう。おい、彼女にアールグレイを」
社長は部下らしき別の男に声をかけると、デスクの引き出しから一枚の写真を持ってきて、ロザリーの向かいのソファに座った。
「こいつはエマニュエル・ベッカーといってな、商売敵の会社で新しく社長になった男だ。こいつのせいでうちの毛皮製品の売り上げが大幅に落ちている。だから君に来てもらったというわけだ」
部下が紅茶の入ったティーカップと砂糖の瓶を運んできて、テーブルに置く。ロザリーは銀のスプーンで砂糖をすくって紅茶に混ぜた。銀のスプーンと溶けていく砂糖を交互に見つめ、ようやくカップに口をつける。
「その、エマニュエル・ベッカーさんを撃てば良いんですね?」
「ああ、よろしく頼む。もちろんお礼もきちんとする」
「分かりました」
ロザリーは紅茶を飲み干すと、トランクからペンとメモ帳を取り出してエマニュエルの名を書き、社長の顔を見上げた。
「社長。エマニュエルさんの住所って、ご存じですか?」
「知ってるよ。前にあいつと名刺を交わしてね……そこに書いてあった」
社長がエマニュエルの名刺を差し出す。ロザリーは名刺を見ながらメモを書き終え、ソファから立ち上がった。
「では、行ってきます」
フックス社長の屋敷を出ると、来た道を戻って石の橋の前で足を止める。ここは警察も介入できない無法地帯。しかしこの橋を渡った先は、善良な人々が暮らす平和な町だ。ロザリーの家もこの先にある。彼女が町と無法地帯を行き来する殺し屋だということは、誰にも知られてはならない。
ロザリーは橋を渡り、メモを見ながらエマニュエルの邸宅へと足を進めた。鼻歌を歌い、なるべく軽い足取りで、楽しげに見えるよう心がける。
「あら、ロザリーちゃん。こんにちは!」
顔見知りの女性に声を掛けられ、元気良く挨拶を返す。
「こんにちは!」
「ずいぶん大きな荷物ね。どこ行くの?」
「エマニュエルさんのところ。お菓子を届けに行くの」
「そう。気をつけてね」
「はーい!」
ロザリーは明るく笑ってみせた。
エマニュエルの邸宅は、町はずれの高級住宅街にあった。
周囲に誰もいないのを確認して屋根の上に登り、準備を着々と進めていく。そして準備が整った後、トランクからあらかじめ用意していたケーキの箱を取り出し、玄関先に向かう。
呼び鈴を鳴らすと、柔和そうな男性が顔を出した。
「こんにちは! エマニュエルさんですか?」
「あぁ、そうだけど……君は?」
「初めまして、ロザリーといいます。フックス社長から頼まれて、ケーキをお届けに来ました」
「え、フックス社長から? 嬉しいなぁ、ありがとう」
エマニュエルはにっこり笑い、差し出されたケーキの箱を何の疑いも無く受け取った。
「では、失礼します」
「ありがとう。フックス社長によろしく伝えといてね」
「はい」
ぺこりとお辞儀して、扉が閉まる音を待つ。そして素早く屋根に登り、用事を済ませて地上に降りる。再び呼び鈴を鳴らす。
「ん、どうしたの? 忘れ物?」
「うん」
ロザリーは柔らかく微笑んで、自分の身体の前にスタンドを置いた。そこにガトリングガンを置き、銃口をエマニュエルに向ける。
「もうひとつ、渡したいものがあるの」
目を見開いたエマニュエルの顔面にいくつもの穴が開く。どろりとした赤が噴き出す。
「ごめんなさい」
ロザリーは何度も何度も銃弾を撃ち込んだ。呻き声を遮るように。息を吹き返す暇を与えぬように。そうしてエマニュエルが動かなくなったのを確認すると、邸宅の庭に穴を掘って血まみれの亡骸を押し込み、上から土をかけて固め、近くにあった木の枝を挿した。
簡素な墓の前で十字を切った後、ホースを使って顔や服に付いた返り血を洗い流す。もう手慣れている作業だが、やはり好きにはなれない。
ロザリーは深くため息を吐き、ガトリングガンをトランクにしまった。
フックス社長の屋敷で多額の報酬を受け取ると、ロザリーは再び橋を渡り、平和な町に戻った。花屋で季節の花のブーケを買って、大好きな人が待つ自宅へ向かう。
「おばあちゃん、ただいま」
家に入って奥の部屋を覗けば、祖母がベッドから柔らかい微笑みを向ける。
「おかえり、ロザリー。何か獲れたかい?」
「ううん。熊を見つけたんだけど、弾が全然当たらなかった」
「そう……血の匂いがするけどねえ。何発かは当てたんじゃないのかい?」
「……うん。でも全然ダメよ。弾がそれて、結局、逃げられちゃったの」
祖母には、猟師である叔父に猟銃の撃ち方を習ったのを生かし、森へ狩りに出かけていると伝えている。だから、祖母は何も知らない。孫が殺し屋の仕事をしていることなど、全く知らない。
「……そうだ、帰りにね、お花買ってきたの。そろそろ花瓶のお花が枯れちゃうと思って」
「まあ、ありがとうね。花瓶に挿しといておくれ」
「うん」
ロザリーは明るく笑ってみせた。
「ねぇ、おばあちゃん」
「何だい?」
「早く、おばあちゃんの病気が治ってほしいな」
「そうだねえ」
「お医者さんに治してもらうためのお金、まだ足りないの?」
「そうだねえ……お前のお父さんとお母さんが、工場で頑張ってくれてるんだけどねえ」
「……頑張る。私、おばあちゃんの病気が治るまで、頑張るわ」
「そうかい。ありがとうね。ロザリーにも、心配かけちゃって悪いね」
祖母の温かい手が頭を撫でる。
「ううん、いいの」
医療費を稼ぐため。両親を助けるため。そしていつか、祖母に元気になってもらうため。しばらくは血生臭い仕事を続けていくしかない。ロザリーは微笑みながら、そっと、拳を固く握りしめた。
〈つづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
