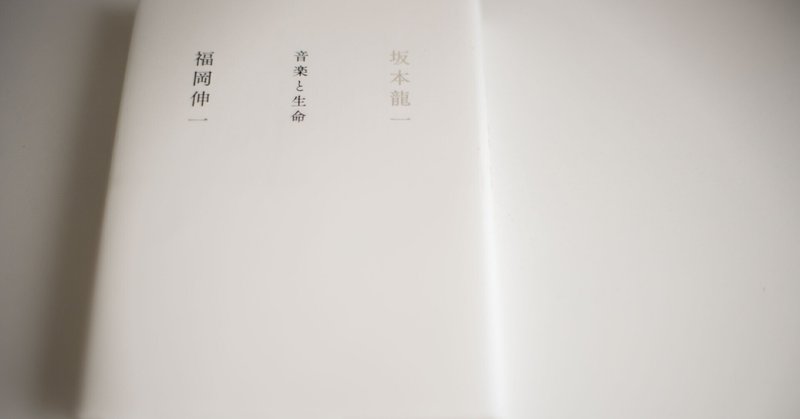
地と図
お気に入りの珈琲店の店主から一冊の本をお借りした。
音楽と生命 / 坂本龍一 福岡伸一
認識の在り様を問う正解のない話題に惹き込まれた。
意味性を与えられる以前のすべて = N(ノイズ)
人が認識するために意味づけられた情報 = S(シグナル)
「地」とは、そこにあるすべて(ノイズを包含する)。
「図」とは、認識として捉えられるように構造化された情報(シグナル)。
世界は圧倒的なノイズと限定的なシグナルで成り立っている。
ところが、人はノイズを認識することができない。
故にノイズを分析し意味づけを行い、理解しようと努力し続けてきた。
それが科学の発展ということだった。
しかし世界を構成するノイズは際限がない。
人類がどこまで努力してもノイズの全てをシグナルにすることは敵わない。
つまり人は本当の意味で世界を認識することができない。
その矛盾を知った上で、認識を理解すべきことに気づく必要がある。
西洋の分析主義に限界を感じ、東洋の易やインド哲学に興味関心が向いていると語られていた。
しかし、東洋のそれさえも認識の俎上にのぼる以上、シグナル化された部分であることに変わりはない。
ほんの少しだけ、分析至上主義の科学的アプローチより不可視な何者かを意識した解釈であるという程度に過ぎないのだ。
「地」と「図」である。
地図とは地形図の略称だと思っていたが、先に書いた通り情報化されていない全体像に情報がプロットされたものということらしい。
なるほど地形とそれに付随する標高や緯度経度、あるいはその場所の植生や利用形態、地点地点の呼称や建物等の情報が網羅されている。
しかし現実に存在するのは、そこに記され得ない複雑で変化に富んだ流動的な何かに満ち溢れた世界だ。
ボクたち人間は須く「意味のあるもの」の呪縛に囚われている。
この呪縛からは抗い難く逃れられない性質の生き物なのだ。
図画・図工:明らかにしたいものを形象として表現したもの
意図・企図:目的をもって明示された計画
図書:なにかしら明らかにされたものを著した書物
意味があるものに価値があり、認識できるものが有益である…「有意義」という言葉は象徴的にその事実を照らし出している。
世の中のデジタル化が進み、あらゆるものが可視化され情報化され、どこに出かけるにも誰かが見たり経験した景色の追体験に終始する。
「図」ばかりを追い求め、そこに「図」があることを確かめて満足してしまってはいないだろうか。
そこに「地」があることに想いを巡らせ、未知と無知に可能性を求める感性を取り戻す必要があるのではないか。
いま示されている「図」は、「地」と照らし合わせて妥当な「図」といえるだろうか。
本書の中では、星座を引き合いに2次元平面で捉えた位置関係の情報が本質ではないことが説かれている。
現代では、星座の無意味性は誰しもが理解しうるが、同様な認識の齟齬は未だあらゆる場面に散在しているわけだ。
にもかかわらず、個の本能として未知のものに出会おうとする「冒険」が世の中から失われているように思えてならない。
既知へのアンチテーゼではない。
今この瞬間の日常でさえ、未だ膨大な未知に包まれて生きているという感覚、無限の可能性に溢れているという感覚を、改めて目覚めさせるべき時代が訪れているように思う。
しかし人の認知が情報に支配される構造原理である以上、ここを超越することは不可能だろう。
感性と科学の頂を仰ぎ見る巨頭同士の対話は、それでもなおその構造原理の限界があることを知り、既知の情報がすべてではないと理解して生きることの重要性を語り明かす。
人はどこかで情報化未満の「地」を軽視し、情報化された「図」を上等と見ている節がある。
「地に堕ちる」あるいは「図にのる」という慣例表現は象徴的だと思う。
文字や言葉の意味理解が軽薄になりつつある現代ではあるが、こうした事実は漢字文化圏に「地」と「図」の概念が存在していた証左のひとつかもしれない。
人の世に、これでいいという唯一無二のゴールはあり得ない。
ただひたすらに「今を違える道」を追い求めることしかない。
知り得たことに驕らず、絶えず未知を訪ね続けよ。
それが人の生きる道である。
音楽と生命科学。
まったくジャンルの違うアプローチから、奇しくも同じ世界線を思い描いた巨人ふたりの異床同夢。
未知を求めることを「求道」と表現した先達の叡智に頭がさがる。
