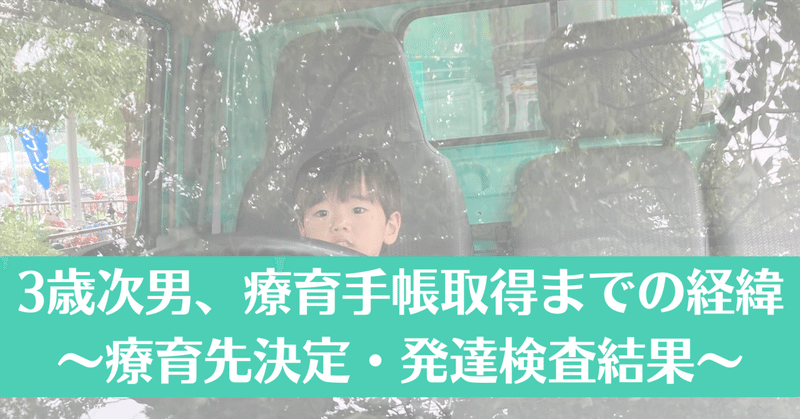
3歳次男、療育手帳取得までの経緯~療育先決定・発達検査結果~
次男3歳にはASD(自閉スペクトラム症)の疑いがあり、2022年9月から療育を受けています。
まだ、苦手なことも多いのですが、目まぐるしく成長しています!
発覚のきっかけなどは、ざっくりとこちらの記事にも書きました。
読んでいただければとても嬉しいです!
2022年8月、次男にASDの傾向があるとわかってから、私はこんなことをしました。
役所の心理士と面談
発達専門の小児科を受診
役所で受給者証の申請
療育先を決める
小児科での発達検査
療育手帳の申請・判定
療育手帳取得
小児科にて最終的な診断を受ける
1~3についてはこちらの記事をどうぞ。
今回は、4・5について書いていきます。
療育先を決める(2022/8末~9初)
療育とは
療育を受けられるのは、身体障がい・知的障がい・精神障害(発達障がいを含む)のどれかに該当する子どもです。
小学校就学前の6歳まで児童発達支援、小学生~高校卒業(18歳)までは、放課後デイサービスで療育を受けます。
療育内容は一律ではなく、その子の発達状態に応じて、変わります。
次男の場合は、まだ言葉がはっきり出ていないので、発語を促すようなトレーニングなど。
絵本を読んでもらったり、おもちゃで遊んだり、遊びを通してルールを教えてもらったり。
そんなに堅苦しいカリキュラムはなく、人数少なめの幼稚園のようなイメージだと、個人的には思っています。
できないことを無理強いすることはなく、子どものペースに合わせて、ゆっくり教えてくれる感じです。
児童発達支援の事業所を探す
私の場合は、受給者証の申請を終えてすぐに、療育先を探しはじめました。
まず、PCで近隣の事業所をリストアップ。
市区町村名+療育(児童発達支援)とかで検索すると、近隣の事業所が出てくると思います。
まずは、自治体ホームページでどの地域に、どのくらい事業所があるか調べて、
それぞれのホームページを見るなどして、1つ1つ情報収集しました。
Googleドキュメントで表を作成し、連絡先などをメモ。
まず療育とはなんなのかもいまいちわかっていなかったので、片っ端から連絡しました。
まずは直接見学に行って説明をしてもらい、その後体験させてくれるところが多かったです。
「なるべく子どもに合ったところを…」
「子どもが気に入ったところを…」
とか思いながら1日で数か所見学に行ったりとかして、事業所を探しまくってました。※真夏にチャリ爆走女
が、途中で考えが変わりました。
連れて行くのは私なんやし、スタッフの方と話をするのも私。
探す範囲を広げていったら、療育施設なんて無限に見つかるし、きりがない。
子どもはどんなところでも好きなおもちゃがあれば気に入るし、範囲を限定して、その中から私が良いと思ったところにしようと決めました。
療育施設との契約
最終的に、合計8か所の施設を見学させてもらい、3か所の事業所と契約しました。
契約のときは、受給者証が必要です。
が、既に申請していて、届くのを待っているって伝えれば、待ってくれるところもありました。
契約した事業所のうち、1か所が親子療育。
2か所が、送迎ありの分離療育です。
どの施設も、とても丁寧に、事業内容など説明してくれました。
見学→体験→契約と、契約までに何度か足を運ぶ必要があります。
初回が2022年9月12日だったので、そこそこ早く療育を始められたのではないかな。
8月末から9月初めは、見学や体験の予定を詰め詰めにしていました。
次男も疲れているせいか、夜泣きがおさまらず、ぶちぎれて私の髪をもぎとろうとしたこともあります!(おい)
私も疲れたけど、次男もよく頑張ってくれたと思います。ありがとね
小児科での発達検査(2022/9/14)
新版K式発達検査2020
初回受診から約1ヶ月後、小児科で発達検査をしてもらいました。
予約したときは、「1ヶ月先?!長~~~」と思いましたが、バタバタしすぎてたのもあり、あっという間だった
息子が受けた発達検査は、「新版K式発達検査2020」です。
検査には、約1~2時間かかります。
型はめパズルをしたり、積み木を先生と同じ形に積み上げてみて~と言われたり。
母は手伝ったり声をかけたりしてはいけないので、ひたすら次男の動きを見ていました。
率直な感想としては、「えっ普通の3歳児、こんなことできるん??」と感じるテストが多かったです。
次男には到底できなさそうなものが多かった。
たまに、「あ~これも無理か~」「おっそんなことできるんか!」と、発見することも。
途中でテストそのものに飽きてしまったり、まだ遊びたいおもちゃを片付けられて泣いてしまったりしましたが、なんとか最後までテストを受けることが出来ました。
発達検査の結果
検査から1週間後、小児科で検査結果を聞きました。
結果はこちらです。
【新版K式発達検査2020の結果】※(2歳8か月時点)
姿勢・運動:115(3歳1ヶ月)
認知・適応:65(1歳9か月)
言語・社会:55(1歳6か月)
全領域:66 (1歳9か月)
小児科では、検査中のあらゆることを観察し、記録してくれていました。
その中でも、特になるほど~~と感じたのは、こちらです。
好きな遊びに熱中すると、指示は全く入らない
模倣の課題では、手本に積み木を繋げた(他人の物・自分の物という区別がまだ理解できない)
視覚優位で、物の形を見分けることが得意
「見ただけで何をするかがわかりやすい課題」に取り組むのが得意
人とのやり取りに興味を持ちにくく、物への興味が強い
自分のペースで取り組み、人からの働きかけに応じにくい
次男、この時点で、全体的な発達が1歳9か月程度。
約1年の遅れがあるにもかかわらず、運動能力が3歳を超えている。
そりゃ~育てにくくも感じるわな、と思いました。
運動能力はもう本当にすごくて、興味のあるものを発見すると、ミサイルのように突っ走ります。
自分の目的地しか見ていないので、壁など障害物にぶつかって、怪我をすることも多数。
危険察知能力も低く、階段で3段目くらいから飛び降りたりします。
ただ、乗り物が大好きな次男、「動いている車」は怖いのです。
なので、車道に飛び出すことは、今のところありません。これからもずっと怖がっていてくれ頼む。
療育手帳は、発達指数75以下と測定された人が対象です。
次男は、全領域の発達指数が66ということで、先生から「療育手帳を取れる数値です」と言われました。
わかってはいたものの、はっきりと数値で表されると、ずしっときますね。
発達検査を受けたことで、次男の現状と、苦手なことや得意なことがわかったので、とてもよかったです。
まとめ
自力で療育施設を探す場合は、範囲を限定した方が良いと思う
子どもに合うかどうかも大切だけど、親の第一印象で決めていいと思う
正式に療育が始まるまでに、何度か足を運ぶ必要がある
発達検査の所要時間は、約1~2時間
親は手出し・口出しをせず見守る
次男の発達は約1年の遅れ(発達指数66)
運動に関しては3歳超え
発達指数75以下だと療育手帳の対象になる
発達検査によって、育てにくさの原因がわかった
発達検査によって、次男の「得意」と「苦手」がわかった
苦手なことは苦手でしゃーない、得意なことを伸ばしていけたらいいな~と思っています。
でも、彼は人との関わりが苦手で、自分のペースを乱されたとき、つい手を出したり、物を投げたりしてしまう。
これは、苦手やからしゃーないで片付けられることではないので、どうにか怒りの感情を、暴力ではない形で解決できるようになってほしいなぁ。
またまた長くなってしまいました~、続きは今度!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
