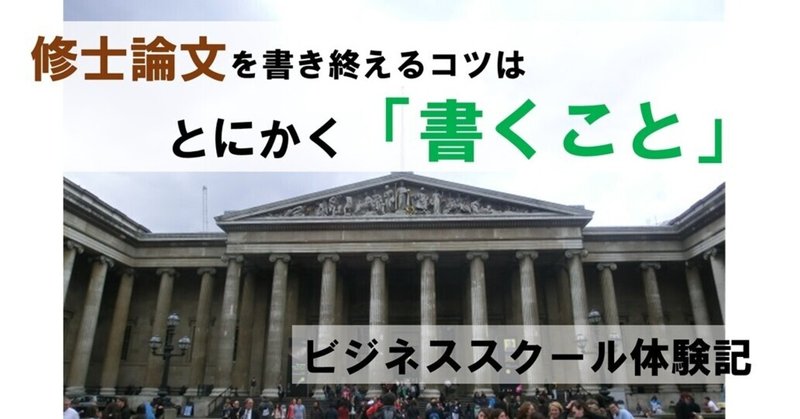
【MBA/体験記】第28話「卒論たちの沈黙」
こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!
前回の『能ある鳩はMBA』では、
「ビジネススクールの授業を乗り越えるためには、教科書の10倍のマンガを読め!」
という、まともなMBA志望者が見たらそっとページを閉じそうな内容について語りました。
今回は、修士号につきものの「卒業論文」について語ります。
1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!
Master of Business Administration
いまさらながら、MBAとは”Master of Business Administration”の略です。

Masterは「修士」、
Business Administrationは「経営管理」であり、
MBAとはいわゆる「修士号」であり、一般的には修士(経営学)の学位が与えられます。
響きは良いので、鳩はいつも自己紹介のときには、
「MBAの白山鳩です」ではなく、
「マスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーション……ホワイトマウンテン・ピジョンです」
と自己紹介しています、ええ。もちろん。
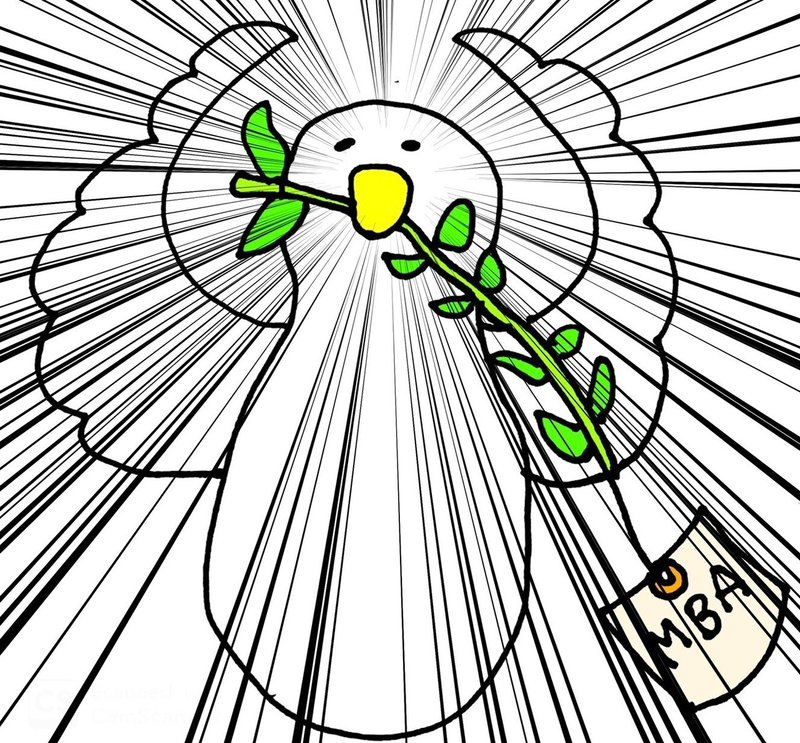
さて、いつものようにどうでもいい前置きが長くなりましたが、
MBAを取得するには修士論文が必要、というわけですね。
MBAの修士論文を書くときのスタイル
さて、個人的にはMBAの修士論文というのは、さっさと書いたもん勝ちだと思っています。
アカデミックな世界における「引用の作法」などは守りつつも、基本的にはゼミの先生の指導を守っておけば、修士号で卒業できないということは無いでしょう。
言い方は悪いですが、ビジネススクール側も商売でやっているので、
少々高くても学費を払ってくれる生徒たちには、適度に刺激を与えて卒業させてくれるところがほとんどです。

とはいえ、「どうすれば卒論は書きやすくなるか」くらいのポイントはありますので、以下は鳩が意識していた内容を列挙します。

構想:書きたい要素を並べてみる
「自分がいま、会社でやっていること/やりたいこと」に沿ったテーマとする方が、筆は進みやすいでしょう。
とはいえ、「自分が取り組んでいる課題の本質」に迫るというのは、なかなか難しいものです。
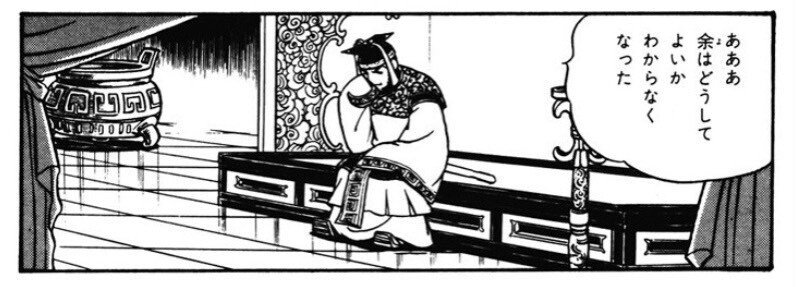
自分の書きたいテーマを見つけるおススメの方法としては、
ズバリ他人と会話することです。
このとき、相談相手からアドバイスをもらうのではなく、
ひたすら相手から質問だけを繰り返してもらい自分の考えを吐露する方が、自分の抱えている本当の想い、そして本当の課題に近づきやすいでしょう。
入学同期の方などと、古代中国でも定番のウェブ会議ツールなどを使いながら、自分の思いを確認してみてください。
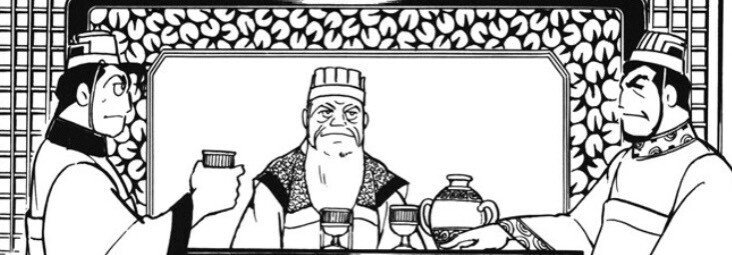
情報収集
ある程度構成を考えたら、次は情報収集に移りましょう。
その際、ご自身と似た業界の先輩が書いた修士論文を参考にすると、どんな情報が必要か考えやすくなります。
なお、情報収集するときはあらかじめ、
・どんなフレームワークからどのような示唆を導くか
・どんな結論が導かれるかの仮説
を決めておくと、情報収集ははかどります。
日常業務でもそうですが、時間は無限にあるわけではないので、
ある程度の仮説を持った上で情報収集
→満足いかなければ仮説を再構築して再び情報収集
という流れを踏むのが良いでしょう。
逆を言えば、やたらめったに情報収集していくと、その後の執筆にあてる時間が目減りしていくので要注意です。

論文中に盛り込みたい要素やキーワードについては、
先ほど言及したように知合いとの会話から探ってもいいですし、
ゼミの先生の指導を仰いでも良いでしょう。

また、論文執筆にあたりインタビューをすることがあるかもしれません。
その際は、同じコンテンツであっても複数の人間にインタビューするのがおススメです。
多角的な視点で情報が浮かびあがってくること、間違いありません。
加えて、
「本人はインタビューでは何をしゃべり、何をしゃべらなかったのか」
を、公表されている資料や他の人物へのインタビューと比較していくと、情報の見え方も変わってくることでしょう。
インタビューだからといって、常に本当のことをペラペラ話してくれるとは限らない、というわけですね。

執筆:外堀を埋めるのか、さっさと書き始めるのか
しっかりと構想を固めてから書くべきか、
とにかく執筆に手をつけるのが先か。
ここは人によって意見が分かれるところでしょう。
鳩の個人的な意見としては、
「①盛り込みたいテーマ」「②全体のアウトライン」が決まり、
「③情報収集」がある程度終わったなら、
さっさと書いてしまった方が良いと思っています。
理由の1つ目は、安心できるからです。
執筆に移らないままじりじりと時を過ごしていると、実際に執筆へ着手する踏ん切りがつかないまま、時間だけが過ぎ去っていくというのは往々にしてあることです。
「いや、ギリギリに追い込まれた状態で締切効果を狙うべきだ!」
という考えもあることでしょうが、ご自身や家族の突然の事故や病気、転勤などで執筆が思うように進まないリスクもありますので、注意が必要です。
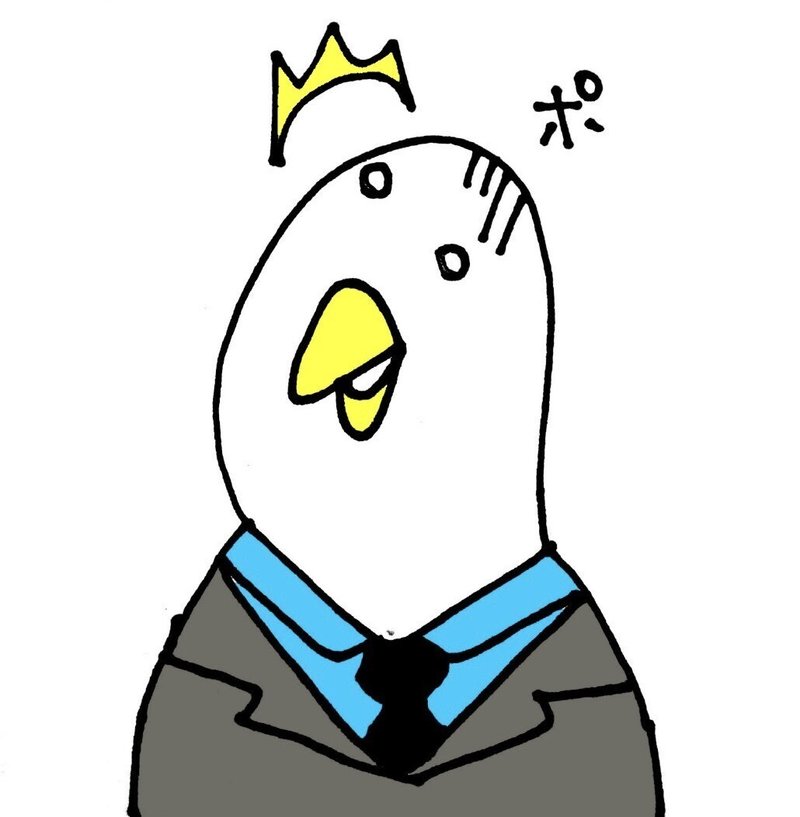
理由の2つ目は、「書きながら思いつくことがある」から。
ある程度の構成は事前に考えているものの、執筆をしているうちに新たに見えてくる視点・視座というのもあります。
事前に考えていた要素はとりあえず盛り込みつつ、新たな視点も入れ込んで行って、そうして最後に構成や紙幅を踏まえて内容をブラッシュアップする方が、より内容に厚みが出ると鳩は考えます。
そしてこれもまた、締切ギリギリで思いつこうものなら筆の入れようがありませんが、早めに手を動かしておけば柔軟に対応できます。

アカデミックの作法を守る
さて、執筆に際しては修士論文ですから「アカデミックの作法を守る」ことが求められます。
論文の執筆においては、剽窃をしないこともさることながら
「正しくパラフレーズする」
「引用の作法」
といったポイントがあります。
以下の2冊は修士論文を書く際の基本的な知識として役に立つでしょう。
どんなにいいことを書いていても、アカデミックのルールを守っていなければそれだけで「読むに値しない」と判断されても文句は言えません。
基本的な内容を押さえることで「ちゃんとした」論文を目指しましょう!

修士論文で悩んでいた人の特徴
以上、修士論文の執筆にあたってのポイントを書き並べてみました。
一方、筆が進まない生徒たちにも、共通する特徴があります。いくつか並べてみましょう。
①目の前のことに集中していない
明らかに進捗がまずいのに、ああだこうだと理由をつけて全く筆を動かさないタイプの人がいます。
とりあえず書き始めればいいのに、いつまで経っても情報収集をしていたり、なんならあえて遊びに行ったりしている人もいますが……。

……とりあえず、目の前の修士論文をいつまでに終了させるかを考えてスケジュールに沿った執筆をおススメします。
②言われたことをやらない
先生や学友に相談しておきながら、アドバイスされたことを実践せず、悩み続ける人がいます。
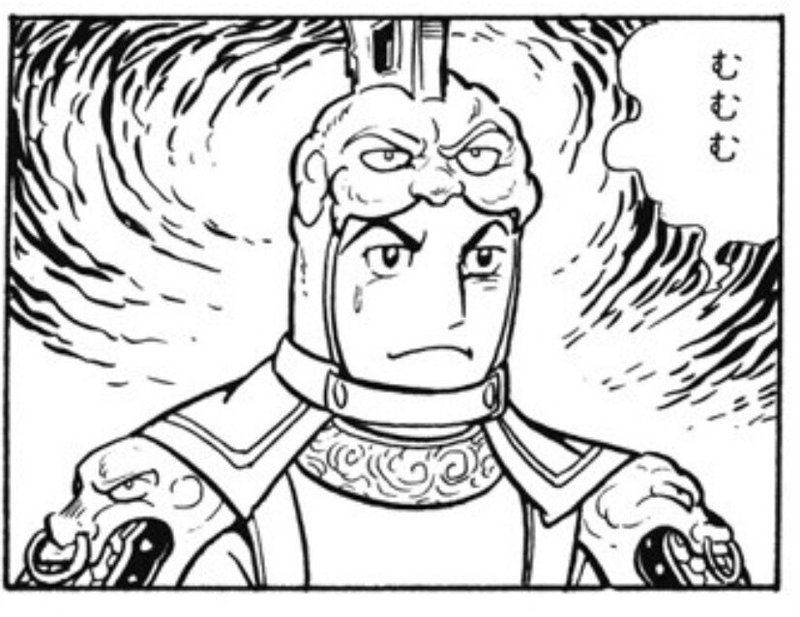
「どうも、自分にはしっくりこない」
「言われたアドバイスが正解かわからない」
という思いから「むむむ」となっているのでしょうが、
傍から見れば「なにがむむむだ!」と言いたくなります。

一人で考えても行きなずんでしまったから相談したにもかかわらず、人の話を聞かずに悩み続けるというのは、もはや「悩むのが趣味」と言えるのではないでしょうか。
とりあえず、アドバイスを通じて感じたことを頼りに筆を動かしてみる。
その執筆を通してしっくりこなかったときに初めて、再度悩めばよいのではないかなと鳩は思います。

というわけで以上、いろいろ書いてみましたが、
「とりあえず、行きなずんだら筆を動かしてみる」
というのが一番の答えではないでしょうか。
書くというのもなかなか難しく、興が乗るまでは手が重いというもの。
しかし人間はその作業を一度始めれば、だんだんと作業に没入して楽しくなってくる、という特性も持っています。
いま、論文が進んでいないという方がいらっしゃれば、とりあえず書いてみるというのが一番の良薬ではないでしょうか。
以上、修士論文に関するポイントでした。
次回、能ある鳩はMBA第29話「頼むからハイコンテクストにしてくれ」
お楽しみに。
to be continued...
参考資料
・挿入マンガ①③④⑥⑩:横山光輝『三国志』(潮出版社)
・挿入マンガ②:寺沢武一『コブラ』(集英社)
・挿入マンガ⑤⑦⑧⑨:島本和彦『吼えろペン』(小学館)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
