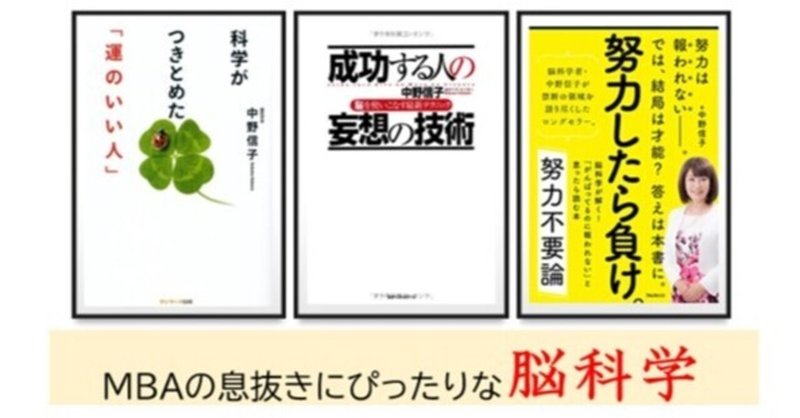
【ビジネススクール/MBA/体験記】第34話「成功する運のいい人は努力不要論」
こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!
前回の『能ある鳩はMBA』の記事はこちらです。↓↓↓
さて、前回は、
「インド神話と、ビジネススクール」
の関係について書きました。
今回は、
脳科学者・中野信子さんの著者と、ビジネススクール
についてまとめています。
1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!
『成功する人の妄想の技術』
脳科学者である中野信子さんは、
出版物も多く、テレビにも多くご出演していらっしゃるので、
お名前をご存じの方も多いかもしれません。
鳩も、ビジネススクールに入学してからも、ときおり著書を読み返しておりました。
さて、ある日、『成功する人の妄想の技術』を読んでいたときのこと。
本を読み進めているうちに、
「支配性」の高い人物は、リーダーになる傾向にある
というくだりに、目が留まります。
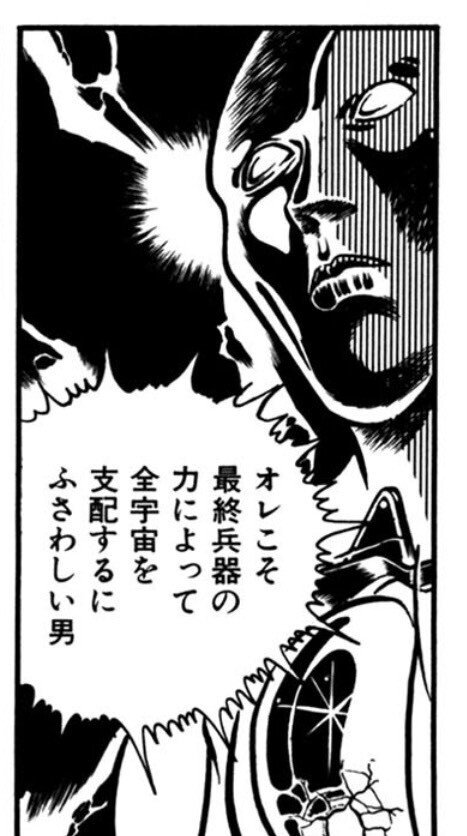
全宇宙を支配するぐらいの気概がないと、リーダーは務まらない、
ということでしょうか……気になります。
さらに読み進むと、同書には、
優秀な人がリーダーになるとは限らない
という驚きの記載がありました。
「数学の問題を複数人で解く」
というグループワークにおいて、
「誰がリーダーに選ばれるか?」
というテーマの実験が、同書では紹介されています。
すると、被験者も第三者も、同じ人物をリーダーに選びました。
しかし、ここで選ばれたリーダーたちは、
特に数学の能力がほかのメンバーより秀でているわけではなかったのです。
では、どのような基準で、彼らはリーダーとして選ばれたのでしょうか?
(中略)
とても単純なことなのですが、ビデオを見ると、
「支配性」の高い学生は、一番最初に発言していたのです。
さらに彼らは、
ほかの学生よりも強い調子、
確信に満ちた様子で話す傾向がありました。
つまり、この実験から、
「実力のある人がリーダーになる」のではなく、
「確信のある人がリーダーになる」ということがわかったのです。
この記載を見た鳩の脳裏には、瞬時に、
ビジネススクールでのグループワークの様子が浮かびました。
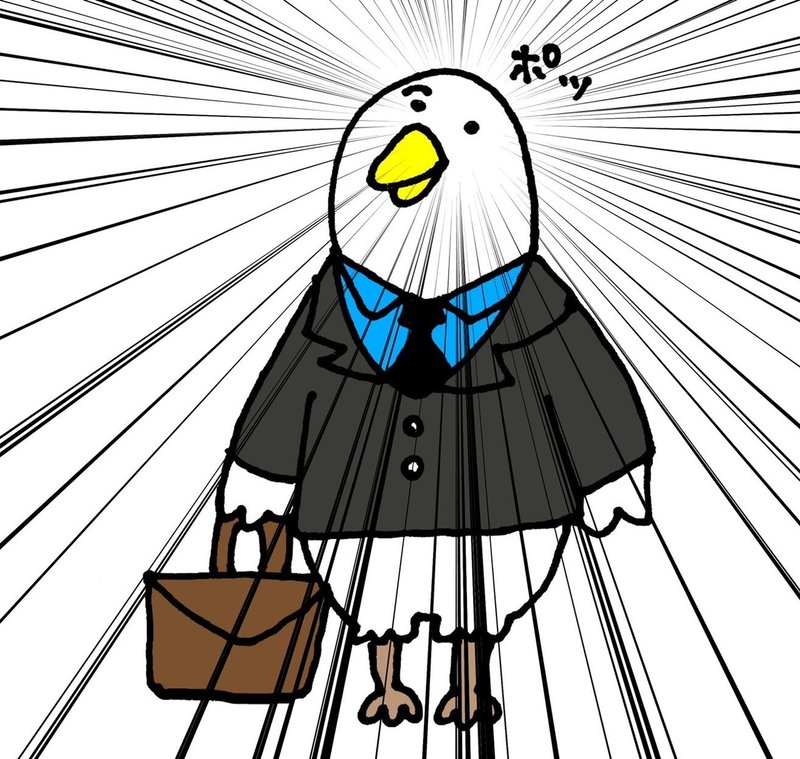
グループワークにおいて、全体を取りまとめるファシリテーター役を務めるのは気が引けるというもの。
しかし、だからこそ、鳩は積極的に、
「では、もしよければ、ファシリテーターをしてもよろしいでしょうか?」
と、最初に発言して、ファシリテーター役を引き取っていました。
ファシリテーターをしていると、
「何も考えていなくてもバレない」
というメリットを享受できるから、という後ろ向きな動機からのことでしたが、
「最初に発言して、まとめ役をする」
ということを繰り返しているうちに、
自然とリーダー役っぽい立ち回りの経験が増えました。
すると、入学直後に比べると、
無駄に自信をもって授業に臨めるようになった気がします。

『科学がつきとめた「運のいい人」』
本の内容が、現実でも再現性をもって確認できたことで、
「あ、これ、進研ゼミでやったヤツだ!」
状態となった鳩は、予習もそっちのけで、さらに次なる本を読み進めました。
次は、『科学がつきとめた「運のいい人」』です。
「自分は運がいい人間だ、と決め込んでしまう」
ことは、運をよくするコツのひとつだそうです。
実は、運がいいと思っている人も悪いと思っている人も、
遭遇している事象は似ている場合が多いのです。
しかしその事象に対するとらえ方、考え方が違う。
対処の方法も違う。
長い年月を積み重ねれば、おのずと結果は大きく変わってくるでしょう。
だからやはり、何の根拠も無くても
「自分は運がいい」
と決め込んでしまったほうがいいのです。
ビジネススクールには、いろいろな方々がいます。
単純に頭のいい生徒もいれば、
ある程度の役職に上り詰めるまでの経験をしてきた生徒もいます。
働きだして五年そこそこの鳩は、そんな人たちに囲まれていると、
授業中はいつも、まるで、
ジェットコースターの上で果し合いでもしているかのような気分でした。

授業に参加するのが、せいいっぱいって表情(かお)の鳩でも、
思い上がりじゃねェ……
俺が……ッッ 有利だ!!!
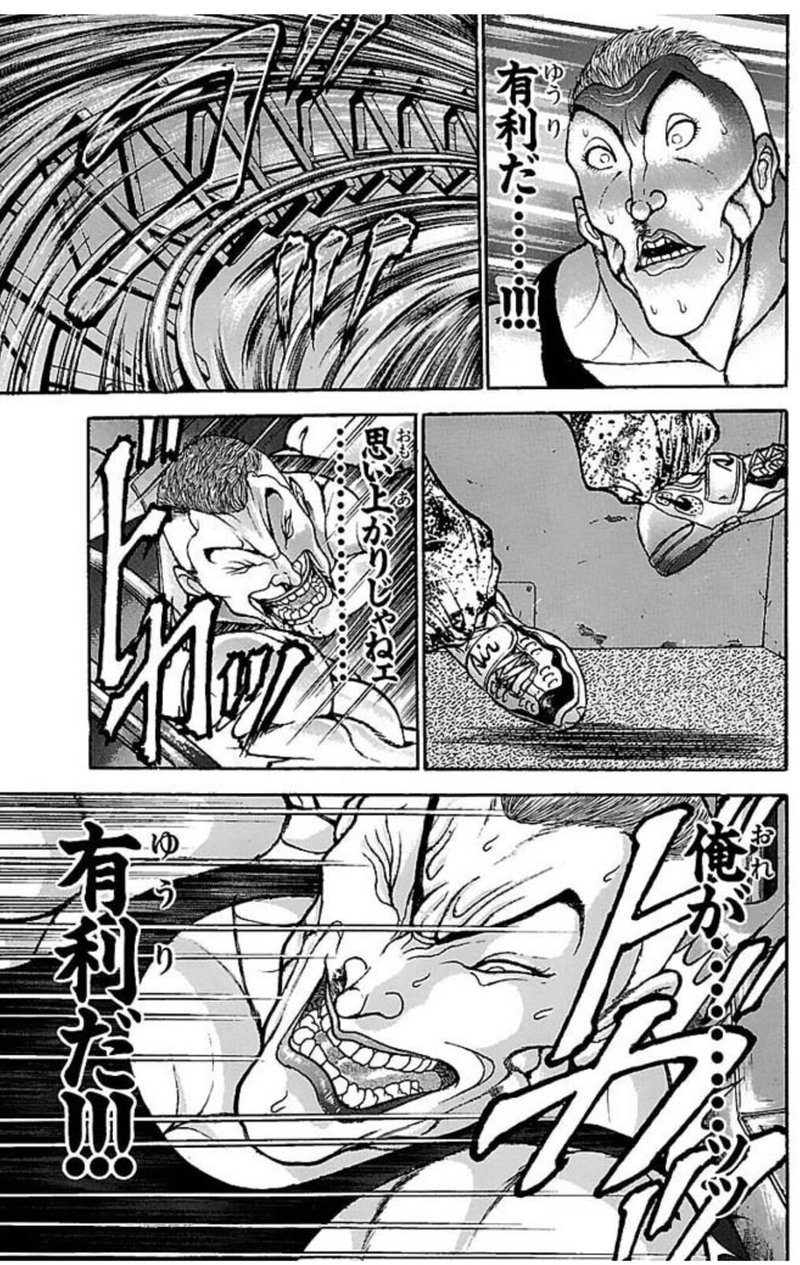
そう自分に言い聞かせながら授業に参加してみると、
不思議なことに、
本当に授業内容が自分に有利なような気がしてくるのです!
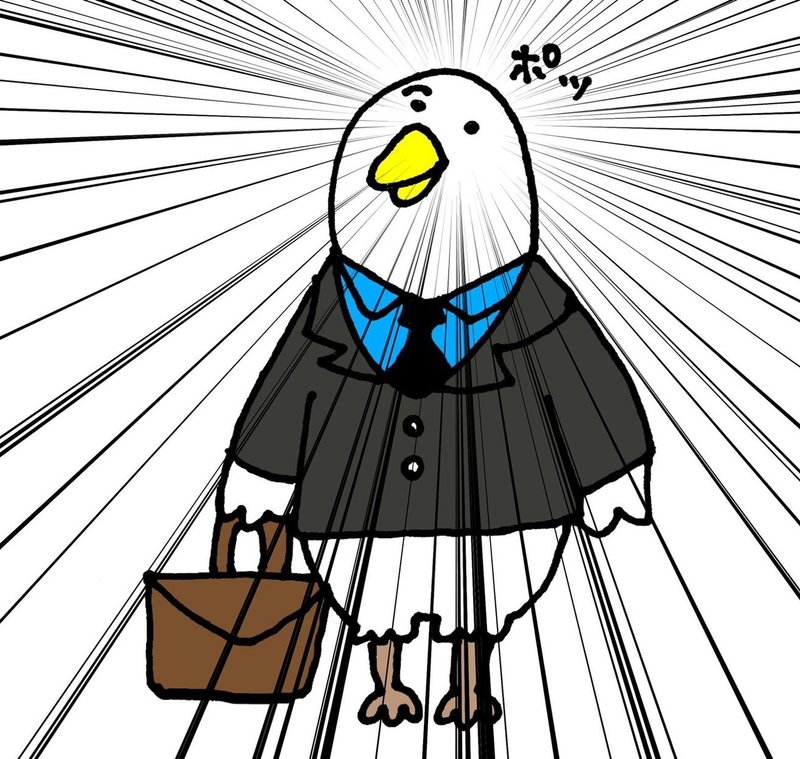
自信が出ると余裕が生まれ、
余裕が生まれると発現のクオリティが上がっていくのが、
自分でもわかりました。
みなさん、ビジネススクールには根拠のない自信で臨みましょう。
『努力不要論』
最後に、鳩を導いてくれた本は、
『努力不要論』です。
これまで、
「リーダーになるためには、まず発言しろ」だとか、
「自分は運がいいと思いこめ」といった、
前向きなメッセージが続いていたところに、
「努力したら負け」とはどういうことなのでしょうか。
同書の、
「役に立つことしかしない人間は家畜と同じ」
という衝撃的な表題の項では、
「役に立つかどうか」
「儲かるかどうか」
というモノサシだけで狙いを定めて努力をするのは、
「野蛮」だと切り捨てていました。

努力に中毒してしまっている人は、
いったんここは負けておこうとか、
いったん逃げておこうとか、
相手にも勝たせるけど自分も徳をしようとか、
冷静に考えることを本当に嫌がります。
なぜなら、自分の行動を美しくないように感じ、
得られる快感が減少してしまうからです。
自己犠牲的な振る舞いを他者に強要したり、
あるいは自分も寝てない自慢とか病んでる自慢をしたりという人も、
努力中毒の典型です。
会社だろうと、ビジネススクールだろうと、
「妙に高圧的だけど、深みを感じさせられない人間」
がいるのはなぜだろう、と鳩はいつも考えていました。
そんな鳩にとって、この文章は、
これまでの「ビジネススクール体験記」で、鳩が時折感じていた周囲への違和感が凝縮されています。
この手の人間に遭遇すると、
心の中のラインハルト様はいつも、
「俗物だな」とつぶやいていました。

要するに、一般的に努力というと、
多くの人が注目するのは野蛮な部分になるわけです。
すぐに結果が出るかどうかに目を向けてしまう。
(中略)
そもそも、役に立つネジになるための努力は誰にでもできます。
目的が明らかで戦略も多く示されているのですから、実行すればいいだけ。
すでにレシピがある料理を、そのとおりにつくればいいようなもので、簡単なことです。
本当に難しいのは、役に立たない部分をリッチにしようとする努力です。
この不景気に何を言っているのだ、と言う人は多いでしょう。
でも、そういう反論をしてしまうことこそが野蛮です。
役に立たないことができるのは、人間が高度な文化を持つ証だからです。
誰はいくら稼いでいるだとか、
誰がどのくらい出世するだとか、
そんな話だけに終始してしまう。
あるいは勉強や趣味にしても、
自分が楽しむためではなく、
他人に自慢するために努力している。
そういう人間と会話していると、
「努力している……だが、ただそれだけだ」
と感じてしまいます。

一方で、ビジネススクールに来ているのに、
飄々としていて、妙に奥ゆかしく、
それでいて成績も優秀だ、というタイプの人が時折います。
そういう人と話してみると、ビジネスの話も、趣味の話も、
奥行きがあるように感じられるなあと思う鳩でした。
さて、次回、次回、『能ある鳩はMBA』第35話
「鐘・鐘・鐘」
お楽しみに。
to be continued...
参考資料
・挿入マンガ①:寺沢武一『コブラ』(集英社)
・挿入マンガ②:島本和彦『吼えろペン』(小学館)
・挿入マンガ③④:板垣恵介『バキ』(秋田書店)
・挿入マンガ⑤⑥:田中芳樹(原作)藤崎竜(作画)『銀河英雄伝説』(集英社)」
・中野信子(2013)『科学がつきとめた「運のいい人」』 (サンマーク出版)
・中野信子(2013)『成功する人の妄想の技術』(ベストセラーズ)
・中野信子(2014)『努力不要論』(フォレスト出版)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
