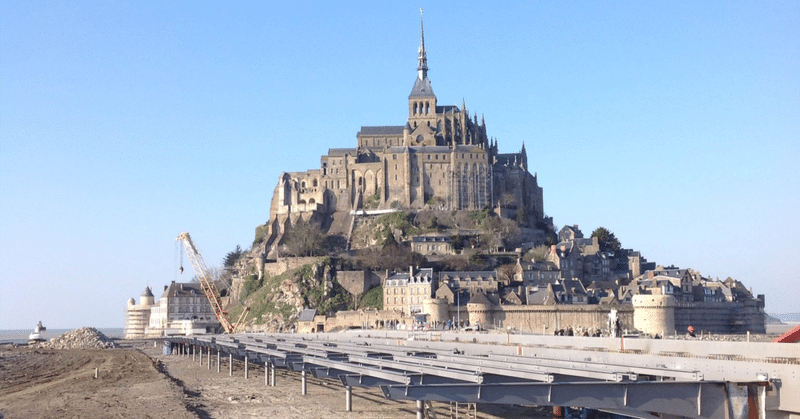
ルソーは教育学者ではない
本記事で扱う論文は以下のリンクから読むことができます。
画面右側にある「PDFをダウンロード」という赤い部分をクリックしてください。
さて、この企画も3回目になります。
原聡介、宮寺晃夫、と続きまして、今回は森田伸子論文を紹介します。
この森田論文もまたスリリングな内容なのです。それは、教育思想史研究とは「誤読」である、という命題に集約されます。この森田テーゼは以後、何回か言及されることになりますので、覚えておいてもいいかもしれません。
それと、森田氏が述べる「真の目的論」というのも大切です。
いずれにしても、原VS宮寺に割って入る森田氏の論考を読んでいきましょう。
森田は、まず「教育目的」についての学生の素朴な意見を取り上げるところから始める。
授業で扱うテクストには(執筆者は宮寺晃夫)、「戦前までの教育と比べて、戦後の教育状況を教育目的が曖昧で分かりにくくなっている状況」として記述してあるが、これは学生の実感とはかけ離れていることを指摘する。
つまり、現代にははっきりとした目標があるではないかと、そう学生たちは考えているのだ。
現代の教育の目標とは何か。
それは「学歴社会をより高く登って、より良い就職先を見つける」という目標である。このハッキリとした目標に対して、早々に諦めてしまう子どもたちがいかに多いかと、そのように現代の学生たちは状況を認識している。
この後に森田氏の拓跋な比喩が登場する。
以下に引用してみよう。
一流大学卒の資格や大企業の社員のポストを手に入れるというような目的は、馬の目の前にぶら下げられた人参のようなもので、目的とは呼べない。実際の目的は、その人参をぶら下げている見えない手こそが知っているのであって、その手の持ち主のことを「権力」と呼ぶ。この権力が馬たちを人参でつって連れて行こうおしているゴールこそが教育の目的の潜んでいる場所である。
これは現代の学校教育を説明した文章ではないか。
GIGAスクール構想によって導入されたパソコンを、「いかに子どもたちに使わせるか」ばかりに専心して、まんまと経済産業省が求める「ICT人材」を製造する学校教育は、政府の「御用教育」か「下請け教育」の様相を呈している。そして、そんな自分の姿を客観視さえできていない。
ここで、森田は教育目的を3つに分類する。
①私的な目的(保護者など)
②公的な目的(国家や企業)
上記、①と②を否定した、
③「真の」目的
かつての社会主義教育学は、この③に社会主義社会の建設を据えていたが、現代ではここに「子どもの内在的自然の開発」が入り込んでいる。
そして、原氏の問題意識を以下のように要約する。
氏は近代教育学の内在的目的論が、結局のところ、目的なき技術主義、あるいは目的設定を公的な誰かに委ねたままの下請けとしての教育学(御用教育学)に陥っている、として批判する。そしてその思想史的背景(と言うより責任)を、「近代教育思想」に遡って検証しようとする。
森田はここで、そもそも「目的のない教育や学習は存在するはずがない」と述べる。それは、武術を使わない世の中になっても武術がなくならないように、国語が整備されてラテン語を使う人がいなくなってもラテン語を学ぶことがなくならないように、それらの目的は常に「誰か」によって決めらていると述べる。その「誰か」とは、「教育に寄せる人々の私的な関心」だったり「「社会」と名づけるしかない歴史的に変容する公的な存在」との「無限に複雑な網の目状の組織」である。
そして、ここから森田は次なる関心へ議論を進める。
教育目的については、上記の目的3分類によれば、第三の項を考えざるを得ないことが、まさに教育学的言説であると述べる。
そして、森田の関心は、この「教育的言説」そのものであると。つまり、第一と第二の項(上記の目的を決める「誰か」)と第三の項(教育学的言説)とのズレを対象化していきたい。たとえ、その先に待っているのが「教育学的思惟そのものが解体し、そのがれきの前に立ちすくむ」ことになったとしても。
森田は、原論文における「教育可能性概念」における「不透明さ」を指摘する。この概念は「誰の属性」なのだろうか。そこから森田は原論文の叙述をもとに議論を再構成する。
「教育可能性」が子ども側の属性だとすれば、それはルソーの教育観と合致することになり、子どもの中の自然に従って助成していくことになる。これは、内在的目的論とも言えよう。
「教育可能性」が教師側の属性だとすれば、それは外在的目的論に容易に利用されることになる。教師が教育したいように子どもたちを育てることができるのであるのならば、それは「可能性」というよりは、粘土を捏ねて好きな形を作るようなイメージの「可塑性」の方が合っている。
この概念は、ロックのタブラ・ラサ(白紙論)からきているが、これは原も指摘している通り、デカルト的本有観念(元々、人間には観念が備わっている)を否定し、観念の起源を「学習による経験」とするための認識論状の方法概念であった。これ自体はルソーの文脈とは別であるはずだが、それが合わさることになる。
つまり、子どもに内在している無限の可能性を、教育を通して外在的に助成していくことになる。
さて、この内在的目的論について、その歴史的系譜を考えてみたい。
17世紀思想の特徴としては、精神と物質の二元論であった。精神という人間の理性は、物質の運動法則を捉えることができた。それは、力学的、数学的(物理学)な自然学の時代である。しかし、そこでの目的論は「神のみぞ知る」ということで、神学の領域にされた。実際、長い間、大学の筆頭学問は「神学」であったのだ。こうやって目的論を棚上げにできたからこそ、体系の精神が花開いたとも言える。ただ、精神と物質は全く別のものであり、その二つを繋ぐことに苦心していたとも言える。
それが、18世紀になると、物理学から生物学へ移行し、それぞれの生命の中に「自然」という世界を見出すようになる。つまり、二元論的世界観が「自然」という中に統一されて一元的世界観が作られることになる。この時に、神学の領域だった目的論も自然に取り込まれることになる。これがまさにルソーの「子ども観」である。だから、ルソーが述べる「自然」というのは、この18世紀的思想における自然であり、それは「無機物から生命あるもの、感覚的存在から英知あるもの、およそこの世界に存在する全てのものがそれぞれの位置にあって全体としての目的を実現する、そうしたより大きな目的論的自然と切り離すことのできない自然であって、決して実証的な意味での子どもの心理的特性といったものには還元されない自然なのだ」と森田は論駁する。
19世紀後半になると、公教育制度が始まり、それと同時に教育学が生まれた。それまでも「教育思想」はあったが、「教育学」はなかった。教育学は、教育を目的的に考察しようとする思惟形式を持つ。そうした目でルソーを見れば、彼は立派な「教育学者」である。
しかし、「子どもの自然」という言葉に、実証心理学的な発達概念を見つけるのは、近代の教育学者たちなのである。
これを森田は「誤読」であると論破する。
そして、森田は、近代教育思想から近代教育学への道筋を辿る、この「誤読」のあり方を解明することこそが求められると述べて、論を閉じる。
