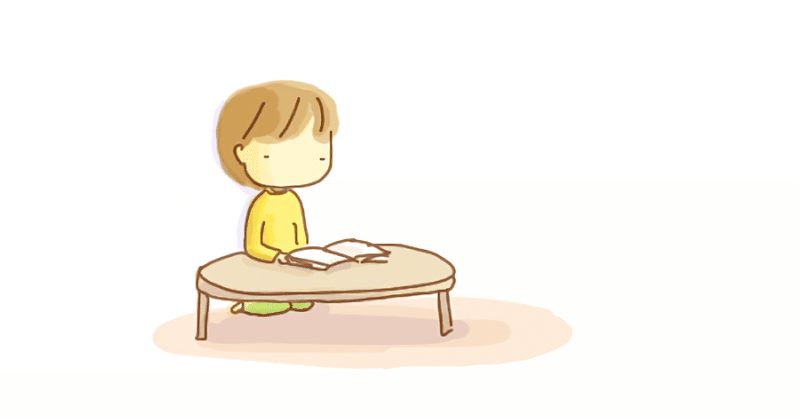
読書体験は「未来」を先取り?
僕自身は30歳も過ぎてから「読書」に目覚めた人なので、あまり偉そうには言えませんが、それでも読書について書いてみます。
僕は「活字」が苦手な人でした。大人になってからも同様で、漫画は読めるけど、活字だけの本は読めませんでした。
でも、「この世界のことを、もっと知りたい」と思えて、そのために「読書」を始めてみると、今でも「本が好き」であり続けています。隙間時間には「読書」をするので、小さなカバンには「お供の一冊」を必ず持ち歩いてます(今は、『日本辺境論』)。
どうして読書ができるのかを考えてみると、「世界を前よりも知れている自分」という「未来」を描けるからかなと考えています。
内田先生は「読書体験」について以下のようの述べています。
「読んでいる私」と「読み終えた私」は砂場で両側からトンネルを掘っている二人の子どものようなものです。掘り進めてゆくうちに、だんだん向こうからも掘り進む手が近づいてくるのがわかる。最後の薄い砂の壁が崩れると、手と手が触れあい、風が吹き通る。ああ、ついに出会えたという達成感がある。一冊の本を読み終えるというのは、そういうふうに「私が読み終えるのを待っていた私」ともう一度出会うことなんです。
これは秀逸な例え話ですね。
読書は「はじめ」から「終わり」までが直線のように流れる営みではないんです。まず「読み終えた自分」が想定されて、そこで得られる達成感をエネルギーにして「はじめ」から読む。
僕の読書方法は、「はじめに」を読んで、次に「目次」でざっと中身を確認して、「終わりに」を読む。そして、読み終わりに再度「終わりに」を読むと、「あぁ、これはこういう意味だったのか」となる。
「終わりに」をいきなり読んでも、意味は半分くらいなんです。でも、通読した後に読むと、はじめの「半分くらい」のモヤモヤが解ける。出会い直しですね。
読書体験というのは、そのように「順逆が狂った形で現象する」のです。
上記の例えのすぐ後に、内田先生は、今度は「ラーメンを食べる」ことに例えていますので、引用しますね。
ご飯を食べるのだってそうでしょう。真っ暗な部屋で、テーブルに置かれた大皿からラーメン啜って食べても、ぜんぜん美味しくない。あれは、あとどれくらい汁が残っているかとか、二枚目のチャーシューはそろそろ食べてもいいだろうとか、最後の一口を口中に投じるときの麺とメンマのバランスは頃合いであろうかという、全体のプログラムの中で腹具合を按分しながら食べるから美味しいのであって、あとどれくらい麺や汁やチャーシューが残っているか「わからない」まま真っ暗なところで食わされても美味しくもなんともない。
「全体のプログラム」という言葉通り、我々は読書体験を「そのページを読む自分」だけに分節できないのです。それは、あくまで「全体における、そのページ」なのです。さらに言えば、その本を読むだけにも文節できない。つまり、その本を読むことになった経緯も含めて、今、私はそのページを読んでいる。全体のプログラムを広く捉えられるほど、読書体験は豊かになる、そういうことなのかと思います。
