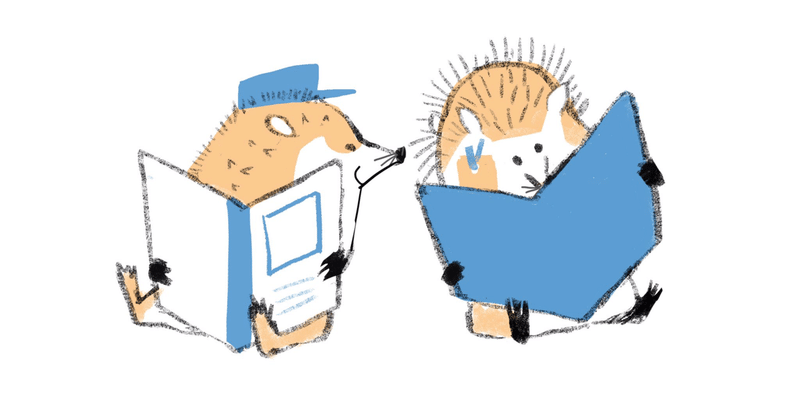
『ふつうの相談』(東畑開人)と精神科看護師のケア
話題になっていた東畑開人さんの『ふつうの相談』という本を読んだ。
ネタバレも避けたいし、要約をすることも難しいので、短い本だからぜひケアに携わる人には読んでほしい。
この本では、専門的な心理士による心理療法と、世間の人達が常々行っている原石のようなふつうの相談(この本で言うところのふつうの相談0)との接続性・関係性を立体的に描き出している。
様々なところで行われている「ふつうの相談」には、様々な「知」が参照され、ミックスされて用いられている。
世間の人達が行うふつうの相談の原型は、世間の常識的な感覚である「世間知」であり、心理療法家たちのふつうの相談の原型は、臨床心理学の様々な学派の理論や技法に沿った「学派知」であり、ここの臨床現場で多職種が行うふつうの相談の原型は、風土に合わせて脈々と蓄積されてきた「現場知」である。
さて、この記事ではこの本に描かれていないことについて述べたいと思う。
それは、精神科看護師による「ふつうの相談」には、往々にして「知」が参照されていない、ということである。
これは悪い意味ではない。そして、精神科看護の学問性を否定するものでもない。
精神科看護のユニークさの一つに、「知」を参照せず、看護師一人ひとりの「人柄」「キャラクター」そのままで患者とお喋りをするという点が挙げられると私は思っている。
この本に、次のようなシーンが出てくる。
青年がデイケアで「クマのような看護師」に「最近、またエロいことばかり考えてしまいます」と相談する。「クマのような看護師」は「そういうことを考えちゃう年頃だよな」「考えすぎないようにって言われても、難しいよな」と返し、最終的には「また小まめにどうなってるか教えてな、一緒に様子を見ていこう」と言い、共に卓球のラケットを運ぶ。
これは、「クマのような看護師」その人だからこそのユニークな返答であると思う。もちろん現場知が全く参照されていないかといえばそういうことはないが、人生の先輩として、そして青年を思いやる者として、お喋りをしている側面が大きいのではないだろうか。
そもそも、看護という学問は、学問としての独自性が曖昧である。
バイオ-サイコ-ソーシャルモデルが地にあるが、「バイオ」は「医学」よりも浅く、「サイコ」は「心理学」より浅く、「ソーシャル」は「社会福祉学」よりも浅い。
浅いがゆえに、看護師一人ひとりは「ただの一人の人間」として、学問の鎧をまとわずに裸で患者と対峙していかなくてはならない、そんな側面がある。
私はそういうところに看護の魅力を感じている。
精神科病棟に入院すると、病棟看護師それぞれに「人柄」があり、患者たちはその人の人柄に応じて話す内容を変え、「推し看護師」を作ったりなんかもする。
年の近いお兄さん看護師Aさんとは、もっぱら「楽しい話」をする。共通の趣味であるHIPHOPのどの曲が好きか、駅伝がいかにアツいか、どんな髪型にしたいか。
同い年の看護師Bさんとは、互いの悩みを打ち明け合う。Bさんの恋愛事情について聴いたり、将来の夢に向かっての試行錯誤を話したりする。
貫禄のあるベテラン看護師Cさんは、人生がどうあるべきか、パートナーシップとはどうあるべきか、を滔々と説いてくれる。ひたすら「過去を忘れて未来の楽しいことを作りなさい」と言われる。
お互いの似た生い立ちを打ち明けあった看護師Dさんは、「僕もこういうことあったなぁ」と私の昔話を聴きながら目に涙を浮かべる。
とにかく優しい看護師Eさんには、ひたすら甘えに行く。「パワーください!」というとギューッと握手してくれたり、「お守り」と言いながらナース服のポケットからいい香りのするハンドクリームを出して私の手に塗ってくれたりする。
これらの関係はひたすらに裸の付き合いでありながら、同時に友達との愚痴の言い合いとは異なった、「ケアの関係」「癒やしをもたらす関係」が保たれている、という特殊性がある。
精神科の看護師は、人柄と関係性に基づいた「自分なりのケア」を編み出して提供しているのだと思う。
精神科看護師は、学問の鎧をまといすぎない「生身の人間」であるからこその、癒やしの力を持っている。
記事を気に入ってくださった方、よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは今後の執筆活動に使わせていただきます。
