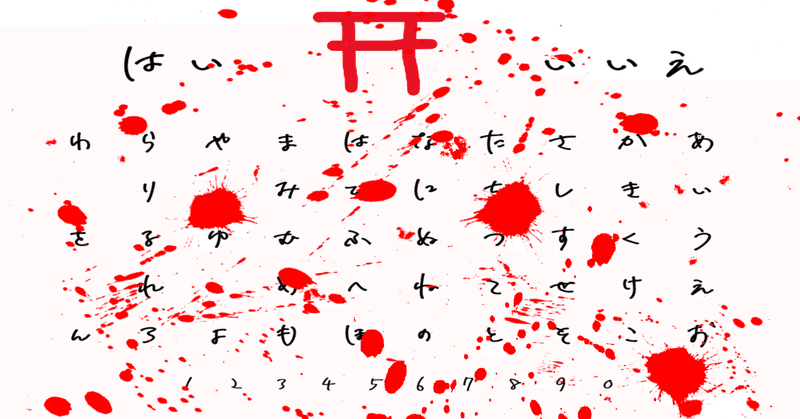
降霊の箱庭 ~第一話~
<前話>
まるで、白い城塞だ。
校舎を見てまず初めに浮かんだのは、そんな感想だった。
職員室は、四階建ての校舎の二階部分、ちょうど生徒玄関を見下ろす位置にあった。この中学校の校舎全体が城塞ならば、この職員室はさしずめ物見櫓といったところか。
学年主任とクラス担任に挨拶を済ませ、母親が帰っていった後。
「じゃあ、行こうか」
三十代くらいの女性担任に促され、職員室から教室に向かうことになった。
かすかに生徒たちのざわめきが聞こえてくる渡り廊下を、担任教師と並んで歩く。聞けば一年生の教室が一番上の四階で、学年が上がるごとに階が下がっていくのだという。
「一年生は頑張って階段を上れ、上級生を労われ、ってことでこんな階層なのかねぇ」
こちらの緊張をほぐそうとしているのか、冗談めかした口調で担任教師は言った。
一年五組の教室に辿り着く。
再び担任教師に促され、ぐっと覚悟を決めて教壇に上がる。
途端にクラスメイトたちの視線が品定めするように集まってきて、思わず身が竦んだ。
「紹介します。転校生の一並達季君です」
「は、初めまして。よろしくお願いします……!」
最初の「は」の音で自分の声の調子を確認してから、一気に言って頭を下げる。本当はもっと気の利いた自己紹介などできればよいのだが、今の達季にはこれが精一杯だった。
幸いにも拍手で迎えられ、指定された席に着く。担任教師の計らいだろうか、席は一番後ろの一番窓際、つまり最もこの教室を見渡せる場所だった。
「よろしく」
隣の席の男子生徒が、友好的に声を掛けてくる。
少し開いた窓から入ってくる五月の風が、頬を撫でる。
どうやら、自分は受け入れられたらしい。
まずまずの滑り出しに、達季はほんの少しだけ肩の力を抜いた。
ここF県は、言ってしまえば「田舎」である。
人口は多くない。娯楽施設も多くない。歴史は古く、時に日本の政治や文化に大きく関わる地となったのも確かだが、しかし県の広報担当のアピール下手のせいか、それがどうにも魅力として他の都道府県に伝わっていないような気がする。
最近は新幹線を延伸して引き入れようという機運が高まっているが……さていざ誘致したところで、一体どれほどの効果があるのか、当の県民たちが疑っている節があった。
松原市はそのF県の中で、二番目の規模を誇る。
日本海側の貿易の玄関口として、それなりに栄えている。今は稼働停止しているが、原子力発電所があるのも大きいだろう。実際、隣の神浜町から引っ越してきた達季は、駅前の賑わいや学校の大きさに驚かされたものだ。
「三十六人か……名前、覚え切れるかな」
担任教師からもらったクラス名簿を見ながら、達季は口の中で小さく呟く。
松原市内に存在する六つの中学校(一つは私立、もう一つは小中統合校だが)のうち、達季が転校することになったのは、その中で最も大人数の生徒がいる米野中学校だった。
生徒総数、七百名。一年生だけで六クラスあり、これでも例年より少ない年度なのだという。
父親が元から松原市で働いていたのと、年度始めにのっぴきならない事情が重なったのとで、ゴールデンウィーク明けという何とも中途半端な時期に転校する羽目になった。
上手くやっていかねば。
改めてそう心に誓い、ぐるりと教室を見回した達季は……とある席に置かれた物に気付き、ギョッとした。
先程の挨拶の時は、緊張しすぎて気に留める余裕もなかったのだろう。だがいざ気付いてしまえば、なぜ先程気付かなかったのかと自分の目を疑うくらい、その席は異様な雰囲気を放っていた。
席主のいない席。
その机の上に。
花瓶に活けられた、白菊の花が。
――!
慌てて手元のクラス名簿と照らし合わせる。
席主の名は「市川奈々絵」となっていた。
「あ……あの、」
担任教師が朝の連絡事項を伝えている中、達季はこっそりと、右隣の男子生徒に声を掛けた。
「あそこの席、何があったんですか?」
ん? と笑顔で応えた男子生徒は、しかし達季の目線の先の物を察知し、途端に表情を曇らせた。
「ああ……つい最近、ね」
慎重に、言葉を選んでいる様子で。
「ちょっと色々あって……亡くなったんだ」
ぞわっ、と。
決して寒い気温でないにも関わらず、鳥肌が立った。
彼の声の響きで分かった。
「市川」という女子生徒の亡くなり方が、単なる病気や事故ではなさそうなことが。
「…………」
達季は、平穏が好きだ。
平和に平穏に平凡に生きていきたいと、常々思っている。
転校初日という一大イベントがあった時点で、今日はもう平穏ではない。そのうえ、いざ入ったクラスの席の上に献花があったとなっては、心が乱れるのも仕方なかった。
――落ち着け。
自分に言い聞かせる。
そして必要以上に熱心に、担任教師の話に耳を傾けた。
時間割は進んでいった。
幸いにも、前の学校と同じ教科書を使う学習がほとんどで、勉強面に不安はなかった。
「先生から案内役、任されてるからさ。俺に何でも訊いてよ」
おまけに隣席の間宮颯志という男子生徒は、とにかく爽やかで親切だった。達季だけではなく、誰にでも分け隔てなく嫌味なく接するので、その彼の隣にいると、達季も自然とクラスメイトとの交流が進んだ。
たまにいるのだ。こういう、男子からも女子からも好かれる生徒が。
羨ましくはあるが、自分がそれを見習えるとは思えない。こういうのは向き不向きがあるのだ。ただ波風立てない人間関係が築けるなら、達季にはそれで充分だった。
昼休み。給食を食べ終え、クラスメイトからの質問攻めもようやく落ち着いた頃、達季はふと廊下に出た。
この四階全体の空気を何となく見ておくためだ。
「わぁ……改めてやっぱり、大きな学校だ」
廊下の東側突き当たりの壁の前に立つ。右手にはグラウンドに面した窓が、左手には一年生の教室が並ぶ。ちょうど二組と三組の間に、トイレと階段がある構造である。
達季は歩き出した。
順番に、並んだ教室を眺めながら。
ぱた、ぱた、と、学校指定の上履きの音を鳴らしながら。
五組を、四組を、通り過ぎる。
ぱた、ぱた。
三組の横を通り過ぎる。
階段を、トイレを、通り過ぎる。
ぱた、ぱた。
二組の横を通り過ぎる。
そして一組に差し掛かる。
ぱた……ぱたり。
その歩みがふと、止まった。
目線は、西側の一番端の教室に向いていた。
そこは空き教室らしかった。人の気配が全くなく、教室入口に「〇年〇組」というプレートも掛かっていない。
それは別にいいのだ。空き教室くらい、全国どこの学校にもある。
達季が注目したのはそこではなく、その空き教室の入口に張り巡らされた、無数のテープだった。
立入禁止と書かれた黄色いテープが。
無数に、縦横無尽に、ヒステリックに、教室の前と後ろの入口を封鎖するように貼られていた。
「……何だ、あれ」
興味が湧くのは当然だった。
一組のさらに奥にあるその空き教室に向けて、達季は一歩踏み出した。
ぱた、と再び鳴る靴音。
ずず、とその一歩分だけ教室が近付く。
ぱた、ぱた。
ずず、ずず。
いつの間にか、周囲から音が消えていた。
いや実際に消えたのではない。ただ妙にその教室に意識が引き寄せられて、達季の耳に、外界の音が届かなくなっただけである。
ぱた、ぱた。
ずず、ずず。
近付く。
近付いていく。
そしてとうとう、空き教室に差し掛かる。
ぱたっ。
ずずっ。
足を止めた。
教室の中は窺い知れなかった。廊下に面した教室の窓には、曇りガラスがはめられているからだ。
しかし入口扉の窓だけは、普通の透明ガラスになっている。
黄色いテープとテープの隙間、少しだけ見える窓が。
「…………」
空気が冷えていた。
ここだけ、まるで冬のようだった。
「…………」
気になる。
この空き教室の中が、とても気になる。
「…………」
この中を見たい。
いや、見なければ。
「…………」
最後の一歩、教室に近付く。
そしてテープの合わせ目に指を掛け、窓から中を覗こうとした時だった。
「何をしているッ!!」
雷鳴のような声が響き、達季は文字通り飛び上がった。
途端に周囲の音が戻ってきた。空気も、先程まで感じていた冷たさはどこへやら、五月の暖かなものが満ちていた。
バックンバックンと心臓が鳴っている。
今まさにテープに伸ばそうとしていた指を引っ込める。
動転していた。こんなことをしでかすなんて、普段の自分では考えられないことだ。操られるか導かれるかしていた、としか思えない愚行だった。
「そこから離れなさい!」
達季の意識を引き戻したのは、「生徒指導部」と書かれた名札を首から下げた、五十代くらいの男性教師だった。
「ん? 見慣れない顔だな……ああ、転校生か」
まさに憤怒の形相になっていた教師だが、しかし達季の顔を見ると、ほんの少しだけ表情を和らげた。
「急に怒鳴って悪かった」
「いえ、あの、その……僕こそ、すみませんでした」
未だに落ち着かない心臓。自分の不可解な行動に対する動揺と罪悪感、怒鳴られた恐怖から、達季は男性教師の顔をまともに見ることができなかった。
「ここでは先日、事故があったんだ」
「…………」
「だからこうして、教員が交代で見回っている。転校初日だから大目に見るが、今後は不用意なイタズラなどしないように。いいな?」
別にイタズラのつもりはなかったが、反論する勇気もまたなかった。
達季への注意を終えると、男性教師は去っていった。
呆然。しかし教師の声を聞いた何人もの生徒たちが、その怒鳴られた当事者である自分を見ていることに気付いた瞬間……達季は顔から火が出るほど恥ずかしくなって、急いで男子トイレに駆け込んだのだった。
<次話>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

