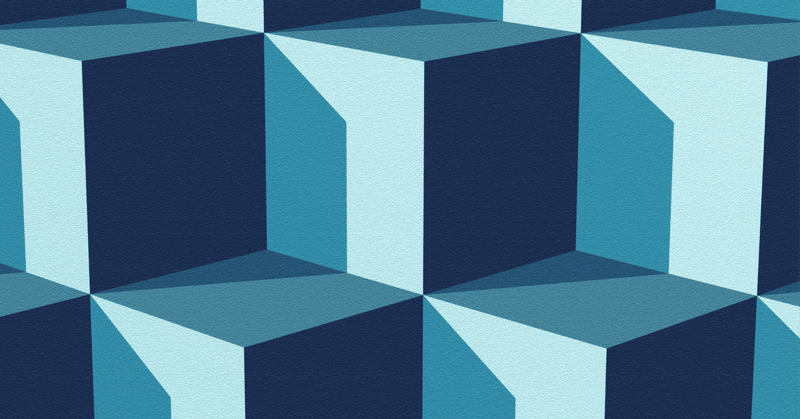
ひっこし先ではじめて読む本
引っ越し先で最初に手に取った本は、志村ふくみの『色を奏でる』だった。志村ふくみ、染織家。着物の色を染める人。この本は贈り物としていただいたもので、くれたのはバレエの先生だった。
同じ芸術家同士、通じるものがあるのかもしれない。先生はこの人の本が好きで、自分で持っていたのをわたしにくれた。15歳のときだった。本の最後のページには、いつも先生が使っている青のペンで「メルシーちゃん、15歳の誕生日おめでとう」と書かれている。
あれから軽く10年は経っている。15歳。世間的にはティーンエイジャー真っ盛りの、人によって女性の一番美しい時期らしいが、自分としては思い出したくない一年だった。嫌いな担任の先生、自分の不調、性悪なクラスメート。
16になる前に実家を離れて、ぜんぜん知らない都市で寮生活を始めた。地元が田舎だったせいで、いきなりの都会はメンタルに悪かった。毎日気が狂いそうだった。髪型を変えて、爆発したマリリン・モンローみたいになった。それがぜんぶ15の時の話。
そうか、先生が本をくれてたんだっけ……。「15歳の誕生日おめでとう」と、まるで昨日書かれたみたいに鮮やかなインクの色を見る。当時の日々がそのまま記録されているみたいな本のたたずまいに、久しぶりに中身を読む気になった。
着物を染める人の、色との共同生活。植物から布を染め上げることへの、静かな情熱。
ジャコメッティは「すべての色の基調は灰色(グレー)だ。パリが好きなのもその灰色のためだし、人生そのものが灰色ではないか」といった。それにたいし宇佐美英治さんは、「人生はもともと灰色ではあるけれど、三日のうち二日が灰色で、一日が薔薇色に感じられたら、それは最良の日ではないだろうか」と答えたと言う。
その一日の薔薇色は灰色の磨りガラスをとおして見える薔薇色ではないだろうかと、そう思ったのは私である。
昨日、結婚生活を始めたアパートの、私の部屋にも磨りガラスがはまっている。こういうガラスを通して見ると、外はどこもぼやけて見えて、ぼやけているからきれいに見える。少しぼんやりとしているくらいのほうが、世界は美しい。これは自分でそう思うのか、誰かがそう言っていたのか知らない。
人生そのものが灰色だ。そうかもしれない。単調で退屈な色。火が燃えたあとの残りかす、タバコをもみ消したときの色。もう火がついていない、情熱の抜け殻。
でもそうなってからじゃないとわからないことって、たくさんあるんじゃないか。20代で知れたようなこと言うじゃんと言われそうだけど、いまの私は過去の私と比べて年老いている。年齢が1桁のころのような、爆発的な成長も、若さあふれる10代の日々ももうない。
働くようになって結婚して、身体の成長はとっくの昔に止まっていて、なにもしなくても自分が伸びていくわけじゃないのをわかっている。灰色がどんな色か、わかるようになってからが人生だ。案外ジャコメッティが言いたいのはそういうことかもしれない。
それでいて、たった一日、磨りガラスの向こうの風景がきれいに思えたら、それは自分が思う以上の「よい日」なのだ。薔薇の色はどぎつく赤いけれど、人々がバラ色というときに思い浮かべるのは幸せなピンクで、ピンクと灰色の相性はいい。
単調な毎日の中にたったひとつ美しいことがあったら、それで十分じゃないかね?
このページは、そう言っているように見える。でもこのセリフに心底納得できるようになるには、自分はまだ若すぎる。たったひとつしか美しいことのない人生や毎日は嫌だ、とどこかでまだあがいていて、あがけるだけの元気がある。諦めがつかない。よくも悪くも。まだ灰色を知りたくない悪あがき。
英語版もあるよ
本を買ったり、勉強したりするのに使っています。最近、買ったのはフーコー『言葉と物』(仏語版)。
