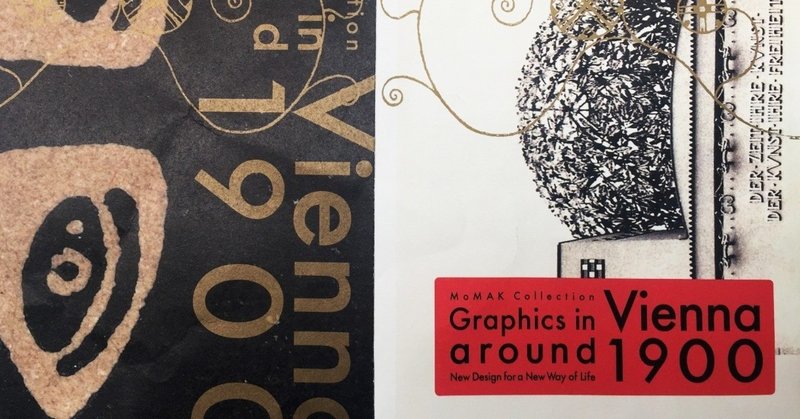
コロタイプ印刷と、デジタルが持ちえないアウラ
先週末、京都国立近代美術館で開催中の『世紀末ウィーンのグラフィック デザインそして生活の刷新にむけて』という展示に行ってきました。
1897年の分離派結成から1914年の第一次世界大戦勃発までのウィーンでは、グスタフ・クリムトやヨーゼフ・ホフマンらを中心に、新しい時代にふさわしい芸術そしてデザインのあり方が模索され、数多くの素晴らしい成果が生まれました。中でもグラフィックの分野は、印刷技術の発達や雑誌メディアの隆盛を背景に、新しい芸術の動向を人々に伝え、社会に浸透させる重要な役割を担いました。
ウィーン分離派や、当時のオーストリア周辺の時代背景、美術史的なことについて、僕は全く無知なので詳しい方に譲るとして、ここでは印刷技術という観点で僕が見て、そして驚嘆した事柄について書いてみたいと思います。
約百年前の、高度に完成された印刷技術を目の当たりにした。
と言うと、この企画展示が当時の高度な印刷技術を辿る主旨のものと誤解されそうなので一応補足しておくと、展示物の内訳はだいたいこんな感じでした。だいたいです。
複製技術で作られたものでないもの(技法は様々):22%
印刷物(カラーリトグラフ):35%
印刷物(木版多色刷り):30%
印刷物(ステロ版などその他の技法):10%
印刷物(コロタイプ):3%
印刷技術に関して言うと、カラーリトグラフの美しさも相当なものでしたが、技術の高度さとはむしろ真逆の、技法としては当時(1900年前後)としても一時代前のものである木版刷りが多かったのが印象的でした。
写真技術やその複製技術が発達していく時代にあって、最新のテクノロジーから敢えて距離を取っているように感じました。
時代的にはこれより20年ほど前のイギリスのアーツアンドクラフツ運動とか、20年ほど後の日本の民藝運動なんかみたいな。
そんな展示の中で僕が衝撃を受けたのは、展示の点数にして数点にも満たなかったコロタイプで刷られた作品。
それは、1903年と1904年に刷られたクリムトの作品でした。
原画と並べて展示してあった訳ではないので、例えば色の再現性がどれほど高かったのかは知る由もありませんが、原画かと見紛う程のディテール表現と色彩の量感があって、そこには複製品とは思えないモノとしての一回性のようなものーアウラが、確かにありました。
さて、このコロタイプという印刷技術。
美術印刷に適した技法で、現在もその技術を残しているのは、日本では京都の便利堂のみ(実際は世界で唯一というのが正確らしい)...という程度の情報は以前から知っていたものの、恥ずかしながら印刷された現物を見たことがなかったし、その手法についても詳しくは知りませんでした。
コロタイプ印刷とは
「とは」とか言って語れるような身分ではないので、あくまで書籍などから拾った知識で少し紹介するにとどめますが、僕がコロタイプの何にそれ程感銘を受けたのか、何故レプリカの絵画にアウラを感じたのかだけは伝わるように書いてみようと思います。
コロタイプの仕組みや工程については、こちらの本を参照しました。
コロタイプは1855年にフランスで発明され、1876年にドイツで実用化されました。
ゼラチンを塗ったガラス板を版として、露光した部分だけが硬化して水をはじくようになる性質を生かして階調を表現する印刷技法です。(とか分かったような口ぶりですが、本見ながら書いてますからね)
日本でも昭和の前半くらいまではモノクロ印刷の技法として一般的で、数千単位の大ロット印刷には向かないため、印刷部数が千部以内にとどまる卒業アルバム用としては昭和40年代頃までは現役だったのが、大量生産を行う上でオフセット印刷の利便性に敵わず廃れていったといいます。
この印刷技法の最大の特徴は階調の連続性です。
というか僕が感動したポイントは間違いなくここにあります。
階調が連続していることの何がそんなに特殊なのか、それを知ってもらうためには、まず現在カラー印刷の技術として最もポピュラーであるオフセット印刷について説明しなければなりません。
これについては、以前にもちらっと書いたことがあります。
こちらから一部引用すると…
アナログ製版から製版工程がほぼ全てデジタル化された現在のDTPに移行しても変わらないオフセットカラー印刷の原理は、光(RGB)を記録した連続した階調を持つ画像を、インキで物理的に再現できるCMYKの4色に分解して、且つ網点という0か1かの二値的な点の集合データに変換した上で重ね合わせ、擬似的に色再現するというもの。重ね合わせるといっても、CMYのインキを本当に重ねてしまうと色は濁っていくばかりなので、人間の目の解像度を騙せるレベルの小さな点を完全に重ならない程度に配列させて色を見せています。この4色分解と網点生成という工程によって、元画像と印刷物には決定的で不可逆的な断絶が生まれます。つまり、どれだけうまく色再現されたように見えていても、印刷物としてアウトプットされたものは全て、元々の画像とは全く別の原理で作られた点の集合でしかありません。
オフセット印刷が発明されたのは1904年。
ちょうど僕が美術館で見たクリムトの作品が刷られた年です。
コロタイプの発明は1855年なので、約半世紀の開きがあります。
この半世紀の時間の中に、印刷技術におけるアナログ(連続した情報)とデジタル(離散的な情報)の境界が引かれています。
オフセット印刷に限らず、シルクスクリーン印刷でもグラビア印刷(※1)でもインクジェットやレーザープリンタでも、CMYK(+α)でカラー表現する全ての印刷手法は、基本的には上に引用した中でも書いた通り、各色の版を0と1の二値(二階調)に置き換えるという原理では共通しています。(その0と1をどれくらい細かいサイズで配列出来るかなどによって各印刷技法の階調表現の豊かさが異なってくる訳ですが)
0と1。
オフセット印刷が発明された時点では、もちろんコンピュータなんて世の中に存在しなかった訳ですが、階調という連続量を0と1に置き換えることで再現性を高めようという発想からスタートしている時点で、オフセット印刷は生まれながらにしてデジタルな存在だったと言えそうです。
対してコロタイプは、版面の細かなしわに付着したインキ量の多寡によって階調を表現するため、階調は連続しています。
それから色の再現方法も異なります。CMYKの透明インキを完全に重ならないように配列するオフセット印刷などの手法とは違い、コロタイプでは不透明なインキを薄い色から順に塗り重ねていきます。
CMYKをベースにしつつ、それを更に細かく分版し、原画の再現に必要な色は製版技師が全て別々の版に焼き分けるんだそうです。
インキも特殊で、顔料の配合率90%以上(!)と圧倒的に高いそう。(オフセットのインキでは20~30%程度)
僕が見たクリムトの絵が何色刷りだったかは分かりません。
至近距離で目を凝らしてみても、実際に描かれた絵画のようにしか見えなかったのは、階調の連続性もさることながら、顔料の含有量が多いことも影響していたのかもしれません。
※1 グラビア印刷には、コロタイプと同じくインキ量の多寡で階調表現をするコンベンショナル法と、オフセットと同じく網点を使う網グラビア法があります。僕は仕事で使ったことがないのでこの辺あまり詳しくないです…
なんだかんだ言ってにわか知識の僕があれこれ書くよりも、本家便利堂さんの画像付きで説明されたブログを見てもらうのが良いかと思います。
↓短くコロタイプを紹介したこちらの動画も。
あのアウラはなんだったんだろう?
最初に展示の比率を書いた通り、今回の展覧会では複製技術を用いたものでない水彩や油絵、鉛筆画などの作品も並んでいて、本来は当然そちらの方にこそアウラが宿るはずです。
にも関わらず、クリムトのレプリカに最もアウラを感じたのは何故か?
もしかしたらこれは、ただの職業病なのかもしれません。
印刷物と聞くと、職業柄、網点がどうなってるかとか何色刷りかとかに注目して観察するので、まず導入の時点で興味の度合いが違います。
なのに、いくら仔細に見ても複製技術であることの取っ掛かりを与えてくれない。まずはそんな存在の揺るがなさに圧倒されました。
そして、百年という時間を直線的に捉えて、技術は進化し続けているという無批判な思い込み。それが打ち砕かれた衝撃がありました。
僕はそれを、恐らく誤用ではありますがアウラと呼んだ訳ですが、そうした印象の背後にあるものが何かを考えていくと、上述の通りアナログとデジタルの対比というところに収斂していきました。
すると思い出したのが、現在写真展も開催されている(関西でもやってくんないかなぁ…)落合陽一氏の「質量への憧憬」という表現。
我々が今ブラウン管にみる質量性は液晶やLEDや有機ELの時代から見た価値観に基づいている.テクノロジーは変わる.メディアアートの時代性は時代によってそのテクノロジーの風化を伴うエイジングをする.しかしデジタルデータはどうだろうか.もちろん処理能力が上がればより高精細に見えるようなアルゴリズムもあるかもしれない.しかし解像度の足らない画像データから見えるのはノスタルジアだろうか,それともエイジングだろうか.
僕は、液晶やLEDや有機ELの時代にあって、オフセット印刷は完全に「枯れた技術」だと思いながら自分が仕事を通して生み出してきたものに向き合ってきました。
ところが、今回の百年前のコロタイプとの出会いから得た視座は、過去から見返してもそれは「枯れていた」ということです。
僕はその要因に「紙やインキというアナログなマテリアルでありつつ、そこに載っている情報はデジタルに処理されている」という中途半端さにあるという気がしています。
ちょうど、音楽のデジタル配信とアナログレコードに挟まれたCD(プラスチック盤にデジタルデータが収まっている)のような存在というと分かりやすいかもしれません。
現在普及している技術よりもむしろ優れていた過去の技術に触れることで、この「枯れた技術」の「水平思考」(©横井軍平)のさせ方を深く考察していければと考えています。
ところで、便利堂さんに知り合いはいないのですが、実は声を掛けようと思えば掛けれるくらいの距離にはいるので、早速コンタクトを取ってみようと考えています。
それから、今週末には京都国立博物館でこんなトークセッションがあるようなので、これにも行ってみようと思います。
レクチャー「グラフィック表現の背後にあるもの―世紀末の印刷―(仮)」日時:2月2日(土)午後2時~3時30分
講師:寺本美奈子(グラフィックデザイン・キュレーター/武蔵野美術大学非常勤講師)
会場:京都国立近代美術館 1階講堂
定員:先着100名(当日午前11時より1階受付にて整理券を配布します。整理券はひとり1枚のみお渡しします)
参加費:無料
多分noteを書いていなかったら、クリムトの絵にどれ程感銘を受けていたとしても、便利堂さんにコンタクトを取ったりトークセッションに出掛けたりという行動までは起こさなかった気がします。
書いたことに対する責任が、行動を促します。
※2月8日追記
この記事を書いた後、上述のレクチャーを聴きにもう一度同展示会を見て回ったのですが、最初に行った時はコロタイプの衝撃があまりにも大きすぎて、他の展示の評価が自分の中で不当に低くなってしまっていたことに気付きました。特にカラーリトグラフはコロタイプと同じく階調の連続性においても素晴らしい再現性を持ち、発色も鮮やか。
記事がnoteのおすすめ入りして思いの外多くの方に読んでいただけたようなので、そんな主観に引っ張られたせいで大きな事実誤認があった冒頭の展示内容の比率を書いた箇所を訂正しておきました。
どうもありがとうございます。 また寄ってってください。 ごきげんよう。
