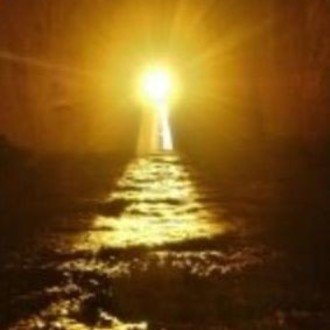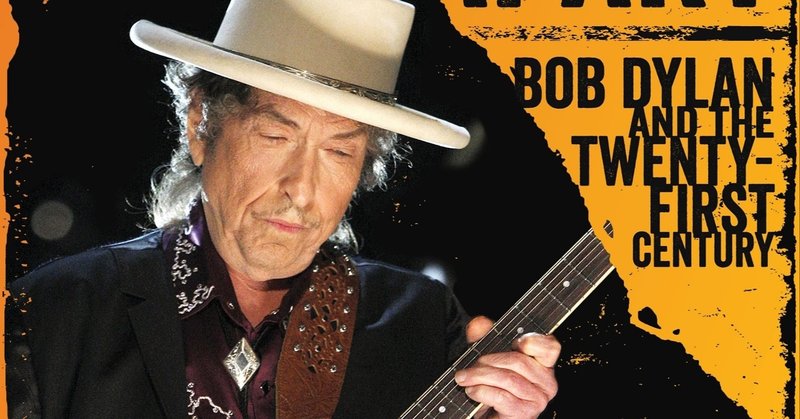
[英詩]ディランとシェークスピア(7)
※ 旧「英詩が読めるようになるマガジン」(2016年3月1日—2022年11月30日)の記事の避難先マガジンです。リンク先は順次修正してゆきます。
「英詩のマガジン」の主配信の10月の1回目です(英詩の基礎知識の回)。
本マガジンは英詩の実践的な読みのコツを考えるものですが、毎月3回の主配信のうち、第1回は英詩の基礎知識を取上げています。
これまで、英詩の基礎知識として、伝統歌の基礎知識、Bob Dylan の基礎知識、バラッドの基礎知識、ブルーズの基礎知識、詩形の基礎知識などを扱ってきました(リンク集は こちら )。
また、詩の文法を実践的に考える例として、「ディランの文法」と題して、ボブ・ディランの作品を連続して扱いました。(リンク集は こちら )
ボブ・ディランが天才と審美眼を調和させた初の作品として 'John Wesley Harding' をアルバムとして考えました(4回)。(1), (2), (3), (4).
*
6回前から Andrew Muir, 'Bob Dylan & William Shakespeare: The True Perfoming of It' (Red Planet Books, 2019) をベースにして、ボブ・ディランとシェークスピアについて考えています。
6回前は、シェークスピアでもディランでも使われる 'kill me dead' の句について主に考えました。
5回前から3回前まで、ディランの8年ぶりの新曲 'Murder Most Foul' を扱いました。シェークスピアの悲劇『ハムレット』1幕5場から引用されたタイトルです。
5回前は タイトルと韻律と 1. と 2. (1-54行) を、4回前は 3. (55-92行)を、3回前は 4. (93-164行) を考えました。
*
前々回はダニエル (Anne Margaret Daniel) の論文 'Tempest, Bob Dylan, and the Bardic Arts' ('Tearing the World Apart: Bob Dylan and the Twenty-First Century', eds., Nina Goss and Eric Hoffman, UP of Mississippi, 2017, 所収 [下]) に基づいて、アルバム 'Tempest' (2012) 所収の 'Soon after Midnight' について考えました (タイトル、'sing your praises', 'now or never', 'more than ever')。
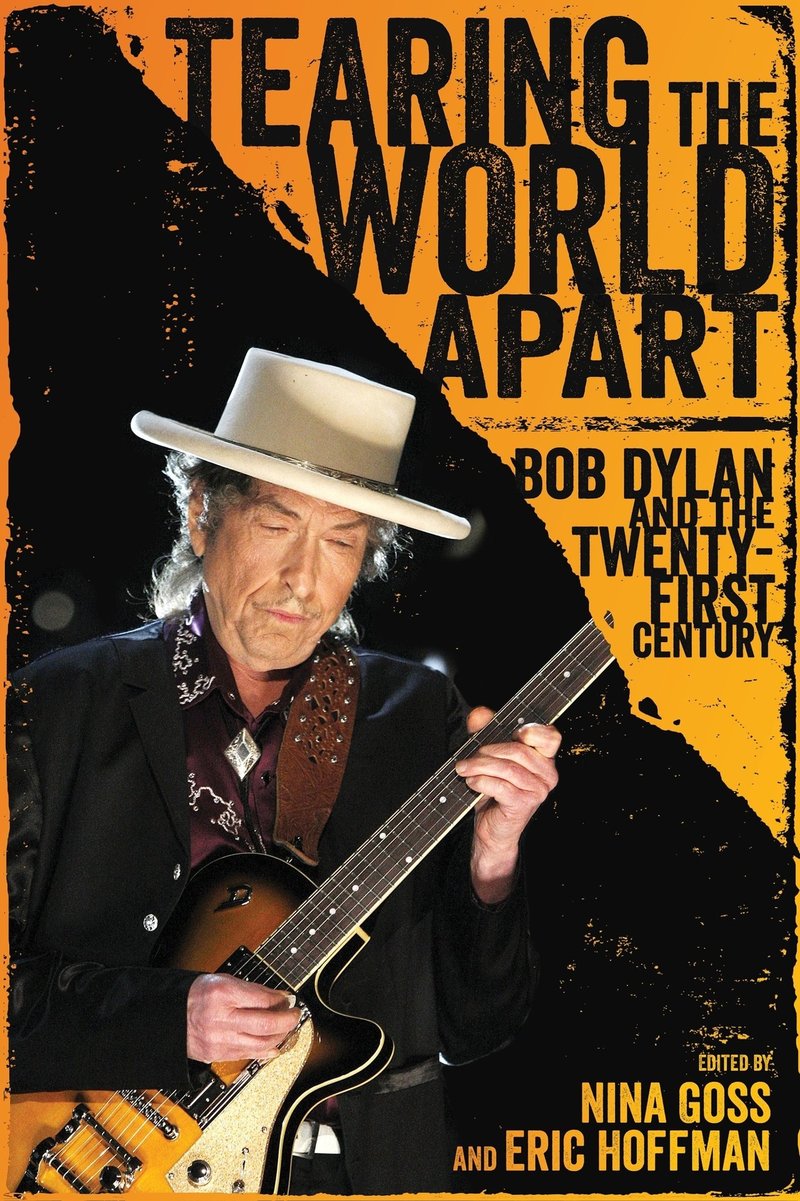
前回も、同論文に基づいて、アルバム 'Tempest' 所収の 'Narrow Way' と 'Long and Wasted Years' について考えました (頭韻、行内韻)。
今回も引続き、同論文に基づいて、アルバム 'Tempest' 所収の 'Scarlet Town' について考えます。「シェークスピア期に遡る英語がディランの 'Tempest' には生き続けている」ことを具体的に見てゆきます。
あとで述べますが、そのような英語の特徴は、シェークスピアだけでなく、同時期の英訳聖書にも見られるものです。今回は、その両方の影響を考えます。
*
参考文献 の表は、文字数の関係で、別のノートに移しました。
※「英詩が読めるようになるマガジン」の本配信です。コメント等がありましたら、「[英詩]コメント用ノート(202010)」へどうぞ。
このマガジンは月額課金(定期購読)のマガジンです。月に本配信を3回お届けします。
英詩の実践的な読みのコツを考えるマガジンです。
【発行周期】月3回配信予定(他に1〜2回、サブ・テーマの記事を配信することがあります)
【内容】〈英詩の基礎知識〉〈歌われる英詩1〉〈歌われる英詩2〉の三つで構成します。
【取上げる詩】2018年3月からボブ・ディランを集中的に取上げています。英語で書く詩人として最新のノーベル文学賞詩人です。
【ひとこと】忙しい現代人ほど詩的エッセンスの吸収法を知っていることがプラスになります! 毎回、英詩の実践的な読みのコツを紹介し、考えます。▶︎英詩について、日本語訳・構文・韻律・解釈・考察などの多角的な切り口で迫ります。
_/_/_/
'Scarlet Town'
ダニエルは、'Scarlet Town' は、その音楽的祖先において、アルバム 'Tempest' の全曲のなかでシェークスピアの時代にもっとも近いと指摘する。
「音楽的祖先」(its musical antecedents) が複数になっているのは、この種のバラッドは数多い歌の伝承を経て現代に続いているから。なかでも有名な祖先はスコットランドのバラッドの 'Barbara Allen' で、1690年代後半になってから出版された。
出版こそ、その年代だが、実際にはもっと古くから唄われていた。が、どれくらい前からかということは分らない。伝統バラッドの年代を決めるのはむずかしい。
それでも、たとえば、日記で有名なピープス (Samuel Pepys, 1633-1703) が1666年にこの歌を 'Barbary Allen' と呼んだことが知られている。(*) だから、この時代にこの歌が知られていたことは確かである。
(*) 臼田 昭『ピープス氏の秘められた日記――17世紀イギリス紳士の生活』(岩波新書、1982) という名著がある。同氏によるサミュエル・ピープスの日記の翻訳もある。実際の日記(1666年1月2日付)には '..but above all, my dear Mrs Knipp whom I sang; and in perfect pleasure I was to hear her sing, and especially her little Scotch song of Barbary Allen.' と記されている (ソース)。
*
'Scarlet Town' の歌詞は、'Barbara Allen' にあった伝統的詩句のエコー ('where I was born' や 'Sweet William on his deathbed' など) が見られるものの、「ほとんど闘争的なまでに現代的であろうとしている」('try almost militantly to be modern') とダニエルはいう。
それは「あたかも、これほど有名な歌の重圧からもがき出て、独自の歌であることを示そうとしているかのよう」('as if fighting their way out from under the weight of such a celebrated song and proving themselves') であると。
そのために、'Set 'em up, Joe' (「ジョー、元気にしてやれ」) と歌い手はふっかけ、'his flat-chested junkie whore' (「ぺチャパイのヤク中のあばずれ」) と座っていると唄う。確かに、このあたりは現代的な言い回しに見える ('set up' はいろいろな意味があるので、状況を特定しないかぎり、曖昧)。
ところが、最後になると、歌の言語はエリザベス朝の欽定訳聖書の英語 (伝道の書) に戻り、シェークスピアのソネット19番と交わる (keeping company with) とダニエルは言う。
'em
この最後のところについては後で検討するが、その前に、'Set 'em up, Joe' は果たして現代的表現なのかを問うてみたい。ダニエルは、同じアルバムの 'Early Roman Kings' の分析でも 'Gonna shake 'em all down' が現代的あるいは少なくとも20世紀的なひびきだと指摘している。本当にそうか。
ダニエルの論じ方は、えてして、〈これは現代的表現に見えるが実はシェークスピアも使っていた〉のように言う。だから、ここも、そういう含みがあるかもしれない。じじつ、後者については shakedown が Grateful Dead の連想を呼ぶことを指摘しつつ、実はこれはシェークスピア的な表現だと言っている。
*
英語史に通じている英文学者なら知っていることではあるが、一般には誤解されているかもしれないので、念のために書いておく。
'em は辞書では them の略式の使い方と、あるいは省略形とみなされており、話し言葉で them の代わりとして用いられる語と書かれている。
が、本来は、中英語の hem に由来する。hem は古英語の3人称代名詞の複数与格 him に由来する。
一方、現代英語の them は古ノルド語由来である。
時代的には、古英語は449年〜1100年頃で、中英語は1100年頃〜1500年頃、近代英語は1500年頃〜1900年頃である。現代英語は20世紀以降の英語。
われわれが焦点を当てているシェークスピアや欽定訳聖書の英語は、近代英語前半の初期近代英語 (1500年頃〜1700年頃) に属する。
'Scarlet Town' 最終連
それでは、エリザベス朝の英語に戻るとダニエルが指摘する最後のところを見てみよう。
その最終連を引用する。
If love is a sin then beauty is a crime
All things are beautiful in their time
The black and the white, the yellow and the brown
It’s all right there for ya in Scarlet Town
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?