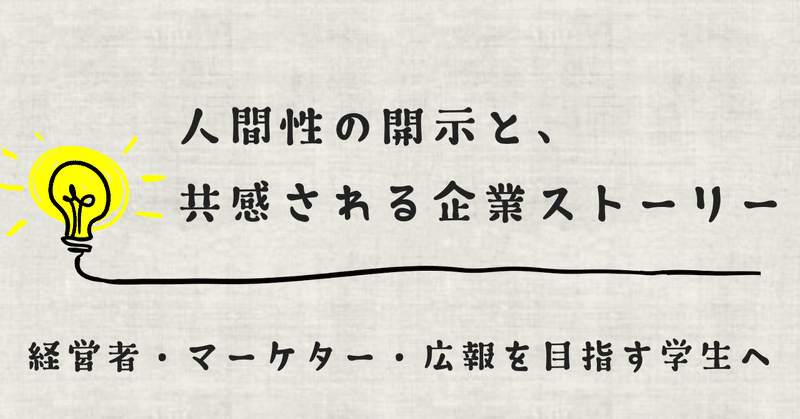
人間性の開示と、共感される企業ストーリー|前編
経営、マーケティング、パブリックリレーションズに関心のある学生向けに、企業のブランディングに資するストーリーテリングについて書いてみたい。
キーワードの説明
ブランディングの定義は多様であり、「ブランディングとはある目的や用途に対して、その製品ならではの付加価値を伝えること」、「ブランディングとはブランド価値を高める施策である」のように、少し物足りなかったり、同語反復的だったりする。ここでは次の二つの定義を念頭に置いてほしい。
ブランディングとは、企業やプロダクトやサービスを「独自のもの」「比類なきもの」として認知してもらい、他社と差別化をされた状態をつくる活動である。これは企業のステークホルダーの認知の働きに重きを置く、企業広報の担当者が親しんでいる定義だろう。
ブランディングとは、事業やプロダクトの資産価値(ブランドエクイティ)を上げるための活動である。ブランドエクイティの構成要素は、ブランドロイヤルティ、ブランド認知、ブランド連想、知覚品質、その他のブランド資産である。これはブランドの価値に注目したデイヴィッド・アーカーなど、マーケティングや経営学の視点からの説明だ。
認知を軸に説明する定義は、ブランディング活動のゴールをイメージしやすい一方で、価値を軸にした定義は、ブランディング施策を起案する際に役に立つだろう。
ストーリー(story)とナラティブ(narrative)は、ほぼ同義で使われることも多いが、語源に起因する用法の違いと、応用分野での用法の違いがある。
ストーリー(story)はヒストリー(history)と語源を一にし、過去の出来事を時系列に書いた物語であることが多い。また、歴史(History)が特に人間の歴史を指し、歴史書には人間社会以外の編年記が書かれないのと同様に、ストーリーには出来事の当事者である人間が登場し、当事者の思考や行動、社会の出来事が描かれる。
ラテン語のhistoria、ギリシア語のἱστορί(イストリ)には共通して、「過去の出来事を調べ、学ぶことによって得られた知識」という意味・用法があった。現在の英語や日本語でも、ストーリーは複数の人や組織の活動、社会状況を背景として書かれ、多数を読み手として語られることが多い。歴史(History)の多くが私たちの生前の出来事の説明であり、先人が書いた個別の歴史(history)を読むことによって学習される知識であるように、ストーリーは書き手と読み手の距離を前提として書かれ、距離を乗り越えようとする。歴史の書かれ方がそうであるように、ストーリーは書き手が替わっても大筋で内容が変わらず、読み手によって内容の理解が大きくばらつかない、という共通理解(common understanding)の状態を目指して書かれている。一方で(進歩史観のような)進化や発展のテーゼや、葛藤や失敗を経て成功に至る経緯、因果応報、起承転結など、ストーリーテリングの既存のフレームワークの制約を受けている。
ナラティブ(narrative)は基本的にストーリーと同じ意味(物語、出来事の記述)を持つが、語源はラテン語のnarrationem(出来事について語る、知らせる、物語る)であり、フランス語や英語の用法では語り手の視点と経験に基づいた語りを指し、個別性や当事者性が強く現れた物語のことである。企業で使われるナラティブの用法も、医療、看護、福祉の分野でのナラティブ・アプローチをはじめ、マーケティングのナラティブ・アプローチのように、当事者が語る経験や解釈の個別性を重視する。人間の行動様式や動機づけへの「アプローチ」の手法として活用されることもあり、ナラティブでは読み手が語り手(書き手)に歩み寄り、未だ語られないことを含めて聞き取り代弁することもある。
ストーリーとナラティブのどちらが上位概念だとは言いがたく、社会や集団のストーリーの中に個人のナラティブがエピソードとして登場する場合もあれば、個人のナラティブが巨大化しながら社会のストーリーを飲み込んでしまう事例もある。前者の例は、多くの報道記事、ドキュメンタリーや、ドフトエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』のように三人称の説明文をベースに多様な個人の語りが含まれた小説や演劇が含まれる。後者の例は、政治家による自身と時代の回顧録や、映画『フォレスト・ガンプ』などの作品であり、一人称のナラティブのなかに社会史がエピソードとして織り込まれる形式を持つ。
事業はストーリーテリングの連続である
さて、「事業の目的は顧客を創造することだ(There is only one valid definition of business purpose: to create a customer.)」というのはピーター・ドラッカーの言葉だ。事業は作り手の行為と買い手の行動により成立し、事業を三人称で説明したり一人称で語ったりするとき、それはストーリーの形式をとる。事業とストーリーテリングの関係は不可分で、ストーリーは事業に先立つ。
事業のストーリーは世界・社会・集団・個人のフレームの中にあり、戦略を含む大きなストーリーから、一つのプロダクト開発の経緯を語る小さなストーリーがある。上述のキーワードで説明したように、ストーリーは集団の内部や集団間で共有されストックされることを前提とした情報形式なので、アカウンタビリティ(説明能力、説明責任)、パブリシティ(公開性)の特徴を持っている。
一方のナラティブはフレームに縛られない自由で原始的、個人的(primitive, private)な語りであり、世界・社会・集団の各層から距離をとって個人的な解釈や意見を述べる視点が、ナラティブには含まれる。「組織と私の価値観の相違が大きくなり、私は組織を辞めることにした」という語り(cf. #退職エントリー)は、ストーリーとしてではなくナラティブとして理解しやすい。そしてフレームに縛られないナラティブは、個人が他の誰にも断ることなく発信したり取り下げたりすることができる。
また、ナラティブは所属する組織に断ることなく、個人が持ち運ぶことができる。「私は何者で、何のために仕事をしているか」というナラティブは、所属する組織を超えてポータブルなものである。そしてナラティブには特定の聞き手だけに向けられる限定公開性もある。親しい間柄で交わされる結論のない自己開示や、ナラティブ・アプローチで聞き出される他言無用の物語が、限定公開のナラティブだ。
もちろん、組織のストーリーと個人のナラティブが一貫性(integrity)を持つこともある。「私は社会の何の課題を解決するために事業をしているか。なぜ私がこの組織の一員として、この事業をやっているのか」という語りは、ナラティブであり、ストーリーである。
とりわけ事業の創始者や経営者が自己を開示する語りは、事業の創業ストーリーであり、経営戦略そのものである。私は何者か(who I am)、なぜ事業を始めるのか、誰の何の課題を解決するのか、なぜここに組織を作るのか。経営者個人のナラティブはただちに社会に向けられたストーリーとなり、他者が行動をする判断材料となる。最初の従業員、開発者、投資家、銀行、最初の顧客にとって重要なのは事業やプロダクトではなく、経営者が自ら語るストーリーだ。もう一度ドラッカーを引用すると、事業とは顧客を創造することであり、事業家と顧客が同じ方向を向いて行動するために必要なフレームが、ストーリーである。
当事者によるストーリーテリングは人を惹きつけ、関係性を強化する
企業の起源や、事業が永続する理由にかかわる重要なストーリーのことを、デイヴィッド・アーカーはシグネチャーストーリー(signature stories)と呼んだ。著書、Creating Signature Stories(邦題『ストーリーで伝えるブランド』)のなかでアーカーはシグネチャーストーリーをこう定義する。
What is a signature story? It is an intriguing, authentic, involving narrative that delivers or supports a strategic message clarifying or enhancing the brand vision, customer relationship, organizational values and/or business strategy.
シグネチャーストーリーとは何か。それはブランドのビジョン、顧客との関係、組織の価値体系、そして事業戦略を明確にしたり強化したりする戦略的メッセージを伝え(あるいは)サポートする物語だ。シグネチャーストーリーは興味をそそり、当事者性があり、人を惹きつける物語である。
筆者による翻訳
シグネチャーストーリーの例はこの著作に詳しい。L.L.Bean、ノードストローム、バーバリー、ライフブイ、トヨタのプリウス、バークレイズ、コカ・コーラ、などグローバルなブランドの事例が多く、同時にアーカー自身が書いているように、偉大なシグネチャーストーリーを見つけるのは簡単ではない。
より身近な事例、私たちが勤めているような日本企業の、偉大なストーリーはどんなものだろうか。例えばカシオ計算機のG-SHOCK(腕時計)の開発ストーリーだ。
カシオ計算機に勤める社員が、社内の廊下で同僚とぶつかって腕時計を床に落とした。高校の入学祝いに父からもらった腕時計が、バラバラに壊れた。同じ頃、道路工事をしている人々が作業中に腕時計を外していることに気づいた。社員は思いつきで「落としても壊れない丈夫な時計」の企画書を提出し、開発を認められた。3階の設計室のトイレの窓から試作品を落とす実験を数百回続けたが、毎回、時計のモジュールが壊れてしまった。期日が迫り、退職を覚悟したとき、公園で遊ぶ子どものゴムボールを見て構造を思いつき、試作品を完成させた。それは3階から落としても壊れなかった。量産された時計はその後40年間で1億3千万個以上出荷されている。
G-SHOCKの開発ストーリーは、発売から30年目のプレスリリースにも書かれ、発売から40年を超えた現在、カシオ計算機の自社ページやアプリにも掲載されている。
G-SHOCKの開発ストーリーの強さは、製品が買われ続けているというアウトカムとはもちろん関係がない。強いストーリーは、語られた時点で強い。強いストーリーは当事者の信念と行動の物語であり、人間性(humanity)がある。
人間性の要素は、デイヴィッド・アーカーがシグネチャーストーリーの要素として挙げた当事者性(authenticity)に近いが、ここで少し整理したい。物語を、その当事者が書くこと(authoring)により、書かれたテキストは本物の(authentic)資料として認められる。これがテキストの当事者性であり、社会での流通に耐える資料的価値を意味している。人間性は、物語の内容や、語られる姿勢を通じて開示される人間の本性のことを指している。
強いストーリーには人間性の要素がある
ストーリーにおける人間性の要素を整理してみよう。G-SHOCKの開発ストーリーのみならず、多くの企業の「強い」開発ストーリーに見られるのが下記の要素である。
イニシアチブと動機の軽薄さの二面性: 自ら起案して開発に着手したものの、失敗が続く。なぜ開発計画がない状態で、率先して手を上げたのか、後悔している。もう辞めてしまいたい。
他者に影響される弱さと、成功するまで続ける強さの二面性: 試作に失敗し続けていることを同僚に知られたくないため、隠れた場所で開発を続けた。成功の道筋は見えなかった。しかし他に誰もやる者がいなければ、成功するまで続けた者が勝つと信じた。
努力と偶然の要素の二面性: 偶然による発見や、ひらめき、意図しない失敗作に含まれた変化点が、成功のブレイクスルーになった。ブレイクスルーは必ずしも努力の結果とは言えないが、人並み以上の努力や集中なくしてその小さな変化点に気づくことはなかっただろう。
人間性を感じさせる要素を、私はこのようにいくつかの二面性として説明した。人間性は、行為への意思の強さと弱さ、能動性と受動性、主体と客体、努力による結果の必然性と制御できない外部性(偶然性)の両極のあいだで生き残ろうとしてもがき、どこにも安住できない何かである。あるいは、今日の強みが明日の弱みとなり、ある集団での有能が別の集団で無能となるように、関係性の中でしか評価されない他者性や、束ねられ序列化される他者性に直面しながらも、比類なき個として現象したいと願い、行為することもまた、人間性である。
シモーヌ・ド・ボーヴォワールは『第二の性』(1949年)の中で、能動性と主体性を強調する文化が、人(「女性」)をあたかもモノか自然のように客体視する「他者性」を疎外の仕組みとして説明した。ボーヴォワールのシンプルなフレームワークは古びることがない。『第二の性』から75年後に生きる私たちも、能動性と主体性に偏った人間観によって、関係性や偶然に影響される行為や生そのものを却下されかねない生きづらさと闘っているのではないだろうか。
人は女に生まれるのではない、女になるのだ。
教育社会学、組織開発の勅使川原真衣は、人間の「強み」「スキル」「能力」を、事業や個人の社会的成功に必要な要素だとみなす人材開発業界に異議を唱えた。たしかに私たちは、企業への就職や人事評価、研修制度を通じて、能力の不足を指摘され、主体的な学習による能力向上を推奨され、「強み」に対する「弱み」を克服するように奨励される。
勅使川原の思考は、人が組織を作る理由に向けられているように思う。もし特定の能力について個人間のばらつきが高いレベルで平準化されたり、個人のさまざまな能力が全方位に拡張されたりするような「人材開発」が成功してしまったら、人間は組織をつくる動機を持ち続けることができるだろうか。各人が扶(たす)け扶けられる働き方が不要になったとき、あえて徒党を組んで事業に乗り出すチームやカンパニーは生まれるのだろうか。
否、私には、人の能力ではなく人間性を重んじる人々が事業をつくるときが、継続企業(going concern)が誕生する瞬間だと思われてならない。
日本語の「会社」や「同僚」という言葉から失われつつある意味として、カンパニー(company)の概念を覚えておきたい。カンパニーはパンを分かち合う仲間を語源とし、旅を共にする連れ合い、友人、会社の意味で使われる。戦友というニュアンスもあるのは、軍隊の編成における中隊(company)が、戦場と兵站を共有して戦い、文字通りパンを分かち合う集団の単位であり、「なぜ、いまここで共に戦うのか」というストーリーを共有すべき仲間であったからだ。同時に、軍隊のカンパニーは人格としての隊長が一人で統率でき、肉声により命令を伝達できる100名から200名の集団である。これは人間が良好な関係を維持できる認知上の限界(ダンバー数、Dunbar's number)と一致する。
カンパニーは能力主義では維持できない。互いの人間性を開示して、「私」「あなた」のストーリーを共有し、「私たち」のストーリーを語り始めたときに、強いカンパニーが生まれる。
組織の素のままの原点(raw origin)としての人間性
マイクロソフトのクリエイティブ・ジャーナリスト(あるいはストーリーテラー)として6年余勤めたミリ・ロドリゲスは、ブランドを人間のように見立て、語ることの意義を説いている。
When it comes to brand storytelling, vulnerability is quite the opposite of powerlessness. It is a mighty force that bursts open emotional awareness. If story is magic, vulnerability is the magic wand that unleashes genuine connection with our audiences.
ブランドのストーリーテリングについて言えば、(人間の)弱さは無力さとは真逆のものだ。それは感情的な認知を一挙に開いてしまう強大な力だ。ストーリーが魔法だとすると、弱さはオーディエンスとの本物のつながりを生み出す魔法の杖なのだ。
Vulnerability in storytelling works because it poignantly reminds us of our humanity.
(人間の)弱さがストーリーテリングにおいて役立つのは、それが私たちの人間性を痛切に想起させるからだ。
筆者による翻訳
ブランドを一人の人間として語ること、あるいは経営者の人生を通じて見せることは、当事者性の強い(authentic)ストーリーを通じて、ブランドの弱さや失敗の歴史を見せることに他ならない。素のままの原点(raw origin)を開示するストーリーテラーが最も信頼を集める、とロドリゲスは書いている。
企業広報の立場で、自社の経営や製品開発の失敗をプロアクティブに開示することは可能だろうか。言うのは簡単だが実行は難しいだろうとロドリゲス自身が書いている。しかし私には、日本企業には人間性の開示によるブランディングに成功している事例が少なからずあるように思われる。日本文学や日本映画の美学的実践において、喪失による本質の暴露、ゼロからの再起、信用の失墜と回復をテーマとする物語が支持されてきた。少し脱線すると、米国の文学や映画では企業人の失敗はすなわち失職に直結し、ネガティブから再起し成功する物語が古典として受容されている。ロドリゲスが推奨する「弱いが、むしろ強い」ブランドストーリーの例も、スターバックスのハワード・シュルツ、アップルのスティーブ・ジョブズの辞任と復活のストーリーである。
オーディエンスに支持される「回復」のストーリー
企業のストーリーテリングにおいて、挑戦や成長、課題解決は主要なテーマだ。一方で、単純なサクセス・ストーリーよりも、人間性の要素である動機の軽さ、偶然の要素、成功を信じて愚直に続けた努力など、ゼロ地点あるいはネガティブからの回復のストーリーはオーディエンスの共感を得られやすい。
特に、企業の人間的な弱さや失敗の歴史がオーディエンスの期待に先行して語られるとき、読み手にとってはある種の美学を伴って認知される。それは人間のレジリエンス(しなやかな回復力)への美的感覚であり、演劇(悲劇)のカタルシスのような認知作用だ。
悲劇は、哀憐と恐怖とを作興する出来事を含み、それを通して、かやうな情緒の其[悲劇の]瀉泄《カタルシス》を行ふ。
津波で多くの従業員が亡くなり、施設と在庫を失った酔仙酒造(岩手県陸前高田市)の復興のストーリーは、地域のみならずインターネット上で多くの反響があり、ほどなくして大手の新聞やテレビ局の取材を受けることになった。このストーリーは災害被害からの復興を振り返ったものだが、経営者の信念と努力という主体性の成功物語ではない。事業継続をほとんど諦めながらも、他者に影響され、苦し紛れの再建計画を作り、ライバル企業の設備を借りながら生産を再開した経緯を綴っている。
もう最初はダメだと思った。自己破産だな、としか思わなかった。通常の感覚では、再建は厳しい。無理だと思った。
陸前高田の飲食組合の関係者から声をかけられた。「お前、本当にやるんだって? やるんだろう。だから俺たちも頑張るからよ」。そう言われた瞬間に、これは大変だ、嘘でもいいから事業計画を作り、最善を尽くそうと思った。
また、平時に定価が2千円台だった自社の酒が、震災後に7万円以上で取引されているという話を聞き、堪らない気持ちになった。「うちの酒はそういう酒じゃない、普通の人に楽しんでもらう酒なんだ」。早く、生産を再開すべきだと思った。
筆者による抜粋と要約
ここでは当事者としてのナラティブが、社会・(顧客)・組織・個人のストーリーと一体化し、一貫性を持っている。正直な自己開示が読み手にカタルシスを与え、他者と共に回復を指向する経緯は、普遍的で、美しい。
酔仙酒造のストーリーを通じて、自己の行動の評価や支援者への感謝は控えめであり、どこまでも人間的な感覚に根ざしたナラティブが続く。それらは当事者の行為を評価する語りではなく、主体性を評価することを回避しながら、ありのままの実存を見つめて語られた言葉であるように感じるのだ。
(後編に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
