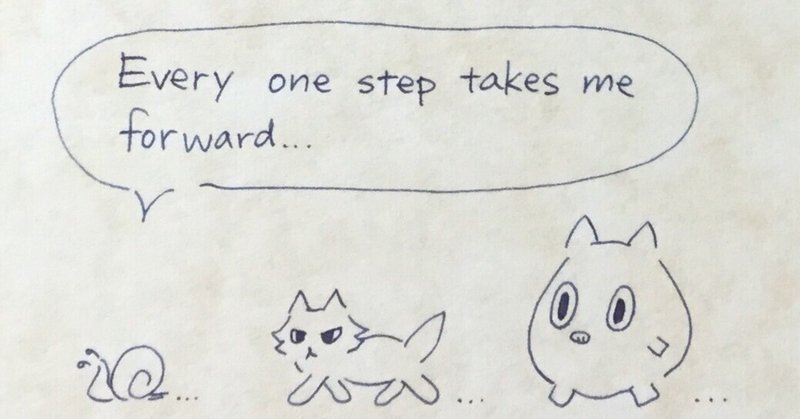
「著作権」って変な言葉?ー法律用語はつくられるー
(※3/27の16:00頃公開後、タイトルを変更、本文の流れをよくするために追記、文字の強調をしました)
著作権は難しい。少なくとも私には難しい。一応それなりの資格も持っているので、ある程度は理解しているつもりだが、いまだに「無理くり飲み込んでいる」感覚である。なぜか。
条文は辞典ではない
「著作権法とは何か」「著作権とは何か」を考えるとき、人が向かうのは条文(法律の内容が書かれた文書)である。一番正確な根拠なのでそれは当たり前なのだが、条文に使われている言葉というのは、誰かが生み出した「造語」の場合がある。これに思い至ったのは、2012年の著作権法改正があったとき、法案の作成に関わった行政官の方のお話を伺ったのを思い出したからだ。「なるべく誤解のない表現をするためにどうすればいいかなと、通勤中も入浴中もずっと考えていた」と(※1)。
日本の著作権法は1899年に施行された(この時のものは現在では「旧著作権法」であり、現行の著作権法は1971年に施行されている)。それまで、福沢諭吉によるという「版権」という言葉が日本にはあり、こちらの方が耳馴染みがある向きも多いかもしれない。しかしながら、この言葉には問題があった。「版」とは印刷をするために木を彫った「版木」のことを指し、葛飾北斎のような、クリエイターその人そしてその作品ではなかったからである(※2)。日本が開国し、世界と同じテーブルで取引するために、当時最先端の法律であるベルヌ条約(※3)を参考に新たな法律を制定する必要があった。「著作権」という語を使ったのは、旧著作権法の立案者である水野錬太郎が考えたというもの、もしくは、1886年スイスのベルンで開催された著作権保護同盟会議に参加した、黒川誠一郎による訳語、など諸説あるようだ。
「著」という漢字がもともと含む概念は文章であるが、著作権法上、その対象は絵画、音楽、写真、建築、舞踊、映像など多岐に渡る。この「言葉のもともとの意味」と「法律の言葉が定義する内容」に食い違いがあることが、理解しにくい原因となっていると思う。
・・・水野は、広く著作物に関する権利ということから著作権と名付けた。創作者権、作品権などの議論もあったという。
後年こんな批評がある。FM東京の松尾松太郎「新著作権法とラジオ放送」は、著作権法が難しい理由の一つとして、著作権が名称からして常識的でない、本来著作権は、書籍その他の印刷物には適切で、その後生まれた絵画、彫刻等の美術的著作物、音楽的著作物はまだしも、映画、放送、建築、舞踊などの権利を著作権の名で呼ぶことにいささかの抵抗を感ぜざるを得ないという(13頁)。
成文堂、2003、106-107頁。太字は筆者。
辞典は人々が知っている言葉を用いたもの
見坊豪紀氏が「辞書とは、だれかが現実に使ったことばを反映している、という性格を持っているはずである。だれも現実に使っていないことばが辞典にのっているとすれば、おかしなことである」(※4)と述べている。辞典での著作権の説明を見てみよう。
【著作権】
(Copyright)知的財産権の一つ。著作者がその著作物を排他的・独占的に利用できる権利。その種類は著作物の複製・上演・演奏・放送・口述・展示・翻訳などを含み、著作者の死後一定期間存続する。
【著作物】
著作者が著作したもの。著作権法では、文芸・学術に関する著述のほか、音楽・絵画・彫刻・建築・写真などの作品を含む。
【著作権】
[法]無体財産権の一つ。文芸・学術・美術・音楽などの範囲に属する著作物をその著作者が経済上独占的に利用できる権利。著作物の複製・翻訳・興行・放送などを内容とする。その権利は著作者の生存中および死後一定期間存続する。
【著作物】
著作によって創造されたもの。著作権法上では、文芸・学術・美術・音楽・写真などの創作作品のほか、演奏・歌唱などの創造的所産も含む。
【著作権】
著作者が自己の著作物の複製・発刊・翻訳・興行・上映・放送などに関し、独占的に支配し利益を受ける排他的な権利。著作権法によって保護される無体財産権の一種。
【著作物】
②著作権法上、思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの。
知的財産権、無体財産権の選択については、辞典の発行時期にもよるだろう。個人的には、【著作権】については2つ目の『学研国語大辞典』、【著作物】については1つ目の『広辞苑』の説明がわかりやすいと感じたが、それでもストンとは落ちない。
法律用語と感覚の距離感を縮めるアプローチが必要ではないか
私がここで申し上げたいのは、「法律の条文がわからないのは、読み手の理解力がないからではない」ということだ。常々思うのだが、法律を勉強し始めると、法律用語、専門用語で理解することが当たり前になってしまい、それ以前に持っていた感覚を忘れてしまう。法律の条文を誰もが理解しているべき日本語として用いるようになり、その枠組みでしか考えられなくなってしまう。法律家は「勉強してください」と気安く言うけれど、自発的に勉強なんてなかなか誰もができるものではない。義務教育できちんと教わるわけでもなく、十分な説明も周知されないまま、「知らない方が悪い」とは酷というものだ。
『おさるのジョージ』で有名なハンス・レイは、第一次世界大戦で従軍中、夜空を見上げて星座の本で勉強しようとしたが、星座のつなぎ方の説明がわからず、自分でわかるようにつなぎかえたという。それが『星座をみつけよう』という子供向けの本になり、人々の星座の学習書として親しまれているそうだ(※5)。そのエピソードも、私が「条文に頼らない著作権の理解」を考えるきっかけとなった。早稲田大学・知的財産法制研究所の招聘研究員であられ、2019年に亡くなった結城哲彦氏はこう述べる。「著作財産権が、我々の生活の中で身近な存在となってきている今日、これを「寄らしむべし、知らしむべからず」にしてはならず、「寄らしむべし、知らしむべし」でなければならない」(※6)知的な活動というものは、血の通った、人を救うものであってほしいと、常々思っている。

※1 確か、第30条の2における「付随対象著作物」という言葉の話で出てきたと思う。「付随対象著作物」というのは「いわゆる映り込み」で、たとえば、街中で写真を撮ったときに被写体とは関係なく映ってしまった、宣伝用のドラえもんのイラストなどである。
※2 「版権」に関しては、「知財業界でサーチャーといえばこの方」の酒井美里氏が面白い記事をお書きである。
※3 正式名称「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」。著作権保護のための国際的な取り決め。
※4 見坊豪紀『辞書をつくる 現代の日本語』玉川大学出版部、1976、90頁。
※5 H. A. レイ著・絵(草下英明訳)『星座を見つけよう』福音館書店、1969。
※6 結城 哲彦「著作権とのつきあい方―「○○できる権利」と「○○されない権利」早稲田大学知的財産法制研究所[RCLIP]、2002。https://rclip.jp/column_j/%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%e3%81%a8%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%81%82%e3%81%84%e6%96%b9%e2%80%95%e3%80%8c%e2%97%8b%e2%97%8b%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e6%a8%a9%e5%88%a9%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c/
2022/3/27閲覧。
【参考文献】
文化庁監修、著作権法百年史編集委員会編著『著作権法百年史』著作権法情報センター、H12(2000)。
吉村保『発掘 日本著作権史』第一書房、1993。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
