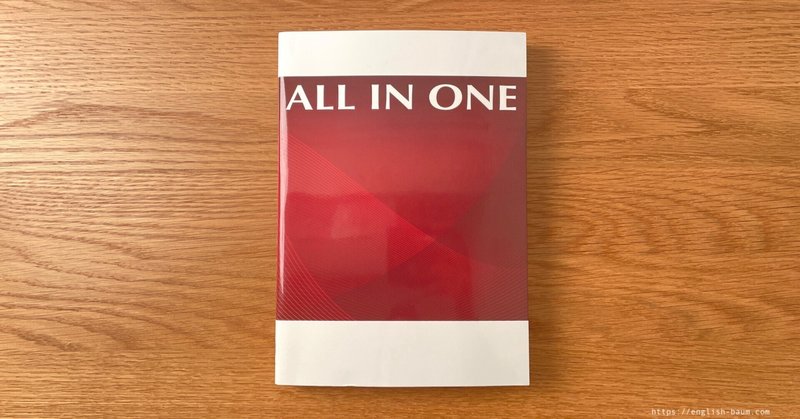
教員の All in One ノート
全教員にオススメしたい「ノート術」を記事に書きました。
僕自身5年の研究と実践を重ねていて、今では、仕事必須のアイテムになっています。
■All in One とは。
1つのノート(One)に見たい全ての情報(All)があるということ。
見たい情報とは、頻繁に見る内容 & 携帯したい内容 のことを指します。
この記事における早く帰る教師術とは「アクセスしたい情報に瞬時にアクセスできる術」です。
「あれ?あのプリントどこやった?」
「えーと、どこのフォルダだったかなー。」
とアクセスしたい情報に迷うことは、All in One ノートにはありません。
PCの中に情報があっても、それにアクセスするのに時間がかかります。
「該当フォルダまでクリックを進めて、wordを開く」というスピードよりも、All in One ノートをパッと開く方が早いです。

ノートはコクヨのバインダーノートを使っています。ルーズリーフでページを抜き差しできるので、バインダーノートは普通のノートよりも軍配が上がります。
■どうやってノートをつくるのか。
見たい情報をB5サイズに縮小印刷をして、カッターで端を切り、ルーズリーフに のりで貼っています。

■どんな情報がノートにあるのか。
1ページ目から順番に記載します
❶自分のクラスの生徒の名表(片面)
出席番号の横に名前。
字体は教科書体で正しい漢字を記載
名前にフリガナがふっている
名前の横に出身小学校も記載する

【いつ使う?】
学級開きの際に名前と顔が一致していないときに使う。
願書など正式な名前の漢字の確認で使う。
生徒同士の友人関係を出身小学校という視点から見るときに使う。
❷学年の生徒の名表(両面)
出席番号の横に名前
名前の横に所属している部活動
部活動の横に中学校に在学している兄弟がいるかの有無

【いつ使う?】
他クラスの生徒が何部に所属しているか知りたいときに使う。
懇談の日程を組むときに兄弟関係を把握するときに使う。
自クラスの生徒が欠席したときに、手紙を届けることのできる兄弟がいるかどうかの確認で使う。
❸自分のクラスの委員・係の名表(片面)

【いつ使う?】
自分のクラスの生徒がどの役割か を知りたいときに使う。
(担任の皆様。自分のクラスメイトの係を覚えていますか?僕は覚えてません(-_-;))
❹自分のクラスの生徒の男女別背の順(片面)

【いつ使う?】
集会などで男女別背の順で並ぶときに、だれが欠席しているかを確認するときに使う。
仲の良い友達としゃべりたい生徒は、ずるをして背の順を勝手に入れ替えることがある。それに気づくために使う。
体育委員が長縄のクラスメイトのポジショニングを決める時に、担任が背の順を伝えるときに使う。
➎教員の名表(片面)
先生の数が多いと、他学年の同僚の先生の役職が分かりません。
そのため、第1回職員会のページをコピーしてルーズリーフに貼ります。
職員の苗字と名前
だれがどの部活の顧問なのか。
職員の担当教科
【いつ使う?】
正直あまり使わない。4月はよく確認していたが、いずれ覚えてくる。
教室で先生の下の名前を言って、苗字を当てるクイズをしたりするときに使う。(下の名前は生徒内で浸透していないので、けっこう盛り上がる)
➎行事予定と部活予定(両面)
かなり、よく見るページです。
両面見開き1ページの左側に行事予定、右側に部活予定を載せるのがポイントです。学校の動きと部活の動きを見開き1ページで見ることができます。


僕は、年間行事予定もノートに貼っています。ただあまり使わないですね。
卒業式や体育会、文化祭などの大きな行事の日程は変わりませんが、細かい日程はけっこう変わるので、職員会で周知された”正しい”月ごとの予定の方をよく使っています。
また体育会のシーズンのみ、体育会の練習日程をバインダーに挟んでいます。そのシーズンに限っては、よく見る予定だからです。
(体育会が終われば、リングからそのページを外します。)
➏一日の流れと未来メモ(片面×日数)
毎朝、出勤してすぐに見るページです。毎日見るルーティンになっています。


朝のSTで伝えたいことや、個別に生徒に伝えたいことを、TO DO リストの形式で書くページです。
【タスク漏れがなくなる未来メモ】
未来メモとは、例えるならiphoneの「リマインダー」のこと。
僕は、未来のページを2ヶ月先まで作っています。この記事を書いている今は、10月31日までのページをルーズリーフに挟んでいますね。
なぜ未来メモでタスク漏れがなくなるのか。
例えば、9月22日(木)に学校給食がないという予定だったとします。
その連絡を必ず21日(水)に念押しで生徒たちにしなければなりません。
「連絡しないといけない!」と思いついたのが、9月5日だとしましょう。9月5日から21日(水)までに、このことをずっと忘れないように覚えておくのは無理です。
そこで、21日(水)のページに「給食アナウンスをする」と書き込んでおくのです。僕は毎朝必ずこのノート開くルーティンがあるので、過去に しこんだリマインダーが21日(水)朝に機能してくれるのです。
単に、手元のTO・DOリストにタスクを書いていても、TO・DOリストは日々更新されていくので、”給食がない”アナウンスをするタスクは埋もれてしまいます。
だから、未来の自分がベストなタイミングで見るであろうページに、未来のTO・DOを書いておくのです。頭に思い浮かんだその瞬間にリマインダーをセットするのです。
【いつ使うのか?】
毎朝、今日1日のタスクを確認するときに使う
未来で話しておきたい話を、今思いついたときに、未来のページに書きこむために使う。
【どんなときに使うのか?(あくまで一例)】
朝の職員会で「地域からクレームがあった。クラスで登下校のマナーを指導してくれ。」とアナウンスがあったら、すぐにノートに書きます。それを帰りのSTで言うのです。(メモしておかないと帰るころには俺は忘れてる)
クラスの生徒が〇月×日にスクールカウンセリングを予約したら、〇月×日のページにそのことをメモしておく。当日に「今日カウンセリングあるよね」と声をかけるためである。
2月13日に「チョコ持ってくるなよ」という話をする。このように、〇月×日のタイミングで伝えたい話が思い浮かんだ瞬間に、その日のページにメモしておく。
9月に生徒に向けて「だいぶ先の話だけど、バレンタインのときにチョコ持ってくるなよ。」というのは、効果ありません。時期が的外れすぎて忘れるからです。
話には”旬”があります。ここぞというタイミングで、”この話”を生徒の心に刺したいという感覚が教師には必要ですね。
■神アイテム
All in One ノートをさらに便利にするアイテムがあります。
❶カラーインデックス
生徒情報 ■ 行事予定 ■ 日常メモ ■ 白紙のページ
のように、各ページに■仕切り(カラーインデックス)を差し込むことで、ペラペラめくり時間を削減し、見たいページを早く見ることができます。

※コクヨのバインダーノートには、カラーインデックスが ついています。
❷ファスナーつきポケット

All in One ノートの一番はじめと、一番最後のページにファスナーつきポケットを2つ挟んでいます。
"ノートに貼っておくほどでもないが、もっておきたい書類" をこのポケットにいれておきます。
また、落としてはいけない紙、生徒伝えで渡す保護者への封筒などもこのポケットにいれます。
ファスナーがついているのは、安心ですね。
❸付箋12枚
ルーズリーフノートの最後のページには、カラーインデックスを差し込み、その片面に6枚(両面で計12枚)の付箋を貼っています。

職員室以外の場所(付箋が手元にない場所)で付箋を使いたいときに、サッと使うことができます。
教室でワークチェック行って、「返却お願いします」などメモを残したりなど、付箋を携帯できることは便利です。
❹保存用ノート
月日が流れるごとに、1日ごとのページの枚数が多くなるので、ノートは重たくパンパンになっていきます。
ルーズリーフの良いところは、いらなくなったページをリングから外せるところです。既に過ぎた日のページは、一応捨てずに、保存用ノートに保管しています。
僕は黒色ノートをメインで使い、保存用に赤色ノートを使っています。

9月には、4月の行事予定のページは使いません。いらないページを黒から赤に移し替え、メインである黒ノートを軽くします。
また、学校は1年サイクルの行事が何年もループする場所です。新年度スタート時に、昨年度の1年の流れが分かる保存用ノート(赤ノート)があると、どのタイミングでどんな仕事に着手すればよいか確認することができます。
「えーと、去年は、いつごろから その仕事はじめたかなー」
と、記録を振り返ることができるのはメリットです。
■ボトルネックはどこなのか。
【ボトルネック】
瓶の首が細くなっている部分を指す「bottleneck」に由来し、ワークフロー(業務の一連の流れ)のなかで、業務の停滞や生産性の低下を招いている工程・箇所のことを指す。
自分の仕事の どこに時間がかかるかを考えてみました。
”知りたい情報を知る速度”が遅いことに気付いたのです。
PC上にショートカットをつくることもしていますが、やっぱり紙のノートを開く速度の方が早いです。
いかに早く 望む情報にアクセスできるかを考えて、辿り着いたのが この All in One ノート。
早く帰る教師術の一歩目は、自分の仕事のボトルネックがどこにあるかを把握することだと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
