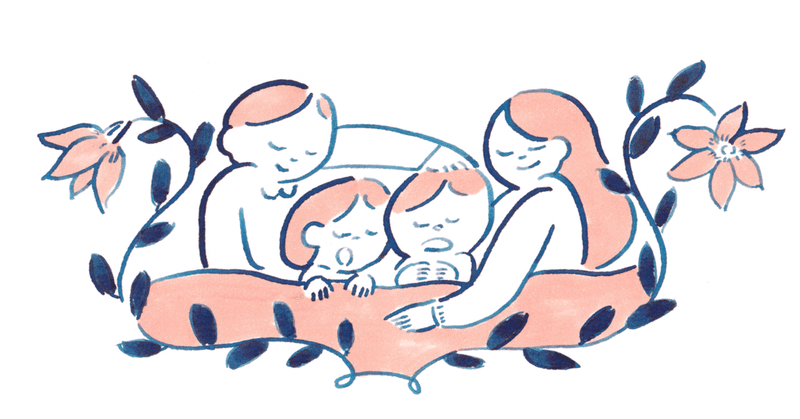
助けてと言える力
心の病を抱えている人の中には、
「助けて」と言えない人が少なからずある。
上手に「助けて」と言えないから、
周りの人が、
弱っていることや困っていることに
気づかなくて、
事態が悪化していることがある。
はたまた、
わかりにくく表されるので、
それに周りがびっくりしてしまって、
離れていってしまうこともある。
そういった場面を見てきているので、
自分の子には、
上手に「助けて(手伝って)」が
言えるようになってほしいと思っている。
この「助けて」が言える力は、
どう身につくか?
心の病にかからずに過ごしている
大人の中にも、
人になかなか手伝ってほしいと
言えない人っていると思う。
一方で、困った時には上手に
「お願いします。」
と言えて、
また助けてあげようと思わせる人もある。
こう言った人に助けを求める力というのは、
乳幼児期の親との愛着関係の中で
育っていくと言われている。
自分で何もできない時期って
生活の全てが「助けてもらう」になっている。
乳を与えられ、
不快を取り除いてもらい、
快を与えてもらう。
泣いて求めたら、
ちゃんと与えられる。
もう少し大きくなって、
いろいろなことが自分でできるようになっても
時々誰かにしてもらいたくなったら、
「やって」と言うとやってもらえる。
「やって」と言っても
怒られたりせず、
受け入れてもらえる安心感があるから、
「やって」と言える。
大人で「助けて」が言えない人たちは、
おそらく小さい頃のどこかで、
「やって」と言って
怒られたり、
「自分でやってね」と受け入れてもらえなかったり。
「やって」と言うことに
傷つきの体験がある人たちかもしれない。
誰かに助けを求めると自分が傷つくかもしれないから、
「助けて」と言えずに自分だけで抱えてしまう。
健全な甘えを受け入れてもらえて
「助けて」が言える大人になっていくのだ。
こういったことを
体験としてちゃんと理解したのは
少し前のことで、
息子がもっと小さい時には、
息子の甘えを
受け入れるかどうかに
迷っていた。
迷っていたから、
受け入れたり、
受け入れなかったりして、
息子も、だから、
わたしの顔色を伺うようになった。
「今日はいいのかな?」
「今日は、お母さんだめって言うかな?」
と考えているのが伝わってくるような日がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
