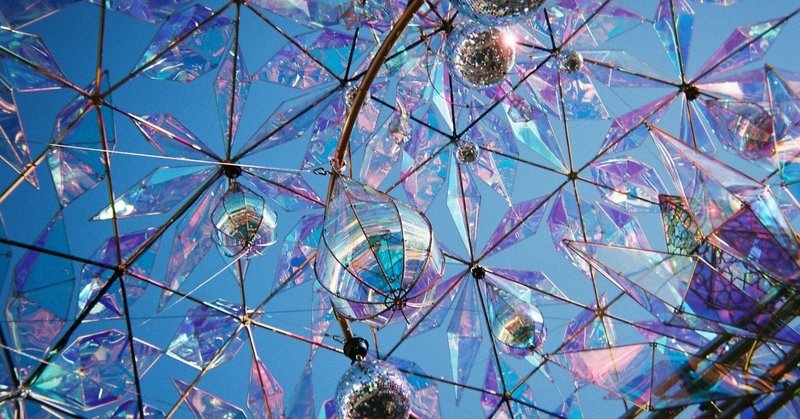
哲学で「やりたいことをやる人生!」の言葉の裏側を紐解いてみた
おはよう、こんにちは、こんばんは!
今日は、最近久々に胸アツな良書に出会えたので、熱りが冷めないうちにnoteに書いてしまおうとおもう。
今日の参考資料はこちら!
この本が直接的に題名に関する内容を述べているわけではないが、個人的な見解としてこの本の内容が多くの現代人が直面するであろう表題に関する問いになんらかの答えを導き出す材料になるような気がしたので、今回のこの本から引用することにした。
ちなみに私は「哲学」に関しては全く無知だ。
哲学?フロイト?ニーチェ?ソクラテス?なんだっけ。。。レベル。。(※フロイトは哲学者ではなく精神科医です)
そんな人間でもちょっと読めば、
「哲学?あ〜私はボードリヤールが好きでしてね〜」
とほんの少しマウントとれるくらいには理解できるように分かりやすく哲学史を解説してくれてるのがこの本だ。
この本では近代哲学〜現代哲学をメインに「合理主義→実存主義→構造主義→ポスト構造主義→これからの哲学(筆者の見解)」が解説されている。
個人的には、ニーチェやポスト構造主義〜筆者の見解が非常に面白かった。
が、合理主義〜構造主義も、これまでの哲学者たちの戦いを知る上ではとてもためになるとおもう、歴史は未来を教えてくれるからね。(でも私は軽くすっ飛ばして読んだ、、)
今日はこの本の中で、特に面白いと感じた、
・ニーチェ
・デリダ
・ボードリヤール
・筆者の見解
についてざっくりまとめて最後に私の主観を述べてみようかとおもう!
それでは、れっつご〜
1.ニーチェ
「神は死んだ」という名台詞で有名なニーチェが一体どんな哲学者だったのか??
「ニーチェ」という哲学者を知っている人は多くても、彼の主張を具体的に知っている人は少ないかもしれない。(私もその一人だった)
彼はなにについて哲学をした人だったのかというと、「ニヒリズム(虚無主義)」を唱えた人物で、言ってみれば、「宗教離れの火付け役」だった。
彼の主張をざっくり本書から引用するなら、
「神?正義?そんなもんどっかの頭のいいやつが作り出した嘘っぱちでしょ」
「だいたい宇宙なんてなんの意味もなくただ存在してるだけで、人間が生きていることになんの意味もないよ」
「それなのに、神様信じて殺し合いしたり、正義感振りかざして人を追い詰めたりしてさ、まったくもってバカバカしいね」
というような主張で、ニーチェは200年先の未来で、
宗教(神、究極の理想)が人類の精神安定剤として使えなくなる日を見越し、それに代わる新しい人生観、新しい聖書を作ろうとした
のだ。
そんな彼が新しく作り直した現代の聖書なる思想は、「永劫回帰(えいごうかいき)」を元としており、とっても軽くいうならば
「今を肯定して生きよう」
という主張から成っている。
ただ、偉大なるニーチェの哲学をこんなありきたりな言葉で処理してしまうのは申し訳ないので、限られた文字数ではあるが少しだけ「永劫回帰」の思想について触れてみよう。
まず、彼は神のいなくなった世界で、ニヒリズム(史上最悪の未来)を乗り越えるための哲学を考えるには、考えうるどんな史上最悪の出来事(ニヒリズムA、B、C・・・)よりも、最強に史上最悪の出来事(ニヒリズムX)を想定し、それを乗り越える哲学を考えること、
つまり、雑魚を倒すたくさんの魔法ではなく、ラスボスを一撃でぶっ倒す一打を考え出す方法を取ることで哲学を構築しようと試みた。
史上最悪のニヒリズムXとはなんだろうか・・・
それが「永劫回帰」だった。
ロシアの文豪、ドストエフスキーは小説「死の家の記録」のなかでこんなことを書いている。
「重罪犯人に自分の罪を思い知らせるなら、穴を掘り土を移動させ、それをまた埋めて元に戻す、という作業を永遠と繰り返させればよい。それは究極の拷問であり、最後には精神に異常をきたすであろう。」
・・・。
考えただけでゾッとする。。笑
そもそも私たちは、どんな不幸も「一度しかない唯一性、かけがえのないもの」だからそこに価値を見出して乗り越えることができている。
その唯一性、というのは死の上に成り立っている。
「山の上まで石を運ぶ作業」も「一度きり」なら頑張れるはずだ。
しかし、その作業が何億回と無限に続くものだったらどうだろう。
しかも何度繰り返そうとも、寸分たりとも狂いなく同じ景色、同じ状況が訪れるとしたら、そんな行為は無価値で、無意味で拷問だ。
故にニーチェは「永劫回帰」を史上最悪のニヒリズムとして定義づけた。
そして、かくかくしかじか、ニーチェは理論上、(詳しくは本を読んで欲しいが)宇宙は永劫回帰しており、無限に時間を進めていくうちに
いつかは必ず「同じ組み合わせ」があらわれ、再び同じ運動がはじまる
宇宙が永遠に回帰している
ということを証明した。(理論のアラを探そうと思えば結構あるんだけどそこはニーチェ曰く、本質的な問題ではないそう。(突っ込みどころ満載だな、、w))
その上で、この永劫回帰の無意味な世界を乗り越えるにはどうすれば良いか?
ニーチェの出した答えが、
「永劫回帰する運命を積極的に受け入れ、もう一度味わいたいと願えるような『今』を見いだしなさい」
というものだった。
当たり前の些細な瞬間。そんな程度で構わない。その瞬間(今)を逃さず、全身全霊で味わい、自分から「よし!」「ビバ!」と肯定するのだ。もしもその肯定が、「何億年、何兆年、気の遠くなるような時間をかけても、もう一度ここに戻ってきたい!」と願えるほどの肯定・・・、「真の肯定」であったとしたら・・・、それはもはや「その瞬間」だけの肯定にとどまらない!太陽系も銀河系も含めた生滅する宇宙、すなわち永劫回帰そのものの肯定となるだろう!なぜなら、永劫回帰があるからこそ、再び「あの今」に、「あの出来事」に、「あの人」に出会えるからだ。
「今を大事にしよう」という言葉は現代でもよく耳にする言葉だが、実際にその言葉通りに生きている人は少ない。
多くの人は「理想」「幸福」「目標」・・・と未来型の思考法だ。
しかし、未来になんの希望も見出せなかったらどうなるだろう・・・
どんなに順風満帆な人だって、そういった瞬間は人生で一度や二度ばかりではなく訪れるはずだ。
そんな時に、ニーチェ的思考は全ての人に分け隔てなく光を与えてくれるのかもしれない。。
うわ〜ニーチェ長くなりすぎた。。。笑
2.デリダ
ここからいきなり飛んで、「ポスト構造主義の哲学」に入る。
「ポスト」とは「次の」という意味だが、「ポスト構造主義」というのだからその前には「構造主義」という風潮があった。
構造主義を否定し、乗り越えるのが「ポスト構造主義」。
では、「構造主義」はなんだったのかというと、
「西洋、東洋、未開を問わず、とにかく全部並べてみて、そこから『普遍的な構造』を見つけ出すことで物事の本質を把握しよう」
という、一見全知全能そうに思える主義で、世界的に大ブームになった。
だが、結果として構造主義は「なにを取り出すか」の完璧なお手本となる例がないなどの様々な理由で結局破綻してしまう。
そこで登場したのが「ポスト構造主義」。
ただ、構造主義の上に「ポスト」とつけられただけのこの主義は、構造主義以降、世界を圧巻するような主義主張がいまだ現れておらず、とりあえずこの呼び名で、と据え置かれているのだという。
この、「ポスト構造主義」は言い換えれば「真理批判主義」とも呼ばれるようだが、
そもそも哲学とは
物事(世界)から真理(本質、構造)を探し出す学問
なのに、「真理批判」とは何事か・・・
そう、「ポスト構造主義」とは「反哲学主義」なのだという・・・
なんじゃそりゃーーーー
ついに私たちの知らぬまに、人類は哲学を批判する哲学にたどり着いていたようだ・・・
でもこうなったのにはちゃんと哲学史的背景がある。
本書を読んで貰えばわかるが、私たちは「真理を追い求める営み」、つまり「たった一つの真実を突き止めること」に失敗したのだ。
それは最強の哲学、「構造主義」が破綻してしまったからだという。
また、時代が真理を求めていない、ということもある。
もし世界が
唯一正しいもの、真の宗教、理想の政治思想
を求めて争おうものなら、核で人類地球そのものを滅亡させてしまうからだ。
そこで「お互いの立場を尊重しましょう」「多様性を大事にしましょう」と、ポスト構造主義的な思想が哲学界に浸透していった。
真理を求め、議論すること自体がタブーになっていったのだ。
そんな時代に現れたのが、最新最強の哲学者、デリダだ。
しかし、デリダは死ぬほど読みにくくとても難解なことで有名で、例えばこんな感じである。。。
「『数たち』は幾度か、自らを迂回の運動と定義している。したがって、あなた方が『数たち』について語りえたあらゆる言説がそこには含まれている。そのような言説の過剰はあらかじめ決まっていて、予期されていた。それゆえ、『数たち』は自分自身によって自らを再標記している。10はⅪを含んでいる。その未完成=半過去はあなた方の前未来を超えている」(ジャック・デリダ『散種』藤本一勇・立花史・郷原佳以訳、法政大学出版局)
デリダ自身が、「この本は解読不能です」と本の中で言っていたりするようだから、意味を理解しようとして読むこと自体が馬鹿馬鹿しい。
そもそもデリダは読み手側で好き勝手に意味を与えて読むべき本なのだという。
デリダは、そういう発想が古いんだよと言う。つまり、「ある現象に対して、それを説明するための正しい理論が一個だけあって、一個しかない」というのはつまらない先入観にすぎず、後進の若者たちの柔軟な発想を奪う老害的な考え方だと、デリダは言うのである
主義主張をし答えを提示すること自体が、古いのだ、というのがデリダの主張。
デリダも、前時代の哲学の破綻に伴った時代の要請によって登場した新しい価値を提示した哲学者なのだ。
3.ボードリヤール
デリダと同じ、ポスト構造主義の重鎮ボードリヤールは雑にいうと、
「もう俺たちの社会で、何もかもどん詰まりやで〜」
そして、
資本主義社会(現代社会)は決して破綻しない自己完結したシステムである。資本主義社会は、すでに『生産時代』を終えて『消費時代』に移っており、しかも記号を消費する時代になったから破綻しないのだ
と主張した。
確かに、私たちって、もう「生活必需品が足りない!」という状況にはないよね。
とにかく使い捨て、使い捨て、消費消費して、経済を回せ回せで生きている。
「おまえらは、次々と生み出される有りもしない見せかけの記号(ゴール)に踊らされて、社会(校庭)という小さな枠の中を死ぬまで走り回ってるだけなんだよ!そして、それが永遠に続き、おまえらは、もうそこから抜け出せないんだよ!」
ボードリヤールは、今の時代を「記号を消費する時代」と名付け、私たちはそのありもしない記号消費のために働き、経済をまわして、人生を消費し、気がついたら死んでいるのだという。
うわ〜恐ろしいけれど納得しかない、、、
じゃあ、「記号消費、やめます!」と言っても、それも「記号消費をしない」という「記号」で自分に酔いしれてるだけなんでしょ〜?
と、なんとも皮肉ったらしい主張だ。
この理論には抜け道が一切ない。
「モノを買います!」「はい、そのモノは一種の記号です!あなたは記号消費社会に捕らわれています!」
「じゃあ、そんな社会を変えます!」「はい、それも記号です!あなたは記号消費社会に捕らわれています!」
「じゃあ、普通に生きます!」「はい、それも記号です!あなたは記号消費社会に捕らわれています!」
デリダもそうだったが、独自の理論の中で完結させようとするのが「ポスト構造主義」の特徴だ。
で、詰まるところ筆者曰く、
人類は、「真理」や「構造」を見つけ出すことについて完全に失敗に終わってしまった
ようだ。。
人類は、社会の中にとらわれ、その構造の中でしかものを考えられず、そこから抜け出せもしない。
できることは社会システムを維持するためにただグルグルと回り続けるだけ・・・
デカルトの時代から長々と説明してきた哲学史であるが、ここに終了が宣言される。現在に追いついたから哲学史の説明を終了するのではない。まさにこの現代において哲学二五〇〇年の歴史が終了したから、ここで説明を終了するのだ。すなわち、「哲学は死んだ」のである。
ちーん。。。
4.筆者の見解
著者の見解としては、次の時代の哲学として考えるべきテーマは三つあるらしいが、ページの都合上、この本では一つに絞って書かれている。(残りの2つ、めちゃくちゃ気になるな・・・)
筆者に言わせれば、私たちのやっている仕事の全てに高い価値があるわけではないという。
昔は、
生活に必要なものを作りたい→仕事をする
だったが、今は
とにかくお金はグルグル回したい→仕事をする
極論、経済を回すためなら穴掘りでも良いということだ。
そのくらい、経済を回すことは私たちの社会で最優先事項だということ。
でも、筆者はこう投げかける。。。
僕たちは、今、記号消費社会に生きているが、僕たちがやっている仕事、もしくはこれから就職してやろうとしている仕事は、実は、この「穴掘り」なのではないだろうか。
うええええええーーーー!!
痛恨の一撃来た〜〜〜!!
って感じですね。笑
そんなこと言ったら、もうおしまいよ〜〜
それに対して、筆者はどのような提示をするのか・・・
これがめちゃくちゃ面白かったんだけど、ここはこの本の醍醐味なので是非とも読んでもらいたいな〜ってことで、最後に私の感想だけ載せておきます!(ごめんよ〜〜笑)
5.みっぱ的考察
いや〜哲学初心者にとっては現代の闇をえぐりにえぐりまくってるこの本、とてもスリリングで楽しかった!
そして自分の胸に手を当てて考えると、思い当たることがグサグサ刺さって、本当に時間を置いて何度も読み返したい本だな〜と思った。
実は、この本、最初kindleの試し読みでインストールしてみて面白そうだったから地域の図書館で予約して読んだんだけど、
「これは・・・ちゃんとKindleでハイライトして手元に残しておかんとあかんやつや・・・!!」
と思い、Kindleで買いなおしてバッチリハイライトしまくった所存でござりまする。。。!!
結構中間部はすっ飛ばして読んじゃったんだけど、(というのもやはりさすが哲学・・・初心者がまともに体当たりすると思考のがんじがらめで頭がカチ割れそうになった・・・)気になる部分だけでも、もうこんなにnoteが書けるくらい!
本当に読んで学びがあった!と感じられた本でした!!
最初に「やりたいことをやる人生!」を哲学で紐解いてみた!という題をつけたんだけど、ここに来るまでの大部分がここに触れていなかったね〜(すみません。。)
軽く、最後の筆者の提示をネタバレすると、「俺たち究極的には穴ほって埋める作業で経済回してるんじゃね?経済の奴隷だよな、おい」って言ってる部分のラストで筆者は
「あなたは、本当にそれをするために生まれてきたのですか?たった一度しかない貴重な人生、その大半をそれに費やしてしまって本当に幸せですか?」
と読者に問を投げかけている部分に、今回の表題の鍵となる部分が込められていると私は感じ取った。
途中で、こんなことも出てくる。
「じゃあさ、グーチョキパーを永遠と出し続けるとお金がもらえるとしたら、人生の八〇%、ずっとグーチョキパーを出し続けるんだ。えーそういうのが『仕事する』ってことなんだ?わー、意味わかんなーい。頭おかしいんじゃないの笑」
極論だが、そういったことや、多くの現代哲学者たちが「資本主義の終わりはこない」と述べている事実を天秤にかけて、じゃああなたはどうしますか?
と、デリダ的に言えば、「一つの主義主張を受け手に読み取らせようとはせず」考えることが私たちのやるべきことなのではないかな〜と。
そう思ったのでした!
今日はそんな感じ〜
これを機に気軽に哲学してみよう!という気持ちになりましたよ!
現場からは以上で〜す!!
是非、この本読んでみて!
では、また〜!!
みっぱ
サポートしていただいたお金で本を買いたいです✽.。(*´ー`*)
