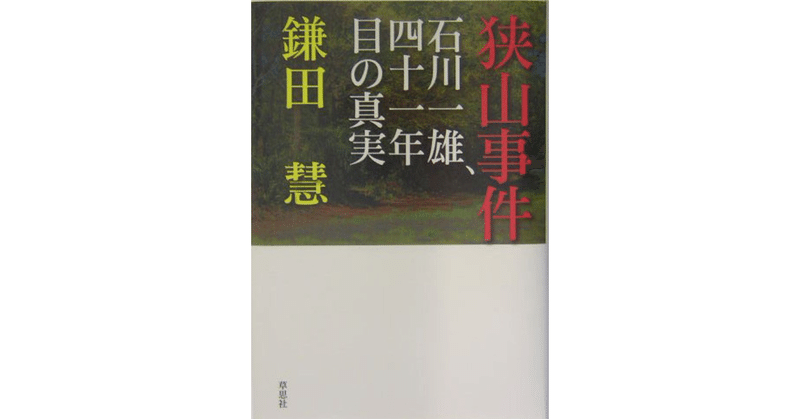
読書メモ|狭山事件|石川一雄、四十一年目の真実|鎌田 慧
「成田悠輔博士が弟修造氏に送った読書リスト」から選んだ本の1冊です。
世良田事件とは、関東大震災のときに組織されていた「自警団」を中心とした連中が、差別発言に対して糾弾行動に起ちあがった世良田村に住む被差別部落23戸の人たちを、竹槍、日本刀、鍬、鳶口、万能などで武装して襲撃したものである。
*********
「水平社」は、被差別部落のひとびとが、自身の行動によって自分たちの解放を目指すとした運動で1922年3月京都で創立され全国にひろがった。
*********
非識字者に共通する体験だが、彼もまた市役所や郵便局にいくとき、右手に包帯を巻いていった。包帯をした手をみるだけで、係の人が「代わりに書いてあげましょう」と同情してくれるのだ。
*********
石川一雄が、日雇仕事から脱出して、中堅工場の社員になりえたのは、この企業(東鳩製菓)が食品会社として成長しはじめていたからである。こんどはぬかりなく、職安に提出する書類は、友人に書いてもらった。履歴書は姉の夫である石川仙吉が作成した。無事に採用されたのは、本人の人柄のよさが面接担当者に好感されたからと考えられる。
検察官が口述し、書記官に筆記させたこの「供述書」のきわどさに、文字を読み書きできない男を罪にひきこもうとしている愚弄と焦燥がよくあらわれている。任官4年目、一雄より6歳上、30になったばかりの若い検事がベテラン検事に混じって功を焦っていた焦燥が、(供述書の)冒頭に書かれた「善枝さんを殺したり、関係したり、死体を埋めたり、脅迫状を書いたり、二十万円取りに行ったりした」という畳み込んだ記述に刻み込まれている。これらの罪状は、一雄が断固として否認しつづけてきたものだが、そう書いたあとに、いきなり「三人でやったことです」と「鉄パイプ泥棒」という主語を消去して、強引に結びつけている。いかにもひとを陥れるやり方である。
石川家が麦飯から白米の生活になったのも、まだ27歳にすぎない六造(一雄の兄)の甲斐性からだった。その大黒柱が逮捕されてしまえば、元の木阿弥になる、一雄はそれを恐れていた。
*********
次男の一雄が逮捕されたことで「石川土建」はゆき詰まった。そればかりか、市内の木工場で働いていた妹の雪江も、ガム工場で働いていた弟の清も、失職した。
*********
六造:「おれの仲間が、両親をなんとかしてやれっていって、五十何万かくれたんです。集めてくれたんですよ。顔も知らないひとも協力してくれたっていうんだね。両親が年とってる、だから、なんとかしてやれやってね。肥料のはいってるビニール袋があるでしょう、あれに入れてくれたんだね。紙幣や硬貨、いろんな種類があったね。ふるえたね。おれはね、親父に言ったんだ。昔うちにきたことあっただろう。入れ墨いれたのもいただろう。それを「てめえの仲間はみんなやくざだ」っていったろう。親父よくみろ、なんだかわかるか、かねじゃねえかって。おれにじゃないんだ、両親にやってくれってくれたんだ。昔「やくざだ」っていってたけど、やくざがこんなことしてくれっか。おれの仲間だぞ、といったんだ。なんだかぽろっとおっこったね。泣いたんだんよ、親父は。
無収入になった石川家はその50万円で食いつなぐことになった。ハガキが4円のころである。
死刑判決のあと、六造が面会にきた。
「あんちゃんが犯人だと思ったから、おれ認めてしまったんだ」
「おれにはアリバイがあんだ、お前までそんなこと思ってんのか、ふざけんなバカ野郎!」よほど悔しかったのだ。得意先を訪問していた六造のアリバイは不動のものだった。
「お前が自白しなければ、六造をひっぱるぞ」長谷部警視が一雄をおどかしたのは、六造のアリバイを知っていてのことだった。
三鷹事件の死刑囚・竹内景助の助言
「無実を主張した弁護士がいるようですが、本当にやってないのかどうか、ぼくに話してくれませんか。この通り、ぼくは石川さんの記事をもっているんだ」「ぼくも実はやってないんだ。石川さんも無実の罪みたいだけど、ぼくみたいにならないうちにはやく無実を訴えなくては」竹内は一審では無期懲役だったが、控訴した先の東京高裁は事実審理もおこなわず、異例にも検事求刑の「無期懲役」を上回る「死刑判決」に切り替えた。それまでは尊敬していた共産党員の罪をかぶるつもりだった竹内も、無罪になった被告たちが急に自分に冷たくなったのを目の当たりにして、ようやく無実を主張
するようになっていた。
犯人が身代金を受け取るため、佐野屋の前に姿をあらわした夜、息子が家で寝ていたのは家族が一番よく知っていた。それでもその息子は死刑である。リイ(一雄の母)は食事をとらなくなっていた
獄死する前、風呂であった竹内景助の胸は洗濯板のように痩せさらばえていた。彼以外の共産党員の被告が無罪となって釈放を勝ち取ったとき、「アカハタ」は「全員釈放」との大見出しを立てた。非党員だった竹内は、いわば党員釈放のための生贄のようだった。竹内としては日本の革命のために共産党員たちを救うヒロイックな自己犠牲のつもりだったが、共産党のあまりにもあっけらかんとした仕打ちは、竹内にほぞを噛む無念だけを残した。
一雄はほかの死刑囚たちをうらやましく感じていた。文字を読み書きできなかったことが、自分の運命をひとに任せっきりにした。供述調書をつくらせ、それを自分で読むこともなく、ろくに確認しなかった。その悔しい想いがあった。読み書きできるようになって、自分自身で闘わなければ死刑台へ続く道から脱出できないとの想いがつよまっていた。
熱心に文字を教えてくれたのは刑務官
文字を取得できたことで、心の炯眼を養い、石川一雄という人間を作り変えてくれたのは紛れも無い事実です。というのは、社会にいたころの私は読み書きができない負目もあって、自分をへんに捻くれた人間にしてしまっていたような気がしてならないからです。読み書きができるようになっただけで、こんなにも私の気持ちを豊かにしたり、心の中を広々と開拓してくれようなんて考えてもみませんでした。(部落解放同盟発行「狭山差別裁判」1990年2月号)
運動の時間と3度の食事以外は、ペンを離さない。小学校さえ満足にあがることができなかった(家が貧しいゆえに)私であるので、「狭山事件」の真相をどう綴ったら国民のみなさんにわかっていただくことができるであろうか。余計時間必要としなくてはならず「せめて中学校でもでていたら」と自分のあき盲に腹立たしさを覚え本当に情けなくなる。しかし、「俺よりももっともっと不幸な人がいるのではないか」と自分自身に言い聞かせ今では訴訟の合間をぬって習字、勉学と一字でも身につけようと学んでいるのである。
一審は、被告自身なにも争わず、すべてを認めるだけだった。供述調書の作成は赤子の手をひねるようにどうにでもなった。刑事たちも容疑者がなんでも認めてくれる安心感があった分だけ操作も杜撰になった。死刑台に送ってしまえばあとはなにも問題にならなかったはずだ。が、番狂わせだったのは、あろうことか、非識字者の石川一雄が獄中で文字を学んで、自分の裁判をみつめなおし広い世界を感じるようになったことだった。生きるための、必死の学習が始まっていた。
*********
目がよくなるまで一切書物はやめようかと思うが、私が筆を止めると代わりに訴えてくれるひとがいないのでペンを休ませられない
*********
獄中の日曜日は静かな上に静かで、看守が巡回する足音まできこえてくる。小さな覗き穴のフタをあけては独房囚を覗いていく。独房には悪さするようなものは何一つない。布団、食器類のみである。それでも10分間隔で巡回している。本担が休みで、臨時の担当さんがくると2-3分おきに巡回してくる。絶えず監視されている人間ほど惨めなものはない。
独房からはシャバ(世間)が見える。夜などは色とりどりのネオンの花が一生に咲き誇ったようでとてもきれいである。私は時々、獄窓から眺めては涙を落とす。私も男だ。無性に女が恋しくなる。時には気が狂いそうになる。無実の罪に陥れ、長い年月女気のないこのような中に放り込まれたら誰でもおかしくなる。しかし、私は中田善枝さんを殺していないのであるから、裁判が長引こうとも死刑は絶対にないし、青春を踏み躙られた私は2度と戻れないが、しかし、わたしには明日があり、女が恋しいが今は無実の罪を晴らすため全力でぶつかろう。高いコンクリートの塀で子供の姿は見えないが、今日は日曜日なのでキャッキャと騒ぐ子供の声が聞こえてくる。楽しそうに弾んだ声が聞こえてくる。ふと、私の小さい頃が思い出される。貧農だったために欲しいものがあってもなにひとつ買ってもらえず、毎日ボロをまとっていたが、それでも元気いっぱい飛び回っていた頃が思い出されて悲しくなってしばしなき濡れた。
*********
法廷の裏口に向かう、小柄な「死刑囚」の姿が新聞社のカメラマンによってとらえられている。夕刊の写真だった。それをみてわたしは息を呑んだ。
救援運動のなかで「無実の石川青年」と呼ばれていた被告は、額が大きくうしろに後退し。背中を丸めた、50も半ばを過ぎた疲れ切った中年男のような姿であった。まだ、34歳でしかなかった。その急速な老化が、11年半に及ぶ獄中生活の秋霜烈日を改めてかんじさせた。この日の驚愕と痛憤が私に石川一雄の半生を書かせるバネとなった。
弁護人席から抗議の声があがった
「上田鑑定(※1)はどうなったんだ」
「裁判長、それはペテンだ」
傍聴席も総立ちになっていた
「こんなの裁判じゃない」
「デタラメ裁判だ」
怒号にかぶせるように寺尾裁判長は「閉廷します」と宣言してたちあがると、あっというまに後ろの扉の中に姿を消した。
(※1)被害者の胃の内容物から死亡時刻を割出して自供の矛盾をあきらかにした新証拠のこと
*********
被告の父富造さんが退廷しようとする裁判官めがけて突進しようとした。「こんな裁判があってたまるか。今まで何をしてきたんだ」唇をひきつらせ体全体で込み上げる怒りをぶちまけた。
*********
(その日の朝日新聞夕刊)「寺尾裁判長らは、2年前に審理を引き継いだ後、自らは証拠調べをほとんど行わず、証人調べは一人として行わなかった。いかにも結論を急いだという感はまぬがれない」
最高裁判所の判決は「上告棄却」だった。事件発生から14年の月日が流れ石川一雄は38歳になっていた。
*********
懲役囚として配属されたのは靴工場だった。彼自身の希望だった。技術が身に付く仕事を選んだのは「手に職をつける」との考えからだった。刑務所から解放されたあとの生活を視野に入れていた。あとの話になるが、たしかに「懲役刑」は一人前の靴職人としての技術を身につけさせた。しかし、釈放されたときには、すでに手縫い靴の時代は去っていた。
*********
おそらく下獄後はさらに現在に数倍する生活の苦渋と人生の悲哀は付きまとうことでしょう。でもこれは自業自得でありますから、どんな苦しみにも耐え抜く覚悟でいます。なぜなら無学の結果騙されたとはいうものの、どんな拷問的取り調べにあおうともやってなければたとえ「善枝を殺したといわなければおまえも殺してしまうぞ」といわれても、認めなければよかったからであり、してみれば地獄の責苦にのたうつのも自業自得でありますから、誰も恨んではいけないのかもしれません。しかしこれはわたしの泣き言として聞こえるかもしれませんが、無知な私を利用して平気で罪を着せ得る警察のやり方が少しも非難されず、罰せられず、今なお堂々と治安維持という美名によって権力の名を恣にしている現状を多くの国民のみなさまが黙していることに対して、声を大にして訴えなければなりませんし、今後絶対にこのような差別犯罪によって不幸な人間が作り出されないように私の事件を教訓化し、厳しく警察をはじめとする司法権力に対する監視を続けていて欲しい・・・
*********
兄は自慢ではないけれども、今までに一度も警察沙汰はなく、それに兄の収入で一家を支えていることを思えば、兄が逮捕されれば当然一家心中を意味し、従ってもし兄が本事件に関係あるならば、極道者の私が身代わりになってやろうとおもったのも事実であります。まして、取り調べ過程において地下足袋と万年筆が自宅から発見されたという捜査官の言葉を信じた結果「10年でだしてやる」との約束とあわせて一審維持の伏線としてあったのです。
*********
「上告趣意書」は被告が弁護士および弁護団に依頼し、弁護団が手分けして作成するのがふつうである。無知だったばっかりに警察官につけいられた男が独力で文字を獲得し、それまでの屈服を払いのけるべく書き綴られた「上告趣意書」は、弁護団作成のものに吸収され、3ヶ月後最高裁へ提出された。かれの手書きの草稿をみると心から湧き上がる怒りがまっすくに伝わってくる。
石川一雄が仮出獄したのは、平成6年12月21日だった。いきなり寝込みを襲われて逮捕された日からすでに31年7ヶ月も経っていた。
*********
父親の富造は9年前、姉のヨネは8年前、母親のリイは7年前に亡くなっていた。リイの他界が母親思いの一雄に与えて打撃は大きかった。報せをうけて何日間か昏倒状態になっていたほどだった。
*********
自宅で寝ていても獄中のことをよく思い出した
仕事が終わった後、消灯の9時まで4時間を勉強時間にあてることができた。それが一雄にとっての幸せだった。監獄にいたからこそ、監獄からでるための勉強ができたというのは矛盾である。が、社会にいて勉強する機会がもてなかったからこそ、監獄に入ることになったのだ。その無念を晴らすための独習だった。
*********
「(人生を)無駄にされたことよりも、自分を犯人にでっちあげた人間が死んでしまったことが悔しかったですね。その方がとても強かったですね」
獄中でいつも同じ夢をみた。長谷部梅吉の家を訪ねていく夢である。レインコートの襟をあて、人目をしのぶようにして家を探す。狭い路地の奥にある家に長谷部の表札をみつける。思い切って声をかける
「ごめんください」玄関先に娘がでてくる
「長谷部警視はおられますか。むかし、お世話になったものですが」不審そうな顔をむけて娘が答える
「父は3年前に亡くなっております」
「しまった」
大きな声をだして、目が覚める。いつも同じ夢だった。
*********
「いつもかわいそうだなと思うのはさっちゃんのことです。ほかのひとと結婚していたらもっと幸せな人生を送れたと思うんです。実際泣き言を言わないので救われています。」
徳島出身のさちこが、石川一雄と結婚することになったのは、狭山事件の集会に参加するようになっていたからである。彼女自身も被差別部落の出身で差別に苦しんでいた。解放同盟の運動のさほどつよくない、その分差別がつよく残されている地域だった。
*********
1995年7月、石川一雄が仮出獄してから8ヶ月後徳島で交流集会があった。この時初めて彼女は一雄にあった。かれは孤独で控えめ、寡黙だった。飲まず、食べず、厳しい姿勢で端座していた。思っていたとおりのひとだと思った。翌年の夏、阿波踊りのとき一雄が徳島へ遊びにきた。さちこは釣りの名所として知られている月見が丘海岸に案内した。そのとき、彼がまわりの景色にみとれ、少年のように無心になって泳いでいるのを目にして、さちこは心を動かされた。その年の12月仮出獄2年目の日に結婚した。冤罪を晴らすための二人三脚の旅である。入籍しただけで結婚式はあげていない。
*********
この事件は、重要参考人として取り調べを受けた元作男のほか、参考人として取り調べをうけたふたりが自殺、遺族のうちふたりが自殺している。
石川一雄さんは、まだご存命です。60年経ちますが、まだ戦っています。和歌山カレー事件なども冤罪といわれていることも考えると、なにも変わっていないのかもしれません。少し前に「福田村事件」という映画を観たのもあわせて、被差別部落に関しての知識が少し増えました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
