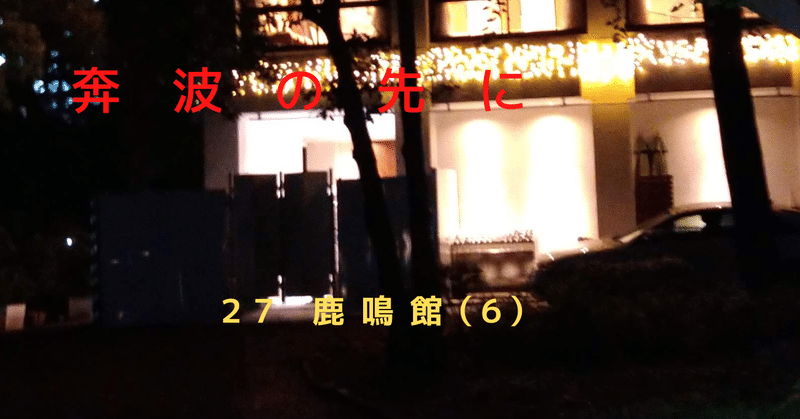
【小説】奔波の先に~井上馨と伊藤博文~#160
27 鹿鳴館(6)
馨も希望通りの日比谷近くの旧薩摩藩の藩邸の土地を手に入れる事ができた。
土地が決まったことで、設計も本格的になった。設計はジョサイア・コンドル、工部省のお抱え外国人で工部大学校の教師を勤めている。そういえば、博物館もこの男の設計だったなと馨は思った。軽やかな感じでは駄目だとはっきり言っておく必要があると考えていた。
「君が設計担当のコンドル君か」
「よろしくお願いします」
「単刀直入に言う。ヨーロッパのゴシック様式で作って欲しい」
「外国人との社交場とお聞きしています。でしたら、和風を取り入れた方が、日本の社交場としてオリジナルなものとなりますが」
「オリジナルなとか日本風、東洋趣味も取り入れないで欲しいのだ。だいたいコロニアル様式とは何だ。植民地様式だろう」
「そのようなモノマネ…」
「モノマネで結構だ。いや、できる限りのモノマネをして欲しいくらいだ。伊藤も礼装を洋式にしようとしたら、医者のベルツに和装の方がいいと言われたらしいが。君たちは東洋趣味があるからそう思うだけだ。他の外国人は日本のものを見下している。我らは日本も欧米も、同じ舞台に立っていることを見せる必要があって、やっているのだ。この社交場もそのための道具だ。この点を理解の上作って欲しい」
「他のものに頼むべきだ」とコンドルは口に出しかけたが、ここは我慢するしかなかった。
「わかりました。ご意向に沿った形で、建築案をお持ちいたします」
あっそうでしたと付け加えていった。
「ただ、提示された予算では、見栄えの良いものはできかねます」
「装飾までは、あまり手がかけられん、という事だな。わかった。できる限りの事をしてくれれば良い」
馨はコンドルを送り出すと、窓の外を眺めた。皇居の周りに、レンガ・石造りの官庁を集約させる。一つの街を造り、その周辺に劇場やホテルがあれば、そこだけでもパリの町並みが、できるかもしれない。そういう意味でも、この社交場は、大きな役割を果たすことに、なるだろう。本当はここまで、大きなものにする必要はなかったというのは、己の心に押し込んでおけばいい。実際、あれだけ最初は評価されなかった、銀座のレンガ街も大きな道も、変わってきたではないか。
ある日、馨が社交場の図面を開いていた時、急に扉が開いた。
「井上さん、おられるか」
「誰じゃ、ではないの。中井か」
馨は立ち上がり、入ってきた中井に握手をしようと、手を差し出した。しかし中井はその手を取らず、軽く抱いた。
「ずいぶんお疲れのようだ」
「うるさい、いいから離れろ。わしは男と抱き合う趣味はないんじゃ」
「これは、ハグっちゅうのは、知っとっはず。いい加減に馴れろ」
ふっと、机の上に広げられた図面が、中井の目に入った。
「これはなんか。図面のようじゃっどん」
「外務省が中心になって作ろうとしておる、社交場の図面じゃ。ここにダンスフロアーもある。パーティーを開き、非公式な情報交換をする場を作ろうと思っちょる。一応宿泊もできるんじゃ」
「ほう、出世した高官たちの語らいの場か」
「ずいぶん皮肉な物言いじゃの」
中井はしばらく黙っていた。何かを考えていたようだった。
「あっそうじゃ。こいを自分に名付けさせて、もれんじゃろうか」
「おぬしがか」
「鹿鳴館」
中井はつぶやくように言った
「鹿鳴館じゃと」
「そうじゃって。『鹿が鳴いて賓客を迎える』詩経じゃ。実際に迎ゆったぁ音楽じゃろうが、悪うなかち思う」
「たしかにの。鹿鳴館か」
「気に入ってくれたか」
「あぁ、鹿鳴館。これはええの」
「これで鹿鳴館は、聞多さんとおいの協働じゃ。協働といえば原敬君は元気か」
「あぁ、フランス語のわかるもんは外務省でも少ないからな。そろそろ外に出そうと思っちょる」
「そうか。そいでは、うちん娘を嫁にもろうてもらわんとな」
「貞ちゃんもそねーな年頃か」
サポートいただきますと、資料の購入、取材に費やす費用の足しに致します。 よりよい作品作りにご協力ください
