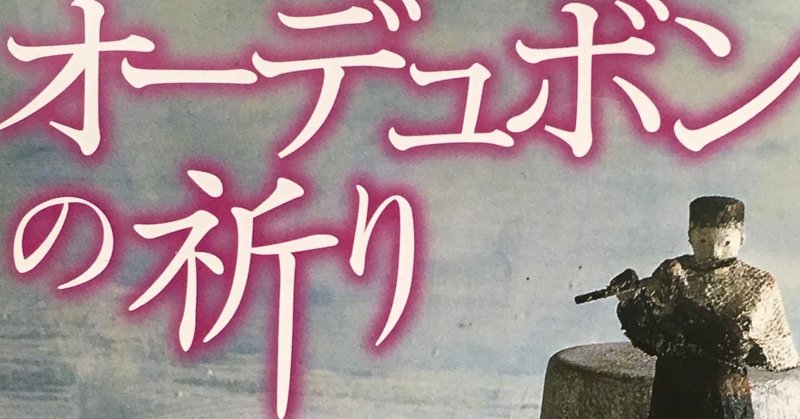
オーデュボンの祈り について、世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド と比較して考える
伊坂幸太郎の オーデュボンの祈り(以下、オーデュボン) について考えてみたい。その際、この作品をミステリーではなくファンタジーとして捉えてみたい。つまり、ここで書かれていることを一種の比喩として捉え、私たちの世界にとって何を言いたいのかを考える。また、似た構成を持つ村上春樹の 世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド(以下、世界の終わり)と比較することで、時代背景・作者の問題意識の違いについて考えたい。
結論は、
虚構/現実を等価なものと認めた上で、敢えて虚構の世界を選択する 世界の終わり に対して、
虚構/現実の世界が等価であることは自明な前提とした上で、システムが立ち上がり終わるまでを描くことでその不可能性を示したのが、 オーデュボン である。
というものだ。
1985年に書かれた 世界の終わり から15年後に書かれた オーデュボンは、虚構の世界と現実の世界が交互に描かれ、最終的には合流する という点で似たような構成をとっている。
世界の終わり:虚構=ハードボイルド・ワンダーワールド 現実=世界の終わり
オーデュボン:虚構=荻島 現実=仙台
一方で、結末に関しては、大きくその趣を異にする。
世界の終わり では、虚構と現実がショートを起こし、どちらか一方の世界にしかいられなくなった主人公は、ある種の倫理的な責任感から、虚構の世界に残る決断をして終わる。
オーデュボンでは、虚構と現実の世界がスムーズかつシームレスに繋がり(主人公は仙台に戻れることが暗示されている)、荻島に 欠けているもの(=音楽) がもたらされるところで終わる。
世界の終わり が読者に考えさせる バットエンド
オーデュボン が祝福を暗示した ハッピーエンド
のようにも見える。
本当にそうか?
主人公の役回りも異なる。
世界の終わり において、主人公は物語を進める原動力だ。実質、この物語は主人公の頭の中で完結していると言ってもいい物語であるからだ。
オーデュボン においては、主人公は狂言回しの猿・ただの観察者だ。確かに何度か主人公は物語の中で決定的な役回り(手紙と自転車)を果たす。だが、それ自体がすでに上位の存在に動かされての行動であったことが後に明らかになる。ここでいう上位の存在、物語の原動力とは誰か。もちろん、案山子の優午と荻島のルールである桜だ。
優午と桜の役割とは何か。
システムを維持するために要請される〈外部〉だ。
ゲーデルの不完全性定理
ドフトエフスキー カラマーゾフの兄弟の 大審問官 の章
サハリのサピエンス全史
あるシステムを維持・安定させるためには、システムの外部にある存在が必要である という主題は繰り返し語られてきた。オーデュボン もこの系列に連なる作品だと言えるだろう。
それは、優午の哀しみ・桜の非人間的な存在感といった形で現れる。
世界の終わり に システムを支える〈外部〉 という発想がないわけではない。それは、一角獣 というモチーフで語られる。人々の自我の重さを背負って、一角獣が犠牲になることでハードボイルド・ワンダーワールドは維持されているのだと。だが、物語の主題はそこにはない。
世界の終わり においては、現実と虚構が等価であること、さらに一歩進んで、主人公が虚構を選択することに物語の焦点が当てられている。
世界の終わり(現実)とハードボイルド・ワンダーワールド(虚構)
題名からして、現実と虚構を等価に並列している。
1985年時点では、現実と虚構が等価である という主張自体が驚きであり、中心的なモチーフになり得たのだ。
オーデュボンの祈り という題名の表しているものは何か。
作中で説明されているように、オーデュボンとは、リョコウバトを愛した動物学者であり、仮にリョコウバトが滅びゆく未来を知っいてもどうしようもなかっただろう存在、優午が自分を重ねた人間ということになる。そこには、未来を俯瞰する視点とそれを知って尚、未来を変えることのできない悲しみが表出されている。そう、優午は未来を知っている案山子なのだ。未来を知って尚変えることが出来ない時、人は祈るのではないだろうか。
優午が群集心理による一種の集団ヒステリーによる錯覚だったのか、客観的に存在していたのか、という問いには意味がない。重要なことは、意思決定・資源配分(政治経済)は現実には、最も効率的にはなされない。その大きな原因の一つは、情報の不完全性であり、荻島では優午の存在によって、効率的な政治と経済が行われていただろうということだ。
もう一人のキーパーソン桜の機能は何か。
法の執行・暴力装置である。法の執行に属人性が加わってはならない。にもかかわらず、現実には、完遂されない。誤審と思われる事例は存在する。警察権力を始めとした公務員の汚職は存在する。法の執行とは、人間離れした、超越的、抽象的、神にも近しき存在にされなければならない。その理想の具現が桜の造形だ。日比野は桜を自然現象のようなものだという。桜の行為が常に正しいと言っているのではない。桜は意志や善悪と言った価値とは無関係の存在であると思っているのでそもそもその行為が正しかったどうかが問題にならないと言っているのだ。理想的な法の執行装置である。政治 経済 司法 において荻島は理想の世界:ユートピアだと言えるだろう。
だが、それは裏返せば、私たちの世界のシステムの不可能性を言っているに等しい。私たちには優午のような存在も桜のような存在もいないからだ。
祈り という言葉にもの悲しさを感じるのは、そこに不可能性の暗示を含んでいるからかもしれない。
優午はなぜ死んだのか。システムの〈外部〉として、システムの内部の存在がその役を担うと、その存在は壊れるのだ。あるいは、桜のように生命活動はしていても人間として壊れるのだ。ここにも、きれいなもの悲しさ=祈り ともいうべきモチーフの反復を感じる。
荻島にかけていたもの=音楽について。
ヴィトゲンシュタインは
語り得ぬことについては、沈黙しなけばならない
として、哲学=言語と、その他の問題=音楽、絵画、舞踏をはじめとする芸術で扱うべき領域の区別を求めた。
言語には扱うことができず、芸術には扱うことができる領域とは何か。
共感性、身体性、感染といった領域だ。
荻島では音楽だけでなく、園山によって絵画もまた彼の家内に隠されていた。舞踏においては言及すらされていない。荻島の始祖、支倉常長はなぜ、音楽を不要のものとして遠ざけたのか。
音楽の持つを熱狂、逸脱させる力を恐れたのではないだろうか。このように見ていくと、荻島とは、超越的な政治 経済 司法 装置をもち、かつ、人々の熱狂を可能な限り抑えられることで維持されてきた一種のディストピアでもあるように思える。
確かに優午は、また荻島の人々は、荻島に欠けているもの=音楽を心待ちにしてしていただろう。だがラストシーン、静香が約束の丘でアルトサックスを吹いたあと、何が残るだろう。
熱狂、感動の後に残るのは、優午なき世界で熱狂することを知ってしまった人達なのだ。
資源の非効率な分配、不適切な意思決定が起こるのことは避けられない。人々は以前より逸脱を起こしやすくなっている。荻島というシステムは不安定化し、おそらく自壊するだろう。唯一の希望は、名もなき少年が作った優午の代わりの案山子だが、これに関しても祈るしかない。
1985年。大量生産・大量消費の経済システムが立ち上がり、広告・金融業が栄えた時代の空気を反映して、村上春樹は、虚構を現実と等価とし、あえて虚構を選んで見せた。そこには今後も続く、消費社会への希望も含まれていたはずだ。
2000年。フェイクニュースが氾濫し、異世界転生ものが人気を博す現在において、虚構と現実が等価であるという言い方にほとんど新鮮なものは感じられないことを見越してか、伊坂光太郎は、虚構か現実であるか否かに関わらず、システムの不可能性に焦点を当てた作品を書いた。
オーデュボンの祈りは希望の物語ではない。
システムの不可能性を 祈り によってつなぎとめようとする
これは悲しい物語なのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
